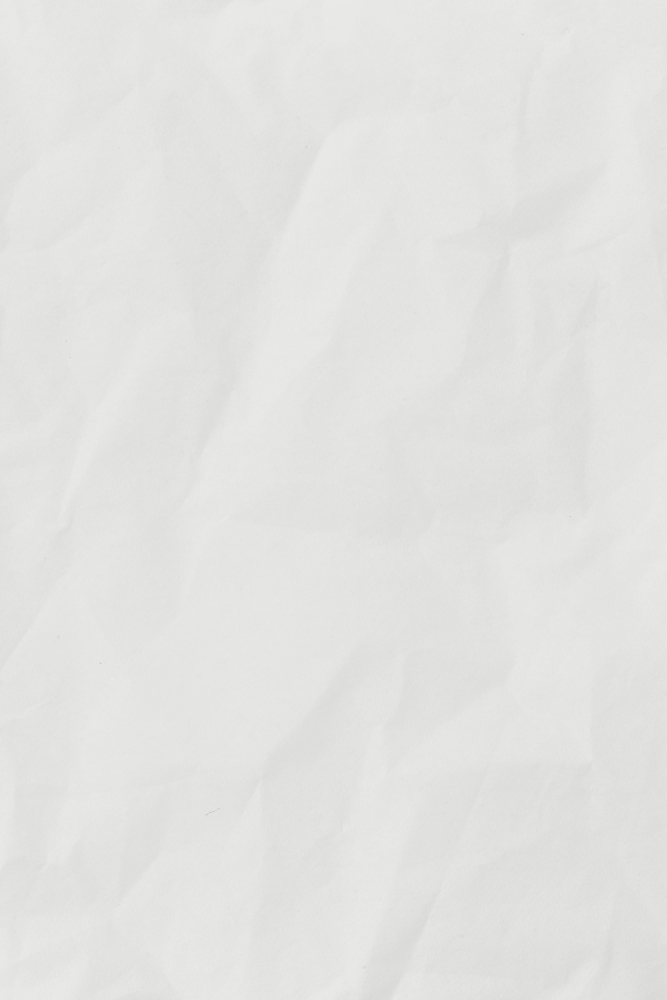カンオケダンス陽関三畳
シェイクスピアとの対話でわかったあまりにも深い沼。
創作物である自分達は、単純に作者の考え得ること以上の行動に、いまいち順応出来ていない時がある。
だが神だ、英霊だ、何だと言っても、この惑星が紡いできた歴史や礎とされた事象を事実として認識し、知識として活用できるのだからどう見ても不備が無い。
だからややこしいのだ。
親と呼べるものはエキストラと化し、親と呼べるものはこの惑星に眠ってしまった。
それはひとつの永眠だ。
自分達を創った世界は、もう目覚めはしないのだ。
会いたい誰かがこの世にいないなんて、ただつらいだけではないか。
登場人物はもう、減りはしても増えやしない。
そしてそれは、このカルデアに居る限り、ホームズとモリアーティも同じ数の内なのだ。
しかしそんなホームズの心の内など、モリアーティが知る由もない。
彼からしたら今のホームズは過保護な宿敵でしかなかった。
「確かに魔力の枯渇で死にかけではいたけど、彼だって殺すつもりであんなことした訳じゃないんだし…ちょっと今回は大袈裟過ぎないか君?」
「大袈裟…?」
「大袈裟だろ…死なないんだから適当に拘束して放っておけばよかったんだから」
その一言に、ホームズは怒りしか抱けなかった。
モリアーティの手を強く握りしめたまま立ち上がり、そのまま彼を見下ろして顔を近付ける。
頭突きでもされそうなそれに、モリアーティは反射的に目を閉じて奥歯を噛み締めた。
だが次の瞬間にそれは無く、あったのは自分の肩にホームズの頭が置かれる衝撃だった。
「――……ホームズ?」
「大袈裟な訳ないだろう」
「……どうした」
「大袈裟な訳、ないだろう…」
創作物である自分達は、数の中で生きていると言っても過言ではない。
捲られる紙の中で、スクロールされる画面の中で、認識された数…覚えてくれている人数の中で生きている。
当然それは「覚えてくれている」から存在できている。
そしてそのことは決して、今ホームズの目の前で生きているモリアーティとイコールではないのだ。
「私にとって…君は君しか居ないのに…大袈裟な訳ないだろう」
ホームズの言葉に、モリアーティは息を忘れる。
「そんな誰か」から与えられたかったものを、「そんな誰か」の周りに強く愛された宿敵から与えられていたのだから。
…いつもの憎まれ口も思い付かない。
余裕なんて無い。
握られた手を振りほどく力も湧かない。
ただ重いだけであるはずのホームズの頭部が、酷く愛しい。
(…………あんまりだ…こんなこと……)
共に死ねた筈なのに。
生き返ったって、またあの地に赴いて…遺体の一部でも拾い上げてくれたなら、まだ笑ってふざけて怒れたのに。
だがそんなこと、それこそ目の前のホームズに言ったって、何も変わりはしない。
だからこそホームズは、わかっていて怒っている。
「――もう何回めだ…まったく。あーなんだ…悪かったよ…別に、君の気持ちを蔑ろにしようって訳じゃなくてだな…あー…その……上手くまとまらん。そのだな…今は……文句の方が先に浮かぶんだがネ……なんと言うか…なんだ……なんてものを産み落としたんだろうね…我らが父は……」
「……まったくもって同感だな…」
そこには、ホームズの手を握り返し、彼を真似る様に相手の肩へ自分の頭を預けるモリアーティの姿があった。
◆
数日後、レイシフト先であるイギリス・ミンステッドにて。
「苔だらけじゃないか」
「死んでから何十年経ってると思ってるんだ、おまえ」
「そもそもなんでこんな…いやまぁいい、せっかくの墓参りなんだ。楽しく話そう」
「……私は恨みつらみで終わりそうだがネ」
「ははは、素直でいいじゃないか」
―終―
.
創作物である自分達は、単純に作者の考え得ること以上の行動に、いまいち順応出来ていない時がある。
だが神だ、英霊だ、何だと言っても、この惑星が紡いできた歴史や礎とされた事象を事実として認識し、知識として活用できるのだからどう見ても不備が無い。
だからややこしいのだ。
親と呼べるものはエキストラと化し、親と呼べるものはこの惑星に眠ってしまった。
それはひとつの永眠だ。
自分達を創った世界は、もう目覚めはしないのだ。
会いたい誰かがこの世にいないなんて、ただつらいだけではないか。
登場人物はもう、減りはしても増えやしない。
そしてそれは、このカルデアに居る限り、ホームズとモリアーティも同じ数の内なのだ。
しかしそんなホームズの心の内など、モリアーティが知る由もない。
彼からしたら今のホームズは過保護な宿敵でしかなかった。
「確かに魔力の枯渇で死にかけではいたけど、彼だって殺すつもりであんなことした訳じゃないんだし…ちょっと今回は大袈裟過ぎないか君?」
「大袈裟…?」
「大袈裟だろ…死なないんだから適当に拘束して放っておけばよかったんだから」
その一言に、ホームズは怒りしか抱けなかった。
モリアーティの手を強く握りしめたまま立ち上がり、そのまま彼を見下ろして顔を近付ける。
頭突きでもされそうなそれに、モリアーティは反射的に目を閉じて奥歯を噛み締めた。
だが次の瞬間にそれは無く、あったのは自分の肩にホームズの頭が置かれる衝撃だった。
「――……ホームズ?」
「大袈裟な訳ないだろう」
「……どうした」
「大袈裟な訳、ないだろう…」
創作物である自分達は、数の中で生きていると言っても過言ではない。
捲られる紙の中で、スクロールされる画面の中で、認識された数…覚えてくれている人数の中で生きている。
当然それは「覚えてくれている」から存在できている。
そしてそのことは決して、今ホームズの目の前で生きているモリアーティとイコールではないのだ。
「私にとって…君は君しか居ないのに…大袈裟な訳ないだろう」
ホームズの言葉に、モリアーティは息を忘れる。
「そんな誰か」から与えられたかったものを、「そんな誰か」の周りに強く愛された宿敵から与えられていたのだから。
…いつもの憎まれ口も思い付かない。
余裕なんて無い。
握られた手を振りほどく力も湧かない。
ただ重いだけであるはずのホームズの頭部が、酷く愛しい。
(…………あんまりだ…こんなこと……)
共に死ねた筈なのに。
生き返ったって、またあの地に赴いて…遺体の一部でも拾い上げてくれたなら、まだ笑ってふざけて怒れたのに。
だがそんなこと、それこそ目の前のホームズに言ったって、何も変わりはしない。
だからこそホームズは、わかっていて怒っている。
「――もう何回めだ…まったく。あーなんだ…悪かったよ…別に、君の気持ちを蔑ろにしようって訳じゃなくてだな…あー…その……上手くまとまらん。そのだな…今は……文句の方が先に浮かぶんだがネ……なんと言うか…なんだ……なんてものを産み落としたんだろうね…我らが父は……」
「……まったくもって同感だな…」
そこには、ホームズの手を握り返し、彼を真似る様に相手の肩へ自分の頭を預けるモリアーティの姿があった。
◆
数日後、レイシフト先であるイギリス・ミンステッドにて。
「苔だらけじゃないか」
「死んでから何十年経ってると思ってるんだ、おまえ」
「そもそもなんでこんな…いやまぁいい、せっかくの墓参りなんだ。楽しく話そう」
「……私は恨みつらみで終わりそうだがネ」
「ははは、素直でいいじゃないか」
―終―
.