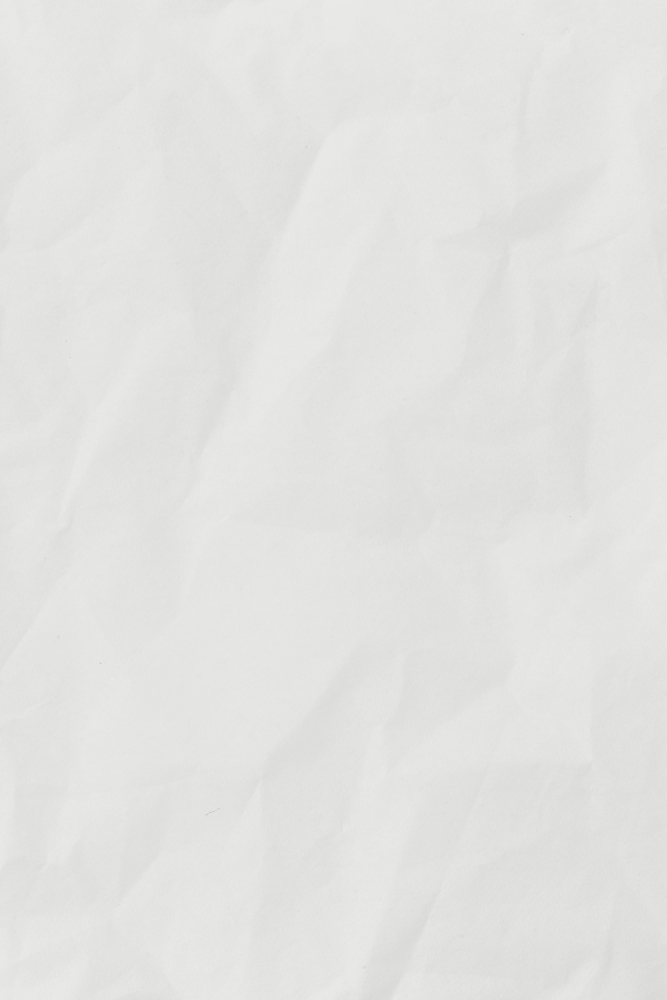邂逅:S
「本当にこの子の感情が二の次なら、結論から言わないのは変じゃない?」
チクリと刺すような指摘 に、今度はS が片眉 を下げる。
「……痛いとこ突きますねぇ」
「あべこべだと思っただけだけど」
「これでも、30代半 ばに差し掛かるくらいなもんでして。いきなり掴みかかってくるじゃりんこ相手でも、優しく順序は踏みます」
悄然 とした様子でユビへの溜め息を堪 えるS から目を逸 らし、博雪 は何度か小さく頷 いた。
「……じゃりんこか。まぁ、そうだね。それならうん、わかった。僕は何も言えなさそうだし、ユビに任せるよ」
博雪 の突然の承諾 に、ユビとS は目を大きく丸める。
「深刻 そうな話な上に、ここまで小出しを続けられると気になるだろうし。まぁ身内の話なんだから、ユビならもう知る方に舵 切るでしょ?」
すんなりと訊 ねられたそれに、ユビは驚きが抜け切らないまま、ゆっくりと首を縦に振る。
博雪 は先ほどからユビに凭 れ掛かったままの体勢を解 き、自分のコーヒーが入ったマグカップを取った。
そしてユビと自分の立ち位置を入れ替 える。
「まぁ狭 いから僕も聞くことになっちゃうけど、どうぞ。あぁでも、ユビが手を出しそうになったらそこまでね。さっきも言ったけど僕、これでも今は保証人だから、ユビを叱 ることもしなきゃでね」
速い口調でされた博雪 からの忠告に、S は真顔となったが、ユビは硬直 する。
「ランチタイムが終わるまでに、よろしく」
かくして、10年前にこの世を去ったユビの兄――白雪 一姫 についての幕が上がる。
そうして、今しがた博雪 からユビへの確認を許可されたS は、改めてユビへ向き直り、もう一度一姫 について話す。
「えーっと、じゃあ改めて…2007年の6月、お前の自宅から約3km離れた廃公園で白雪 一姫 、当時19歳の遺体が発見された。死因は不明だとされてますが、俺が立ててる予想は別」
「……なんで? つーかもうお前呼びかよ…」
短時間で湧いてきた怒りや焦り、そして唐突な博雪 からの突き放しにより急激に不安が押し寄せてきたユビは、恐る恐るS へ聞き返しながら苦言を漏 らす。
勢いが弱まったユビの様子に、感情が綯 い交 ぜになったことで、現状に対処しきれていないのだろうとS は考えた。
繊細 なところに触れている自覚もある。
それ故 にS は目を少し泳がせ、カウンターに肘 をついた手の平に額 を預けた。
一姫 の死因について僅 かに怯 えて見えたユビに、目を合わせず可能性を伝えることにする。
「……あー、まぁ、お前の兄ちゃんなんだけど…白雪 一姫 は、致死 量以上のドラッグを所持していた筈 なんですよ」
「――…は?」
「もし俺の調べが当たってるなら、オーバードーズによる心筋 障害での死亡って可能性の方が遥 かに高い」
S からの突拍子 も無い言葉に、ユビは何も返せなかった。
そしてS の言葉を聞いていた博雪 もユビと似た反応で、口をぽかんと開けている。
S は顔を上げ、そんな2人の反応を確認すると、当然の反応だと流して言葉を続けた。
「2007年に白雪 一姫 は、ここらの地域で大手と言われるフロスト社に高卒で就職しました。その時アルバイトとして、同じ業務部署に配属されていたフロスト社の次期社長候補…毒嶋 匡 と接点を持ちました」
ユビは初めて聞く毒嶋 匡 という名前に、首を傾げる。
しかし博雪 の目は鋭いものとなった。
2人の反応が真逆であることに、S は触れない。
「…ここからだ。ここからが確認したいところです、白雪 ユビ」
「え…?」
「お前の兄ちゃん、日記つけてませんでした?」
「え」
――……何故 、それを知っているのか。
まるでそう言いたげなユビの訝 しむ声と表情に、S は確信を抱く。
「つけ続けてたんだな。それ、読ませてくれます?」
S は先程額 を預けていた手の平をユビに向け、薄っすらと頬 を丸める。
そんなS の切り替 えが早い態度に、ユビは瞬間的な苛 立ちを覚えた。
しかし、背後に博雪 が居ることを忘れてはいない。
ユビは小鼻をひくつかせ、向けられたS の手の平目掛 け、戯 れ程度の速度で手を振り下ろす。
すると店内に、小さく渇 いた音が響く。
痛みを伴 わずとも、それはS にとって予想外の衝撃 であった。
咄嗟 にS はユビに叩かれたことへ、ウソ泣きをする子供のように抗議 する。
「暴力反対」
「乞食 反対」
「…なるほど、確かに。タダで見せてくれってのは無しですな。なかなか上手い返しするな〜、ユビ」
「呼び捨てにすんな!」
ユビは結局その場で声を荒げてしまい、博雪 に肘 で脇腹 を小突 かれる。
.
チクリと刺すような
「……痛いとこ突きますねぇ」
「あべこべだと思っただけだけど」
「これでも、30代
「……じゃりんこか。まぁ、そうだね。それならうん、わかった。僕は何も言えなさそうだし、ユビに任せるよ」
「
すんなりと
そしてユビと自分の立ち位置を入れ
「まぁ
速い口調でされた
「ランチタイムが終わるまでに、よろしく」
かくして、10年前にこの世を去ったユビの兄――
そうして、今しがた
「えーっと、じゃあ改めて…2007年の6月、お前の自宅から約3km離れた廃公園で
「……なんで? つーかもうお前呼びかよ…」
短時間で湧いてきた怒りや焦り、そして唐突な
勢いが弱まったユビの様子に、感情が
それ
「……あー、まぁ、お前の兄ちゃんなんだけど…
「――…は?」
「もし俺の調べが当たってるなら、オーバードーズによる
そして
「2007年に
ユビは初めて聞く
しかし
2人の反応が真逆であることに、
「…ここからだ。ここからが確認したいところです、
「え…?」
「お前の兄ちゃん、日記つけてませんでした?」
「え」
――……
まるでそう言いたげなユビの
「つけ続けてたんだな。それ、読ませてくれます?」
そんな
しかし、背後に
ユビは小鼻をひくつかせ、向けられた
すると店内に、小さく
痛みを
「暴力反対」
「
「…なるほど、確かに。タダで見せてくれってのは無しですな。なかなか上手い返しするな〜、ユビ」
「呼び捨てにすんな!」
ユビは結局その場で声を荒げてしまい、
.