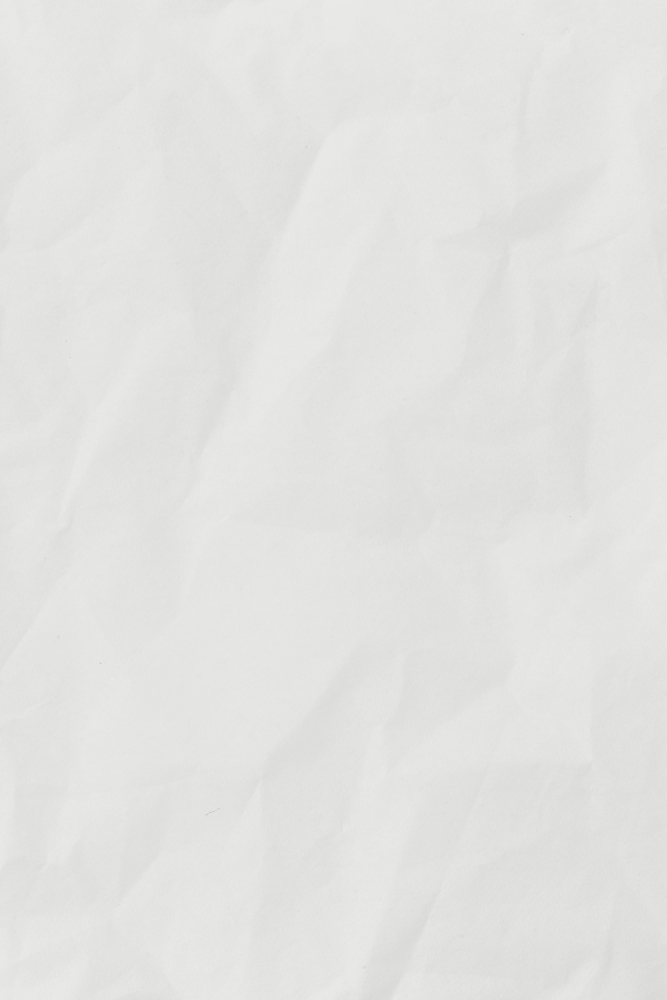邂逅:S
――…キッチンに立つユビはコーヒーラテを持ち、その隣で博雪 はホットコーヒーを一口 飲む。
湿気 による不快感を解消する為、店内の冷房を強めに効 かせているので、温かい飲み物が丁度 良いのだろう。
しかしいくら平日といえど、ランチタイムにS 以外の客が居ないというのは、殺風景 なものだ。
だがそれも店主と従業員が客と共に飲食をしている時点で、この喫茶店には何の痛手でもないのだろうことが窺 える。
やる気がないというより、必要最低限の決まりを守りながら運営すること――それが大事である印象だ。
S はユビと博雪 の様子に然程 驚くことも無く、先程まで座っていた窓際席からカウンター席へおしぼりを移動させ、勝手に腰を下ろす。
そうしてユビと博雪 の2人と向かい合いながら、カフェオレを飲んだ。
冷えた胃が温まり、良いコーヒーの香りとまろやかな牛乳の甘さを味わってから、ポツリと現状に対する心情を漏 らす。
「……マジで客来 ねぇんだな、この店」
その小声に眉 を釣り上げたユビが一言返そうとするが、博雪 に軽く腕で小突 かれたことで止まる。
「お客様ー、失礼ポイント加算しとくねー」
「いやぁ、噂 通りで驚いたんですよ。後でちゃんとランチ注文するんで、見逃して下さい」
「…はいはいそーですか。それで、ユビにどういったご用件が?」
目を合わせない博雪 からの切り出しに、S は困った風に笑 みを作る。
すると煙草 を入れていた胸ポケットの奥から、手の平に収まる大きさに切られた1枚の写真を取り出した。
それを2人に見えるよう、カウンターテーブルの上へ置く。
S が差し出したその写真には、ユビとは髪型だけ違う、ユビによく似た誰かが写っていた。
博雪 は写真の人物を一瞥 すると一度ユビに視線を向け、もう一度写真を見て、瞬 きをする。
「………ユビに見えますけど」
「そっくりですがユビ君じゃないですよ。彼のお兄さんです」
その一言で、漸 くS と博雪 の目が合う。
今までの胡散臭 さから打って変わり、S の表情は真剣そのもの。
そして何より、当事者であろうユビの顔から血の気 が引いていた。
「2007年の6月…今からちょうど10年前です。ユビ君の住んでいた共同住宅から約3km離れた廃公園で、白雪 一姫 君、当時19歳の遺体が発見されました」
抑揚 無くされた説明に、ユビは喉 を詰 まらせながらもS へ問う。
「――なん、で…んな、兄さんのこと……」
「死因は当時のローカル新聞によると心不全とされていますが、それ以外は名前と年齢のみの記載でした。こんなものは、死因不明だと言ってるようなもんです」
「おい!」
ユビはキッチンから乗り出し、淡々 と話すS の胸ぐらをカウンター越しに掴む。
しかしそれはすぐさま博雪 により離され、ユビは一旦 、博雪 の後ろに立たされた。
だがそれで感情の衝動 を抑えられるわけもなく、声を上げる。
「お前、何しに来た!」
正真正銘 の怒りと焦りが混じったその問い掛けに、S は答えない。
ユビに掴まれて皺 になった部分を手で払い伸ばしながら、何事も無かったかのように話を進めていく。
「…持病も無く、通院履歴 も無い。短期間とはいえ新入社員でありながら、会社部署 内での成績も悪くなかった。死に直結するような人間関係でのいざこざや噂 も立たず、問題無く仕事してた青年が前触れも無しに死ぬ…それは異常です。なのに誰も触れない。極め付けの心不全なんて、そんなの『死んだ原因がわかりませんでした』って言ってるのと変わらない…そう思いませんか?」
演技かかった困り顔で場を譲 らない、そんなS の話を聞きながら、博雪 はユビを背で抑 え続ける。
そしてS の疑問を冷たくあしらった。
「つまり何が言いたいのかな?」
「彼の死に、不明なんて結論を出す可能性は低い…ということです」
「…って言われても、僕がそれを聞いて何か解決しますかね?」
「いえ、これは彼の死に繋 がった原因を解決するための話でなく、彼の死因に繋 がった誰かを探してる、俺の話です」
S は気にならなくなる程度にシャツの皺 を伸ばしきると、対面する博雪 へほんの少し顔を寄せた。
「俺は俺の目的の為に、ユビ君に確認したいことがあるんです」
その言葉が嘘ではないことは真剣な表情で分かる。
しかし博雪 は片眉を下げて黙る。
――数秒の沈黙。
縮まった2人の距離と重苦しい空気は、無視され続けたユビが博雪 を後ろへ引っ張ることで、無理矢理に破る。
背丈での体格差と若さからくる衝動 的かつ突発的な力量に、博雪 は勝てそうになかった。
突然後ろへ引っ張られたその時、ユビに凭 れ掛かることで倒れないよう耐 えたのだ。
ユビも短い時間で幾分 か落ち着きを取り戻せたように見えるが、怒りと焦りは薄まっていない。
「俺は…司法解剖 の結果は心不全で…それが原因で倒れて、吐 いて窒息 したって、親から聞いたぞ」
ユビは博雪 の背後から頭ひとつ飛び出した状態で、S を見下ろしながら語気を強める。
「どうして可能性が低いなんて言い切れるんだよ。そうじゃなきゃ何だよ。兄さんの何を知ってんだ、お前」
これまでの流れで、感情的になればなるほど博雪 によって止められると学んだため、ユビは努めて冷静を装 いながらS に問う。
「家族の俺より、兄さんを知ってんのか?」
最後に少し上擦 ったユビの声に、2人と向き合っているS は僅 かに眉間 の皺 を寄せる。
先程のように割り切った態度を取り続ければいいものの、良心の呵責 に苛 まれるだけの道徳心がS にもあるのだ。
「…あー、なんだ……家族でも知りすぎない方が良いことってのはあるもんです」
「だったら、それだったら、アンタがここに直接来たことがおかしいだろ」
「百も承知なんですよ、ンなこたぁ…それでも俺は俺の目的の為に来てるんです。それは、ユビ君の感情を二の次にするって言うしかないんですよ」
S は瞼 を浅く閉じながら瞳を左右に動かし、瞬 きを繰 り返したら再度、ユビを見る。
「ユビ君が兄ちゃんの白雪 一姫 を好きなら好きな分、傷付くことを確認しに来てるんです。俺は」
そう力 無くユビへ告 げると、S はカフェオレを一口飲んだ。
ごくりと喉 を鳴らしたら、すぐにマグカップを元の位置へ戻す。
そしてそれを合図に、板挟 みのまま黙って見ていた博雪 が口を開いた。
.
しかしいくら平日といえど、ランチタイムに
だがそれも店主と従業員が客と共に飲食をしている時点で、この喫茶店には何の痛手でもないのだろうことが
やる気がないというより、必要最低限の決まりを守りながら運営すること――それが大事である印象だ。
そうしてユビと
冷えた胃が温まり、良いコーヒーの香りとまろやかな牛乳の甘さを味わってから、ポツリと現状に対する心情を
「……マジで客
その小声に
「お客様ー、失礼ポイント加算しとくねー」
「いやぁ、
「…はいはいそーですか。それで、ユビにどういったご用件が?」
目を合わせない
すると
それを2人に見えるよう、カウンターテーブルの上へ置く。
「………ユビに見えますけど」
「そっくりですがユビ君じゃないですよ。彼のお兄さんです」
その一言で、
今までの
そして何より、当事者であろうユビの顔から血の
「2007年の6月…今からちょうど10年前です。ユビ君の住んでいた共同住宅から約3km離れた廃公園で、
「――なん、で…んな、兄さんのこと……」
「死因は当時のローカル新聞によると心不全とされていますが、それ以外は名前と年齢のみの記載でした。こんなものは、死因不明だと言ってるようなもんです」
「おい!」
ユビはキッチンから乗り出し、
しかしそれはすぐさま
だがそれで感情の
「お前、何しに来た!」
ユビに掴まれて
「…持病も無く、通院
演技かかった困り顔で場を
そして
「つまり何が言いたいのかな?」
「彼の死に、不明なんて結論を出す可能性は低い…ということです」
「…って言われても、僕がそれを聞いて何か解決しますかね?」
「いえ、これは彼の死に
「俺は俺の目的の為に、ユビ君に確認したいことがあるんです」
その言葉が嘘ではないことは真剣な表情で分かる。
しかし
――数秒の沈黙。
縮まった2人の距離と重苦しい空気は、無視され続けたユビが
背丈での体格差と若さからくる
突然後ろへ引っ張られたその時、ユビに
ユビも短い時間で
「俺は…
ユビは
「どうして可能性が低いなんて言い切れるんだよ。そうじゃなきゃ何だよ。兄さんの何を知ってんだ、お前」
これまでの流れで、感情的になればなるほど
「家族の俺より、兄さんを知ってんのか?」
最後に少し
先程のように割り切った態度を取り続ければいいものの、良心の
「…あー、なんだ……家族でも知りすぎない方が良いことってのはあるもんです」
「だったら、それだったら、アンタがここに直接来たことがおかしいだろ」
「百も承知なんですよ、ンなこたぁ…それでも俺は俺の目的の為に来てるんです。それは、ユビ君の感情を二の次にするって言うしかないんですよ」
「ユビ君が兄ちゃんの
そう
ごくりと
そしてそれを合図に、
.