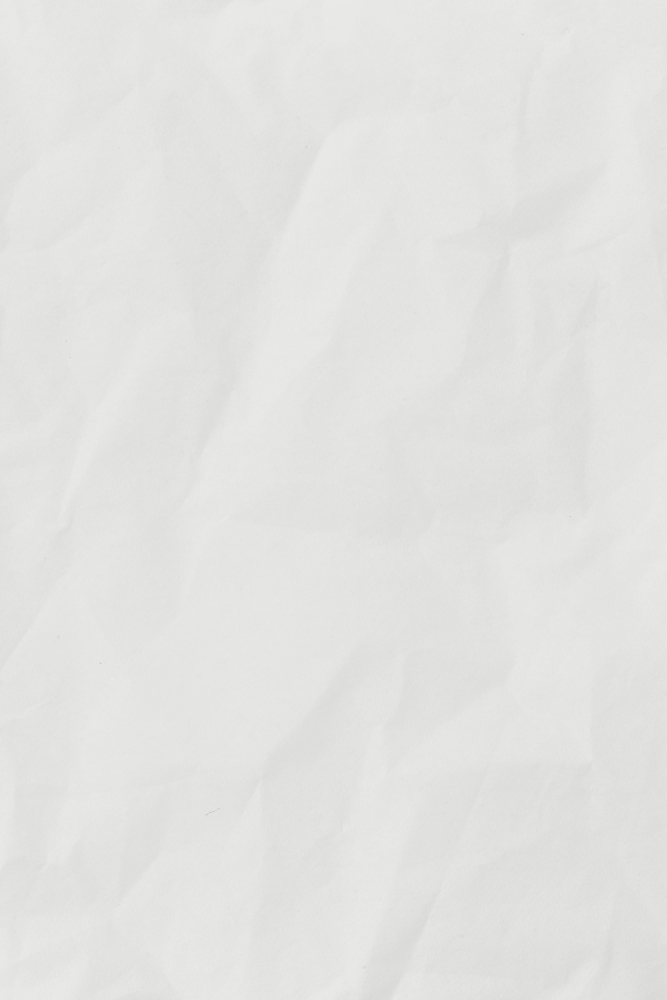しちの探偵事務所
そして数分後、博雪 はブレンドコーヒーを辰海 に、レモンティーをツヅリに提供した。
するとそれを合図としたのか、辰海 はユビと博雪 へ向けてカウンターに名刺を置くのだった。
しかし、営業に赴 かれるような心当たりの無い博雪 は疑念 を抱く。
「…なんです?」
「私 、しちの探偵事務所という組織運営をしております、伊良 辰海 と申します。私の横にいるのは所属員の獅子谷 ツヅリになります。少々事情がありまして、突然の訪問、座ったままでのご説明と先ほどのご無礼 をお許しください」
そう言うと、辰海 とツヅリが同時に頭を浅く下げる。
博雪 はそれを見やり、眉間 に皺 を寄せた。
だが博雪 の隣で一連の流れを見ていたユビは、辰海 の話す事情というのが見えず、外に誰か居るのだろうかと首を窓のある方向へ伸ばす。
しかし外は変わらずの天気と暗さで、何もおかしなところは無い。
僅 かな時間を置き、差し出された名刺にユビと博雪 は手を伸ばさず、形式上とはいえ辰海 とツヅリに頭を上げるよう伝えた。
彼女達と改めて向き合い視線を交えると、博雪 は質問せずにはいられない状況だと理解する。
「……探偵ですか。何でしょう、何か探し物ですか?」
「探し物…というわけではありません。訊 ねたいことがありまして、白雪 一姫 さんについて、そちらの白雪 ユビさんとお話させていただきたく」
辰海 の申し出に、一瞬で場の空気は凍る。
また『白雪 一姫 』が尋 ねられたことに、ユビは困惑しか抱けない。
居なくなってから10年が経つこの時期に、連日探し求められる兄の過去。
ユビの顔面からはまたも血の気 が引いた。
そのままユビが絶句 し、微動 だに出来ず棒立ちになっていると、博雪 は漸 くカウンターに置かれた名刺を手に取った。
辰海 の先程の説明通り、そこには事務所の住所や電話番号等の常識的な記載がある。
S のふざけた名刺とは大違いなそれに小さく頷 くしかない。
すると博雪 は、ユビの兄である一姫 の名を先に出した時点で詐欺 でもないだろうと踏み、挨拶 することにした。
「この喫茶店のオーナーで、白雪 ユビの保証人になります…赤松 博雪 です。よろしくお願いいたします、伊良 さん」
「ご丁寧 にありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いいたします」
「それで、ユビと話したい内容というのは…?」
自己紹介も程々に、博雪 は本題に移るよう辰海 に目配 せする。
「…赤松 さんもお聞きになられますか?」
「えぇ。ユビはまだ未成年ですし、内容によっては独断が難しいところもあるかと思いますので」
顔面に張り付けた微笑 で一歩も引く気配 を見せない博雪 に、辰海 は一度頷 き、ツヅリも営業的な笑顔を博雪 へ返す。
そして保証人として間違っていない態度だと納得したのだろう辰海 は、浅く頷 き直した。
「わかりました。それでは口外 されないようご協力を」
「もちろんですとも」
目も頬もニコニコとしているのに腹の探り合いをしている博雪 とツヅリに、あまり表情筋が動いていない辰海 が、ユビの横と前に位置する。
現状にユビは不気味 さで動くことも笑うことも出来ず、差し出された名刺を見つめるのみだ。
すると辰海 とツヅリは互いに了承も得られたからと気を取り直し、各々飲み物を口に運ぶ。
嚥下 されるそれらを聞き届けながら、ユビは改めて辰海 とツヅリを一瞥 した。
昨日 はS の第一印象が胡散臭 く最悪であったことと、同性であったことから怒りと焦りを露 わに出来た。
だが今日は違う。
目の前の女性は2人してまだまともで、一般的に必要とされる情報が記された名刺を先に提示し、頭を下げて挨拶 をしたのだ。
(やっぱS …おかしかったよな……)
あと1時間もすれば会うこととなる存在に、ユビは鳩尾 部分がキリキリするのを感じる。
そうやってユビが遠くを見つめながら苛 つきを思い出しているとは露 知らず、辰海 が話を切り出した。
「それではお話なんですが…今から約13年前、この県である問題が起きていました。若者を中心にドラッグが流行 ったんです」
まるでお伽噺 のような抑揚 で話されたそれに、博雪 は小首を傾 げる。
「…13年前、ですか?」
「はい。ドラッグ自体はもっと前から流通していましたが、13年前は安価 に容易 に入手しやすくなった時期でした。俗に云 う〝流行 り〟です」
辰海 の聞き取りやすい落ち着いた声でされる説明を聞きながら、ユビはわざとらしく顔を歪 める。
「俺が4歳の時の治安 どうなってたんだよ…」
「クソだったよ~」
「ツヅリ」
「はい」
話の腰を折るユビに便乗 する形でふざけたツヅリを呼ぶ――そうやって場の空気を引き締めると、辰海 はコーヒーを飲むことで仕切り直しを示した。
それを後ろめたそうに待ちながら、ユビとツヅリは時たまに目を合わせる。
博雪 も少しばかり辰海 へ同情し、手を後ろに回して話を待つのだった。
.
するとそれを合図としたのか、
しかし、営業に
「…なんです?」
「
そう言うと、
だが
しかし外は変わらずの天気と暗さで、何もおかしなところは無い。
彼女達と改めて向き合い視線を交えると、
「……探偵ですか。何でしょう、何か探し物ですか?」
「探し物…というわけではありません。
また『
居なくなってから10年が経つこの時期に、連日探し求められる兄の過去。
ユビの顔面からはまたも血の
そのままユビが
すると
「この喫茶店のオーナーで、
「ご
「それで、ユビと話したい内容というのは…?」
自己紹介も程々に、
「…
「えぇ。ユビはまだ未成年ですし、内容によっては独断が難しいところもあるかと思いますので」
顔面に張り付けた
そして保証人として間違っていない態度だと納得したのだろう
「わかりました。それでは
「もちろんですとも」
目も頬もニコニコとしているのに腹の探り合いをしている
現状にユビは
すると
だが今日は違う。
目の前の女性は2人してまだまともで、一般的に必要とされる情報が記された名刺を先に提示し、頭を下げて
(やっぱ
あと1時間もすれば会うこととなる存在に、ユビは
そうやってユビが遠くを見つめながら
「それではお話なんですが…今から約13年前、この県である問題が起きていました。若者を中心にドラッグが
まるでお
「…13年前、ですか?」
「はい。ドラッグ自体はもっと前から流通していましたが、13年前は
「俺が4歳の時の
「クソだったよ~」
「ツヅリ」
「はい」
話の腰を折るユビに
それを後ろめたそうに待ちながら、ユビとツヅリは時たまに目を合わせる。
.