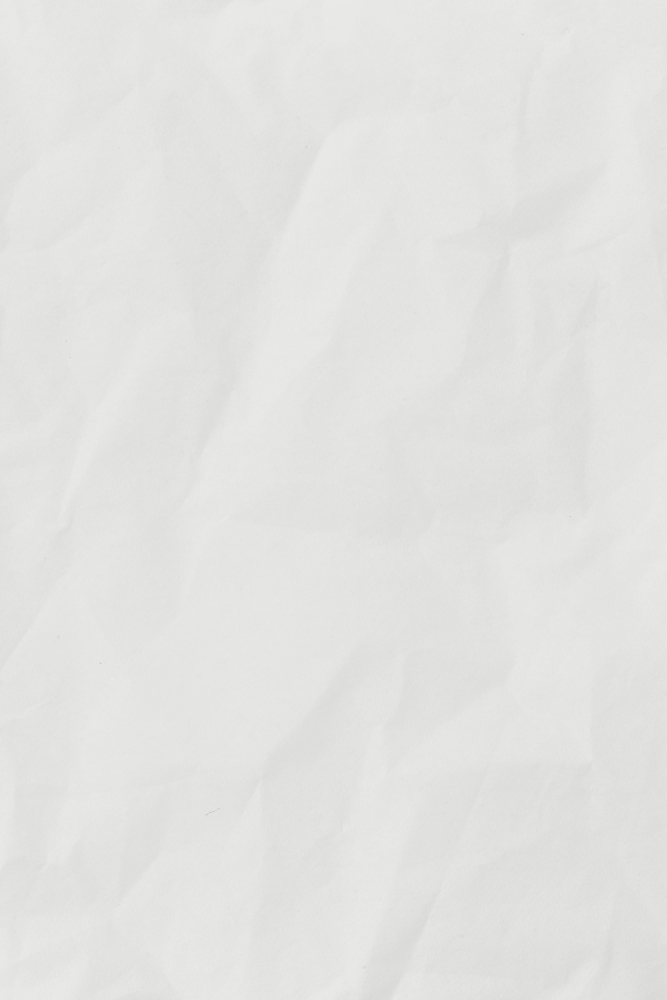ユビと博雪
「話変わるけど、ユビ、S にお兄さんの日記見せるの?」
話しながら冷凍庫の引き出しを開け、中からチョコレートのカップアイスクリームを取り出すと、それをユビに手渡す。
博雪 自身はバニラのカップアイスクリームも持つと、食器棚からスプーンを2つ取り出し、ダイニングテーブルへ向かった。
ユビはそれに着いて行く形で、博雪 と向かい合うよう椅子 に腰掛ける。
そして互いにスプーンを手に持つと、紙製の蓋 を開け、固いアイスクリームの表面を小さく叩いた。
「日記なー、見せるって言っても大したこと書いてないんだよ、兄さん」
「……もしかしてユビが日記持ってるの?」
「うん。そりゃまぁ、アルバムも作らない親だしな。団地の狭 い部屋借りてたから兄さんの祭壇 も作らなかったし、俺が居なくなったら捨てられるだろうと思って」
「…S が言ってたの、出鱈目 じゃなかったんだね」
「んー、でも、心不全で吐いて窒息 したくらいに思っとけって言われたのはマジだぜ。火葬場 に兄さんの骨受け取りに行った時、俺7歳だったけど、見覚えの無い人が車で送迎してくれたのは憶えてるし。タクシーじゃなかったから、それこそフロスト社の人だったのかも…」
「それがS の父親が出した指示って可能性もあるわけか」
「だな。まぁ当時の俺が死因を聞いたところで、理解するってのは難しかったと思うけど」
「……そう…」
「ただ、俺も借り暮らしには変わりないから、兄さんの形見ってなると小さい物がスペース的に精一杯。親も骨だけはどうしようもなかったっぽくてさァ……墓が無いから手元供養 するとか言って、珍しく専門の会社に依頼したの俺ビビったもん。兄さんパック詰めされて返ってきて、これまた小さい骨壺 に入ってて。で、俺が引っ越す時に『日記持って行くなら一緒に持ってけ』って押し付けて来てさ」
「え」
瞬間、博雪 の垂 れた目が大きな円を描 く。
正 しく、目を丸くしていた。
「え、見る?」
「――……じゃなくて、そういうことは一言 ちゃんと言って。知らない内に3人暮らししてたってことでしょ」
「お…あ、言わなきゃダメだったのか。ごめん…知らなくて……」
「いや、かなり特殊 なケースだと思うよ。ただ流石 に僕の心構えがね…」
「……ごめん…」
「うん…まぁ、次は無いとは思うけど、注意しなね…」
世間 一般的な博雪 の感覚に、ユビは自身の感覚がズレていたのかと気付き、素直に頭を下げる。
博雪 も怒っているわけではない。
しかし呆 れる気持ちがあった。
ユビは気まずさから頭を柔 く掻 き、言い訳というには稚拙 な気持ちを吐露 する。
「なんかまぁ、骨っちゃ骨なんだけど…中身がほんと…小麦粉みたいな感じで…」
苦笑いで場を濁 すしかないユビの様子に、博雪 は何も無かったかのように返事をしてやる。
「あー、なるほど、粉骨したんだね。変わり様が凄いから、お兄さんだった実感が無いって言いたいのかな?」
「そう…なん、だよ…なー。壺 もそこらの雑貨店に有りそうな、小さい花瓶 くらいの大きさだし…」
くしゃりと顔を歪 ませながら、手で骨壺 の形を表現するユビに、博雪 は興味を示す。
「へー。さっきはビックリしたけど、その小ささはちょっと見てみたいかも」
物珍しいといった感覚で発言した博雪 へ、ユビは表情を明るいものに変える。
「え、お。じゃあこれ食べたら、俺の部屋来る?」
「……お兄さん、プライバシーも何も無いね…」
変わり身の早いユビへ、博雪 は僅 かに引いた感情を向けた。
その視線にユビは目線を逸 らすと、取って付けたかのように苦笑いを浮かべる。
そしてどうにか話題を変えようと、話している間に溶けたアイスをスプーンで掬 い、これ見よがしに口 へ運んでは、美味 いとわざとらしく喜ぶのであった。
.
話しながら冷凍庫の引き出しを開け、中からチョコレートのカップアイスクリームを取り出すと、それをユビに手渡す。
ユビはそれに着いて行く形で、
そして互いにスプーンを手に持つと、紙製の
「日記なー、見せるって言っても大したこと書いてないんだよ、兄さん」
「……もしかしてユビが日記持ってるの?」
「うん。そりゃまぁ、アルバムも作らない親だしな。団地の
「…
「んー、でも、心不全で吐いて
「それが
「だな。まぁ当時の俺が死因を聞いたところで、理解するってのは難しかったと思うけど」
「……そう…」
「ただ、俺も借り暮らしには変わりないから、兄さんの形見ってなると小さい物がスペース的に精一杯。親も骨だけはどうしようもなかったっぽくてさァ……墓が無いから手元
「え」
瞬間、
「え、見る?」
「――……じゃなくて、そういうことは
「お…あ、言わなきゃダメだったのか。ごめん…知らなくて……」
「いや、かなり
「……ごめん…」
「うん…まぁ、次は無いとは思うけど、注意しなね…」
しかし
ユビは気まずさから頭を
「なんかまぁ、骨っちゃ骨なんだけど…中身がほんと…小麦粉みたいな感じで…」
苦笑いで場を
「あー、なるほど、粉骨したんだね。変わり様が凄いから、お兄さんだった実感が無いって言いたいのかな?」
「そう…なん、だよ…なー。
くしゃりと顔を
「へー。さっきはビックリしたけど、その小ささはちょっと見てみたいかも」
物珍しいといった感覚で発言した
「え、お。じゃあこれ食べたら、俺の部屋来る?」
「……お兄さん、プライバシーも何も無いね…」
変わり身の早いユビへ、
その視線にユビは目線を
そしてどうにか話題を変えようと、話している間に溶けたアイスをスプーンで
.