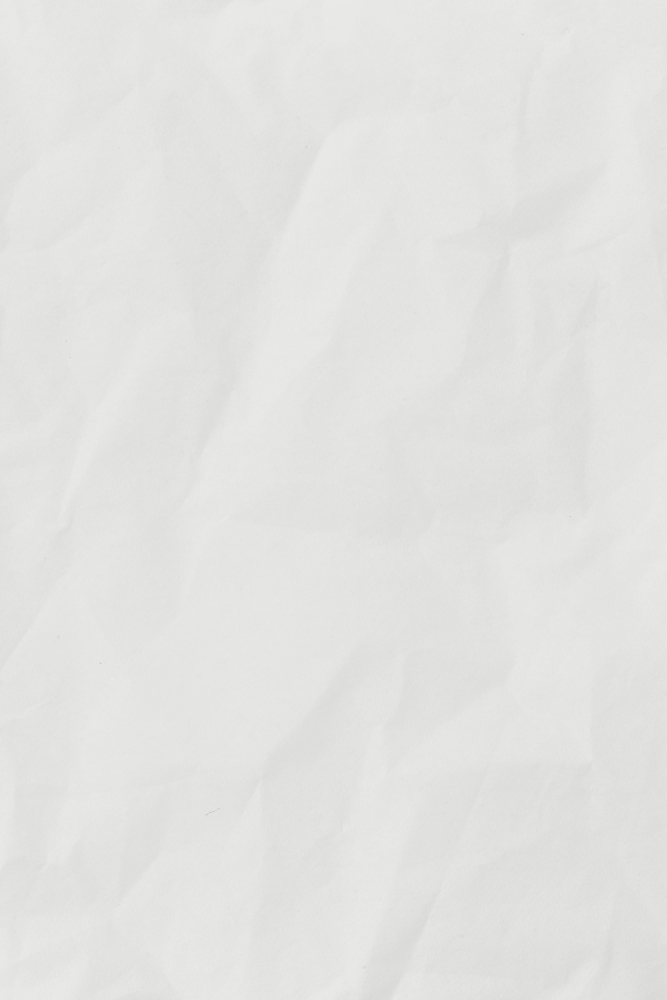ユビと博雪
陽が落ちきる手前、ユビは腰ポケットから型落ちしたスマートフォンを取り出し、時刻を確認する。
そして液晶画面をたっぷり数秒見つめてから大きく一息吐くと、一度顔を上げ、また一姫の遺体が倒れていた場所へ視線を向けた。
考えずとも知っていることがあったと、その事実を思い出し、小さく一笑してユビは博雪に向き直る。
そもそも、博雪の誘いを断る理由をユビは持っていないと気付いたのだ。
「中学卒業したら、赤松さんのお店で働かせてくれます?」
ユビの薄っすら浮かべる微笑みに、博雪の表情は漸く動いた。
その表情は今の今まで空白と表現する他なかったのに、僅かに口角を上げる笑みはどこか無気力で、何かを諦めているようにも見える。
意想外な博雪の笑顔にユビは目を丸くした。
「赤松さん?」
「…あぁ、ごめん。働いてくれて勿論いいよ。むしろ早い答えだったけど、何か決め手でもあった?」
少し覗き込む様に博雪から訊ねられ、ユビは困ったように笑い直す。
「俺も、こんなに暗くなっても心配のメールひとつ寄越さない親がいる環境、嫌だなって思っただけですよ」
この一言こそ、ユビがユビ自身に持つ価値。
一姫が行方不明になった時も、親は自発的に探しに行かなかった。
それを思い出した瞬間、笑って誤魔化したつもりでも、鳩尾に穴が空いたような気がした。
なら自分だって親に探してもらえないし、働く為に必要な金は要らないと言えばきっと快く見送られるだろうと、ユビは結論付ける他無い。
〝そういえばそうだった。自分とは、そんなものだった〟
それがユビの答えであった。
◆
そして時は戻り、2017年の梅雨、ユビと博雪は共に暮らしている。
空になった晩ご飯の皿たちを、2人はテーブルからシンクに移動させようと重ねていた。
カチャカチャと陶器やプラスチックが重なる音がダイニングに響く。
博雪の予想通り、ユビはいつもより少し多く盛られたご飯各種をぺろりと平らげた。
育ち盛りゆえか、どれだけ食べても足りないのだろう。
それでも食べ過ぎは良くないと博雪も栄養バランスに注意しているので、ユビはあまり体重の増減や体調不良を経験していない。
――勉強もアルバイトも家事も、体力が必要であることを無意識に理解しているユビは、食べたら食べただけ動く健康的な青年となっていた。
買い物をすれば必ず重いものを持ち、参考書や筆記用具等を求めては平気で数kmくらい歩く。
今も博雪より皿を持ってキッチンに移動し、それらをシンクへ置いていく。
博雪は動き続けるユビの横を通り抜け、エプロンを身に着けるとシンクへ戻り、スポンジで食器用洗剤を泡立てた。
ユビの置いた食器や器具を順々に磨いては流し、設置された乾燥籠へ置いていく。
少ししたらユビがタオルを手に持ち、籠に収まらないものを拭いていった。
この形は2人が同居しだしてからすぐ出来上がった形だ。
そうして習慣化した動作を2人で行いながら、ふとユビが博雪へ話し掛ける。
「そういえばさ、もう俺がここに住みだして2年目だけど、俺いつ頃引っ越したらいい?」
「…どうしたの急に」
「いやさ、俺あの時さ、進学の事とか親のことで頭いっぱいだったからさ。なんつーか、今思うと博雪に逃げ道っていうか…抜け道教えてもらった感じだし、さすがに卒業した後は就職先探すから」
「あー…うん、そうだね。就職活動するって言うなら、そんなに時間無いね」
「って言っても、まだどんな仕事したいとかは決まってないけど」
「だったら決まるまで居ればいいのに」
「またそうやって簡単に言う」
「簡単だからね」
話している内に博雪は洗い物を終え、布巾でシンクを綺麗にしていく。
それが済むとエプロンを外し、ユビに拭かれた皿たちを所定の位置へ戻していった。
ユビはその間に使用した複数のタオルをひとまとめにして、洗面所に設置された洗濯機へそれらを持って行く。
キッチンの隣に洗面所があるので、ユビは10秒もしないで博雪の隣に戻った。
そんなユビに博雪は首を傾げて訊ねる。
「ユビは僕との生活、卒業と一緒にやめるつもりだったの?」
「へ?」
淡々としたいつもの声。
だが、博雪の言葉はユビにとって意外なものだった。
――博雪はいつも、ユビの意見に否定も肯定もしない。
ただ頷き聞くだけで、そこに感情が見えることはあまり無い。
博雪のこの一言が意味するところを知る由も無いが、ユビは前向きに捉えることにした。
「…本当に卒業してからも居ていいのかよ」
「そもそも、そのつもりだったけど」
「え」
「だってあの時、僕言ったでしょ。働いてくれるなら居候していいって」
当然のように出会った時の話を引き出してくる博雪に、ユビは少しばかり目を見開いて黙った。
「ユビがこの生活を嫌なら僕は何も言わないけど、別にそうじゃないなら自立できる貯金が溜まるまで居ていいんだよ?」
緩く首を傾げたまま与えられる気遣いに、ユビは眉尻を下げ、弱々しい笑みを博雪に向ける。
それは嬉しさや照れ、困惑を誤魔化すものだ。
しかしその心境を博雪に悟られたくなくて、壁を作るように腕を組む。
「相変わらず、メリット少ないこと言うよな」
「まぁ、まだユビがどんな大人になるか分かんないって言うんだから、僕の興味は続いてるわけだし。渡りに船くらいでいなよ」
「あしながおじさん?」
「そんな良いものじゃないかな」
ユビの目線から逸れるように、博雪はスッパリと言い捨てると冷蔵庫へ移動する。
.