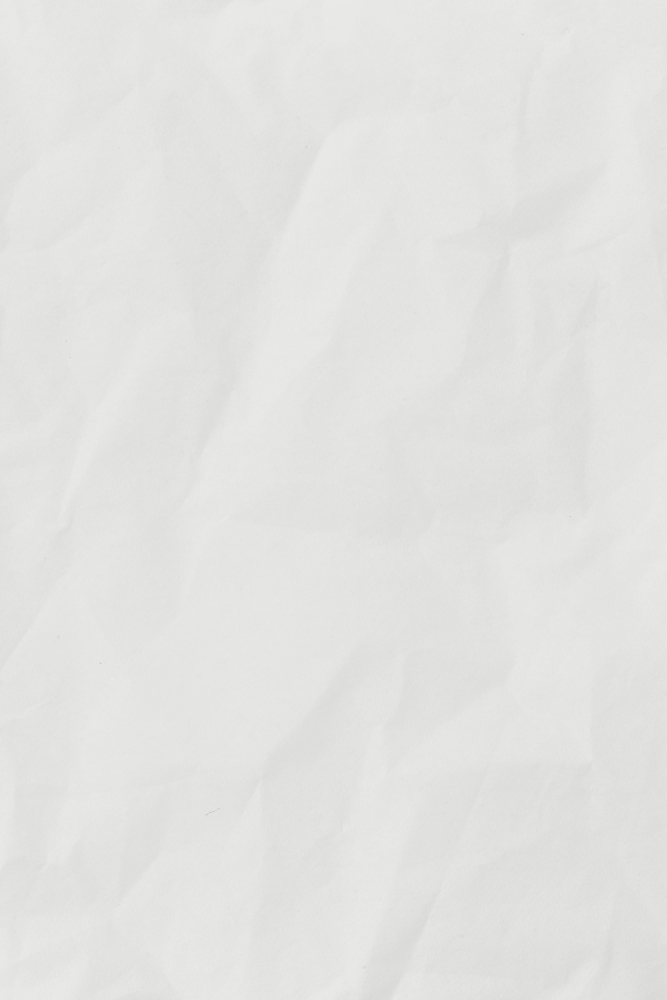ユビと博雪
実は
(いやでも服装は
どうでもいいであろう子供の身の上話を聞いたり、焼き鳥を
そして
くたびれた制服は
多少髪がパサついているものの、黒の中に僅かな緑の光沢が見える。
細身であるのが家庭環境の影響なのか食の好みなのかは不明だが、一般的な価値観で考えると、持て
(…多分、知らないだけで少なからず白人の血が入ってるんだろうな。やっぱり骨格から違う)
だがユビの外見的
どんな人間であっても愛情を受け取っていれば、身なりや表情、仕草や言葉遣い、身に
例え独りで生きているのだとしても、独りで生きられるまで育てた誰かが必ずいる。
だが、
ユビを通して見える愛情というものは、腰ポケットに入っているスマートフォンくらいだろうか。
だがそれも、ユビが働きだせばどうなるのだろうと考えるまでもない……気すらする。
それなのにユビという少年は、怒りも
そしてそれを誰に相談するでなく、見ず知らずの中年に泣きながら話す。
同年代の友達といった存在は、一切語られていない。
それが
――
子供は愛情を与えてもらう為に構ってほしいと泣き、子供自身が成熟すれば、いつの日か義務になるのは親の方だというのに。
兄弟や姉妹といった存在がいれば、家族の関係や形はまた変わっていくというのに。
完成しない形を時間をかけて築いていくからこそ、他人は家族になれるというのに。
そんな移り行き変わっていく愛情を
(……何なんだろうね、本当。お前の人生は)
――面白くないのなら、面白くなってほしい。
ユビという少年がこれからどうしてみたいのか、
〝もし家族から離れることが出来て、己が背負うものも最小限になった時、この少年はどうなるのだろう〟
たったそれだけ。
だからこそ、たったそれだけが知りたい
「…ねぇ、もし働いてくれるなら僕の部屋に
「……いそうろう…?」
「住んでいいってこと。親の目から離れられるから、通信制高校にだって通いやすくなるんじゃない?」
「え!」
「当然だけど給料は出すし、それを学費に
「あ、え、でも、それ」
「なに?」
「
だが
メリットが少ないだなんて
「僕のメリットかー…そうだなー…うん。確かに少ないね。でもそれで困ることも無いし、減るものももう無いんだよね」
「…減るものが、無い?」
「無いよ。僕はユビ君がどんな大人になるのか、少し興味があるってだけだから」
またも淡々とした声と動かない表情筋で話す
どうやらこのどこにでもいそうな男は、どこにでもある価値観だけで生きているわけではないらしい。
生き物として思考が違うのなら、否定も肯定もしないのは当然のことなのかもしれない。
だからこそ、ユビにとって
ユビにもまた、自分と真反対の人生というのはどういうものだろうかと、ぼんやりした疑問が浮かぶ。
――このどこにでもいるオッサンは、自分の
決して短くはない時間の中で色々と話したからか、ユビの思考は迷宮に入ろうとしていた。
まとまらない感情や隣に居る都合の良い条件を出してくる
ぐるぐると頭の中を回る決めなくてはならない悩みや考えに言葉を失っている間、ユビは顔を上げ無言である一点を見つめる。
そこは兄である
(…兄さん……)
心で呼び掛けて
気が付けば長居していたせいで、
夜の
.