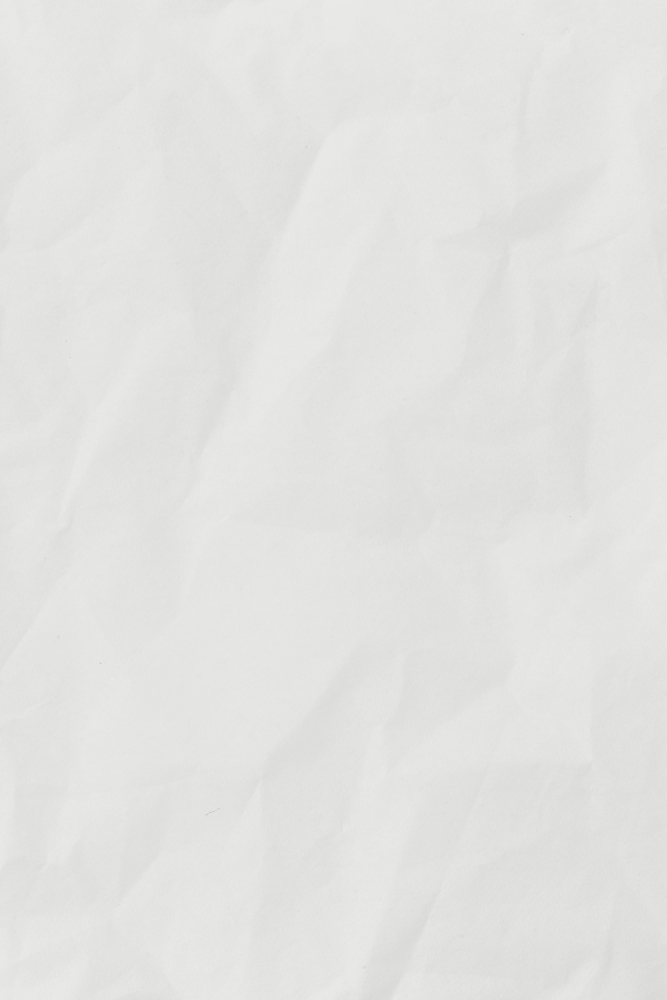ユビと博雪
突然の出来事に博雪 は鳩 が豆鉄砲を食ったような顔をし、身動きが取れなくなる。
だが、はらはらと落ちていく子供の涙に、どうしたのかと心配する引き出しを持ち合わせていなかった。
なんとも居たたまれない中、ユビは自分の乱れた情緒 を早く整えるため、顔をくしゃくしゃにしながらも深呼吸に尽力 する。
何度も何度も深呼吸を繰り返し、少し垂 れた鼻水を荒々しく手の甲で拭 った。
その様子を博雪 は気を揉 みながら見守るしか出来ない。
奇妙 な沈黙 が流れるが、それもユビが泣き止 むことで終わりを迎える。
「…急に泣きだして、すみませんでした……」
「あ、うん。驚いたけど…えっと……どうしたの…?」
博雪 の問いに、ユビは鼻をすすりながら自嘲 の笑 みを浮かべ、答えを話しだす。
「俺、今、中3なんですけど…その、進学できそうになくて…」
「え」
「同級生はみんな夏期 講習とか行くらしいんですけど、その、俺ん家 とにかく貧乏で。俺自身も推薦 とか免除 とか貰えるほど頭良いわけでもなくて……」
「…はー」
「両親にも…特に進学は望まれてなくて。働いて家に金を入れるようには言われてんですけど……」
「はー…」
「俺なりに通信制の高校ならどうだろって調べてるんですけど…多分親にバレたら、その、行くだけ無駄とか言われそうで…」
「はー…」
「なんか、もう、全部、情けなくて。優しくされて、なんか、爆発して――……」
段々と小さく弱々しくなるユビの答えに、博雪 は相槌 を打って残りのビールを飲み干す。
そうして空 になった缶をユビとの間に置くと、残りのビール缶を片手で開けた。
博雪 の淡泊な言動に自身への無関心を感じ取ったユビは、自嘲 を繰り返す。
「――…どうでもいいですよね、こんな、俺なんかの話」
眉を下げ、泣かないよう無理矢理に笑うその顔を、博雪 は焼き鳥をもう一度差し出すことで困惑 の表情に上書きした。
「訊 いたのは僕だよ。どうでもいいことないから、その顔やめて」
「え」
「取り敢 えず食べて。まぁ僕の食べさしで悪いけど」
「…は、い……」
押しの強い博雪 にユビは気圧 され、両手に食べかけの焼き鳥を持つこととなる。
言われるまま、それらをおずおずと食べ進めるユビを眺め、博雪 はビールを呷 った。
そうして2人が飲食を終える頃、辺りは仄暗 くなっていた。
出会ってからそれほどの時間が過ぎていたのかとユビが空を見上げると、酔った素振りの無い博雪 が空き缶をナイロン袋に詰めだしていた。
既 に入れられていた焼き鳥のゴミを下敷 きに、分別などせず、そのまま大雑把 に取っ手部分が結ばれた袋が博雪 の細い手首に掛けられる。
この会話もお開きになる気配 を察したユビは、不慣れながらも博雪 へ会釈 した。
「あ、その、ごちそうさまでした。何か、お返し…」
「要 らないよ」
「そ、です、か…」
出会ってから短い時間の中、博雪 の薄情にも見える受け答えは、ユビの知っている学校の誰とも被 らないもので新鮮だった。
あまり感情が見えない声と、動かない表情筋。
突き放すような冷たい言葉だと思えども、他人に尽くす態度が色濃くて、不思議と嫌ではない。
(…このままお別れかな……)
会話している間、ユビが諦めていることを博雪 は何も否定することなく聞き続け、そして肯定もしなかった。
無関心と感じたのはそれこそ期待の表れで『どうでもいいことない』と伝えてくれたことが、ユビには欣幸 の瞬間であったのだ。
そんな愁 いを帯 びたユビの横顔を他所 に、博雪 はベンチから立ち上がる。
すると視線を少しだけユビに向け、感情の色が無い声で話しかけた。
「お返しは要 らないけど、ひとつ答えてくれない?」
予想していなかった博雪 からの問いに、ユビは慌てて顔を上げる。
「え、はい、なに?」
「ユビ君、中学卒業したら僕のお店で働かない?」
「――……へ?」
唐突な博雪 からの誘いに、ユビの間抜けな息が漏 れる。
働かないかと言った割に読み取れない空白のような表情は、沈む太陽がみせる藍 と橙 の光に照らされていた。
博雪 の言葉の意味を上手く受け取れなかったユビの答えを急 かすかのように、夜の帳 は静かに幕を下ろしていく。
ユビがひとつ呼吸をする度 に、橙 の光が鳴りを潜 めていくのが分かる。
緩 やかに辺りが暗くなっていき、宵闇 が夕間暮 れへ迫った。
時間にすれば短いのかもしれないが、ユビの答えを待つ博雪 には長く退屈に思えるものだ。
当のユビも博雪 の誘いに何も答えられず、上げていた顔をいつの間にか下げていた。
(無理も無いか)
博雪 はユビの様子に小さく息を吐 き、またベンチに腰を下ろす。
「…別に今すぐ答えてほしいわけじゃないから、ゆっくりでいいよ。答えてくれるって約束してくれるなら、また会いに来るから」
「あ…その……」
「僕がユビ君ならその環境が嫌だなって思っただけだし、僕とは真反対な家庭環境なのも気になっただけ」
「――え…」
「僕、裕福なんだよね。僕の世代だとそんなに多くない専門も出てるし…色々とあったけど、苦労らしい苦労は多分経験してない」
じわじわと蒸れる暑さの中、博雪 からの突然の告白に、ユビは眩暈 を覚える。
隣にいるオッサンは、一体何者なのだろうか…――と、今更な疑問が湧いたのだ。
.
だが、はらはらと落ちていく子供の涙に、どうしたのかと心配する引き出しを持ち合わせていなかった。
なんとも居たたまれない中、ユビは自分の乱れた
何度も何度も深呼吸を繰り返し、少し
その様子を
「…急に泣きだして、すみませんでした……」
「あ、うん。驚いたけど…えっと……どうしたの…?」
「俺、今、中3なんですけど…その、進学できそうになくて…」
「え」
「同級生はみんな
「…はー」
「両親にも…特に進学は望まれてなくて。働いて家に金を入れるようには言われてんですけど……」
「はー…」
「俺なりに通信制の高校ならどうだろって調べてるんですけど…多分親にバレたら、その、行くだけ無駄とか言われそうで…」
「はー…」
「なんか、もう、全部、情けなくて。優しくされて、なんか、爆発して――……」
段々と小さく弱々しくなるユビの答えに、
そうして
「――…どうでもいいですよね、こんな、俺なんかの話」
眉を下げ、泣かないよう無理矢理に笑うその顔を、
「
「え」
「取り
「…は、い……」
押しの強い
言われるまま、それらをおずおずと食べ進めるユビを眺め、
そうして2人が飲食を終える頃、辺りは
出会ってからそれほどの時間が過ぎていたのかとユビが空を見上げると、酔った素振りの無い
この会話もお開きになる
「あ、その、ごちそうさまでした。何か、お返し…」
「
「そ、です、か…」
出会ってから短い時間の中、
あまり感情が見えない声と、動かない表情筋。
突き放すような冷たい言葉だと思えども、他人に尽くす態度が色濃くて、不思議と嫌ではない。
(…このままお別れかな……)
会話している間、ユビが諦めていることを
無関心と感じたのはそれこそ期待の表れで『どうでもいいことない』と伝えてくれたことが、ユビには
そんな
すると視線を少しだけユビに向け、感情の色が無い声で話しかけた。
「お返しは
予想していなかった
「え、はい、なに?」
「ユビ君、中学卒業したら僕のお店で働かない?」
「――……へ?」
唐突な
働かないかと言った割に読み取れない空白のような表情は、沈む太陽がみせる
ユビがひとつ呼吸をする
時間にすれば短いのかもしれないが、ユビの答えを待つ
当のユビも
(無理も無いか)
「…別に今すぐ答えてほしいわけじゃないから、ゆっくりでいいよ。答えてくれるって約束してくれるなら、また会いに来るから」
「あ…その……」
「僕がユビ君ならその環境が嫌だなって思っただけだし、僕とは真反対な家庭環境なのも気になっただけ」
「――え…」
「僕、裕福なんだよね。僕の世代だとそんなに多くない専門も出てるし…色々とあったけど、苦労らしい苦労は多分経験してない」
じわじわと蒸れる暑さの中、
隣にいるオッサンは、一体何者なのだろうか…――と、今更な疑問が湧いたのだ。
.