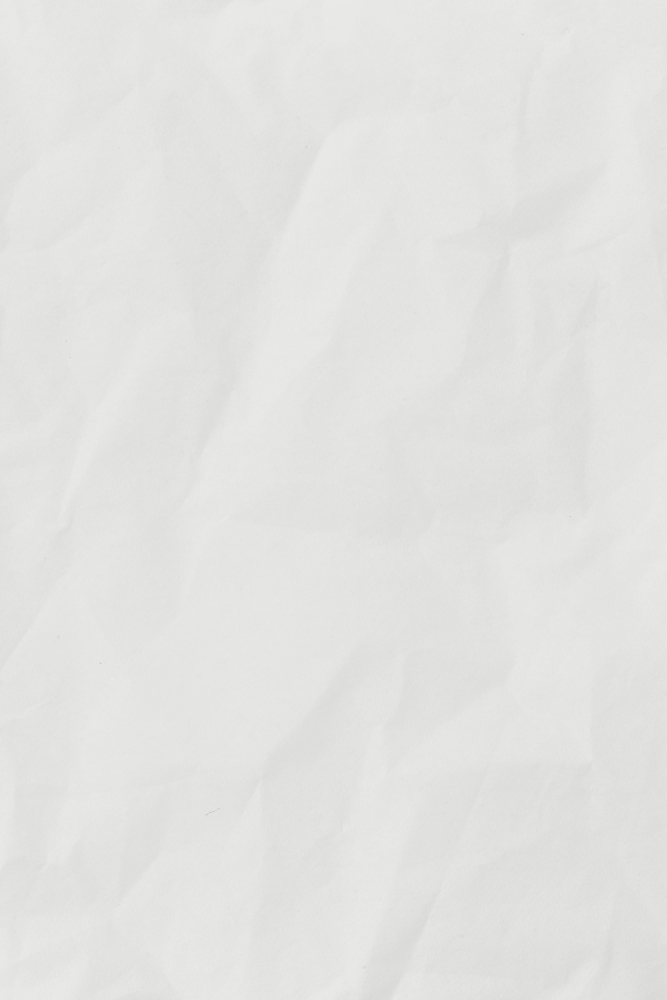ユビと博雪
✦ 表紙イラスト
S の退店後もう一度店を開けるも客は来ず、それから間も無く閉店時間を過ぎたので、ユビと博雪 は帰路へ着いた。
アーケード商店街の端にある喫茶店『赤松 』から徒歩10分程の所に、2人が同居する築10年の8階建てマンションがある。
その内の一室 となる2LDKに元々博雪 が住んでいたので、ユビが居候 している形だ。
2人はマンション内にある掃除の行き届いたパブリックスペースを抜け、エレベーターに乗り、5階のボタンを押す。
下りてきた少人数用のエレベーターに乗り、数秒棒立ちのまま上階に運ばれ、共用廊下を歩いてすぐ辿り着く端の一室――501が博雪 の部屋だ。
ユビが玄関を解錠 し、2人はリビングへ入ると電気を点 けた。
「ただいまー」
「おかえり」
そしてユビの挨拶に博雪 が返す。
これがいつの間にか2人の形となっていた。
帰ってきてすぐ、2人は順番に洗面所で手洗いをする。
それが済めばそれぞれ自室で私服に着替え始めた。
ユビは薄緑 色を基調 とした、上下セットになっているユニセックスサイズの緩 やかな半袖と、7分丈 パンツを身に付ける。
上着の肩部分とズボン横側面には、白いラインがデザインとしてあしらわれていた。
博雪 は灰色を基調とした半袖に黒色の長パンツを身に付けると、部屋から出てキッチンへ向かう。
慣れた手付きでエプロンを着用し、ユビがクーラーのスイッチを入れてから洗面所に向かうのを背後に、冷蔵庫を開けた。
博雪 により早速キッチンで晩ご飯の準備が開始されると、洗面所ではユビがドラム型洗濯機で乾燥までされた衣類を畳 む作業が開始された。
日頃の習慣か、2人は黙々 と家事に勤 しんだ。
そうして20分もするとユビは作業を終え、ある程度のものを指定の位置に仕舞い、それぞれの部屋に置く2人分の私服を抱えたままリビングに顔を出した。
するとコトコトと鍋が煮える音が小さく耳に響き、醤油 と生姜 の豊潤 な香りで鼻の奥が刺激 された。
食欲をそそるそれに、ユビはうきうきと博雪 へ声を掛ける。
「博雪 ~、今日の晩ご飯何?」
「昨日仕込んでおいたから、豚の角煮」
ユビに振り向きもせず、博雪 は茄子 を切りながらメニューを告げる。
そんな博雪 の背後で、ユビは喜悦 の色を満面に浮かべる。
「嬉しいのは分かったから、早く洗濯物置いておいで」
「こっち見てないのに、なんで分かんだよ」
副菜の調理をしている前提ではあるが、博雪 が振り向かなかったことに大した理由は無い。
ユビを見ずとも反応が分かるから――それだけだ。
一見 すると冷たいが、ユビは嬉しさをそのままにして博雪 の態度を気にせず、互いの部屋へ洗濯物を仕舞いに行く。
バタバタと響く低音は、長身の男がせせこましく動いていることを告げていた。
それからユビは自室からリビングに移動し、慣習 となった動作でダイニングテーブルを拭いたり、ランチョンマットを並べだす。
一連の準備が終わったら次はキッチンに移動して、博雪 の邪魔にならないよう冷蔵庫から作り置きのサラダを取り出し、小皿に盛り付けていった。
博雪 はユビの準備に合わせる様に間を置き、温めた作り置きの味噌汁やよそったご飯をキッチンカウンターに置くと、それをテーブルへ移動させるようユビに指示を出す。
すると、ある一点がユビの目に留 まった。
「俺のご飯、いつもより多くない?」
「角煮だしこれくらい食べるでしょ?」
さも分かり切った様子で博雪 から渡されたそれは、今のユビにとって正解だった。
ご飯の量に比例してか、角煮の量も博雪 の皿より少し多く盛られている。
「…たった1年半で俺のこと分かりすぎだろ。なんで結婚してくれる女の人いなかったんだよ」
「生憎 僕の世代は、女が家事して男が外に出て養 う役割分担が当然だったもんでね。どっちも出来ちゃう僕には、奥さんになりたいって言ってくれる人がいなかったんだよ」
「…ははーん? 愛嬌が無いって嫌われたやつ?」
「僕は愛嬌あるでしょ」
「出会った時から割と不愛想だぜ!」
「そんな元気に否定しないでよ。っていうか昔は少し柄の悪い、駄目な部分が目立つ男がモテたの」
「今は?」
「知らない。あとユビが分かりやすいだけだからね、育ち盛りは部活してなくてもよく食べるってのは、お決まりなんだし」
博雪 はユビとじゃれる様な会話もそこそこに、キッチンカウンターへコトンと音を立てて茄子 の副菜の皿を置く。
それをユビにテーブルへ移動させたら、エプロンを脱ぎ、食器棚に付けたコートラックへ掛ける。
ついでに食器棚からグラスをふたつ取り出して、冷蔵庫から麦茶のポットを手に取り、グラスに注 ぐ。
料理で熱くなった手を冷ますように持つと、漸 くテーブルへ向かった。
ほぼ四六時中 同じ時を過ごす2人の食事時間は、いつも「いただきます」と「美味 い」と「ごちそうさま」で埋まっていく。
今更話すことなんてあるのだろうかと思うほど、2人は出会った日から互いをよく見ていた。
.

アーケード商店街の端にある喫茶店『
その内の
2人はマンション内にある掃除の行き届いたパブリックスペースを抜け、エレベーターに乗り、5階のボタンを押す。
下りてきた少人数用のエレベーターに乗り、数秒棒立ちのまま上階に運ばれ、共用廊下を歩いてすぐ辿り着く端の一室――501が
ユビが玄関を
「ただいまー」
「おかえり」
そしてユビの挨拶に
これがいつの間にか2人の形となっていた。
帰ってきてすぐ、2人は順番に洗面所で手洗いをする。
それが済めばそれぞれ自室で私服に着替え始めた。
ユビは
上着の肩部分とズボン横側面には、白いラインがデザインとしてあしらわれていた。
慣れた手付きでエプロンを着用し、ユビがクーラーのスイッチを入れてから洗面所に向かうのを背後に、冷蔵庫を開けた。
日頃の習慣か、2人は
そうして20分もするとユビは作業を終え、ある程度のものを指定の位置に仕舞い、それぞれの部屋に置く2人分の私服を抱えたままリビングに顔を出した。
するとコトコトと鍋が煮える音が小さく耳に響き、
食欲をそそるそれに、ユビはうきうきと
「
「昨日仕込んでおいたから、豚の角煮」
ユビに振り向きもせず、
そんな
「嬉しいのは分かったから、早く洗濯物置いておいで」
「こっち見てないのに、なんで分かんだよ」
副菜の調理をしている前提ではあるが、
ユビを見ずとも反応が分かるから――それだけだ。
バタバタと響く低音は、長身の男がせせこましく動いていることを告げていた。
それからユビは自室からリビングに移動し、
一連の準備が終わったら次はキッチンに移動して、
すると、ある一点がユビの目に
「俺のご飯、いつもより多くない?」
「角煮だしこれくらい食べるでしょ?」
さも分かり切った様子で
ご飯の量に比例してか、角煮の量も
「…たった1年半で俺のこと分かりすぎだろ。なんで結婚してくれる女の人いなかったんだよ」
「
「…ははーん? 愛嬌が無いって嫌われたやつ?」
「僕は愛嬌あるでしょ」
「出会った時から割と不愛想だぜ!」
「そんな元気に否定しないでよ。っていうか昔は少し柄の悪い、駄目な部分が目立つ男がモテたの」
「今は?」
「知らない。あとユビが分かりやすいだけだからね、育ち盛りは部活してなくてもよく食べるってのは、お決まりなんだし」
それをユビにテーブルへ移動させたら、エプロンを脱ぎ、食器棚に付けたコートラックへ掛ける。
ついでに食器棚からグラスをふたつ取り出して、冷蔵庫から麦茶のポットを手に取り、グラスに
料理で熱くなった手を冷ますように持つと、
ほぼ
今更話すことなんてあるのだろうかと思うほど、2人は出会った日から互いをよく見ていた。
.
1/7ページ