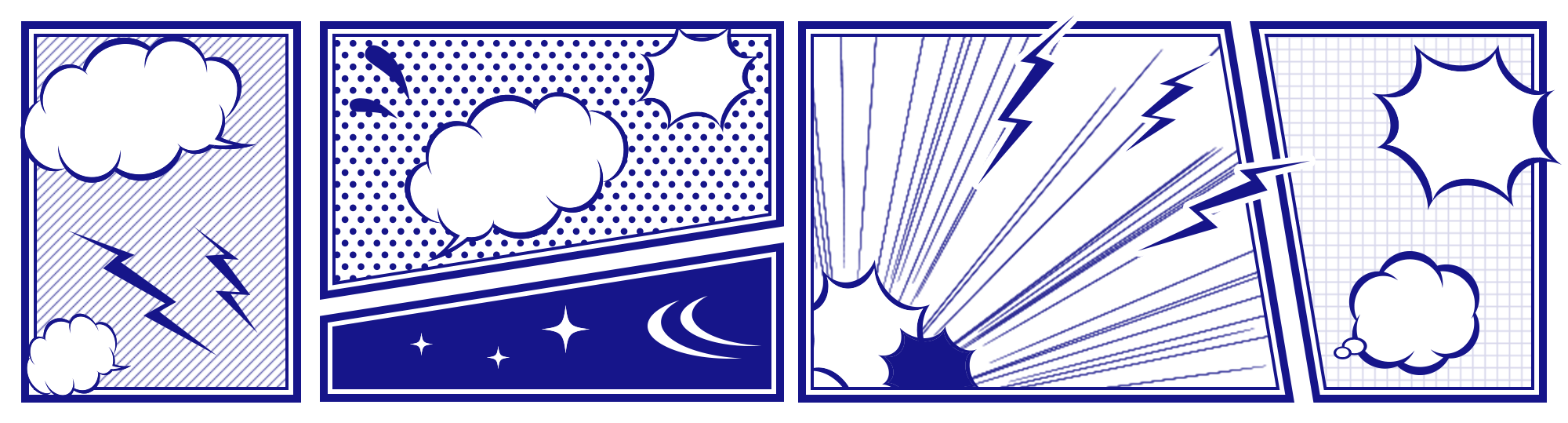ショータイムの終演後
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
外は大粒の雨が降っている。天気が悪くなることはわかっていたので事務所は早々に閉めたし、真宵ちゃんはハナから来なかった。
仕事帰りに事務所に寄ってくれた名無しちゃんに「この天気のなか帰るのは大変だろうからここに泊まったら」なんて言おうとしたときのことだ。
「着ぐるみショー、成功してよかったね」
そう話をふられる。一週間くらい前、着ぐるみショーの代役を務めたのだ。
彼女の言うとおり、それは成功した。次回からは少し休演にして、その間に新しい役者がくるらしい。
ぼくも一応役者志望だったし。それなりに役目を果たせたと思う。……まあ、ぼくが目指していたものとは全くベツモノだけど。
「うん、どうなるかと思ったけど無事終わってよかっ……」
そこで気づいた。どうして、彼女が着ぐるみショーのことを知っているんだ……?
確か、あの事件に彼女は同行していなかったし、着ぐるみショーの話もしていない。
「な、なんで知って……」
「なに? 知られたらマズいことでもあるの?」
「いや、ない、けど……」
「……ふうん」
「…………」
「勾玉、つきつけてあげようか」
「……ま、真宵ちゃんから、聞いた……?」
「司会のお姉さんにデレデレしてた話のこと?」
「あ、あの、名無しちゃん、それは」
「成歩堂くんが可愛い女の子に弱いのは知ってるし? 今更、別に気にしてないよ」
……絶対ウソだ。突き刺さる視線が痛い。
ぼくも所詮男だし、どうしてもああいうタイプの女の子は気になっちゃうというか、あくまで一時のモチベーションのためであって。本気で好きになったのではない、本命は名無しちゃんだ。
うう、やっちまった、悪手だった。自分が悪い。
……いや、脚本が悪い! 違法だ! 訴えてやる!
ただそれを目の前で怒り心頭であろう彼女に言うこともできず。
何も返せないぼくに彼女は指折りながら続ける。
「……セクシーな松竹梅世さん」
「うぐっ」
「……可憐な美柳ちなみさん」
「うぐぐっ」
「……そして今回は一生懸命で可愛い司会のお姉さん」
「うぐぐぐっ」
「知られたらマズいことなんて、ないんだよね? 何でそんなに冷や汗かいてるの?」
「え、ええと」
「ま、成歩堂くんのタイプわかりやすいもんねえ。可愛い系というか、あざとい系というか」
……私とは、違うタイプ。
そう口にすると同時にふっと視線を落とした彼女を見て、傷つけてしまったことを痛感する。
岡崎さんの助けにはなりたいと思った。
正直、前の彼女に似てて可愛いとも思った。……もう一度言うが、これは脚本に文句を言って欲しい。
とにかく、名無しちゃんに怒られた今でも、着ぐるみショーの手伝いだってやってあげて良かったと思っている。後悔はしていない。
彼女もそのこと自体には怒っていないはずだ。
岡崎さんには、どんなにコミカルな演技を見られても恥ずかしくはない。
でも、ゆるい着ぐるみを着てる姿はきみに見られたいものじゃない。
そういう違いをわかってもらいたいがどう伝えたらいいだろうか。
頭を悩ませたとき、外がピカッと光った。
まさか、と思って外を見た途端、ガラガラと大きな音が鳴る。
「あ、雷」
「うわあっ……!」
耳をふさいでその場にしゃがみこんだ。
勘弁してくれ、彼女の前でこんな情けない姿を見せたくない。
心ではそう思っても、体は固まってしまって動かせない。
「ううう……」
「……成歩堂くん」
呼びかけられたのでそろそろと顔をあげると、名無しちゃんはいつの間にかソファに座っていた。
そして、おいで、と手を広げる。
呆れた表情のままで、かつさっきまで怒っていた彼女の行動に戸惑っていると、「ほら」と再度促される。
おずおずと横に座ると、両手で頭を抱きかかえられた。
されるがまま、彼女の胸元に頭を預けると、手近にあった薄手のブランケットを頭から被せられる。
再び雷の音がすると、名無しちゃんがポンポンと、子供をあやすように背中を叩いてくれる。
「女の子にも弱けりゃ雷にも弱いなんて」
「ス、スミマセン……」
「どうしようもな……あ、光った。落ちるよ」
背中をぎゅっと抱かれた数秒後、ドーン! と大きな音がした。
「ひっ……!」
「……知らなかったな、雷怖いこと」
身を固くしたぼくの背中を優しくさすってくれる。
「……キライになった? ぼくのこと……」
「嫌いになるわけないでしょ」
ブランケットに隠れたままおずおずとそう聞くと、凛とした返事がすぐに返ってきた。
「成歩堂くんが他の女の子に目移りしたって、雷を怖がっていたって、好きなままだよ。私の気持ちは変わらない」
「誤解なんだ、名無しちゃん!」
バッとブランケットを外して彼女の顔を見る。
突然のぼくの行動に驚いたのか、ぱちぱちとまばたきをした。
「た、確かに、あの子は可愛いと思うけど、それはあくまでテレビの芸能人とかに思う感覚と一緒で」
「…………」
「きみの方が可愛いし、好きだ」
「…………」
「あの子に恋愛感情なんか、持ってなかっ、たっ!?」
一瞬光ったあと、ドーン! と音がして再びぼくはブランケットに隠れる。
彼女の誤解を解いていた途中だったのに! いや、顔を見るのが怖いからこれはこれで助かった気もす……いやいや、ダメだろ、そんな卑怯な考えは。
そう思っても彼女が無言であるうちは、どんな顔をしているのか確認する勇気が出ない。
「……仕方ないなあ」
そんな声と共に背中をまたさすられる。
「誰かを助けようと一生懸命になるところ、大好きだけど。……大好きだけど、寂しくなるよ、時々」
「……名無しちゃん」
「成歩堂くん、他の人のために頑張りすぎ」
「そう、かな」
「そうだよ。……まあ、やめてって言ってもやめないだろうし、そもそも理解してくれないだろうから」
「…………」
「だから、成歩堂くんを怒るのも、許すのも、こうやって甘やかすのも、私だけにして」
「名無しちゃ……うぶっ」
ブランケットを取って彼女の顔を見ようとしたが、上から押さえつけられて叶わなかった。
だが、なんというか、悪い気はしない。だって彼女はヤキモチ妬いてくれたってことで……あ、いや、反省はしてる!
もちろん反省はしているが、とりあえず彼女の体に腕を回してお言葉通り甘えることにした。
雷の日も、悪くない。
1/1ページ