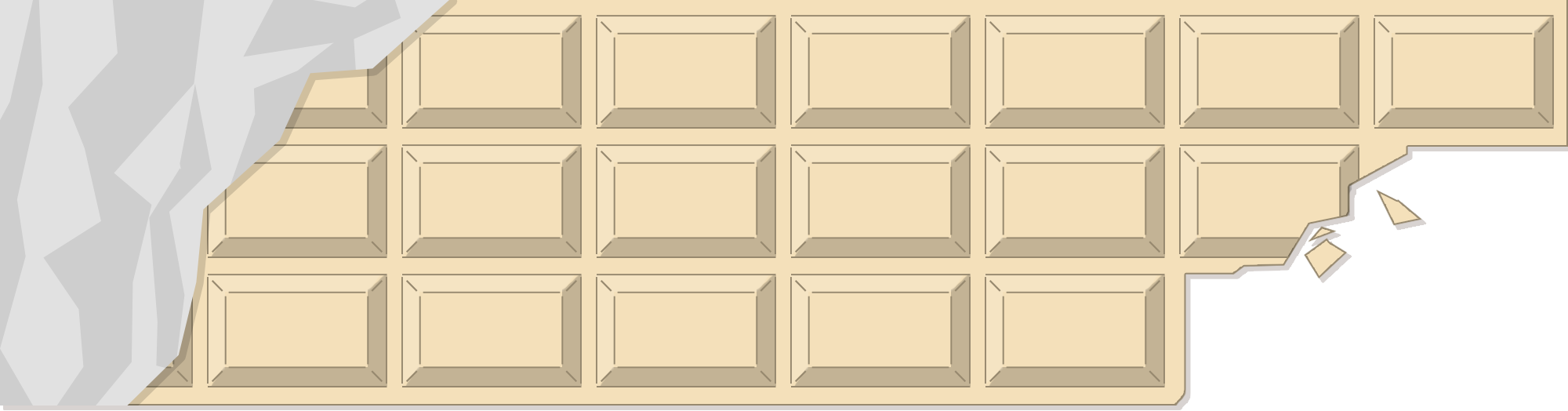味変
所轄から戻った土門は藤倉の元へ顔を出し、そろそろ日が傾き始めた頃、屋上へ上がった。
そこには先客がいた。
一人はマリコ。
そしてもう一人は、珍しく宇佐見だった。
「土門さん!」
いち早く気づいたマリコが声を上げる。
「よお」
「土門さん、お疲れさまです。ではマリコさん、先に戻っていますね」
如才のない宇佐見は、土門に軽く頭をさげると屋上から出ていった。
「すまんな、邪魔したか?」
「何のこと?」
相変わらず察しの悪い女だ、と土門は苦笑する。
「宇佐見さんと話があったんじゃないのか?」
「ううん。これをもらっただけよ」
「ホワイトデーか?」
「ええ」
そこまで答えて、急にマリコはバツの悪そうな顔をした。
「どうした?」
「………土門さん、ごめんなさい」
「榊?」
「私、土門さんにはチョコレートを渡していないわ」
「お前のことだ。一つ買い忘れでもしたんじゃないのか?俺は気にしてない」
大嘘の大見栄だ。
「気にして…な、い、の?」
「ああ。そういえば、蒲原も藤倉部長も貰っていたようだな。あと君嶋にも渡したのか?」
「………………気にしてるじゃない」
マリコはくすっと笑いを漏らした。
「あのね、土門さんにチョコレートを渡せなかったのには訳があるのよ」
「どんな訳だ?」
ぜひ聞きたいものだと、土門は腕を組んだ。
「バレンタインは、いつも仕事でお世話になっている人たちへ感謝をこめて、全員に同じチョコレートを用意したの」
土門は黙って頷く。
「チョコレートを買うときに、ふと思ったのよ。確かに土門さんにはいつもお世話になっているわ。だけどお世話になったお礼として、みんなと同じものを渡すのは、何となく…違う気がして、別のものを用意しようと考えたの。でも何を渡そうか悩んでいるうちに、バレンタインが過ぎてしまったわ」
マリコが真面目に説明している隣で、腕を組み仁王立ちしていたはずの土門は手で口を覆っていた。
そして、その両耳は真っ赤だった。
「土門さん、聞いてる?」
「………………聞いてる」
「なあに?私、何か変なこと言った?」
「いや、変、ではないが…」
「?」
マリコは訳がわからず、訝しげな顔をしている。
「お前、自分が何を言っているのか、自覚がないのか?」
「何って、土門さんにだけバレンタインを渡せなかった理由でしょ」
「確認するが、“俺にだけ”渡せなかったんだよな?」
「ええ」
「その理由はみんなと同じチョコレートを俺に渡すのをためらったから、なんだよな?」
「そうよ」
「つまりそれは、お前にとって俺が、宇佐見さんや蒲原たちとは違う…“特別な存在”だということじゃないのか?」
「………………」
ここにきてマリコも何か、自分が重大な局面に立ち合っているらしいと気づき始めた。
「それは。………なぜだ?」
「………………」
「答えてくれ、榊。お前の返事次第では、俺のこれからの人生が変わる」
「そんな大げさな」
「大げさじゃない。大切なことだ。お前の口から、お前の言葉で、声で、聞きたい」
「私…」
『土門さん』という存在の重さを、マリコは比較してみることにした。
科捜研のメンバーや、蒲原、藤倉部長と比べてみたらどうだろう。
みんなのことは信頼しているけれど、土門ほど安心して背中を預けることは難しい、そう感じた。
では、両親とではどうだろう。
「大切さ」という面では正直、甲乙つけがたい。
でも、『質』が違う。
どう大切なのか、その性質が土門と両親では違うのだ。
最後にもう一人。マリコは別れた相手と比較してみることにした。
一度は愛した相手、拓也と土門さんなら…。
両親同様、二人に対する気持ちは似ている。
両親は、『質』が違った。
けれど拓也と土門では『質』は同じだ。
違うとすれば、それは…『想いの深さ』だろうか。
若さゆえの勢いはないが、今はもっと静かで、それでいて、永く消えることのない情熱の欠片のようなものを、マリコは土門に抱いていた。
すると突然、その欠片はコロンとマリコの口から飛び出した。
「私、土門さんのことが好きなのかしら?」
「………俺に聞くなよ」
土門は「はぁ」とため息をつき、今にもしゃがみこんでしまいそうだ。
「自分で自分の気持ちがわからないのか?」
「わからない、というか、確信が持てないの」
「俺は、そうであったらいいと思う」
「え?」
「お前が俺のことを好きだったらいいと思っている」
「私は…」
「逆にお前はどうなんだ?」
「え?」
「お前は、俺がお前に対してどんな気持ちを持っていたら嬉しいんだ?」
「私に対する気持ち…」
今度はマリコが自問する。
土門さんと一緒に仕事をするのは楽しい。
刑事と科学者という垣根をこえて信頼もしている。
だから、土門さんも同じように思っていてくれたら嬉しい。
そして、できるならこれからもずっと側にいて…。
―――― ずっと側にいて?
ふと、マリコは思考の間で立ち止まる。
あと数年すれば、土門は退官を迎える。
そうなれば仕事はおろか、どこかで顔を合わせる機会すら無くなるだろう。
“ずっと”
それはいつまでをさすのか。
退官までか、それとも…?
「榊?」
土門は黙ってしまったマリコを気にかける。
「急に聞かれても困るよな。すまん。こんなこと、言うつもりはなかったんだが…」
土門はいつからか、マリコへの想いは秘めたまま墓場まで持っていくつもでいた。
惚れた腫れたに騒ぐ歳でもないし、何より、心地よい今の関係性を壊したくないという気持ちが大きかった。
「私は、これからもずっと土門さんと仕事がしたいわ」
「ああ。それは俺も同じだ」
つまりはそういうことなのだ。
特別な関係にならなくても、今のままでいられればいい。
「でもね、土門さんが退官した後はどうなるのか…想像してみたの」
「……………」
土門は黙って聞いている。
「そうしたら、土門さんがいないのは嫌だなぁって。仕事でも、仕事じゃなくても、話を聞いてほしいし、側にいてほしい。………ずっと」
「さか、き…」
緊張で土門の声が掠れる。
「質問の答えにはなっていないかしら?」
「いや。予想以上の答えだ。だが、その答えにはこういうことも含むんだぞ」
土門はマリコを腕に囲うと、おとがいに手をかけ上向かせる。
近づいてくる顔。
「…分かっているのか?」
重なる直前の唇から、声と吐息がマリコの頬をくすぐる。
マリコはただ目を閉じた。
それが、返事。
「ふっ」
唇が離れると、土門は思わず笑った。
「なに?」
「いや、『分からなかった』なんて言ったら、ポリグラフにかけてやろうと思ったんだ」
「失礼ね」、とマリコは膨れる。
「なあ。やっぱりバレンタイン、くれないか?」
「え?」
マリコは驚く。
「実はもらってもいないのに、勝手にホワイトデーを用意しちまったんだ。それを渡すには、お前からバレンタインをもらわないとな」
「明日持ってくるわ」
「いや、今がいい」
「今?何も持っていないわ」
戸惑うマリコに、土門は唇をトントンと叩いて見せる。
「まさか…」
嫌な予感に、及び腰になるマリコ。
でも、ようやく想いの通じ合った相手との触れ合いをマリコもまた望んでいた。
もっと、土門さんと…。
マリコは誰もいるはずのない周囲を見回すと、踵をあげ、おずおずと自分から唇を重ねた。
絶対に拒否されるだろうと思っていた土門は、マリコの思いがけない行動に箍がはずれた。
「足りない。もっとだ」
離れようとする新米の恋人を囚える。
「ここ、職…」
『職場』なんて言葉はストッパーには弱すぎた。
軽くソフトな触れ合いは数を積むうちに、やがて深く熱くなっていく。
「もう、だめよっ!」
唇を腫らして、潤んだ瞳では迫力も半減だが、土門は渋々マリコを開放した。
「バレンタインは渡したから、今度は土門さんの番よ。ホワイトデーを用意してくれたんでしょう?」
「ああ」
「何かしら?」
土門を見上げるマリコはワクワクしている。
「渡せるとは思っていなかったからな、実は家にあるんだ。悪いな」
「なんだ…」
途端に落胆するマリコ。
そんなマリコの耳元で、土門が囁いた。
「だから家に。今夜俺のうちに……取りに来いよ、榊」
その日、仕事を終えたマリコの姿は土門の車の助手席にあったという。
ホワイトデーの正体が何か。
その好奇心に勝てなかったからなのか、それとも……?
だが結局、土門からマリコに渡されたホワイトデーは、テーブルの上に無造作に置かれたまま、朝を迎えることになる。
なぜなら、ビターチョコレートのような夜の帳に隠されて、二人はキャンディーより甘くまろやかに溶けていく時間を過ごすことになったからだ。
fin.
2/2ページ