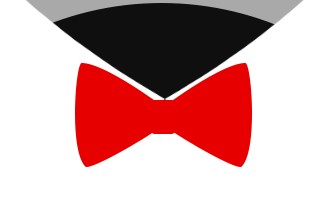土門さんの恋人
翌々日。
久しぶりにマリコが出勤すると、日野は「あと2、3日休んでも良かったのに…」と残念そうな顔をした。
「すみません。これからはちゃんと休むようにしますから」
「本当だね?」
「事件がなければ、ですけど」
マリコはそそくさと自分の鑑定室へ逃げ込んだ。
「事件のないときなんて、ないでしょ!事件があっても休んでもらわないと困るんだよ、マリコくん!」
日野の目の前で、シャッ!とガラスが曇る。
「まったく…」
日野のぼやきは止まらない。
「まあまあ…」
宇佐見がなだめるようにお茶を差し出し。
「はい、所長。怒ると血圧上がっちゃいますよっ」
亜美は溢れる愚癡を堰き止めるために、日野の口へ煎餅を咥えさせた。
「………………」
午後になり、悩みつつもマリコは捜査一課へ向かうことにした。土門はああ言っていたが、やはり忙しいのに科捜研まで足を運ばせるのは申し訳ない。
廊下の途中で、マリコは土門に言い寄っていた女性を見つけた。同僚らしき相手と何事か親密に話しながらマリコの方へ歩いてくる。
「そっか、ダメだったんだ」
「うん。特別な相手がいる、って宣言されちゃった」
「周りに他の人もいたんだよね?」
「そう」
「ふーん。みんなの前でそんな風にキッパリ言い切れるのって、何だかカッコいいよね。相手の子がちょっと羨ましい」
『相手の子』に心当たりのあるマリコは、持っていた封筒で顔を隠すようにして、二人の横を通り過ぎた。
「だよね。やっぱり土門さんは硬派でカッコいいんだよ!」
うんうん、とマリコもそこは同調する。
「また、土門さんみたいな硬派な男を探すことにする!」
マリコはそのセリフにホッとしつつ、彼女の次の恋が成功するように願った。
「ね、藤倉刑事部長とかどうかな?」
願ったけれども…それはいささか難しそうだと思うマリコであった。
マリコが一課に顔を出すと、土門だけが眉を潜め、それ以外の男たちは満面の笑みで椅子やらコーヒーやらを勧めてくれた。
「ありがとうございます」
「こいつらに礼なんて必要ない。それより何の用だ?」
「用なんてなくたっていいだろう」とか「冷たい言い方するなよ」という外野の野次を土門は完全スルーだ。
何なら、ケンカ口調の土門にマリコは吹き出してしまった。だって、分かりやすすぎるほどに不機嫌なのだ。
「御用聞きに来ました。鑑定の依頼はあるかしら?」
「それなら後で蒲原に持っていかせる。お前は科捜研に戻れ」
「はい、はい」
「ごちそうさまでした」とお辞儀をしたマリコは立ち上がり、一課を出ていく。
その後を土門が追った。
「榊。お前、俺との約束忘れたのか?」
「忘れてないわ。だけどやっぱり気になったの。でも…」
「なんだ?」
「そんな不機嫌になるなら、もうやめるわ。他の人達に恨まれそうだから」
「すごいわよ」と言って、マリコは土門の眉間のシワを指差した。
「ふんっ。知るか」
「ねえ。今夜は早くあがれる?」
「多分な。何でだ?」
「デートしない?」
「デート?」
「小さい体のときは一緒にご飯も食べられなかったから」
マリコの提案に、土門の機嫌は一気にV字回復する。
「そうだな。いいぞ。何を食いたいか決めておけ」
「うん。じゃあ、後で」
「ああ」
「あ!」
「ん?」
マリコは土門の胸ポケットをポンと叩いた。
「もうここに入れないと思うと、やっぱり少し寂しいわね。私の場所だったのに」
「お前の定位置はこっちに用意してる」
土門はすっと腕を伸ばすと、マリコの肩を掴んだ。
「いつだって、お前専用の場所だ」
そしてそのまま、胸元に引き寄せる。
一瞬のこととはいえ、天下の京都府警の廊下だ。目撃者はわんさかいた。
手にしていたファイルを落とす者。
立ち止まり、口をポカンと開く者。
頭を抱える者…等々。
「ち、ちょっと、土門さん!離して」
「これでみんな、お前が誰のものか、改めてよーくわかっただろう」
焦るマリコをよそに、土門一人が非常に満足しているのであった。
fin.
9/9ページ