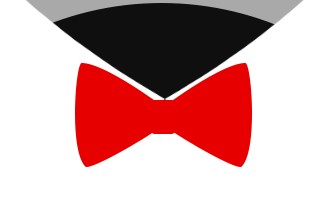土門さんの恋人
翌朝目覚めたとき、マリコの体には何の変化も起きていなかった。変わらず小さいままだ。
「仕方ない。カエルと人間では薬の効きめに違いがあるのかもしれない。もう少し様子を見よう」
そういう土門の励ましにも、マリコは俯いたまま答えられない。
「どうして…」
ポロリ、マリコの左目から一粒涙が零れた。
「なぜ……」
今度は右目から。
ポロリと涙が流れ落ちる。
「おい、さか…き?」
土門はマリコが零した涙に違和感を感じた。水滴が大きいような気がしたのだ。
「え?」
突然、マリコは激しい動悸に襲われた。服を鷲掴み、その鼓動の激しさに耐えるよう体を丸める。
「っう!」
マリコが体を震わせると、足がぐんぐんと伸びていく。手も、体も、あっという間にマリコの体は元通りの大きさになった。
「榊!大丈夫か?痛みは?」
「だい…じょう、ぶ。……え?わたし?」
マリコは息を整えながら何とか答える。
その瞬間、視界がこれまでと違うことに気づいた。土門の顔が小さく見えたのだ。
「戻ったぞ!ほら!」
土門はマリコの手を取ると、自分の顔に当てる。マリコの手は、たやすく土門の頬を包むことができたのだ。
「本当!やっぱり薬の影響かしら?」
マリコはまだ信じられない様子で呆然としている。
「そんなこと、どうでもいい。榊!」
対して土門は興奮し、戸惑っているマリコの体をしっかりと抱いた。
「土門さん。苦しいわ」
少しだけ力は緩んだが、開放はされない。
「お前の体が戻ったら、どうしてもしたいことがあるんだ」
「なに?」
「榊…」
土門はマリコの髪を撫で、頬を包み込むと、その唇を奪った。薄い唇が赤く熟れるほどに長く。
「……よかった。榊」
その声に滲むのは、安堵、感慨、そして歓喜。土門は深く長い息を吐き出した。
マリコもようやく元に戻れたことを実感し、土門の背中に腕を回した。
大好きな人に、自由に触れる。
それはとても贅沢なことなのだと、マリコは気づいた。
「土門さん」
「ん?」
「土門さん」
「なんだ?」
「私の声、聞こえる?」
「ああ。聞こえる。はっきりと。ただそれだけのことなのに、何て幸せなんだろうな」
「私も同じことを思ってた」
マリコはギュッと土門に抱きつくと、顔を上げた。
「土門さん。私、幸せだわ。とても」
そういって綺麗に微笑むマリコに、土門はもう一度口づけた。
「お前、今日も休み…だよな?」
土門はマリコの顔を覗き込むと、どこか歯切れが悪く尋ねた。
「え?ええ。土門さんは?」
「俺はもともと非番だ」
「そう」
「ということは、だ。このまま……いいか?」
遠慮がちに聞かれて、ようやくマリコは今の状況に気づいた。
体が大きくなったために、それまで着ていた人形の服は破れ、今のマリコは生まれたままの姿で土門に抱きしめられているのだ。
マリコは少し困ったように、それでもコクンと頷いた。
『欲望』というより、今は互いの存在と温もりを確かめ合いたかった。
土門はマリコのパーツ、ひとつひとつを確かめるように愛していく。
マリコは熱に浮かされてしまう前に、土門のスウェットの上着に手をかけた。
「ここ。居心地がよくて好きだったんだけどなぁ」
マリコは胸ポケットにそっと触れると、そのまま土門の上着を脱がせた。
「榊?」
「心臓の音がする」
素肌の胸に頬を寄せて、マリコは目を閉じる。
ずっと聞いていたい…、囁く願いは駄目だと即答された。
「どうして?」
「俺だって聞きたいからな」
そういうと、あっという間にマリコはシーツへ逆戻りだ。土門に鼓動を確かめられた後は、もう何も考えられない。
瞼の裏に白銀の光が走るたび、マリコは土門の逞しい肩に爪を立て、縋るばかりだった。