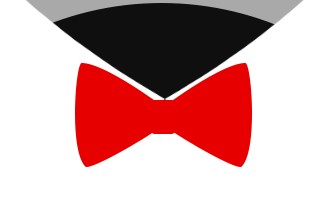土門さんの恋人
気を取り直し宇佐見からのメールを確認したマリコは、土門の手を借りながら大量の論文をダウンロードしたり、印刷したりした。
その後は自分の殻に閉じこもり、黙々と思考を続ける。
土門はそっとその場を離れ、簡単な夕食を用意して先に食べ終えた。風呂に入り、缶ビール一本だけの晩酌を済ますと、マリコは先程と同じ体勢で深く考え込んでいた。話しかけるのは気が引けたが、根を詰めすぎるのは良くない。
「榊。何か食うか?」
その声にはっとマリコは現実世界へ戻ってきた。
「もうこんな時間なのね!」
「そうだ。腹は減ってないか?」
「大丈夫よ」
何だかマリコは興奮した様子だ。
「何かわかったような顔だな?」
「宇佐見さんが、火災のあった大学と提携している海外の大学や研究機関を調べてくれたの。その一箇所でね、おもしろい実験が行われているの」
土門は先を促す。
「アッポトキジンという新薬の研究なんだけど、この薬は細胞の再生機能の向上を目的にしているものなの。火災現場となった薬学部でもこの薬を扱っていたそうよ。そして海外ではすでに両生類…カエルね、投薬実験をしているわ。そうしたら、見て」
マリコが示したのは写真だ。
そこには大小様々な大きさのカエルが写っていた。
「実験開始時にはほぼ同じ体長のカエルを用意したと明記されているわ」
「なに?それじゃあ、この写真はいったい…」
「恐らく再生機能ではない、別の遺伝子に影響してしまった結果ではないかと、研究者は推察しているわ。そして、注目すべきはこの後。3日後の写真よ」
「こいつは本当に同じカエルか?」
そこに写っていたのは、ほぼ同サイズのカエルと、数匹だけ小型のカエルが混じっていた。
「そう。全て同じ個体よ。全部で20匹のカエルを検体として、一枚目の写真のように体長が縮む変化を起こしたのは8匹。うち6匹は3日後の写真のように、もとの体に戻っているのよ!」
「つまり?」
「もし私があの現場でアッポトキジンに触れたことが原因で、こんな姿になったのだとしたら」
「3日後には戻るかもしれないってことか?」
「可能性は高いと思う」
「しかし、そのアッポ…何とかって薬に触った記憶があるのか?」
「現場検証で、私は鉄の箱を見つけて開けてみたの。中は無色透明な液体で、すぐに気化してしまった。だけどほんの数滴、地面に落ちたときに私の手に跳ねたのよ」
「じゃあ、その液体が?」
「この資料によれば、アッポトキジンは無色透明で無臭な液体を加工したものだと書かれている。私が触れてしまったのは、加工前のアッポトキジンじゃないかしら?」
「わかった。今はその可能性に賭けよう」
「ええ。明日元に戻ればいいんだけど…………」
急に勢いを落としたマリコ。
「変化を起こした検体は8匹で、戻ったのが6匹といったでしょう。残りの2匹はその姿のまま…戻らなかったのよ」
「最悪の事態を心配するのは、明日を迎えてからにしよう」
土門はマリコの腰を掴むと、スウェットのポケットへと運んだ。
「居心地はどうだ?」
「ここ、結構落ち着くのよね」
マリコはふふっと笑う。
「俺もだ。お前の気配と温もりを感じられるのは悪くない」
だから、と土門は続ける。
「たとえこのままでも俺は構わない。お前がそばにいる事が一番大事なんだ」
マリコからは、土門の顎しか見えない。そこには薄っすら無精髭が生えていた。
こんなふうに髭が生えるのね、と小さくなったから気づく幸せ。
今しか見られないアングルが愛おしい。
「ね、ここから出して」
土門はマリコを掬い出す。
手のひらに乗せて自分に近づけると、マリコは必死に手を伸ばして、土門の顎に触れた。
「ふふふ。ザラザラする」
「あ、剃ってなくてな。すまん」
「ううん、いいの。私、土門さんの無精髭好きだわ」
「ん?」
「小さくなって気づいたの。もっと、近づいてもいい?」
「もちろん」
土門は、さらに手のひらを顔に寄せた。
「土門さん。ありがとう」
小さすぎる唇の感触は、土門には分からなかった。
全ては明日。
できるなら…。
もう一度、その髪に、頬に、唇に触れたいと。
その願いを胸に秘めたまま二人は眠りについた。