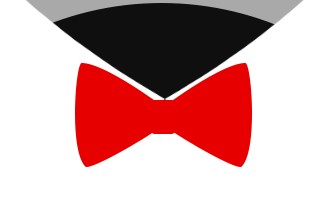土門さんの恋人
自宅に戻り、ようやく土門はマリコのためにPCを立ち上げた。マリコも今は土門のポケットから出て、PCの前に移動したミニチェアに座っている。
「すまんな。結局家に帰ってから確認するはめになっちまった」
「ううん。でも、土門さんて本当に忙しいのね」
「ん?」
「事件があれば捜査だし、なくても事務仕事があるし…それに今日は頼まれて、他の事件の捜査会議にも参加していたでしょう?いつもこんな感じなの?」
「まあ、そうだな」
「土門さん…。よく、科捜研に来る時間あるわね?」
「おいおい」
土門は苦笑する。
「お前の顔を見に行ったら駄目なのか?」
「そんなことないけど…無理してない?」
「ばか。俺が行きたいから時間を作ってるんだ。本当なら鑑定依頼も全部俺が届けたいんだぞ?まあ、蒲原も行きたいだろうからな。今は譲ってやってる」
蒲原云々の事情はマリコにはよく分からなかったが、マリコは本気で土門の仕事量が気になった。
「今度から電話して。私、取りに行くわ」
「必要ない」
ところが、土門はピシャリと断る。
「え?どうして?」
「お前が刑事課へ来ると、色々面倒なんだ」
「なによ、それ」
ぷぅとマリコは頬を膨らませる。マリコは早合点したのだ。
「私が行くと邪魔なんでしょ?ほかの部署の女性と仲良くできないものね!」
「は?何の話だ?」
「さっきも食事に誘われてたし、廊下ですれ違ったときも、剣道の稽古頼まれてたわよね?」
駐車場へ向かう道すがら、土門は生活安全課の若い女性から声をかけられた。
護身術の講習に参加する予定があるから、剣道の稽古に付き合ってくれないかというのだ。
「土門さん、OKしてたわよね?」
「そりゃ、頼まれれば稽古ぐらいはな」
「別に土門さんじゃなくてもいいじゃない。生活安全課の同期や上司がいるでしょ?どうしてわざわざ土門さんに頼むの?」
「そんなの、俺は知らん」
「……………」
マリコはムッとした表情のままだ。
「おい、何を怒ってる?何が気に入らない?」
「そんなの…」
マリコは立ち上がると、PCの前に仁王立ち腕を組む。
「そんなの、決まってるじゃない。土門さんがモテるのが嫌なの!」
ポカーン。
土門は口を開けたまま、しばらくマリコを眺め、そしてクスクスと笑い出した。
「なによ、何がおかしいの?私は本気で…」
「いや。悪い。俺もまったく同じことを思っていたから、可笑しくなっちまった」
「同じこと?」
「そうだ。俺が、お前に捜査一課に来ないでほしい理由もそれだ」
「え?え??」
「相変わらず鈍いな。お前もな、モテるんだぞ?」
「うそぉ!」
目を丸くするマリコに、土門は笑いを仕舞うと眉を持ち上げだ。
「嘘じゃない。スキあらばお前に言い寄ろうとしている男はかなりいるんだぞ」
「だって、これまでそんなこと無かったわよ」
「俺が阻止してたからに決まってるだろ。もっとも、最近は俺に遠慮して、あからさまにお前に近づこうとする奴はいないがな。それでも事情を知らない新人が血迷った行動をしようとしたときは、多少指導してるがな」
ニヤリとするが、土門の目の奥は笑っていない。
「俺の話はわかったか?お前は科捜研にいろ。いいな?」
「…うん」
マリコの顔は心なしか赤い。
「さてと。今度はお前の番だな」
「?」
「お前は俺がモテるのが嫌なんだろう?ヤキモチか?」
「ち、違うわ」
「じゃあ、何で嫌なんだ?」
「もういいわよ、その話は。それよりメールのチェックをしなくちゃ」
誤魔化そうとする小さな体を捕まえると、土門は自分の手のひらに載せて目の前まで運んできた。
「逃がさない。ちゃんと聞かせろ」
「……下して」
「下して欲しかったら、答えろ。どうしてお前は俺がモテると嫌なんだ?」
「…………」
「榊」
土門にたしなめられて、マリコはムスッとしたまま、それでも答えた。
「心配だったの。私の体はこんなになっちゃったから」
マリコはさらに続けた。
「土門さんに今の私は不釣り合いだし、それどころか迷惑かけてばかりで…」
土門はマリコを載せている手とは反対の指で、その口を塞いだ。
「お前は俺の気持ちを疑っているのか?」
「違うわ、違うけど、でも…」
「俺の好きな女はお前だ。だからお前に手を出す男が許せない。正直、お前に気安く触れる佐沢先生を殴りたくなったことも、一度や二度じゃない。俺は独占欲が強いし、ヤキモチ焼きだ。そんな俺が他の女に目移りすると思うか?」
「でも。もし、私の体がこのままだったら!」
「その時はその時だ。俺とお前、二人だけの秘密の生活をするだけだ」
「本当にそれでいいの?だって、それだとその…」
目をそらすマリコが何を言おうとしているのか、土門にもわかっていた。
「それこそ、お前の得意な実験と検証の出番だろ?“色々”試してみればいいさ」
「……何だか、言い方がいやらしい」
ふふん、と土門は何故か得意そうだ。
「無事に体が戻ったときは、そうだなぁ…1週間ぐらいは諦めろよ?」
「何を?」とは怖くて聞けないマリコだった。