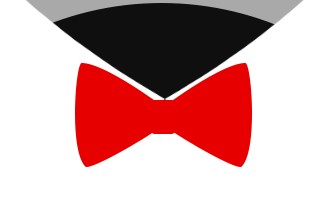土門さんの恋人
外回りから戻った土門と蒲原は、休む間もなく資料作りに追われる。PC作業があまり得意ではない土門は、作成した資料にミスも多い。
「失礼しまーす」
そう言って捜査一課へやってきたのは、大量のファイルを抱えた総務の女性署員だ。
「皆さん、お疲れさまです。各種申請書の直し、ここに置いておきますね」
ドスン、とデスクに積まれたファイルは、ここ一週間の申請書類や領収書だ。
「提出期限は17時です。1分でも遅れた場合は受け付けませんので、よろしくお願いしまぁす」
時計はすでに16時を過ぎている。にっこり笑って鬼のような命を下す女性は、土門の側にやってきた。
「土門警部補、今日は間に合わせてくださいよ」
「わかってる。わかってるんだが…」
「どこで止まってるんですか?」
「ここの入力がなぁ…」
「ああ。ここはですね」
女性は土門の手からマウスを奪う。カチカチッと何度かクリックすると、あっという間に完了した。
「はい。これでよし」
「すまんな。助かった」
「そう思うなら、ちゃんと操作を覚えてくださいよ」
「うっ。…すまん」
「そのうち食事でもご馳走してもらわないと割が合わないな〜」
「社食でいいか?」
「ご冗談。ちゃんとエスコートしてもらわなくちゃ。そういえば、以前捜査でフランス料理のお店へ行ったって聞きました。そこなんてどうです?」
女性はちらっと流し目で土門を見る。明らかに土門に気がある様子だ。
ポケットの中で二人の会話を聞いていたマリコは気が気ではない。女性が話しているのは羽多野の店のことだろう。あの店はマリコにとって特別だ。捜査の一環だったけれど、赤いドレスを着て土門と過ごした時間は楽しく、マリコには忘れられない。その後も二人でイベントや記念日にはプライベートでも訪ねている。そんな二人にとって特別な店に、土門は彼女を連れて行くのだろうか。
「勘弁してくれ。予算オーバーだ。あそこは高級店なんだぞ」
土門はおどけたフリをして、誘いをうまく回避しようとした。
「じゃあ、ワリカンならいいですよね?」
こちらも引き下がらない。
土門はふぅーと息を吐くと、ポケットを軽く叩いた。マリコは息を止めて耳を澄ました。
「悪いが、あの店には連れていけない」
「どうしてですか?」
「あの店は特別でな。連れて行く相手は決まっているんだ」
「特別な店に連れて行く相手というのは……」
「俺にとって“特別な相手”ということだ」
きっぱりと口にした土門を、蒲原も誇らし気に見ていた。
「私ではその相手にはなりませんか?」
「俺みたいなくたびれたオヤジより、もっといい男を探せ」
「でも、私は土門さんが!」
「何度も同じことを言わせるな。あの店に連れて行く相手はもう決まっている」
「…………………」
女性はペコリと頭を下げると、そのまま速歩で戻っていった。取り乱すこともなく、きちんと礼を示すだけでも大したものだろう。
土門は多少心が傷んだが、だからといってどうすることもできない。彼女の想いに答えてやることは無理なのだから。
「土門さん、格好良かったです!」
蒲原は称賛の眼差しで上司を見る。
「問題は、その相手を連れて行けるようになるか……心配だけどな」
蒲原には聞こえぬ小声で呟くと、胸ポケットを覗く。
土門が連れて行きたい相手は、今はナイフよりもミニサイズなのだ。
バチッと目が合うと、マリコはふいっと視線をそらし俯いてしまった。
「?」
そんなマリコの様子が気になった土門だが、次々に電話や呼び出しがあり仕事に忙殺された。
結局この日はそれ以降、マリコはずっと大人しいままだった。