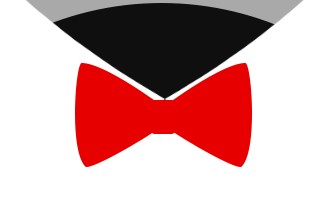土門さんの恋人
ショッピングセンターのオモチャコーナーには人形のブースが設けられ、様々な服が売られていた。オシャレな服から制服、異国の民族衣装も並んでいる。
「どれにするんだ?」
土門はすっかり定位置となった胸ポケットのマリコヘ小声でたずねる。
「こんなにあると迷っちゃうわね。あ、あれ、見せて」
「これか?」
土門はマリコが選んだ服をいくつか手に取ると、マリコに見えるように胸元へ持ち上げた。
その様子は傍から見れば、中年の男性が熱心に人形の服を選んでいるようにしか見えない。それが悪いわけではないが、店員や他の子連れ客には何となく不審に思われても仕方ない。
「あの、お客様。何かお探しでしょうか?」
「あ…」
伺うように声をかけられ、ようやく土門は今の自分の微妙な立ち位置に気づいた。
「いえ。あの、そう、実はですね。娘の誕生日プレゼントを選んでいたんですが、色々あって迷ってしまって」
「ああ、お嬢様の!」
店員の顔から不審感が大分薄らいだ。
「はい。事情があって今は離れて暮らしているものですから、どういったものを喜ぶのか…私にはよくわからなくて」
「そうでしたか。私どもでお手伝いできることがあれば、何なりとお声がけくださいね」
「ありがとうございます」
「それではごゆっくりお選びになってください。失礼いたしました」
店員は、単身赴任か離婚か…離れ離れに暮らしている気の毒な父娘と想像し、態度をコロリと変えて戻って行った。
「嘘も方便!よく思いついたわね」
感心するマリコに、土門はげんなりした顔を見せた。
「さっさと選んで帰ろう。どれにするんだ」
「じゃぁ…」
数着の服を選び終えると、土門は棚の裏側に回った。そこにはコーディネートされたドールハウスが展示されていた。
ワンルームマンションがコンセプトなのか、入口にはミニキッチンが設置され、家電も並んでいる。部屋の中央にはテーブルに椅子、ドレッサーやベッドが置かれていた。
「いっそのこと、ハウスごと買っちまうか?」
「キッチンなんて使わないでしょ。ええと、テーブルと椅子、あと食器があればいいかしら」
「ベッドも買っておこう」
「どうして?」
「気づかずに潰しちまったら怖い」
半分冗談、半分本気で土門はベッドも買い物カゴへ入れた。
「こんなものか?」
「そうね」
「足りないものがあれば、また買いに来よう」
土門が支払いを済ますと、二人は自宅へ戻った。
「とりあえず着替えたいわ。土門さん、買った洋服を開けてくれる?」
「わかった」
次々と土門は買ったものを開封し、テーブルに並べた。
「ちょっと!私こんなの頼んでないわよっ!」
「ん?そうだったか?」
とぼけた土門をマリコはじろりと睨む。
マリコ自身が選んだのはツインニットやカットソーに、パンツやロングスカートといった普通のコーディネートの服だ。
ところがそれに続いて、何故かCAやナース、もちろん婦人警官の制服まであった。
「こんな機会でもなきゃ着れないだろ。試しに着てみればいいじゃないか?」
「嫌よ。着ません!」
「何だよ…似合うと思うがなぁ」
残念そうな土門の声に、マリコは後ろ髪を引かれた。「似合う」という言葉も、マリコの心を擽る。
「い、一度だけよ?着替えるから向こうを向いていて」
言われた通りに土門が後ろを向くと、ゴソゴソとマリコの着替える音がする。
「き、着替えたわよ」
振り向いた土門は、思わず顔を覆って天を仰いだ。
「土門さん?やっぱり似合わない?」
土門の様子にマリコの顔が曇る。
「いや。ヤバすぎる…」
「え?」
ミニマリコのナース姿なんて、何だかイケナイ事をしている気分になってしまう。おまけに何故かやけにスカートの丈が短いのだ。ちょっと手を伸ばせば、指先だけで捲れてしまいそうだ。土門はそんな妄想が止まらず、興奮のあまり鼻血が出そうになった。
「お前、これから何があっても俺以外の前でナース服は着るなよ」
「そんなことする訳ないでしょ」
「わからんだろ。病院で立て籠もりなんてあったら、ナースに扮して侵入するくらいのこと、お前ならやりそうだ」
「………………」
そこは否定しないマリコ。
「もう着替えていい?」
「まて、写真………は、やめておくか」
白い視線に土門はすごすごとスマホをポケットに戻した。
ちなみに、CAと婦人警官の制服は「また今度ね!」と土門はマリコにピシャリと言われてしまった。
ひとまずカットソーとパンツに着替えたマリコは、ほっと息を吐いた。さすがにハンカチを巻きつけただけでは、落ち着かなかったからだ。
「明日からどうすればいいのかしら」
ミニサイズの洋服や家具に浮かれていたが、直面している現実は厳しいものだ。
「俺は明日は仕事へいかなきゃならん。お前はそのまま休むしかないだろう」
「ええ」
「有給消化するように言われてたんだろ?ちょうどいい機会じゃないか」
「だけど、いつ戻るかわからないのよ?そもそも元に戻れるのかしら…」
マリコの表情は徐々に暗くなっていく。
「何か、原因に心当たりはないのか?昨日は何をしていたんだ?」
「昨日は…火災現場へ行ったわ」
「火災現場?」
「そう。大学の研究棟が半焼したのよ」
「出火原因は特定できたのか?」
「まだよ。燃焼の具合から火元は薬学部の部屋だってことはわかったけど、出火原因になりそうな薬物が沢山保管されていたみたいなの」
「もしかして、それじゃないか?」
「え?」
「そこにあった薬品とお前の症状に何か関係があるかもしれんぞ」
「でも体が縮む薬品なんて…」
「新薬の研究、ということはないか?」
「可能性はあるわね。宇佐見さんから資料を送ってもらうわ…と、土門さん、手伝って」
マリコ一人ではPCの起動もキーボードも打てない。土門はマリコのPCから、2通のメールを送った。
一つは日野所長へ、明日も休むという件。もう一つは宇佐見へ、昨日の火災現場の資料を送ってほしいと依頼した。
「ありがとう」
「いや。でもお前一人じゃメールを読めないんじゃないか?」
打てないなら、読むのも難しいはずだ。
「大丈夫よ」
「?」
「土門さん。確か一課のデスクに自分のPC置いてあったわよね?」
「あ、ああ」
「じゃあ、そこから私のアカウントへログインしてもらえば、メールは読めるわ」
「ち、ちょっと待て。もしかして、明日は俺についてくるつもりか?」
「もちろん。私一人じゃ、家にいても何もできないもの」
「しかしな…」
「見つからないように、土門さんのポケットに隠れておくわ」
こうなったら何を言っても無駄だ。
土門はため息という返事をした。