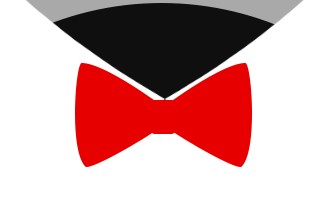土門さんの恋人
翌朝目覚めると、マリコは視界がどこかおかしな事に気づいた。
横を向いて、数秒…。
「ええ!!!!!」
絶叫するも、その声はまるで蚊の鳴くようにか細い。
「土門さん、土門さん!」
隣で眠る土門の頬を叩くが、土門の瞼はピクリとも動かない。
「土門さんてば!」
ペチペチと何度も叩いていると、やがて土門はうるさいとばかりに手を払った。
「きゃぁ!」
その手の風圧に飛ばされ、マリコは布団の上を転がる。
「どうしよう…」
マリコはぺたりと座り込むと、途方に暮れた。
自分の声が聞こえない。
触れても気づいてもらえない。
その原因は…。
マリコは自分の手を見つめる。
「体が小さくなっちゃった……」
土門が目を覚ますと、隣にマリコの姿がなかった。いや、正確にいうと、脱いだパジャマだけが残っていた。
「榊?」
呼びかけても返事がない。土門は布団に起き上がった。
「……………なにぃ!?」
土門の視界に、ベッドの端でちょこんと座る小動物が映り込む。シーツの端で体を巻き込み、今にも泣きそうな顔をしている。
「榊?榊…なのか?」
ミニサイズのマリコはコクリと頷く。何か話しているようだが、あいにく土門の耳まで声が届かない。
「なんだ?」
土門はマリコへ近づく。
それでも上手く聞き取れない。仕方なく土門はマリコを掴むと、自分の顔のそばまで持ち上げた。
「ん?」
すると、ペチリ。
土門は頬に何かがぶつかったような気がした。
「エッチ!」
続いてようやく聞こえたのは、マリコの怒ったような声だった。
「榊?」
「見ないで!」
そうはいっても、瞳をちらりと動かせはマリコの姿は土門に丸見えだ。
「お前、服はどうした?」
「体が縮んで着れなくなっちゃったの!」
そう。
手の中のマリコは小さいながらも、生まれたままの姿だった。
「と、とにかくだな。うーむ」
土門はバタバタと慌ただしくベッドを下りると、クローゼットの中を物色した。中から自分のハンカチを持って戻ると、広げてマリコに渡した。マリコは、四苦八苦しながらも何とかハンカチを体に巻きつけると、ようやく土門の手の中に戻る。そこで土門の手を叩くと、土門はマリコを持ち上げた。
「なんだ?」
「ハンカチ、ありがとう。さっきは叩いたりしてごめんなさい」
「いや。それにしても、何だってこんなことに…」
「わからないの。すぐに戻ればいいんだけど、もし………」
マリコは不安気に瞳を揺らすと、その先は黙ってしまった。
この状況が一番不安なのはマリコ自身だろう。土門には解決の術が全くもってわからない。それならいたずらにマリコの気持ちを掻き乱すより、当面の問題を解決するほうが先決だと、気持ちを切り替える。
「とにかく、まずは着るものをなんとかしないとなぁ。どうすりゃいいんだ」
「土門さん、オモチャ売場に連れて行ってくれる?」
「オモチャ売場?」
「人形用の服なら着られると思うの」
「なるほど。確かに昔、美貴が遊んでいた人形と同じくらいのサイズだな」
リ○ちゃんとか、バー○ー人形とかいう商品名だったはずだ。
「よし、支度をしてすぐに出かけよう」
「すぐ…って、土門さん仕事は?」
「今、うちの班は事件担当じゃないからな。休むさ。お前はどうする?」
「私が休むといえば、所長は喜ぶでしょうね」
働き方改革が一番大切なのはマリコだからだ。
「土門さん、悪いけど私のかわりにメールを打ってくれる?」
「わかった」
土門が二人分の所属先へ連絡を入れ終えると、腹の虫がなりだした。
「榊、何か食べられそうか?」
「私はいいから、土門さんは朝食を食べて」
「お前も何か腹には入れたほうがいい。何か食べられるものがないか探してみよう」
そういうと、土門はマリコを自分の肩に乗せた。土門は気をつけてゆっくりと歩くが、どうしても左右に肩が揺れる。その度にマリコは必死になって、土門の耳たぶにしがみつかなければならなかった。
「すまん。肩じゃないほうがいいか?」
「うん。落ちてしまいそう。あ!ねえ、土門さん。手を貸して」
土門は言われたとおりに、マリコヘ手を差し出した。するとマリコはぴょんと飛び移り、今度は手を下げるように土門へ頼んだ。
「ここ、ここでいいわ。この中に入れてくれない」
マリコは土門のパジャマの胸ポケットにぽすんと収まった。
「ここなら揺れても大丈夫。土門さん、私の声聞こえる?」
「ああ、大丈夫だ」
キッチンへ運ばれたマリコは、土門が小さくちぎってくれたトーストと、みじん切りにしたリンゴを食べると、もうお腹は一杯になってしまった。
「小さな食器やテーブルも必要だな」
「それも多分売ってるんじゃないかしら」
「そうだな。とにかく見に行ってみよう」