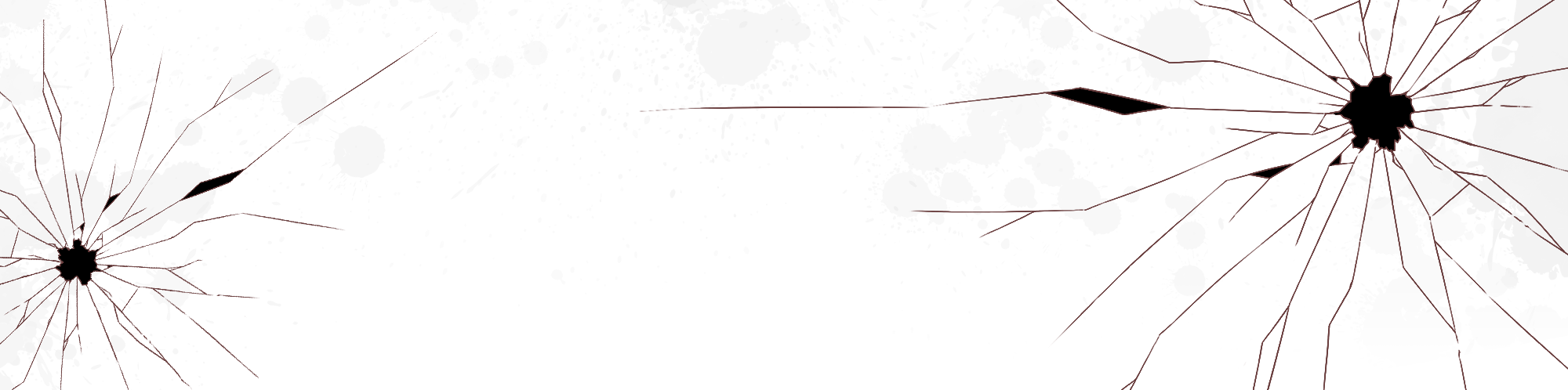殺意の善光寺
その頃、別の場所で一つの事件が起こっていた。
「あんたが、…犯、人…?……………………」
ぐらぐらと揺れる視界。
遠のく意識の先で、神経質そうに自分を見ている女。
せめて着信だけでもあいつに…。
気力だけでポケットに入れたスマホを握るが、それが限界だった。スマホはポケットから落ち、タイル張りの床に転がった。
男が倒れると、キッチンの奥から女がもう一人現れた。二人は男の体をブルーシートで包むと、身動きが取れないよう厳重に結束バンドで締め上げた。
「これからどうするの?」
「そうね…。埋めるか、捨てるか。あなた、贔屓にしてくれる客がいるんでしょう?その人に頼みなさいよ」
「で、でも、そんなこと…」
「だったらあなたが捨ててくれるの?それとも自首する?」
「わ、わかったわよ」
不服ながらも、女はすぐにスマホでどこかへ電話をかけ始める。その様子を見ていたもう一人の女は、どこからか綻び出したシナリオの修正を必死に始めた。
「お疲れさまです」
蒲原が科捜研へ姿を見せたのは定時を随分と過ぎてからだった。
「蒲原さん、お疲れさまです」
敬礼して出迎えた亜美に、蒲原は焦った様子でたずねた。
「マリコさんはいる?」
「鑑定室にいると思いますよ」
「ありがとう」
返事もそこそこに、蒲原はスモークガラスの鑑定室をノックした。
「マリコさん、蒲原です」
「どうぞ」
「失礼します」
蒲原はパソコンのデータを注視したままのマリコへ声をかけた。
「マリコさん、土門さんから連絡はありませんか?」
「え?ないわよ」
マリコは振り返る。
そして目の前に立つ蒲原の表情に眉をひそめた。
「何かあったの?」
「坂井田茉由の職場に聞き込みをした後、俺たちは二手に分かれて京都工科大学と簑島さんの宿泊していたホテルに向かいました。その後、坂井田茉由のアパートで合流する予定になっていたんですが、いくら待っても土門さんが来なくて。何度電話をかけても繋がりません」
「私もかけてみるわ」
マリコはすぐにスマホを操作するが、呼び出し音すら聞こえない。
「坂井田さんは何て?」
「土門さんは来ていないと」
「そう…。藤倉部長へは?」
「報告しました」
「土門さんを最後に確認できたのはどこ?」
「簑島さんが宿泊していたホテルです。そこの支配人から話を聞いた後、土門さんはホテルを出ていったそうです」
「だったら念のため、坂井田さんのアパート周辺の防犯カメラを取り寄せて。土門さんが映っているかもしれないわ」
「わかりました」
走り去る蒲原を見届けると、マリコはもう一度電話をかけてみた。
しかしはやり画面の向こうは無音だ。
「土門さん…」
マリコはスマホを握りしめると立ち上がり、鑑定室を出た。
「亜美ちゃん、至急土門さんを捜索して!」
「………へっ?」
防犯カメラの映像チェックを始めてすぐに土門は見つかった。
土門は坂井田茉由のアパートを訪問していたのだ。ドアの前に立ち、インターフォンを押す姿が映っている。
しかし留守だったのか、土門はアパートから少し離れた電柱に寄りかかりスマホを見ていた。
「俺を待っているんでしょうか」
「きっとそうね」
「あれ?誰か来ますよ」
亜美が画面の端を指差した。
程なくして、映像ではフードを被った人物が土門に声をかけていた。そしてそのまま二人は並んで歩き出す。しかし分かれ道でちょうどフレームアウトし、二人がどっちへ行ったのかはわからなかった。
「誰でしょう?」
「女の人…かしら?亜美ちゃん、拡大鮮明化してくれる」
亜美はキーボードを操作する。
「うーん、画質が悪くてよく分からないわね」
マリコは眉を潜めるが、蒲原は何かに気づいたのか…画面に顔を近づけた。
「涌田さん。このポケットからはみ出しているストラップ…もう少し大きくできる?」
「やってみますけど………これが限界ですね」
「蒲原さん、このストラップがどうかしたの?」
「これ、多分同じ物が簑島さんの遺留品にありました」
「え?」
「長野の善光寺のお守りだと思います」
「それじゃあ、この人は…簑島さんの関係者?」
「もしかしたら、簑島すみれさんじゃないでしょうか?」
「簑島すみれさん?」
「簑島さんの奥さんです」
「でも、今は長野にいるんじゃ…」
「そのはずなんですけど、でも………」
「蒲原さん。千津川警部に頼んで、簑島さんの奥さんの居場所を調べてもらいましょう」
「そうですね!さっそく」
蒲原は一課へ戻って行った。
千津川警部の指示で北本刑事が簑島宅を訪れたところ、留守だったという。
近所の人の話では昨日から雨戸が閉まったままだそうだ。
「簑島さん、もしかして京都へご旅行じゃないですか?」
「なぜそう思うんですか?」
「いえね。先日本屋でお会いしたとき、京都のガイドブックを手にされていましたから」
北本は礼を述べると、すぐにこの件を上司に報告した。