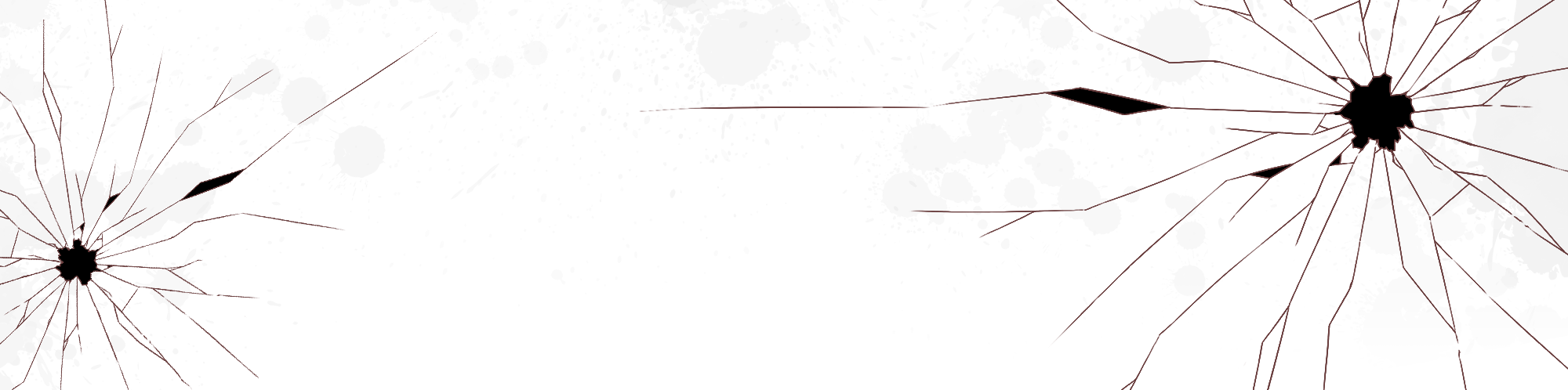殺意の善光寺
マリコを洛北医大へ送った後、京都府警へ戻った土門を待っていたのは一本の電話だった。
「長野県警から電話?俺に?」
訝りながらも、土門は受話器を受け取った。
「はい、土門です」
『お久しぶりです、土門さん。長野県警の千津川です』
「これは!千津川警部でしたか!こちらこそご無沙汰しています」
『戸隠の事件以来ですね。榊さんもお元気ですか?』
「ええ。相変わらず鑑定一色の毎日を送ってますよ」
千津川は喉の奥で笑った。憎まれ口を叩いても、土門は鑑定漬の彼女を誰よりも心配し、世話を焼いているに違いない。
「ところで今日は私に何か?」
『ええ。人物照会をお願いします』
「承知しました。事件関係者ですか?」
土門はメモとペンを引き寄せる。
『被害者本人です』
「ほう。どんな事件ですか?」
何となく興味を引かれて、土門はたずねてみた。
『実は今日、善光寺で死体が発見されました』
「善光寺で?」
『ええ。現在解剖中ですが、恐らく毒殺でしょう。被害者の持っていた免許証によると、現住所は京都府✕✕区です』
「………」
千津川の話を聞くうちに、土門は長野と京都を結ぶ見えない糸のようなものの存在を感じていた。
「千津川警部。実はこちらでも殺人事件が起きていて、自分はたった今現場から戻ってきたところなんです。その現場、どこだと思いますか?」
『まさか………。京都の善光寺ですか?』
「!?」
土門はゴクリと喉を鳴らした。
「千津川警部は、京都の善光寺をご存知なんですか?」
『いいえ。直接は知りません。ただ、こちらの被害者のスマホには、今日の予定の欄に“下京区、善光寺”とありました』
「それは………」
一体どういうことなのか。
とにかく今は情報を集めることが先決だ。
「警部。京都の被害者、簑島冬樹さんは長野の人間なんです。こちらも照会をお願いできますか?」
『もちろんです。土門さん』
「はい」
『近いうちにまた会うことになりそうだ』
千津川警部の予言は、すぐに現実のものとなった。
二人の刑事が再会したのは、古都京都の地だった。
千津川は腹心の鶴井を連れ、特急しなのと東海道新幹線のぞみを乗り継ぎ、京都駅に到着した。
そんな二人を土門と蒲原が改札で出迎えた。
「千津川警部、鶴井さん、ご無沙しています」
「やあ、土門さん!蒲原さんも、お久しぶりです」
土門が近づくと、千津川は手を上げて応えた。
「紅葉の事件以来ですな」
鶴井も嬉しそうに京都府警のコンビに頭を下げる。
ひとしきり挨拶を終えると、四人はひとまず京都府警へ戻ることにした。まもなく捜査会議が始まる。そこで千津川には長野で起きた事件について説明してもらう予定だ。
蒲原の運転する車内で、鶴井は助手席に座っていた。車が走り出して暫くすると、鶴井は電車に乗る前に買ったという長野名物『野沢菜おやき』を取り出した。
「長旅は腹が減りますな。蒲原さんもどうですか?」
「いえ、自分は大丈夫です」
「そんなこと言わずに。ほれ」
半分に割ったおやきを、鶴井は蒲原の口に押し込んだ。
「うわっ」
ハンドルを握っているため手が使えない蒲原は、口だけを不自由に動かして何とかおやきを飲み込んだ。
「ん!上手いです」
「そうでしょう。そうでしょう。まだありますよ」
「鶴さん。蒲原さんは運転中だから、無理強いしたらだめですよ。それより、私にも一つくださいよ」
「いいですよ。土門さんもいかがですか?」
「ではいただきます」
車内には、ほんのり酸味の効いた野沢菜の香りが広がる。
「ところで科捜研の榊さんはお元気ですかな?」
鶴井はミラーごしに土門の顔を見た。
「ええ。相変わらず無茶ばかりしています」
そこには言外に「困ったやつだ」という呆れ半分、心配半分の気持ちが籠もっている。
「そうですか。それはよかった」
「は?全然良くないですよ!」
その様子を隣席の千津川は意味ありげに見ては笑う。心の中を見透かされているようで、土門は途端に居心地の悪さを感じた。