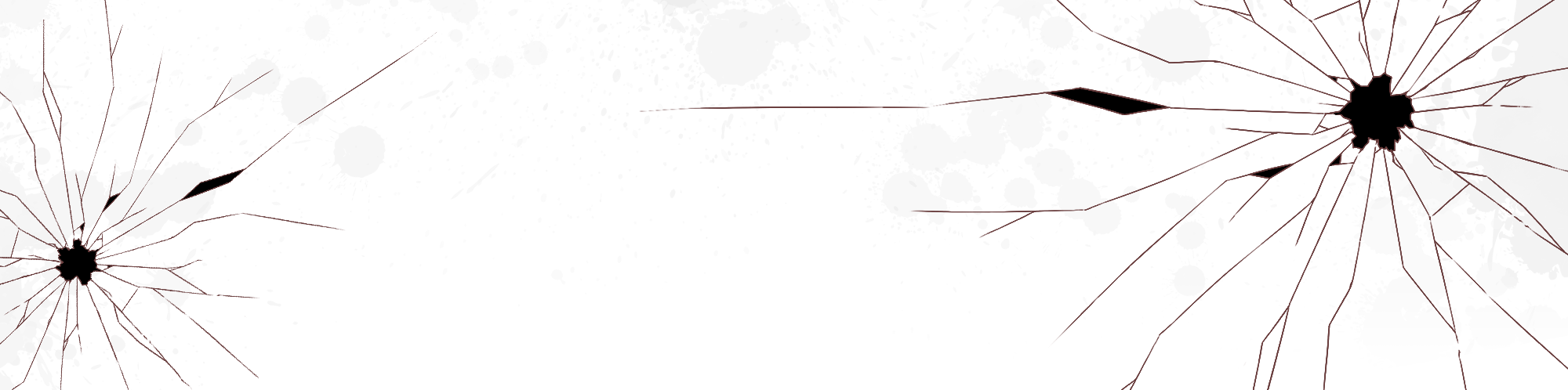殺意の善光寺
一方、京都でも動きがあった。
山道で乗り捨てられた車が発見され、その近くで男女の遺体が見つかったのだ。
女性の身元は坂井田茉由だった。
「相手の男は誰だ?」
藤倉の質問に土門が答えた。
「坂井田茉由の客だそうです。風俗店の店員も男の本名は知らず、遺体は身元のわかるものを所持していないため、特定にはもう少し時間がかかりそうです」
「死因は?」
「青酸化合物による中毒死でした」
「もしかして心中か?」
「断定はできませんが…。この男の指紋をしらべたところ、自分が襲撃されたアパートから発見された指紋と一致しました。おそらくこの男が自分を工事現場に投げ捨てたものと思われます」
土門は苦々しく報告を続けた。
「簑島すみれが逮捕されたことは、全国ニュースで流れていたからな。それを見て、もう逃げ切れないと悟ったか…。いずれにしろ、まずは男の身元確認を急げ!」
「はっ」
長野との合同捜査はここで打ち切りとなり、この事件は引き続き京都府警が担当することになった。
「千津川さんと鶴井さん、帰っちゃったのね。挨拶もできなかったわ」
ここは料亭の一室。
坂井田茉由の事件捜査は継続していたが、簑島冬樹殺害については一区切りとなり、捜査員たちは交代で休みを取ることになった。
たまたま休みの重なった土門とマリコは、たまたま瓜生に呼び出され、今ここにいる。
「一刻も早く簑島すみれと対峙したかったんだろう。俺が生きていることを知れば、彼女は黙秘に転じる可能性もあったろうからな」
「そうか…」
残念そうなマリコに土門は言った。
「今度は仕事抜きで蕎麦とお焼きを食いに行くか?」
「いいわね。土門さん、お焼きを食べたんでしょ?蒲原さんから聞いたわよ」
「鶴井さんからお裾分けされたんだ」
「ずるいわ」
「何がずるいのかな?」
マリコの顔がフグのようにプクリと膨れたとき、唐紙が開いた。
姿を見せたのは瓜生ではなく、まさかの須藤組4代目、その人だった。
「須藤!なんでお前が?」
「久しぶりですね、土門さん。体のほうはもういいんですか?」
須藤は二人の前に座った。
「あ、ああ。その節は世話になった」
「いや。今日あんたを呼んだのは瓜生に頼まれたからでね。何でもあんたから頼み事をされたが、その約束を果たせなかったと気にしていたようだが」
坂井田茉由の行方の件だろう。
「それは、瓜生が気にするようなことじゃない」
「そうですか?それなら、奴にそう伝えておきますよ」
今来たばかりだというのに、須藤はもう立ち上がる。
「帰るのか?」
「ええ。無粋な真似はしたくないんでね。ここは俺の奢りだ。ゆっくりしていってくださいよ」
「は?」
「あんたの快気祝いと…」
ちらっと須藤はマリコを見る。
「激励ですよ」
「なんの?」
「あなた、榊さんですかな?」
工藤は土門を無視して、マリコに問いかけた。
「は、はい。科捜研の榊マリコです」
マリコは急に話しかけられたことに戸惑いながらもペコリと頭を下げた。
「紅葉の事件の際に一度見かけた時も思ったが、かなりの別嬪さんだ。土門さん、あんた苦労するねぇ」
まさか頭、若頭ともに同じ同情を受けるとは…。
絶句している土門の耳元に、須藤という名前の悪魔が囁く。
「なんなら、隣の部屋に布団を用意させようかい?」
固まってしまった土門を見て、須藤は「ははは」と笑い声も高らかに帰っていった。
「まったく刑事をからかうなんて、なんて奴らだ」
むくれる土門とは対象的に、マリコは運ばれてくる料理に目を輝かせている。
「すごい、美味しそう!土門さん、いただきましょうよ」
「あ?ああ。…そうだな」
マリコの正面に座り直すと、土門は熱燗に手を伸ばした。
「待って」
その手より先に燗を奪ったマリコは、立ち上がると土門の隣に座る。
「はい、どうぞ」
土門の手の中の猪口へ透明な液体が注がれていく。
「土門さん、お疲れさま」
「おう」
ぐいっと飲み干すと、旨さに喉が鳴る。
「美味しい?」
「ああ。お前も飲むか?」
マリコは首を降った。
「また土門さんと一緒にご飯が食べられてよかった。美味しいお酒を飲ませてあげられてよかった…」
「榊?」
「土門さん。私の知らないところで、勝手にいなくなったりしないで。約束して。そうじゃないと、もうお酒もピールも飲ませてあげない!」
強気な言葉とは裏腹に、マリコの瞳には不安が揺れていた。
「榊…」
土門はマリコの肩を抱き寄せ、その手をしっかりと握る。離さないという想いが伝わるように。
「約束する……千津川警部にも言われたからな」
「え?千津川さん?」
「いや、何でもない。それにしても、『牛に引かれて善光寺参り』とはよく言うが、俺は『お前に惹かれて参りっぱなし』だな」
上手いことを言った、と土門は笑う。
マリコも「土門さんたら…」とその肩に頭を乗せて微笑む。
「榊。俺はお前のついでくれる酒が飲みたい。これから先もずっとな…」
豪華な料理に、極上の酒。
須藤と瓜生のおかげで、二人は久しぶりにいい時間を過ごした。
けれど本当は飲み慣れた缶ビールにスーパーの惣菜だとしても、そこに居てくれさえすれば十分なのだ。
土門さんが。
榊が。
fin.
15/15ページ