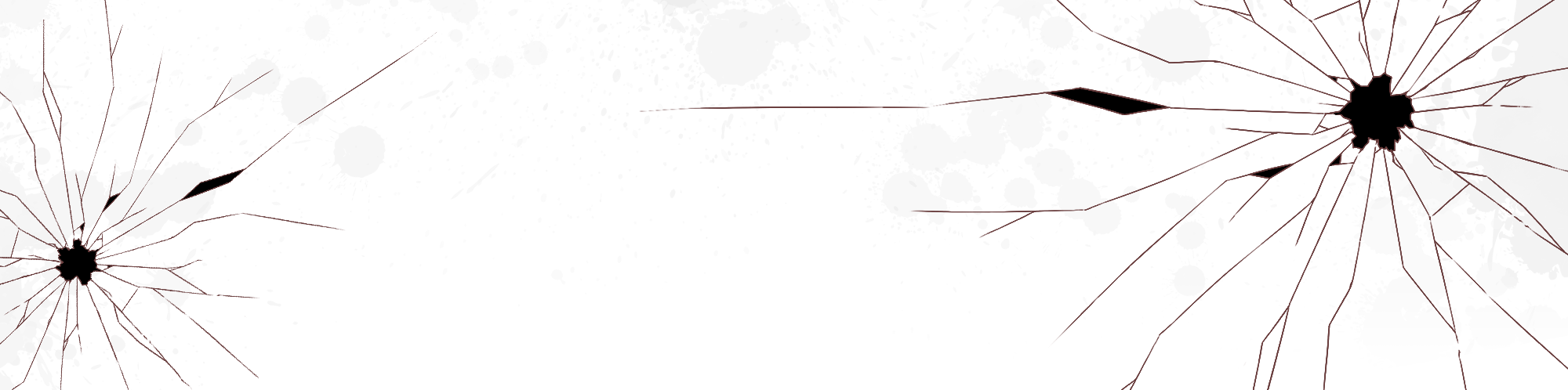殺意の善光寺
マリコ達は夜になっても防犯カメラの分析を続けていた。土門へ繋がる、ようやく掴んだ手がかりだ。何とかこの人物を探し出したいと、全員が必死になっていた。
しかし焦れば焦るほど時間だけが刻一刻と過ぎていく。すでに土門からの連絡が途絶えて半日以上が経とうとしていた。
「みんな、少し休んで。交代で仮眠しよう」
日野の言葉にもマリコは画面から顔を上げようとはしない。
「マリコくん、疲れた頭と目じゃ見逃してしまうよ」
それでもマリコの目は流れる景色を追い続ける。
「では、お茶でも入れましょう。ちょうど疲労回復に効果のある中国茶がありますから」
宇佐見は立ち上がる。
「所長、我々は交代で休みましょう。マリコさんはきっと今はテコでも動きませんよ」
「そうだよね…」
マリコの気持ちが痛いほどわかるだけに、見守ることしかできないことがもどかしい。二人はマリコを見つめ小さくため息を吐くと、そっとその場を離れた。
防犯カメラを睨んだまま、もう何時間が経つのか…マリコには時間の感覚が消えていた。
ふと鑑定室の外へ目を向ければ、机に突っ伏した君嶋と、床に転がる寝袋が見えた。
その向こう側では宇佐見が同じように、画面に向かっていた。
日野も同じだ。こちらは仕切りと目頭を揉んでいる。
みんな疲れている。
それはマリコもわかっていた。
でもどうにも嫌な予感が拭えないのだ。
土門のことを考えようとすると、得体の知れない不安に襲われそうで、マリコはただひたすらに映像を追い続けている。
こんなことなら、昨日も一緒にご飯を食べればよかった。
「飲みすぎだ」なんて言わずに大好きなビールを飲ませてあげればよかった。
そんなとりとめも無い後悔がマリコの脳裏を渦巻く。
――――― どうしよう。
土門さんにもう会えなくなったら ―――――。
突然マリコの目の前から色彩が消えた。
モノトーンの景色は殺伐として寒々しい。
マリコにとっては、土門の存在そのものが生きる彩りなのだ。
彼がいなければ……。
私は生きる屍だわ。
マリコの指先は体温を失い、ひどく冷たかった。
「これ!これ、見てください!!」
宇佐見の上げた声に、全員が彼の鑑定室に駆け込む。
「見つけましたよ、フードの人物!」
その人物が見つかったのは、京都駅の新幹線上りホーム。
時刻は今から4時間前だ。
最終の新幹線に乗ったのだろう。
「もしこれが簑島すみれさんなら、名古屋から特急に乗り換えて長野に戻るはずね。所長。藤倉部長に頼んで彼女を長野駅で確保してもらいましょう。そろそろ長野に着くはずだわ」
「それは無理だな」
背後からの声に全員が振り返る。
「藤倉部長!どうしてですか!」
マリコが詰め寄る。
「この人物が簑島すみれだという証拠は何もない」
「でも、今はほかに手がかり…が……え?」
立ちくらみがしたのか、マリコはガタンと机にぶつかる。
「「マリコさん!!」」
宇佐見と君嶋に支えられ、マリコは椅子に腰掛けた。
「榊、ひとまず休め。この人物のことは引き続き一課でも追っている」
「でも!」
「土門が見つかったとき、迎えに行けなくてもいいのか?」
「……………」
痛いところをつかれ、マリコは渋々引き下がった。
「他のみんなはこの人物の行方を追うとともに、簑島すみれかどうか判定できる材料を集めてくれ」
「わかりました」
藤倉の指示にそれぞれが鑑定室へ散っていく中、マリコは机に突っ伏したまま意識を失うように眠りに落ちた。
「土門、必ず無事で戻れよ」
藤倉はマリコの肩に毛布をかけてやりながら、低い声でひとりごちた。
虚空を睨みながら。