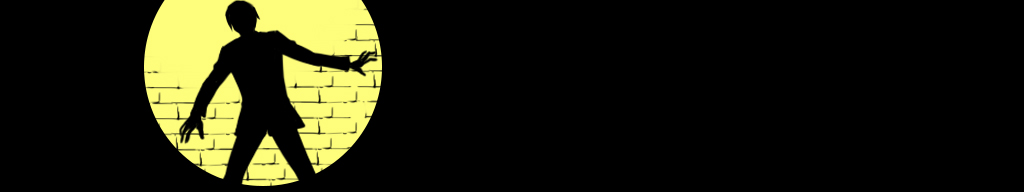3年目の浮気?
嵐のような二人が去ると、部屋は無人のように静かになった。
「コーヒー、飲むか?」
「ええ…。何だか喉が渇いたわ」
マリコは放心したように、溜息交じりに答えた。
土門はキッチンでコーヒーメーカーをセットすると、落ちていく黒い雫を静かに眺める。
淹れたてのカップを2つ用意すると、1つはテーブルに、1つをマリコの方へ差し出した。
「ありが……………」
受け取ろうと伸ばしたその手を土門は掴んだ。
そしてそのまま、片手でマリコを抱き寄せる。
「すまなかった…」
「もう、いいわ。理由も分かったんだし」
「嘘をつけ」
「え?」
「もっと怒れ。
「……………」
「榊、俺には何でも話せ!」
これまで幾度となく聞いたその言葉は、魔法だ。
マリコが必死に隠そうとしていた本心を、簡単に暴いてしまう。
「………なによ」
マリコは土門の胸に顔を埋めると、くぐもった声で秘めていた思いを吐き出した。
「何で『真由美』なんて、呼び捨てにするの?
何で『薫さん』なんて呼ばせるの?
何で腕を組んだりさせるのよ!」
「それから?」
「嫌だから……」
「ん?」
「私のことだけ見てて。私だけ、名前で呼んで。私だけ、私だけよ…『薫さん』て呼んでいいのは……」
土門は押しつぶしそうなほど強く、マリコを抱きしめた。
「そうだ。お前だけだ」
土門は慈しむような瞳で、腕の中のマリコを見下ろす。
「お前だけだよ、マリコ」
「土門、さん…」
「コラ!『土門さん』じゃないだろう?」
土門はマリコを開放すると、視線を合わせた。
「俺の目を見て、俺の名前を呼んでくれ」
「………薫、さ、ん」
コツンと額を合わせると、二人は見つめ合う。
ずっと沈んだまま、無彩色だったマリコの瞳が輝きと彩りを取り戻す。
「美貴の、姉になってやってくれるか?」
「薫さんが望むなら…」
「望むなら?」
テーブルの上に置かれたコーヒーから、芳しい香りが立ち上る。
ブラックコーヒーのはずなのに、部屋に満ちたその香りは。
切なく。
そして、甘く…。
それから、幾年月流れただろう。
「今となっては笑い話だな」
「懐かしいわねぇ」
あの日と同じように、テーブルには2つのカップが並んで置かれている。
「昔。『想い出はモノクローム』って歌詞の歌があったのを覚えているか?」
「ええ。流行ったわよね」
「若い頃は何も感じなかったが…。今になって思う。そんなことはない、ってな」
「?」
「お前との想い出は、何年経ってもモノクロームになんてなりはしない」
「薫、さん?」
「今だって変わらぬ色使いのまま、思い出すことができる。そうだ…あの頃も、今も変わらない。いつだって、鮮やかで、華やいで……」
土門はマリコの小さな手を、己の手で包み込んだ。
そしてあの時と同じように額を合わせると、その瞳をのぞきこむ。
「お前は俺の、『♪麗しのカラーガール』だよ」
ワンフレーズだけの歌声に、二人は笑い合う。
薫さんと一緒なら。
マリコと二人なら。
どんな日常だって、きっと彩り豊かに過ぎていく。
天然色な幸せに包まれて。
………ふたり。
fin.
6/6ページ