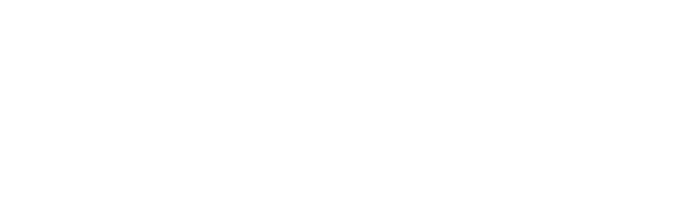結
出口まで見送ってくれたマスターとオパールに別れを告げ、二人は少し離れたコインパーキングへ向かう。
マリコは見慣れた車を見つけると、助手席に乗り込んだ。
イルミネーションの眩しい夜景の中を暫く走ると、土門はそんな明かりと喧騒がふっと途切れた道端に車を停めた。
「土門さん、どうしたの?」
「ん?いや…イミネーションも綺麗だが、俺はこっちのほうが好きなんだ」
そういうと、ウィンドウを下げる。
途端に冷気が車に忍び込む。
それでも構わず、土門は、澄んだ星空を見上げる。
マリコも土門を真似てみた。
「寒いか?」
「少しぐらい平気よ」
そうは言っても、マリコは肩を竦めている。
土門はウィンドウを閉めた。
「榊、ダッシュボードを開けてみろ」
マリコが言われた通りにすると、そこには深紅のリボンが。
「クリスマスプレゼントだ」
マリコはそっと取り出す。
「開けてもいいの?」
土門は頷く。
マリコは慎重にリボンを解き、包み紙を剥がす。
中から現れた箱の蓋を開けると……。
「これは…ブレスレット?」
ピンクゴールドのチェーンには、等間隔に小さなダイヤがはめ込まれていた。
「そうだ。誕生日にアンクレットを渡したたろう?だから、今度はブレスレットだ」
「どういうこと?」
マリコは首を傾げる。
「これで、足枷だけでなく手枷もできた。もう俺の側から逃さない。覚悟するんだな?」
「!」
本気なのか、冗談なのか…。
刑事の目は案外鋭く、マリコには判別がつかない。
「覚悟って…。私、逃げたりしないわ」
「分かってるさ。それでも心配なんだ。たとえ気休めでも、こんなもので繋ぎ止めておきたいほどに、俺はお前を……手放したくない、絶対に」
こんな風に自分を晒す土門は珍しく、マリコは戸惑う。
そしてそれ以上に、心が揺さぶられた。
独占欲は、甘い媚薬だ。
誰だって求められて嫌な気はしない。
それが愛する相手なら尚のこと…。
マリコはさっそくブレスレットをまとうと、その腕を土門の首に巻きつけた。
「ありがとう。土門さん」
そして二人は唇を重ねる。
甘い感触が離れ難くて、何度も繰り返す。
そのうちに、土門の手が怪しく蠢き出した。
マリコの耳の輪郭をゆっくりとなぞり。
「あ…っん」
項を撫であげ。
「ん…っ」
肩を滑り降り、ニットの襟からのぞく鎖骨をくすぐる。
「や…んん……」
口づけの合間に、マリコの声が零れていく。
そして、土門の手がニットの裾から忍びやかに潜り込んだ。
「や、…だ、め…………」
そんな言葉は聞きたくないと、土門の唇がマリコの声ごと吸い上げた。
「…………!!!」
触れられてはいけない場所が、土門の手によって暴かれる。
マリコは必死に体をよじって抵抗する。
すると、マリコの唇は開放された。
「ども、…やぁん!」
口は自由になっても、土門の手にマリコは翻弄されたままだ。
「だ、めぇ。おねが…い」
「本当にだめなのか?」
土門はマリコの体の変化に気づいている。
そのうえで、意地悪にも確かめているのだ。
「だって……。こんな…ところで………」
マリコは熱を持て余しながらも、必死に崩れそうな理性にしがみつく。
そんな危ういマリコに、土門は己が暴れだしそうになるのを止められない。
けれど………。
「そう、だな。……すまん」
土門は何とか、引き留まる。
しかし、まだ続きがあった。
土門は深紅のリボンを取り上げると、マリコの両手をそれでゆるく縛った。
「お前は今夜一晩、人質だ」
そんな“人でなし”のセリフとは裏腹に、マリコに注がれる視線はこの上なく優しい。
ーーーーー そんな瞳で見つめられたら…。
「嫌だなんて、言えるわけないじゃない」
ふっと満足そうに笑うと、土門は車をスタートさせた。
二人を繋ぐ紅いリボンはそのままに。
人質を甘やかす夜は、静かに更けていく。
知っているのは、夜空に燦めく星たちだけ……。
fin.