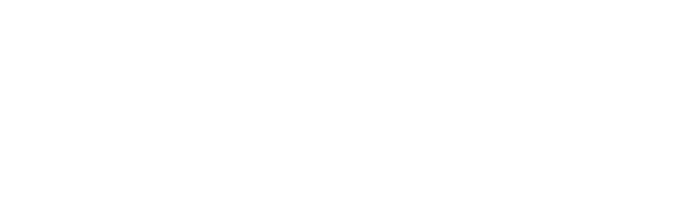結
♪チリン
「いらっしゃいませ」
出迎えてくれたのは、いつもの笑顔と挨拶。
「こんばんは」
「寒いですね…」
こちらも耳に馴染んだ男女の声。
「今日は一段と冷えますね。榊さま、よろしければこれをお使いください」
二人が指定席のカウンターに腰を落ち着けるのを見計らい、Bar『microscope』のマスターはマリコヘひざ掛けを差し出した。
「ありがとうございます」
マリコは、遠慮なく使わせてもらうことにした。
「ご注文は?」
マリコは自分専用のオリジナルカクテルを。
そして土門は自家用車で来店しているからと、ノンアルコールカクテルをオーダーした。
ドリンクを待つ間、マリコは店内を見回した。
今夜は照明がいつもよりやや低めに絞られ、飾られたクリフマスツリーがよく映えている。
クリスマスの夜ということもあり、店内には複数のカップルの姿があった。
どのカップルも身を寄せ合い、幸せそうに微笑んでいる。
自分と土門はどんな風に見えているのだろう…。
そんなことをぼんやり考えていると、目の前にグラスが置かれた。
「「メリークリスマス!」」
土門とグラスを合わせる。
カチン、と響いた小さな音が、今日はいつもより優しく感じる。
これも聖なる夜の魔法だろうか。
「榊さま、土門さま。大したものではございませんが、当店よりクリスマスプレゼントです。いつもありがとうございます」
マスターはグラスに続けて、二人の目の前に小さな箱を置いた。
ラッピングされた透明なその中には、スノードームが入っていた。
「可愛いわね!土門さんのも見せて」
スノードームはいくつか種類があるらしく、マリコは興奮気味に土門のもらった物も眺めている。
「キレイだし、ずっと見ていても飽きないわ。マスター、ありがとうございます」
「いいえ。喜んでいただけたのなら、よかったです」
マスターは小さく笑みを浮かべた。
「じゃあ、これは私たちから……」
そういうと、マリコはシックな色合いの包装紙でラッピングされた包みをマスターに差し出した。
「え?」
「いつも素敵な時間をありがとうございます」
「自分も榊も、マスターからは元気や優しさを貰ってばかりなので、たまにはお返ししようと話し合ったんですよ」
「お二人とも……」
マスターはそう言ったきり、口を閉じてしまった
「ご迷惑でなければ、受け取ってください」
「迷惑だなどと…。ありがとうございます」
マスターはマリコの手からプレゼントを受け取る。
「開けてみてもよろしいでしょうか?」
「もちろん!」
緑色のリボンを解くと、中から現れたのは濃紺のマフラーだった。
カシミア製だろうか、手触りは極上だ。
「榊さま、土門さま。ありがとうございます。大切に使わせていただきます」
心底嬉しそうなマスターの笑顔に、二人の心も温かくなった。
それからは土門とマリコ、時おりマスターを交え、この一年を振り返り思い出話に花を咲かせた。
そして、満を持して現れたのは……。
『ニャー!』
「来たな?」
足元で聞こえた鳴き声に、誰よりも早く反応したのは、仇敵・土門だ。
「オパール、待ってたのよ!」
手を伸ばすマリコの膝に、オパールはひょいと飛び乗る。
いつもは眉を動かす土門も、今日は大目に見るつもりなのか苦笑するに留めている。
「まるで真打ち登場だな?」
『ニャァー』
土門のセリフに、七色の目がキラリと光る。
室内の光量が抑えられている分、その瞳孔は大きく、より意思がはっきりと伝わるようだ。
『まあな』、と。
microscopeの看板猫はロシアンブルーの美しいしっぽを優雅に揺らすと、そのままマリコの膝で丸くなり、目を閉じる。
「オパール、今夜はあなたにもプレゼントがあるのよ」
『ニャッ?』
三角耳がピクンと動く。
「はい。メリークリスマス!私たち二人からよ」
マリコがカウンターテーブルに置いたのは、オフホワイトにラメが散りばめられた大きなリボンの包み。
「マスター、開けてあげてください」
「はい」
マスターの手によって解かれた包みの中からは、高級猫缶の詰め合わせが現れた。
『ニャー!ニャー!ニャニャニャー!!!』
興奮したオパールは、カリカリと爪で缶詰を引っ掻く。
開けろ!と催促しているのだろう。
「榊さま、土門さま。こんな高級品を……」
「たまにですもの。私たちだって今夜はご馳走をいただくんですから、オパールだって、ね?」
オパールは嬉しそうに、マリコの手のひらをペロペロと舐める。
「おい、俺も一緒だぞ!」
しかしオパールはちらりと一瞥するだけで、土門には目もくれない。
「ちっ!」
マリコはそんな一人と一匹の様子に吹き出した。
「申し訳ありません、土門さま。でもせっかくですから、開けてあげましょうか」
マスターがオパールの餌皿に缶詰を開けると、ひらりとマリコの膝から飛び降りる。
そして、餌に向かって……『猫、まっしぐら』。
「現金なやつだな」
「重ねて、すみません……」
「マスターが謝ることじゃないですよ!」
オパールを見つめながら、またしても三人は笑う。
「オパール、美味しい?」
『ニャァ♡』
「ふふふ」
マリコは嬉しそうだ。
そして解かれたリボンを手に取ると、スツールを下り、店内のクリスマスツリーに向かう。
マリコは、先ほど見つけていた猫のオーナメントの上にリボンを結びつけた。
「あのリボン、オパールの瞳の色のイメージにピッタリだと思ったの」
「確かに、そうだな」
二人はクスリと笑う。
そして見つめ合い。
『そろそろ出ようか…』、そう視線を交わした。