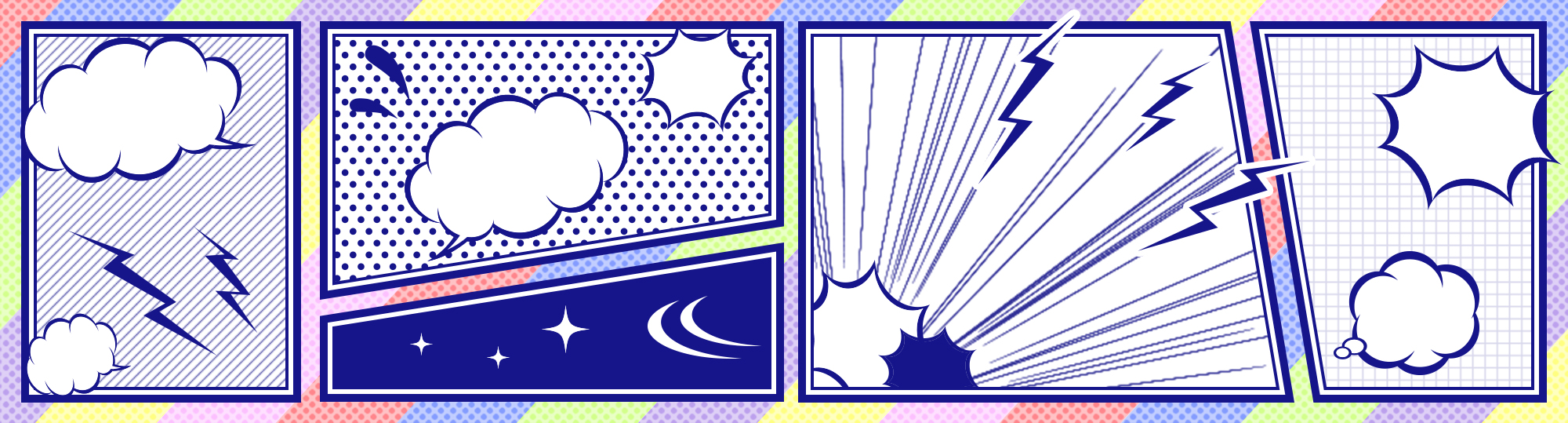アナタは皆に優しくて
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「いいじゃないの、別に休憩中ならとやかく言わなくたって。それより休憩時間はもう終わりの時間でしょ!仕事に戻るわよ」
何とかキジのお陰で巫兎は、その話から逃れることが出来た。
猿門はまだ気になるといった様子だったが、その話はそこで終わり、二人仕事へと戻る。
そしてその日は無事に仕事を終えたのだが、その翌日、突然猿門に呼ばれると、机にはチィーに渡した筈のサボテンが置かれていた。
「それは……」
「71番が隠してるのを見つけたんだが、誰から貰ったのか口を割ろうとしねぇんだよ。まぁ、聞かなくてもわかるがな。こんなことができるのはお前くらいしかいねぇからな」
バレてしまっては仕方がないと、巫兎は隠そうとはせず、チィーに渡したことを認めた。
だが、サボテンを渡すことが悪いことだとは思っていない巫兎はとくに気にする様子はなく、それよりも、猿門がそのサボテンを取り上げたことに腹をたてていた。
「二度とこんな真似すんじゃねぇぞ!」
「何でですか……。何も言わずに渡したことは謝罪します。でも、サボテンを取り上げなくても……」
「アイツに植物は渡せねぇんだよ」
「ッ……!!囚人……だからですか?囚人なら植物さえも愛でることを許されないんですか……?」
「お前、何言ってんだ?」
巫兎は、猿門なら囚人を差別しないと思っていた。
いつも5舎の皆と鍛練をしたり、リャンやウパの相手もしてくれている、そんな猿門は、囚人でも普通の人として扱ってくれるだろうと巫兎は思っていたのだが、どうやら間違いだったようだ。
「そんな人だとは思いませんでしたッ……!!」
「あッ、おい!!」
囚人だからというだけで、植物すらも渡してはいけないという猿門に腹をたて、巫兎はその場から飛び出した。
あんなにチィーは喜んでいたのだ、きっとサボテンを取り上げられて落ち込んでいるに違いないと思い、巫兎は8房へと向かう。
「チィーいる?」
「あ、巫兎ちゃん!昨日はサボテンちゃんありがとう。でも悪いね、看守に見つかっちゃって巫兎ちゃんに迷惑かけちゃったよな」
「ううん。それより、サボテン……」
「ああ!サボテンちゃんのことなら大丈夫。折角巫兎ちゃんが持ってきてくれたけど、見つかるのも時間の問題だと思ってたから」
残念そうにはしているものの、チィーは昨日1日だけでもサボテンの世話ができたことを喜んでいる。
もっと落ち込んでいるものだと思っていたのだが、猿門に取り上げられたことをチィーは気にしていないようだ。
「でも、いくらなんでも取り上げなくてもいいのに……」
「仕方ないさ、他の奴等なら兎も角、俺に植物渡すわけにはいかないだろうからな」
「え?それってどういうこと?」
「あれ?巫兎ちゃん知らなかったんだ?俺、元々薬剤師だったんだけどさ、ちょっと危ない薬に手ぇ出して捕まったんだよね」
チィーが捕まった理由を知らなかった巫兎は、驚きを隠せずにいた。
だが、チィーがそんな薬に手を出したなど信じられない巫兎は理由を尋ねるが、詳しいことは話してはもらえず、ただ、お金のためだったんだと苦笑いする。
「まぁそういうわけでさ、俺に植物を触らせると薬を作るからって禁止されたわけ。でも、あの人はそんな俺に5舎の庭を見せてくれたんだ……」
チィーの目が優しく細められ、嬉しそうに話す姿はとても穏やかで、チィーにこんな表情をさせるあの人という人物が猿門であることは聞くまでもなくわかる。
薬でチィーが捕まったのなら、簡単に5舎の庭を見れるはずもなく、そんなことができるのは猿門くらいだ。
「話してくれてありがとう。私、これから行くところがあるからまた後でね」
巫兎は8房を後にすると、猿門の元へと向かった。
知らなかったこととはいえ、猿門に一方的に怒ってあんな態度をとったのだ、謝らなければいけない。
「あッ!お前何処行ってたんだよ!仕事中は俺と行動を共にしろと言ったはずだぞッ!!」
近づいてくる巫兎に気づいた猿門は怒りを露にしているが、その理由は巫兎が仕事中に消えたことであり、さっきのことではない。
「先程はすみませんでしたッ!私、チィーがヤクで捕まっていたなんて知らなくて……。何の報告もなくサボテンを渡したこと、そして先程の失礼な態度、謝罪いたします」
「何だよいきなり。散々サボっといていきなり謝られたら気持ちわりぃじゃねぇか。だが、これからは俺に報告することを忘れんじゃねぇぞ!」
目の前の猿門を見つめ、やっぱり思った通り猿門は、看守にも囚人にも差別なく接することのできる人なんだと嬉くなる。
「何ニヤついてやがる。本当にわかってんのか?」
「はーい!わかってまーす」
何時ものように適当な返事を返すと、猿門はやれやれといった様子でため息をつくと、何かを思い出したように巫兎へと視線を向ける。
「そういやお前、囚人の資料には目を通さなかったのか?」
「え?だっていただいてませんし」
「は?んなわけねぇだろ!猪里にしっかり頼んで……」
猪里という名前に、巫兎と猿門はあッ、と声を漏らした。
きっと今二人は同じことを考えただろうというときに、猪里が丁度二人の元へとやって来た。
「猪里、お前、この前巫兎に渡すように頼んだ囚人の資料はどうした?」
「あッ!ヤベッ!!」
「猪里てめぇッ!!またサボってやがったなッ!!」
猪里は普段サボることしか考えておらず、もしかしてとは思ったが、二人の考えは当たったようだ。
そのせいで巫兎はとんだ勘違いをしてしまったのだが、改めて猿門のことを知ることができ、猿門という看守を更に好きになった。
「まず巫兎よりお前が俺と行動するべきだな」
「ゲッ!!主任、そりゃ勘弁してくださいよ」
こんな賑やかで楽しい刑務所は、何処を探しても、この南波刑務所だけに違いない。
《完》