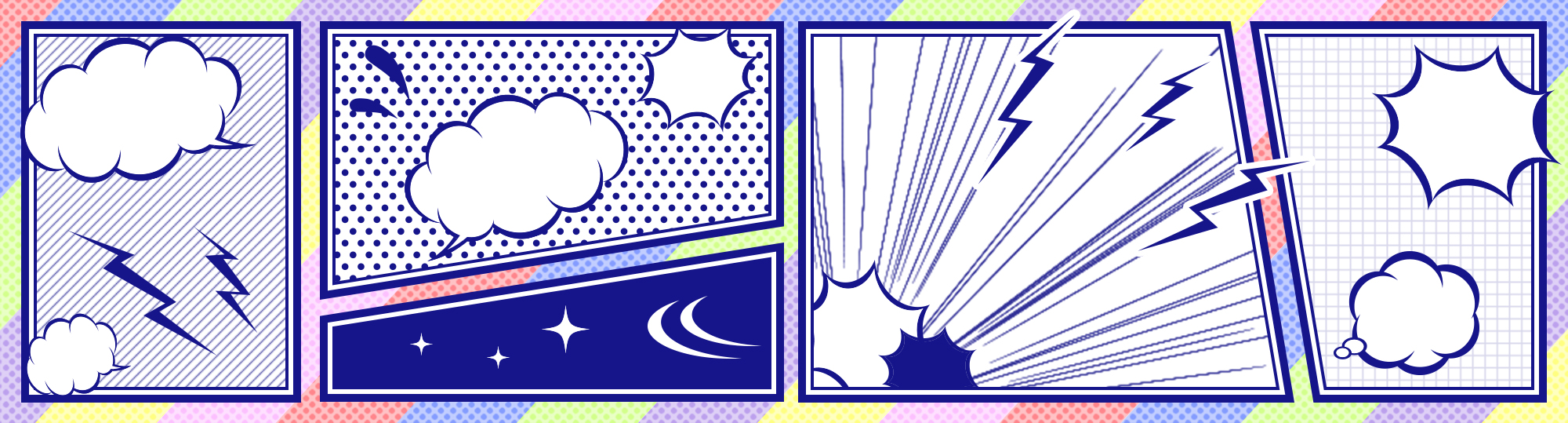大和撫子も恋をする
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
13舎の看守である巫兎は、何処の舎でも人気である。
見た目が美しいというのもあるのだが、その美しさは外見だけに留まらず、内面にも現れている。
仕事もしっかりこなし、誰にでも優しく、そしておしとやか、惚れない理由などない程の完璧な大和撫子。
そんな巫兎は他の看守とは違い、服装は和服であり、普段から和服で身を纏っている。
その理由は、和服以外のものを今までに着たことがないため、看守服を着せてしまうと逆に行動力が低下してしまうからだ。
最初はそんな巫兎に、看守も囚人も驚いてはいたが、今ではすっかり馴染んでいた。
「巫兎、すまないがお茶を淹れてはもらえないか」
「はい、わかりました」
巫兎は、大和の言葉に柔らかな笑みを浮かべるとお茶の用意を始めるが、その動きにすら誰もが見いってしまう。
流れるように滑らかな動作、その一つ一つの動きに無駄はなく、時間の感覚すらも忘れてしまいそうになる。
「どうぞ」
「ああ、すまないな」
大和は、目の前に置かれたお茶を手に取ると、一気に飲み干し美味いと口にする。
何故か大和だけは巫兎の魅力に目を奪われるといったことはなく、こうして普通に彼女と接している。
他の看守や囚人なら、巫兎に声をかけることすら躊躇ってしまうというのにだ。
「主任様に星太郎様、お二人はお茶はいかがなさいますか?」
「い、いえ!巫兎さんにお茶を淹れていただくなんてとんでもないです!!」
「俺も遠慮させてもらう」
それは星太郎やあのハジメですら例外ではなく、巫兎には皆が簡単に近づけないのだ。
別次元の人間、大袈裟に聞こえるかもしれないが、皆の中では女神のような存在となっている。
だが、そんな女神も鈍い男には他の人と変わらないらしく、大和だけはこの南波刑務所で唯一巫兎と普通に話すことができる。
「ヤマト様は今日も5舎に行かれるのですか?」
「ああ、勿論だ!日本男児たるもの体は鍛えておかねばならないからな」
そんな大和に、私もご一緒させてもらってもよろしいですか、なんて巫兎が口にしたため、星太郎とハジメは驚き書類を落としてしまう。
5舎、通称鍛練の5舎に行くということは、何時ものように訓練をしに行くということであり、そんな所に巫兎を行かせる訳にはいかないと星太郎とハジメは慌てて制止する。
「巫兎さん!思い留まってください!!」
「そうだぞ!ヤマトに付き合ったりなんかしたら命がいくつあっても足りねぇからな!!」
「ハジメ様に星太郎様、ご心配ありがとうございます。ですが私は、この書類を5舎の主任様にお届けしなければならないので、その帰りにヤマト様の訓練の様子を見させていただきたいなと思いまして」
書類を手にニコリと笑みを浮かべる巫兎はどこまでも美しく、またも二人は手から書類を落としてしまう。
「では早速5舎に向かおうではないか!」
「はい!」
そんな二人が固まってしまっている間に、巫兎と大和は5舎へと向かう。
その途中、大和の隣を歩く巫兎の耳に声が届いた。
「巫兎は仕事熱心だな」
「いえ、そんなことは」
思いもしない誉め言葉が大和の口から発せられ、巫兎は、私なんかよりも主任様のが仕事熱心ですよと言葉を返す。
そんな些細な会話をしながら5舎へとつくと、巫兎は一旦大和と別れ看守室へと向かう。
「13舎看守の巫兎です。主任様に書類をお持ちいたしました」
「ッ!巫兎か、わざわざご苦労だったな」
「いえ。それでは私はこれで失礼いたします」
書類も渡し終え、大和の訓練の様子を見に行こうとしたその時、5舎の看守である猿門に呼び止められ立ち止まる。
どうかされましたかと振り返り首を傾げると、猿門は慌て出し、何かを思い付いたように口を開く。
「折角来たんだ、お茶でも飲んでかねぇか?」
大和の訓練の様子を見に行くはずだったのだが、折角のご厚意を断るわけにもいかず、お茶を飲むだけなら問題はないだろうと巫兎は猿門の誘いを受けた。
するとらしくもなく、猿門がお茶を淹れようと立ち上がり湯飲みを手にする。
「そんな、主任様に淹れていただくなんて。私が淹れますので」
「気にすんな、お前は客みたいなもんなんだから座ってろ。そういや茶菓子もあったな」
もしこんな光景を他の人が見れば、らしくもない猿門の行動に誰もが驚き、変なものでも食べたんじゃないのかと口を揃えて言うだろう。
とくに5舎副主任の猪里はお腹を抱えて笑うに違いない。
だが、巫兎が見ている猿門はいつもこんな感じであり、とくに違和感などは感じていないのだが、気を使わせてしまっているようで申し訳ない気持ちを感じていた。
そんな巫兎の考えとは違い、実際のところ猿門は、長く巫兎を引き留めておきたい口実にすぎない。
そう、女神の様な存在である巫兎に声すらかけられない者もいれば、この様に少しでも一緒にいたいと積極的な人も存在する。
そして、その両方ともが巫兎に好意を抱いている者であるのだが、どちらも積極性にはかけるため、巫兎には気づいてもらえないのが現状だ。