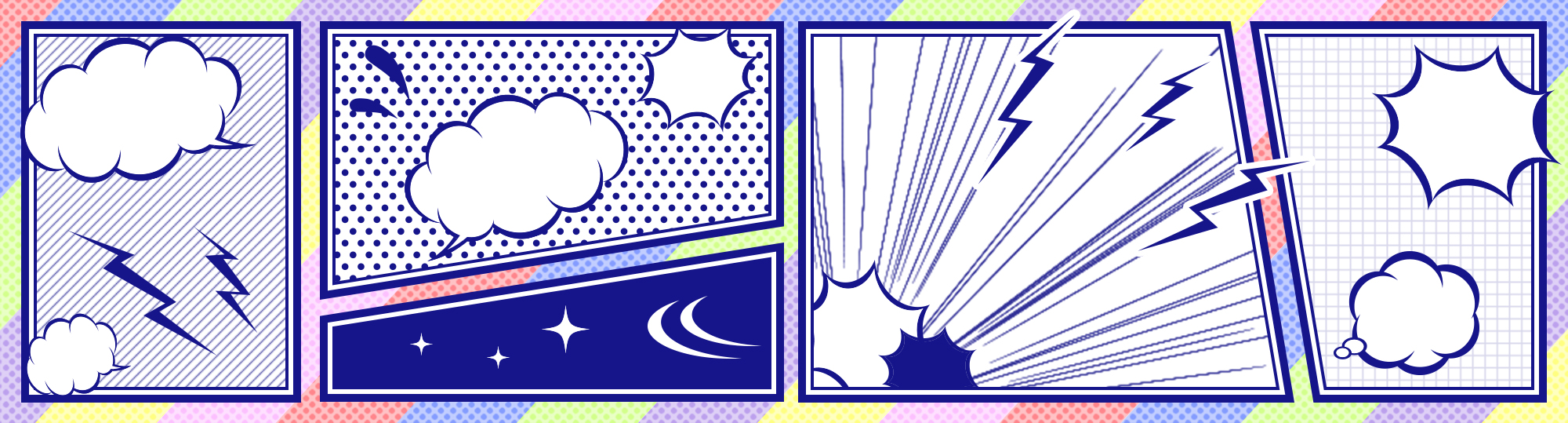引き返すことは不可能
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
4舎地下牢獄には、一人の囚人が収容されている。
視覚は皆無ではあるが、その一方で他の感覚が研ぎ澄まされているため、目が見えているのではないかと思ってしまうほどだ。
だが、地下牢獄に収容されるような囚人だ、どんなことをしでかしたのかなどわからず、上も詳しいことは誰も話さない。
勿論地下牢獄に近づくような者などおらず、4舎の主任看守である四桜 犬士郎が様子を見に数回訪れる程度だ。
「犬ちゃん、その人誰?」
この牢屋の中にいるこの囚人こそ、地下牢獄に収容された危険人物である囚人、囚人番号634番のムサシだ。
そして、今日は何故か犬士郎と一緒に女がこの牢獄に訪れていた。
「ああ、彼女は」
「どうも初めまして!今日からムサシちゃんのお世話をすることになった巫兎です!」
何やらテンションが高い女にムサシは苦笑いを浮かべながらも、よろしくと挨拶をする。
「巫兎、相手は囚人だ、番号で呼べ」
「えー、ムサシちゃんのが可愛いじゃないですかー」
「番号だ。俺はこれから仕事があるので失礼する。あとは任せたぞ、巫兎」
それだけ言うとムサシに何の説明もないまま、犬士郎はその場を去ってしまった。
残った巫兎になんて声をかけたらいいのかわからず戸惑っていると、何やら巫兎がごそごそとしだし、その手には鍵が握られているらしく、金属の音が聞こえる。
一体何をするのだろうかと思っていると、ガシャンと音が響き、巫兎が牢の鍵を開けたことがわかる。
そしてその足音はムサシへと近づき牢の中へと入ってきた。
今のムサシには音だけが頼りだが、ふわりとシャンプーの香りがし、直ぐ近くにいることがわかる。
「え!?何やってるの!?」
「何って、こうした方のが話しやすいでしょ?鉄格子越しに話すってなんか嫌だもの」
さっきから巫兎の行動には驚かされるが、まず気になったことがあり思いきって声をかけてみようと口を開く。
「怖くないの……?俺のこと」
「うーん、私、ムサシちゃんが何で地下牢獄に入れられてるかって知らないんだよねー」
その言葉でようやくムサシは理解した。
巫兎がこんな行動を平気でするのは、自分がしたことを何も知らされていないからなのだと。
ムサシは生まれながらに人体発火という特異体質の持ち主であり、この南波なんば刑務所で行われた新年大会でその力を使い、騒ぎを起こした。
そして、そんなムサシを危険と判断した上層部がムサシを入れたのが、この地下牢獄だ。
「知らないとしても、一応地下牢獄にいる囚人なんだから、もう少し警戒心とか持った方がいいと思うよ」
「…………」
突然黙り込んでしまった巫兎に、ようやく危険という意識を感じたのだろうかと思っていると、地下牢獄に笑い声が響いた。
「あははは!ムサシちゃんにはそんな心配要らないよー」
「え?」
「だって、自分危険だからもっと警戒心持ってー、なんて、普通言わないでしょ?」
そう言い再び笑いだす巫兎に、なんか変わった人だなーと口許に笑みが浮かぶ。
「あ!笑った!」
「なんだか変わった人だなって思って」
「えー、ムサシちゃんのが変わってると思うよ?」
囚人としてはムサシは珍しいタイプであり、看守としては巫兎は珍しいタイプなのかもしれない。
テンションに温度差はあるものの、初対面だというのにこんなに打ち解けているのだから不思議だ。
「ところでさ、なんでムサシちゃんなの?」
「さっき四桜ちゃんにも話した通り可愛いからだよ!話してみたらムサシちゃん可愛かったしピッタリ!」
男として、可愛いは喜んでいいのか微妙なところで反応に困ってしまうムサシだが、ちゃん付けで呼ばれることを嫌だとは思わない。
きっとそれは、ムサシ自身犬士郎のことを犬ちゃんと呼んでいるからなのかもしれない。
そんなことを考えていると、目に触れられる感覚がし、ムサシの体がビクッと反応する。
「この目って、本当に見えないの?」
「うん。でも、最初の時より困ってはいないから大丈夫だけどね」
「そっか……」
巫兎の声音が一瞬下がったと思うと、ムサシの体は暖かな温もりに包まれた。
柔らかなモノが頬に押し当てられ、洗剤なのか甘い香りもする。
視力以外が研ぎ澄まされているため、今の自分の状況がすぐにわかり、ムサシの顔には熱が宿りだす。
「な、ななな何してるの!?」
「うーんとねぇ、抱き締めてる!」
「そうじゃなくて!何で抱き締めてるわけ!?」
巫兎の考えていることが全くと言っていいほどムサシにはわからず、一応ムサシも男、このままではダメだと思ったムサシが放れようとしたその時、優しい声音が耳に届いた。
「こうされると安心しない?」
その言葉で、ムサシは昔のことを思い出す。
ムサシの両親がまだ生きていたあの頃、自分の特殊な体質を知っても、優しく接してくれた両親のことを。
その体質が怖く、いつ自分の身まで滅ぼしてしまうのだろうかと怖くて泣いてしまうこともあった。
でも、そんなムサシには両親という存在や帰る場所があった。
今は無くなってしまったあの場所、暖かな温もりなどすでに忘れてしまっていた。
だが、こうして久しぶりに人に抱き締められ、温もりを感じ、こんなにも落ち着く自分が今はいる。
「安心、か……」
「一人でこんなとこって寂しいよね。目が見えないって辛いよね。でも、ムサシちゃんは一人じゃないから」
「…………ッ……!」
その瞬間、ムサシは子供のように泣き出し、溢れでる涙はきっと今まで流しきれなかった涙だろう。
一人は寂しい、目が見えないのは怖い、そんな当たり前の感情さえ、今までムサシは抑えてきたに違いない。
そんなムサシ自身が気づいていなかったことを、巫兎は直ぐに気づいていたのだろう。
しばらくして涙が枯れると、ムサシはそっと巫兎から放れた。
視力がなくなったムサシの目は見ることはできないが、きっとその目は真っ赤になっているに違いない。
「どう?スッキリしたでしょ?」
「うん、ありがとう。でも、何で巫兎は俺に構うの……?」
「だって、私はムサシちゃんのお世話係だから!」
今巫兎はニッと笑みを浮かべながら言ったに違いない。
目が見えなくても、そのくらいは声音でわかってしまう。
もし目が見えていたら、巫兎の顔も表情も見ることができたのに、なんて、今頃になって視力を失ったことの大きさを理解する。
そんなことを考え落ち込んでしまうと、不意に巫兎の声が耳に届く。
「そういえば、さっき思ったんだけど」
そう言いながら伸ばされた手は、ムサシの手を包み込むように握る。
その瞬間、ムサシの鼓動が大きく高鳴り、重ねられた巫兎の手からは、柔らかな感触を感じ意識してしまう。
目が見えていないから簡単に襲えないだけであり、今は目か見えなくてよかったと感じる。
そんなムサシの心情など知るわけもなく、巫兎はムサシの手を自分の頬へと触れさせた。
「やっぱり!ムサシちゃんの手、温かい!まるでお日様みたいな手だね!」
その言葉は、昔ムサシのお母さんがムサシに言った言葉であり、そんな風に言ってくれたのは、今までにムサシのお母さんだけだった。
人体発火なんてものを一般の人が見れば、化け物なんて怖がるのは当然で、そんな手は、お日様なんて優しいものではないことをムサシが一番よく知っている。
「アンタは、俺が何をしてここにいるか知らねぇんだよな……?」
「うん。誰も教えてくれなかったからね」
今はもう、ここの奴等に埋め込まれたチップのお陰で火は起こせなくなったものの、新年大会でその力を使い、騒ぎを起こしたことを知ったら、巫兎はムサシをどう思うのか。
巫兎もムサシを怖がり、化け物と言い話してくれなくなるのか、そんなことを考えると胸が苦しくて仕方がない。
だが、いつか知られてしまうなら、今話して結果を出した方のがまだ引き返せる。
「俺は、人体発火って特異体質だったんだ」
「人体発火……?」
「そっ、俺の場合は自在に火が操れたから。そんで色々あってここの刑務所の新年大会で騒ぎ起こして、上の奴等が警戒してるってわけ。まぁ、今はここの奴等に埋め込まれたチップのお陰で火は出せないけどさ」
普通に話してはいるものの、視力がないぶん話終えた後の沈黙がムサシを不安にさせた。
体質のことで化け物なんて思われるのはもう慣れていたはずなのに、今は手が震えそうになる。
きっとそれは、相手が巫兎だからに違いない。
どんな言葉が巫兎の口から出されるのか、ムサシの心臓は苦しいほどに早鐘を打つ。
嫌われてしまうなら、怖がられてしまうなら、これ以上自分の中に踏み込まれる前に拒絶されたいとムサシは思う反面、不安や悲しさが心に渦巻いていた。
だが、そんなムサシの不安など、この一言で一気に吹き飛ぶこととなった。
「新年大会!来年は私も参加したいな~」
「え……そこ?他に気にするべきことはあると思うんだけど」
まさかのスルーに、ムサシは驚き伏せていた顔を上げた。
火を使うなんて技は今のムサシにはできないが、それでも、地下牢に入れられるくらいの騒ぎを起こしたムサシを怖がるのが普通だ。
「うん、気にするべきところはあるよ。そんな体質になりたかったわけじゃないのに、辛かったよね……」
そう、このときムサシはわかってしまったのだ。
巫兎に、普通は通じないのだと。
心配そうな声音は本心からの言葉で、怖がっていた自分がバカらしく思えてしまう。
「これで俺は引き返せなくなっちまったってことか……」
「ん?何か言った?」
「いや、なんでもねーさ」
引き返せない、それは、ムサシが巫兎へと向ける想いのことだ。
あとから離れていかれるくらいなら、今離れてほしかったのだが、巫兎はムサシを受け入れ、ムサシのことを知った今でも普通に接し笑みを向けてくれる。
こうなったからにはこの想いは引き返すことができなくなる。
きっとこの先今よりずっと、ムサシは巫兎に惹かれていく。
《完》