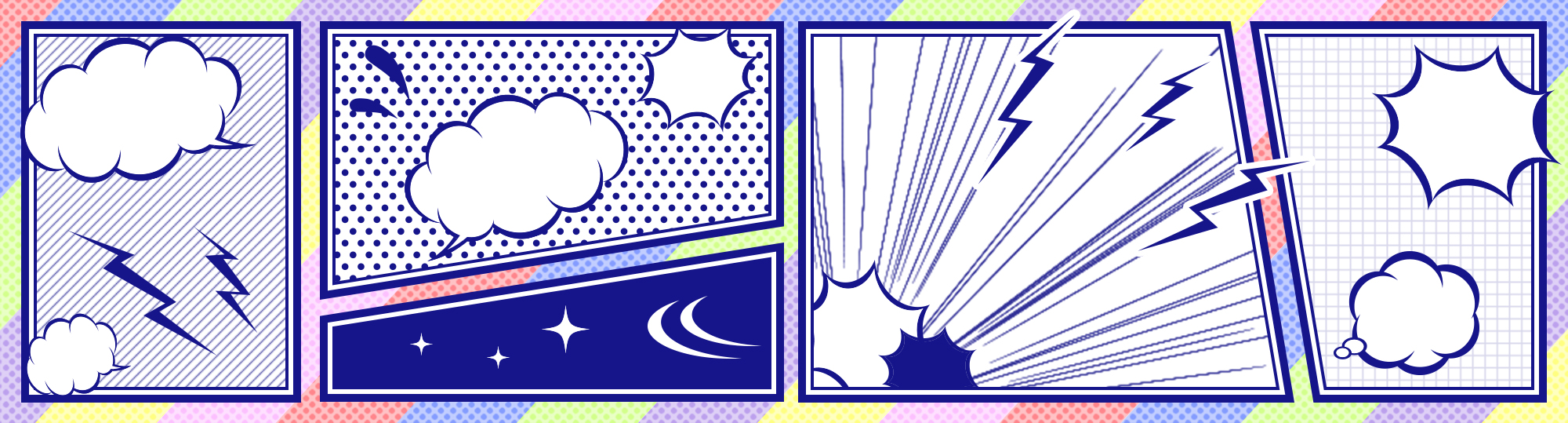makeupは恋を呼び寄せ
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
ここ3舎は、勉学の3舎とも呼ばれているのだが、ここの主任は美しいものが好きな人物だ。
そんな3舎の主任、三葉 キジの元へ、最近手のかかる新人が入ってきた。
「嫌です」
「ダメよ!この3舎の看守なら、美意識を持たなくちゃ」
「そんなの自分だけ持っててください。誰も美意識を持つためにこの職に就いた訳じゃないんですから」
自分の上司であるキジにたいし臆することもなく、新人看守である巫兎はハッキリと自分の意見を口にする。
それも、言ってることが正しいだけに何も言い返すことができないのだ。
「まったくアンタときたら、服装はしっかりしてるのに何で化粧はしないのよ」
「必要ないからです。ここは刑務所、身形は正してもメイクは必要ないですから」
「本当に可愛くない子ね!」
ぷんすこと怒りながらキジは休憩室へ行くと、そこにはハジメと猿門の姿がある。
「機嫌悪そうだな、また新人のことか?」
「もうほんとあったまきちゃうわよ!あの子ったらメイクをしないのよ!?」
「あぁ、そういやいつもしてねーよな」
猿門に愚痴を吐き出すキジを見て、ハジメは小さな声で下らねぇと吐き捨てた。
巫兎が3舎の看守に配属されてからというもの、キジが何度注意をしたところで今回のように拒否されてしまう。
美しいものが好きなキジにとって、美しくないものが傍にあるだけで許せないのだ。
「そうだわ、良いこと考えちゃった!」
その言葉に、猿門もハジメも嫌な予感を感じ、そしてその予感は現実となった。
翌日、巫兎が看守室へとやって来ると、何時もならガミガミ言ってくるはずのキジが何も言わない。
だが、巫兎が看守室へと入ったとたん、キジは巫兎へと近づき腕を掴むと、有無を言わさず椅子へと座らされてしまう。
「ッ!一体なんなんですか!?」
「決まってるじゃない、メイクよ、メ・イ・ク!」
「はぁ……。私はしないって言いましたよね?」
これ以上付き合ってられないと思った巫兎が立ち上がろうとすると、キジに両腕を掴まれビクともしなくなる。
これは男の力であり、巫兎が顔を上げるとキジはニコリと笑みを浮かべた。
その時、目の前にいるのはいつものキジのはずなのに、一瞬男に見えてしまい、不覚にも鼓動が弾んだ自分に巫兎は訳がわからなくなる。
「じゃあ、メイクをするわよ!」
今の巫兎にはキジの言葉など聞こえるはずもなく、ようやく心を落ち着かせると、目の前にはキジの顔がありつい見つめてしまう。
近くで見たキジはとても綺麗で、折角落ち着かせた鼓動が再び高鳴りだす。
「はい、完成よ!」
ようやく聞こえたキジの声にハッとすると、目の前で持たれた鏡に自分が映し出される。
そこに映っていたのは、まるで自分ではない別人のようで、これは本当に私なのかさえ疑いそうになる。
「アナタ、やっぱり美人さんじゃない!」
「……落としてきます」
「えっ!?ちょ、ちょっと!折角メイクしてあげたのに何で落としちゃうのよ!?」
「仕事に必要ないからです」
そういい顔を水でバシャバシャと洗うと、巫兎は失礼しますといい看守室を出ていく。
それからキジの休憩時間となった頃、休憩室ではまたも猿門やハジメに巫兎のことを話していた。
メイクを一度して美しくなった自分を見れば、メイクを好きになってくれるとキジは思ったが、どうやら失敗のようだ。
「何がダメなのよ!あんなに綺麗なのに勿体無いわよ!!」
「お前がそこまで言うほど巫兎は綺麗だったのか?」
「ええ、私達3舎に相応しかったわよ」
そこまで言う巫兎のメイク姿を見てみたいと思う猿門だったが、何考えてんだと頭を振り考えを打ち消す。
「いいんじゃねーの、したくねーってんならしなくてよ」
「はっ!?ダメに決まってんでしょ!!」
「でもお前、それのどこに巫兎の気持ちがあんだよ」
ハジメに言われ気づいたが、確かにこれは自分の考えを押し付けているだけであり、巫兎の気持ちを考えていなかったことに気づく。
今日メイクをしたとき、とくに巫兎は嫌がってなどおらず、自分の変わった姿に驚き瞳を輝かせていた。
そんな巫兎があそこまでメイクをしたがらないのには、もしかしたら理由があるのかもしれない。
「まさかゴリラから教えられるなんてね」
「あぁ!?喧嘩売ってんのか!?」
「キキキッ、ゴリラは合ってんじゃねーか!」
「まぁ、猿は役に立たなかったけど」
「何だとキジ!!愚痴を聞いてやったのに猿呼ばわりかよ!!」
そんな猿門を見て笑うハジメに、猿門とハジメ、もとい、猿とゴリラの喧嘩が始まった。
何時もなら、そんな二人の喧嘩をキジが止めるのだが、喧嘩している二人をそのままにキジは休憩室から出ていってしまう。
そんなキジが向かった場所は看守室だ。
看守室では、巫兎が書類の整理をしており、キジに気づいた巫兎は書類から目を放すとお帰りなさいと言う。
そんな巫兎の元へキジがズカズカと近づいていくと、至近距離まで顔が近づけられた。
「話なさい」
「はい?」
「アンタがメイクをしたくない理由よ。なんかあるんでしょ?」
その言葉の後少しの沈黙が流れると、ゆっくり巫兎の口が開かれた。
「偽者の自分の姿でいたくないんです」
「え?」
「今日キジ主任にメイクをしていただいて改めてわかりました。あの姿は私じゃないって。だから私は、偽者じゃないありのままの私でいたいんです!」
思いもしない言葉に一瞬キジは驚いてしまったが、直ぐに口許には笑みが浮かべられた。
「アンタねー、メイクをしてたってアンタはアンタでしょ?」
「でも、メイクをとったらこんな私ですし……」
どんどん声が小さくなり俯きそうになった巫兎の顔を、キジは手で挟むと、自分へと真っ直ぐ向ける。
重なった視線、近い距離に、巫兎の鼓動が高鳴ったことなどキジは知らない。
「アンタ、メイクをとって本当の姿を見せたら、ガッカリされるとかそんなこと考えてんじゃないでしょうね?」
「はい……」
「はぁ……。もう、そんなヤツは本当のアナタを見てないだけよ!メイクをしようとしなかろうと、内面までは変わらない。アンタは内面が美しいんだから、自信持ちなさい」
そう言い柔らかな笑みを巫兎へと向けるキジは、本当の女のように綺麗で、巫兎の鼓動は更に高鳴り苦しくなる。
「わかったわね?」
「は、はい……」
「じゃあ、早速メイクを始めるわよ!でも、今のアナタにチークは要らなそうね」
「え?」
置かれていた鏡で自分を見ると、何時もの見慣れた姿が鏡に映るが、その頬はほんのり色づいている。
看守室は熱いわけでもないのに、何故か巫兎の頬には熱が宿っているようだ。
「なーに?アタシにそんな顔してくれるの?」
「ッ!こ、これは……」
更に頬を染めていく巫兎の手首をキジは掴むと、腰に手を回し引く寄せる。
近い距離に、キジにも聞かれてしまうんじゃないかと思うくらい、鼓動は早鐘を打つ。
「一応アタシも男だから、その辺よろしくね!」
「ッ……!」
何時ものキジ、そのはずだが、その顔は真剣そのもので男の顔をしている。
「ふふ、本当に可愛い反応ね。いつもは可愛いげないのに」
「そ、それは、キジ主任がメイクメイク言うからで……」
「じゃあ、メイク何て言わない男のアタシなら、アナタはいつもそんな反応をしてくれるのかしら?」
「それは……その……」
腰に回されている手が更に巫兎の体を引き寄せ密着する。
二人の間にある距離はあと数センチで、すでに巫兎の頭も心臓も限界ギリギリとなっていたその時、巫兎を掴んでいた手が緩められ、キジはスッと巫兎から放れた。
「はい、そろそろメイクしましょっか!」
まるで今のことがなかったかのように話が戻されたが、さっきまでのキジの体温がなくなり、何だか寂しいような不思議な気持ちを感じてしまう。
そんな寂しげな表情を見たキジは、巫兎へと耳を近づけると囁くように言う。
「アンタ、アタシに食べられたいの?」
「ッ……!?」
突然のキジの言葉に、今度は耳まで真っ赤に染めキジを見た。
「メイクをすれば崩れちゃうといけないから、簡単には襲えなくなるのよねー。でも、そのままでいたらどうなっても保証はしないわよ?」
本気なのかからかわれているのかわからないまま、巫兎は椅子へと座らされキジの手によりメイクを施された。
そしてその日から、巫兎はキジにメイクを教わるようになったのだが、綺麗になった巫兎の姿に他の舎の囚人も看守も目を引かれ、密かに好意を寄せる者も増えていった。