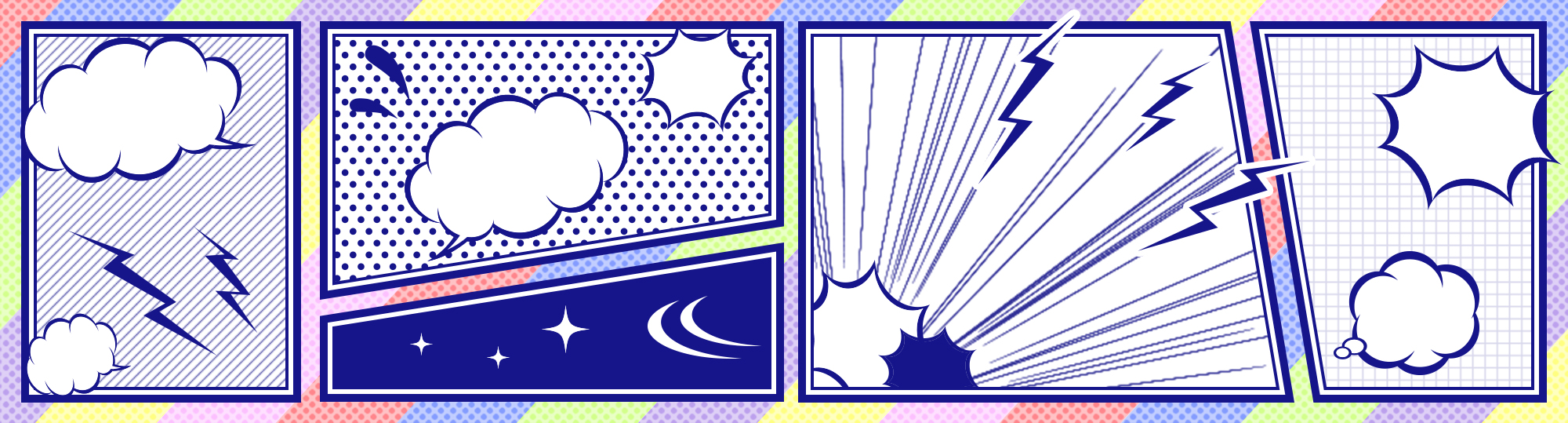時が好きを変えていく
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「そうだなぁ、折角巫兎が手伝うって言ってくれてることだし、少し手伝ってもらうとすっか!」
「はい!何でも言ってください!」
「んじゃ、遠慮なく」
「ッ!?」
伸ばされた猿門の手に突然巫兎の体は抱き締められ、どうしたらいいのかわからず巫兎は固まってしまう。
チィーに抱き締められた時は植物のような香りがしたが、今猿門に抱き締められする香りは、お日様の香りだ。
修行やガーデニングが好きな猿門だ、今日も一人修行にガーデニングとしていたに違いないと、このお日様の香りが告げている。
暖かくて安心する香りに、巫兎はこんな状況だというのに落ち着いていた。
「嫌がらねぇのか?」
「猿門主任から、お日様のいい香りがして落ち着きます」
「ッ……!!」
思ったことを口に出せば、猿門に肩を掴まれ離されてしまう。
「何んなこと平気な顔して言ってんだよッ!?」
「えっと、思ったことを言っただけだったんですけど……。それより猿門主任、顔が真っ赤ですけど大丈夫ですか!?」
「だ、大丈夫だ!!」
耳まで真っ赤に染めている猿門を心配するが、猿門は自分の腕を顔の前にやり隠してしまう。
何か変なことを言ってしまったのだろうかと気にしていると、そんな巫兎に気づいた猿門が腕を下ろし、顔を背けながら口を開く。
「あー……気にすんな、何でもねぇから。それよりやっぱお前は休憩に行っとけ、5舎の奴等の鍛練で疲れてんだろうが」
「はい、わかりました。もし何か私に出来ることがあれば言ってくださいね」
猿門が自分の体を気遣ってくれていることに気づき、これ以上は逆に邪魔になってしまうと思った巫兎は、猿門に言われた通り体を休めようと休憩室へ向かう。
そして巫兎が去った看守室では、猿門が再び椅子へと座ると書類に目を通し始めるが、直ぐにその紙はデスクへと置かれた。
「ッ……何なんだよ、お日様の香りとか落ち着くとか……。んなこと言われたらこっちが恥ずかしくなるっつの……!」
抱き締めた時、猿門からお日様の香りがした、そう言った巫兎だが、同じ様に猿門も巫兎からお日様の香りを感じていた。
5舎の鍛練の様子をこの暑い中ずっと監視していれば、巫兎からお日様の香りがするのも当たり前だ。
「俺だけかよ、こんな気持ちになんのは……」
猿門の胸は巫兎を抱き締めた時からずっと早鐘を打っている。
だが、そんな猿門とは対照的に巫兎は、頬を赤らめてさえいなかった事実に、猿門一人落ち込んでいた。
そんな猿門の気持ちなど知るよしもない巫兎は、休憩室で猪里とお喋りをしていた。
「猪里先輩、今日もサボってましたよね?」
「わりぃわりぃ!今日は競馬の中継があってさー」
「そうなんですか」
「あれ?怒んねーの?」
猿門や他の看守なら怒るところだが、巫兎は全く怒る気配がない。
「何故怒るんですか?中継を見に行けるほど、私達看守のことを信頼してくださっていると言うことじゃないですか!」
「うッ……。お前、それわざとじゃね?」
「え?何か私可笑しなことを言ったんでしょうか?」
不安げに尋ねる巫兎は、間違いなくわかってはいない。
そんな純粋な巫兎は猪里にとっては相性が悪く、そのあと猪里はサボらず働く事となった。
「何だアイツ、休憩から戻ってきた途端に真面目になりやがって。頭でもぶつけたのか?」
そんな猪里の姿を猿門は珍しそうに見つめると、巫兎に巡回に行くように指示を出す。
巡回といっても滅多にトラブルなどは起こらず、巫兎はいつも通り全ての房を見て回る。
「えっと次は、8房ね」
8房の扉を開け中へ入ると、そこにはリャンとウパ、チィーの3人の姿がある。
「うん!全員いますね」
確認が終わり房を出ようとしたその時、突然背後から腕を掴まれるとそのまま引っ張られ、背中が何かにぶつかる。
一体何が起きたのだろうかと振り向こうとすると、後ろから抱き締められてしまい身動きがとれなくなってしまった。
顔だけ見上げるようにして後ろを振り返れば、リャンの顔が目の前にある。
「リャンくん、どうしたの?」
「巫兎さんは、私のことをどう思いますか……?」
突然の質問に一瞬黙ってしまったが、直ぐに口を開き質問に答える。
「どうって、頑張りやさんだなって思うよ。今だって筋トレをしていたんですよね?汗をかいていますよ」
背中に熱いくらいの体温を感じ、筋トレをしていたなんて直ぐにわかる。
「私のことをわかってくれるのは嬉しいですが、肝心なことはわかってくれないのですね」
「肝心なこと……?」
一体何のことだろうかと考えていると、ウパの声が耳に届く。
「リャン、ボク達がいることを忘れていませんか?」
「わかっている。それよりもウパ、嫉妬はしないんじゃなかったのか?」
「これは嫉妬ではありません。巫兎さんが困っているようなので男として助けようとしたまでです」
何やら巫兎の背後で二人火花を散らせているようだが、一体何の話なのか巫兎にはさっぱりわからない。
何だかよくない空気だけは感じ取った巫兎は、どうしたらいいのか考える。
すると、壁に背を預けこちらを見ていたチィーと目が合った。
不安げに見つめる巫兎の瞳を見て、チィーはリャンとウパの間へと入る。
「なんですかチィー!」
「邪魔をするな!」
「二人ともさー、巫兎ちゃんにこんな顔させていいわけ?」
チィーの言葉で二人が巫兎へと視線を向けると、不安げに眉を寄せる巫兎の姿がそこにはあった。
そんな表情をさせたかった訳じゃないリャンは、巫兎から腕を放す。
「すみません……。アナタを困らせたかった訳じゃないんです。ただ私は、アナタに見てもらいたくて……」
苦しそうに声を漏らすリャンに、ちゃんと見てるよと言いたかったが、何故か巫兎はこの時、リャンが言っているのはそういう意味ではない気がし、何も言うことが出来なくなってしまう。
視線を下へと向けるとリャンの直ぐ横で、手にぎゅッと力を込め顔を伏せているウパの姿があった。
「ウパくん……?」
「ボクは、やっぱりアナタに相応しい男にはなれないんでしょうか……。アナタにそんな顔をさせてしまうボクには……ッ!」
二人の顔は苦しそうに、辛そうに歪み、そんな二人の気持ちをわかってあげられない巫兎が何を言っても、二人に届かないと感じた。
自分まで顔を伏せそうになったその時、肩にぽんっと手が置かれ、下げかけた顔を上げれば、笑みを浮かべるチィーの姿がある。
「巫兎ちゃんは巫兎のままで、思ったことを二人に伝えてあげて」
その言葉に背中を押され、巫兎は二人へと向き直ると、思っていることをちゃんと伝えようと口を開く。
「私には、二人がどんなことで悩んでるのか正直わかりません。でも、きっと二人にそんな顔をさせてしまっているのは私なんだということはわかります……」
わかってあげられたらどんなにいいだろう、でも、そんなことを思っていたところで今の二人には届かない。
「だから、これからもっと二人のことを教えてください!」
巫兎の言葉1つで、リャンもウパも顔を上げた。
それは、自分のことを知りたいと、わかりたいと思ってくれた巫兎の気持ちが嬉しかったからだ。
こんな単純なことでも、何の解決にもなっていないことでも、可能性が少しでもあるのなら、今はそれだけで十分なのだ。
「あらら、純粋な子達だねぇ。俺なら、可能性なんかじゃなくて体から先に」
「黙れクズッ!」
「巫兎さんを汚すな!」
「酷くない!?陰でお手伝いしたのにさ!」
好きの種類は人それぞれで、恋愛、友情、色々ある。
でも、もしその種類が違うかったとしても、その好きは簡単なことでまた変わっていく。
そう、この4人の好きが、この先巫兎に届くことがあるかもしれないということだ。
きっとその時には、好きの種類が今と変わっているに違いない。
《完》