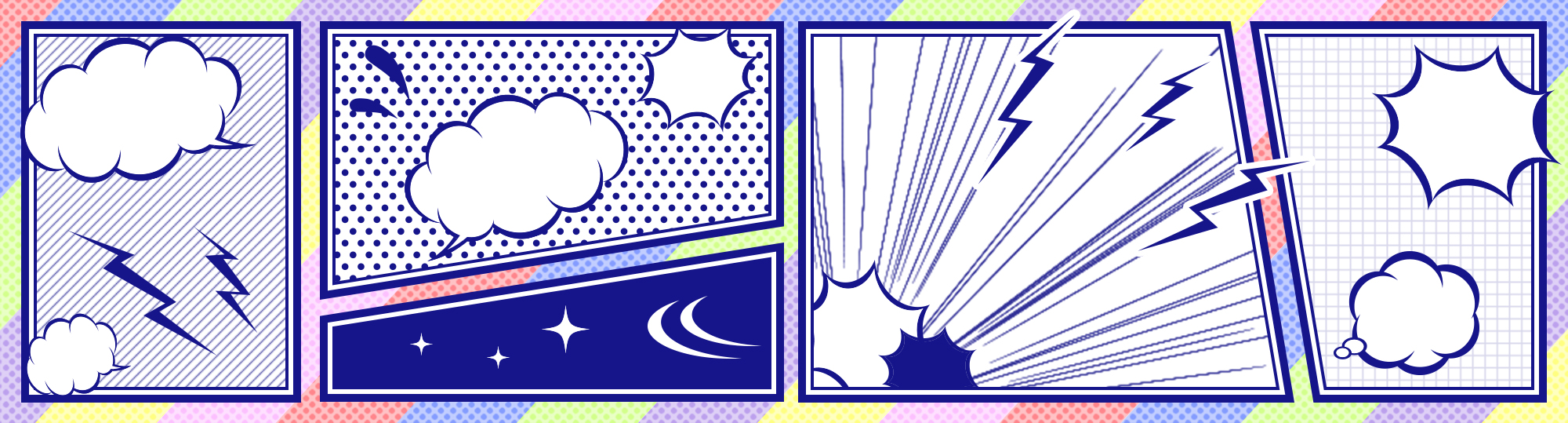秘めた想いに期待をし
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「サンキューな。だがよぅ、もっとましな柄はなかったのか?」
「文句言わないでください!それ、私のお気に入りの絆創膏なんですからね!!」
折角貼った絆創膏に文句を言われた巫兎はぷんすこ怒っているが、その時の猪里がどんな顔をしていたのか、この時の巫兎は気づいていない。
頬を染め、幸せそうに笑みを浮かべる猪里の顔に。
「お前ら何騒いでんだ?」
「主任じゃないっすか」
「猿門主任!?な、何故ここへ?書類の整理などがあったのでは……」
そんな二人の元に現れた人物は、巫兎が憧れている猿門だった。
猿門が現れるなり、巫兎は瞳を輝かせている。
そんな巫兎を見て猪里の胸が軋むのは、恋をしている何よりの証拠だ。
「あぁ、それならもう済ませた。それよりも、今日はサボらず仕事してるみてぇだな猪里」
「主任が厄介なのを俺につけさせてくれたお陰ですよ」
「そうか、巫兎に頼んだのは正解だったみてぇだな。巫兎、俺がいない間、猪里を見張ってくれてサンキューな!」
「いえ、猿門主任のお役に立てるのなら私は何でもしますから!!」
猿門の役に立てたことが余程嬉しいのか、巫兎の頬がほんのり色づいていることに猪里は気づいていた。
だが、猪里は気づいている、巫兎が猿門へ向ける気持ちは憧れなんかじゃなく恋心なんだと。
「そりゃ助かるぜ!このまま巫兎に猪里を見張っててもらうのもいいかもしれねぇな」
「はい、任せてください!」
猿門は冗談を言うようにキキキッと笑いながら言うが、巫兎は本気で言っているようだ。
そんな二人が話す姿を見ていると、猪里の心に陰が差す。
だが、そんな素振りは一切見せず、勘弁してくださいよと猪里は苦笑いを浮かべる。
「それが嫌ならサボらねぇ事だな!」
そう言う猿門だが、猪里にとっては巫兎に見張られるのは願っても無いことだ。
だからってそんなこと口が避けても言えるわけもなく、嫌がる振りをして見せると、気を付けますと返事を返す。
「まぁ、今日は一日巫兎に監視されながら反省するんだな。んじゃ、引き続き任せたぜ、巫兎」
「はいッ!!」
猿門が巫兎に任せた仕事、それが嬉しくて巫兎の口許は緩んでいるが、それとは対照的に猪里の口は弧を描いている。
それもそのはずだ、猿門が現れてからというもの、巫兎は嬉しそうに笑みばかりを浮かべているのだから。
それと比べて猪里に向ける表情は笑顔より怒りのが多く、サボってばかりいれば無理もないことだが、好きな女が他の男に笑顔を向けているのはいい気がしない。
「おーい!どうしたんですか?」
「うわッ!?」
頭でいろんな感情が渦巻いていたため考えていると、突然目の前に巫兎の顔が近づき、驚きに後ろへと下がってしまう。
「そんなに驚かなくても……。人をお化けみたいに」
「突然覗き込まれれば驚きもするっつの!」
そうは言ったものの、普通はこんな驚き方はしないだろう、好きな相手だからこその反応だったのだから。
どうやら猪里が考えている間にその場を去ったらしく、すでに猿門の姿がないことに気づく。
「声をかけたのに返事がないから覗き込んだんですよ。どうしたんですか?何だかいつもの猪里らしからぬ険しい表情でしたけど」
顔に出さないようにとしていたつもりだったのだが、気づかないうちに表情に出ていたようだ。
だが、巫兎が猿門に笑顔を向けてるのが気に入らねぇなんて理由が正直に言えるわけもない。
「お前に今日一日ずっと監視されてたらサボれねぇからな、そりゃそんな表情にもなるだろうよ」
「はぁ、そんなことだろうとは思ってましたよ。本当にサボることしか頭にないんですから……」
適当な理由をつけてみたが、サボるしか頭にないという巫兎の言葉に、猪里の眉がピクリと動く。
今まではサボることしか頭になかったかもしれないが今は違う。
「サボることしか、ねぇ……。そりゃどうだろうな」
「え?」
猪里の言葉に首を傾げる巫兎だったが、猪里はそれ以上何も言わず、ニッと笑って見せた。
今は自分の想いを伝えることはできない。
巫兎の心が猿門にある以上、伝えたところで失恋確定なのは目に見えている。
「お前はどうしたら、俺を見てくれんだろうな……」
「何かいいましたか?」
「いや、なんでもねぇよ」
猪里の想いが届く日が来るのかはまだ誰にもわからないが、このまま引き下がるのも男としてダメであり、そもそも諦められるくらいの軽い想いなど生憎持ち合わせてはいない。
いつか自分を見てほしい、そう心で呟きながら、巫兎監視の元で今日はサボる暇なく仕事をする。
そうしたら、少しは自分も見てくれるんじゃないかと淡い期待を胸に秘め。
《完》