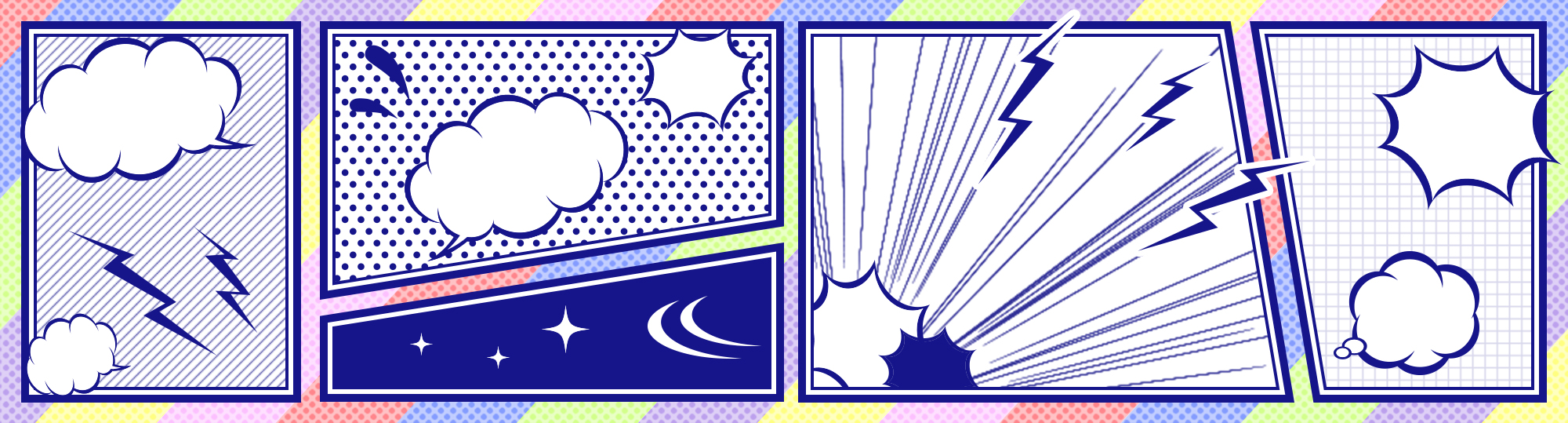秘めた想いに期待をし
名前変更
名前変更お話にて使用する、夢主(主人公)のお名前をお書きくださいませ。
【デフォルト名】
巫兎(みこと)
囚人番号:211
※囚人番号は固定となります。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
お昼の暖かな日差しの中、演習場のベンチに座り競馬新聞を見ながらサボっている一人の男がいた。
この男こそ、5舎主任看守である八戒 猪里なのだが、仕事もせずにいつもサボることばかりを考え、競馬や麻雀などを仕事中にするなどかなりのサボり魔だ。
注意したところで反省などする筈もなく、結局サボる毎日となる。
「おっ!そろそろ競馬中継が始まる時間だな」
「い~の~り~せ~ん~ぱ~い~ッ!!」
競馬中継を見に休憩室へ向かおうとする猪里だったが、背後から殺気を孕んだ声が聞こえ振り返ると、そこには、最近入ったばかりの新人看守の姿がある。
「今は8房の鍛練の様子を見張るのが仕事のはずですが、その手に持っているものはなんですか?」
「け、競馬新聞……」
「はい、没収!!」
巫兎は猪里から新聞を取り上げると、キッと鋭い視線で睨み付けた。
そんな巫兎の視線に猪里は、頬を掻き苦笑いを浮かべているが、ほおっておけばまたサボるのは目に見えている。
「どうせ私がいなくなったら競馬中継を見に行くつもりでしょう」
「ははは、バレたか。あ!お前もどうだ?一緒に競馬」
「結構ですッ!!」
猪里が言葉を言い終わるより先に巫兎は拒否する。
猪里が仕事をサボるのはいつものことで、今日はサボらせまいと巫兎は猪里の隣に座る。
「あれ?お前仕事しなくていいの?」
「はい。今日の私の仕事は猪里先輩がサボらないように見張ることですから」
「ゲッ!マジかよ……」
「はい。猿門主任に頼まれましたから!」
ここ5舎には、主任の悟空 猿門、副主任の八戒 猪里、そして他に、私も含め4名の看守もいるのだが、巫兎はここの主任である猿門に憧れている。
囚人にも看守にも厳しく、時に優しく、囚人達との手合わせや鍛練をする姿はとてもかっこよく、尊敬する者も少なくない。
だが、そんな人が主任を務めるこの5舎で、何故副主任がこんなサボり魔なのか、巫兎は納得できずにいる。
「はぁ……。今日の競馬はお預けかよ……」
「今日はではなくずっとです!アナタがサボるから猿門主任の仕事が増えるんですよ!!」
「アナタって……俺、一応副主任なんだけど……」
「副主任だというのなら、サボらず猿門主任のようにしっかり仕事をしてください!!」
言ったところで反省どころかどうやってサボろうか考えているに違いないが、猿門から頼まれた事だ、絶対にサボらせたりはしない。
そんな二人の元へやって来たのは、グランドを走り終えた囚人番号2番のリャンだった。
「猪里さん、今からお相手していただけませんか?」
「いや、俺はこれから競馬の……」
横から殺気を感じ、いいかけた言葉を呑み込むと猪里は渋々了承する。
そしてリャンとの組手が終わるまでの間、猪里がサボらないように、ベンチに座りながら巫兎は二人の様子を眺めていた。
こうして見ていると、猪里も弱いわけではないのだが、問題はあのサボり癖だ。
目を放せばサボり、巡回に行かせればリャン達のいる8房で麻雀をしていたり、競馬中継を見ていたりと結局サボってしまう。
他の看守は皆働いているというのに、副主任がこんなでは猿門の苦労は耐えず、そんな猿門に迷惑をかける猪里が巫兎は許せないのだ。
「はッ!!猪里さん、最近体が鈍ってきたんじゃないですか?」
「っと、あぶね!まぁ年だからな」
「サボってばかりいるからですよ」
お互いに組手を交わしながら話していると、猪里の視線が一瞬別の場所へと向けられた。
その隙をリャンが見逃す筈もなく、突きの一撃が猪里にヒットする。
「ぐはッ!お前、加減って言葉を知らねぇのかよ……」
「余所見をしていたのに何を言ってるんですか。猪里さんならこんなの簡単に交わせたでしょう。まぁ、誰を見ていたのかはわかりますが」
「うッ……」
猪里が見た方へとリャンが視線を向ければ、そこには巫兎の姿がある。
「猪里さん、わかりやすすぎです」
組手を終えた猪里が巫兎の元へ戻ると、苦笑いを浮かべながら頬を掻く。
「情けねぇとこ見られちまったな」
「情けないというのは、サボってる時の猪里先輩のことをいうんですよ」
「厳しいなぁ……」
苦笑いを浮かべいつも通りの反応を返すが、内心では猪里のダメージは大だった。
好きな女の前でカッコ悪い姿ばかり見せている自分は情けないとは思うものの、今から急に真面目になるなんてのも難しい話だ。
サボり癖なんてのはどうとでもできるが、これがなくなってしまったら巫兎と話す機会が無くなるような気がしてしまう。
そんなことを考えながら苦笑いを浮かべていると、突然伸ばされた手に猪里の腕は掴まれてしまった。
その手は明らかに男のものとは違い、色白で綺麗なその手に鼓動が音をたてる。
こんな手をしているのは猪里が知る限り一人だけであり、この手の人物に気付くと動揺してしまう。
「な、何して……ッ!?」
「はい、これでよし!」
「あ?」
そう言い放された腕を見てみると、そこには絆創膏が貼られていた。
女らしい可愛い柄がプリントされた絆創膏に首を傾げると、巫兎はニコリと笑みを浮かべ口を開く。
「さっき2番くんと組手したときに、腕を怪我してたみたいですから」
全然気づかなかったが、こうして自分のことを見ていてくれる存在がいてくれたことに、なんだか照れ臭くなり頬を掻く。