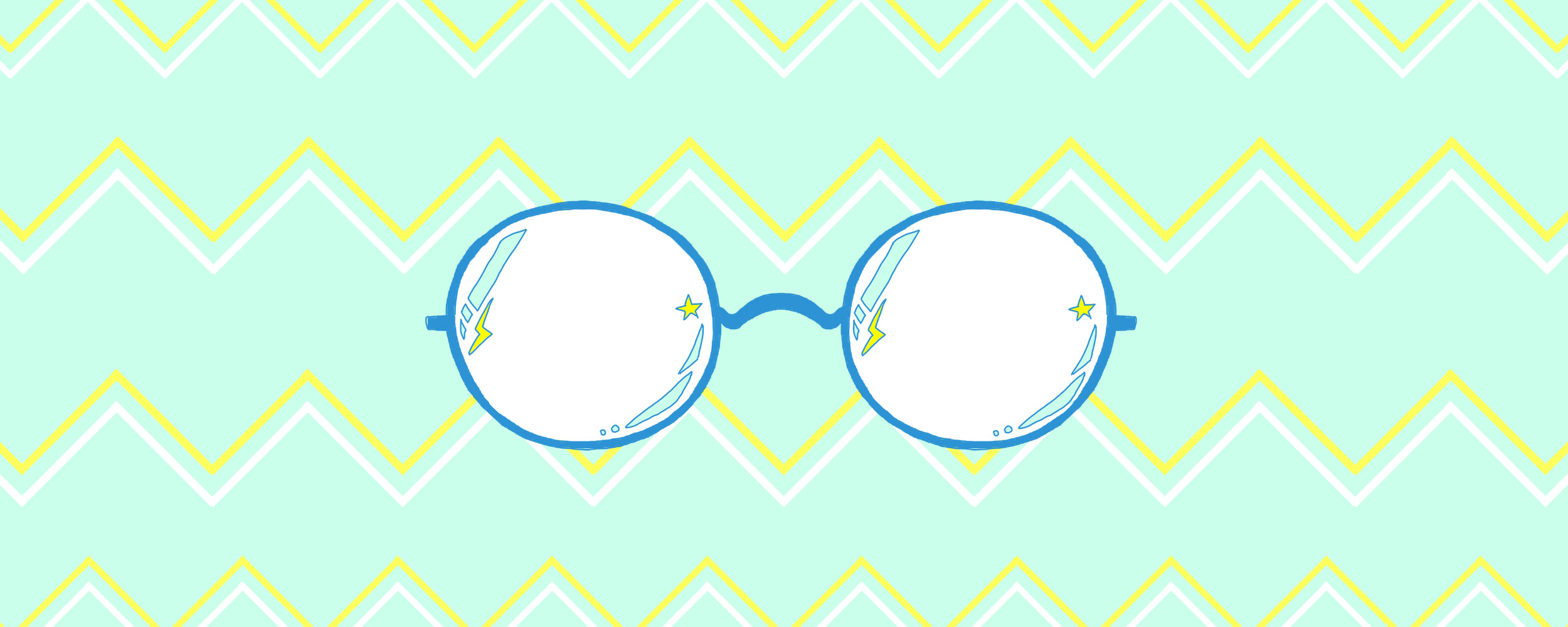青学生活
名前変換
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
あたしは今、ベッドに横たわっている。うっすらと目を開け、今自分が保健室にいるんだと、天井を見て理解し、また瞼を閉じた。
何故、こんなことになってしまったのかというと…
~10分前~
『手塚、ちょっといい?』
『どうした。』
ダッシュや外周などの練習メニューで測定した記録をまとめ、乾にグラフ化してもらった。そこから今のみんなに必要な練習を、乾と一緒に考えたので、手塚に見て貰おうとした。
その説明をし、手塚があたしのノートを手に取ってパラパラ見ていた。どういう反応するかな、なんてドキドキしながら手塚の様子を見ていると、
『危ない!』
誰かの叫び声が聞こえたと思ったら、後頭部に一瞬鈍い痛みを感じ、そのまま視界が暗転した。
どうやら、部員の誰かが打ったボールが、あたしの頭にぶつかったらしい。ボールが頭にぶつかって気絶するなんて、マンガくらいなもんかと思っていた。まさか実際自分が体験してしまうとは。
まだ後頭部に残る痛み。きっとタンコブができているに違いない。気絶したショックと恥ずかしさで、起き上がる気にもなれず、けど部活に戻らないと、なんて考えていると
「冷やすもん持ってきたっス。これでいいっスか?」
シャーッとカーテンが開いた音がした。
「あぁ。貸してくれ。それと、タオルだ。」
「はい。」
今入って来たのはリョーマで、すぐそこには手塚がいるのだと声で分かった。他に話し声がないので、保健室にいるのはあたしを含め三人か、とぼんやり思っていると、枕の隙間に手が入り、その大きい手はあたしの首と頭の付け根を包み込むようにして、ゆっくりと持ち上げた。
そしてまた、ゆっくり降ろされて、後頭部にひんやりとした感覚があった。氷枕だろうか。
いい加減目を開けて、付いててくれた二人にお礼言わなきゃ、と思った時。
「越前。」
「何スか?」
「さっきのツイストサーブはコントロールミスか?」
「まさか。」
「ではレシーブミスだな。」
「そっス。」
なるほど、リョーマの全力のツイストサーブを返しきれず、ガットには当たったもののこっちに飛んできちゃったってわけね。
ていうか、この二人の会話なんて、滅多に聞けないんじゃないか?青学の柱と柱はどんな話するんだろうなんて、好奇心がわいてきて、もうしばらく目を閉じて寝たふりを決め込むことを決めた。
「………。」
「………。」
で、しゃべんねぇのかよ!
その沈黙にこちらが気まずさを覚えると
「起きませんね。伝説のハジケリスト先輩。」
「当たり所が悪かったのかもしれないな。」
そう言うと、手塚があたしの首筋に指を当ててきた。ちょっとびっくりした。
「熱はないし、脈も正常だ。」
「じゃあ大丈夫ってことっスね。」
「あぁ。今のところはな。」
「じゃあ部長は練習戻っていいっスよ。俺がついてますんで。」
「いや、ここは俺が引き受ける。お前は練習に戻れ。」
「でも、元はと言えば俺の打ったボールのせいだし。」
「関係ない。近くにいたのに未然に防げなかった俺に責任がある。」
あれを未然に防いだら最早人間じゃないと思うよって、起き上がって突っ込みたい。
「部長一人じゃ心配なんで、俺も看てていいっスか?」
「…好きにしろ。」
なんだかんだでリョーマは手塚を慕ってるし、手塚もリョーマには期待してるからね、なんか微笑ましいな。
すると、パイプ椅子がギシッと鳴って、リョーマがそこに座ったんだと分かった。
で、
「………。」
「………。」
結局無言の時間が続いていた。二人とも元々無口だっていうのもあるし、手塚なんて話し掛けづらいランキング、年間堂々ナンバーワンのお方だ。
このままではリョーマも可哀相だし、今度こそ起き上がろうと思ったけど、
「部長。」
「何だ。」
「図書室、新しい本入ったっス。」
「本の名前は?」
「覚えてないけど、部長が好きそうな難しい本でしたよ。全部で10冊くらい。」
「そうか。」
リョーマ偉い。クールなところは今も変わらないけど、最初の頃なんて、仲間はいらない、強い相手と戦うことだけしか望まない、みたいな感じだったけど、今や青学の中心にいて、みんなから可愛がられてる。リョーマもみんなに心を開いてきているのが分かる。
現にこうしてテニス以外の話題でも話し掛けていて、あぁ、この子成長したなぁなんて、しみじみ思う。
「………。」
「………。」
それからまた沈黙が始まり、手塚も先輩として何か言ってやれよ、と思っていると
「ベンガル…」
今度はなんと、手塚から話題を切り出した。
「は?」
「ベンガルは元気か?」
ベンガルって何だろう。リョーマの友達?
「あの、ベンガルって何スか?」
「お前は家で猫を飼っていたと思ったが…。」
「カルピンのことっスか?」
「カルピンか、すまなかった。」
「…いえ。」
「………。」
「………。」
ベンガルってちょっと…確か芸人か俳優でそんな名前は聞いたことあるけど…なんていうか…。人んちのペットの名前間違えて、手塚のことだからいたたまれないだろう。ていうかあたしがいたたまれない。
手塚、たまに口を開いたらやっちまった、の場面に遭遇しておいて、助け船を出さないわけにはいかない。
二人のためにもあたしは意を決し、ついに上体を起こした。
「あ、起きた。」
「気付いたか。」
「うん、二人ともずっと付いててくれたの?」
「まぁね。もう起きて平気なんスか?」
「気持ち悪かったり、体に異変は無いか?」
「うん、大丈夫。ちょっと頭がおかしいだけ。」
間違えた、ちょっと頭が痛いだけ、と言おうとしたのに。
「頭おかしいのは元からじゃない?」
「ちょっと!」
「越前、怪我人を刺激するな。伝説のハジケリスト、立てそうか?」
「うん。」
「今日はもう帰った方がいい。念のため病院にも行っておけ。さっきのノートは今日目を通しておく。」
「分かった。」
「越前、伝説のハジケリストの荷物を持ってきてくれるか?」
「ウィーッス。」
「リョーマごめんね。」
保健室を出て行くリョーマを見送った後、手塚の目を見て、静かに言った。
「手塚、ドンマイ。」
しばらく無表情のまま見つめ合ていると、手塚は目を伏せた。
「聞いていたのか。」
「うん。ごめん。」
「………。」
「………。」
その後の手塚の沈黙が気まずくて、なるほど、これが原因だと分かった。手塚の沈黙が心地良い時もあるが、この状況でそう感じることができたら天才だ。
何か言えよと言ったところで、手塚には巧みな話術が無い。よって、お互い余計に気まずくなるのがオチだ。
このままこれが手塚の個性であると受け入れるか、手塚の会話力を高めるために何かできることは無いか考え、提案し、実行するか。
明日大石にでも相談してみようと決意をし、一刻も早くリョーマに戻って来て欲しいと切に願った。
終わり
【後書き】
これを書いていて気付いたのですが、かっこいい手塚を書くのは難しいですね。いや、実際手塚はかっこいいし、頼りになる男です。ですが、彼も仲間達と部活を通じて親好が深まり、天然部分をチラチラ見せるようになったクチかと思います。
不二はサラッと「え?今何ていったの?」とつっこみ、菊丸も「えー!手塚ありえなーい!超ウケる!」と言えるタイプです。
後輩達はなかなかつっこめず、おいおい、ここはつっこんでいいのか?と困ります。
タカさんは寛大に受け止め、乾は冷静に手塚の発言を分析、大石は手塚のフォローに回れば理想的です。
「違うんだよ!な?手塚。手塚はホラ、違うんだよ!」
そしてそのフォローが手塚をより追いつめる結果になることが多々あるよ、とかならなお理想的です。
ここまでお付き合い頂いてありがとうございました。