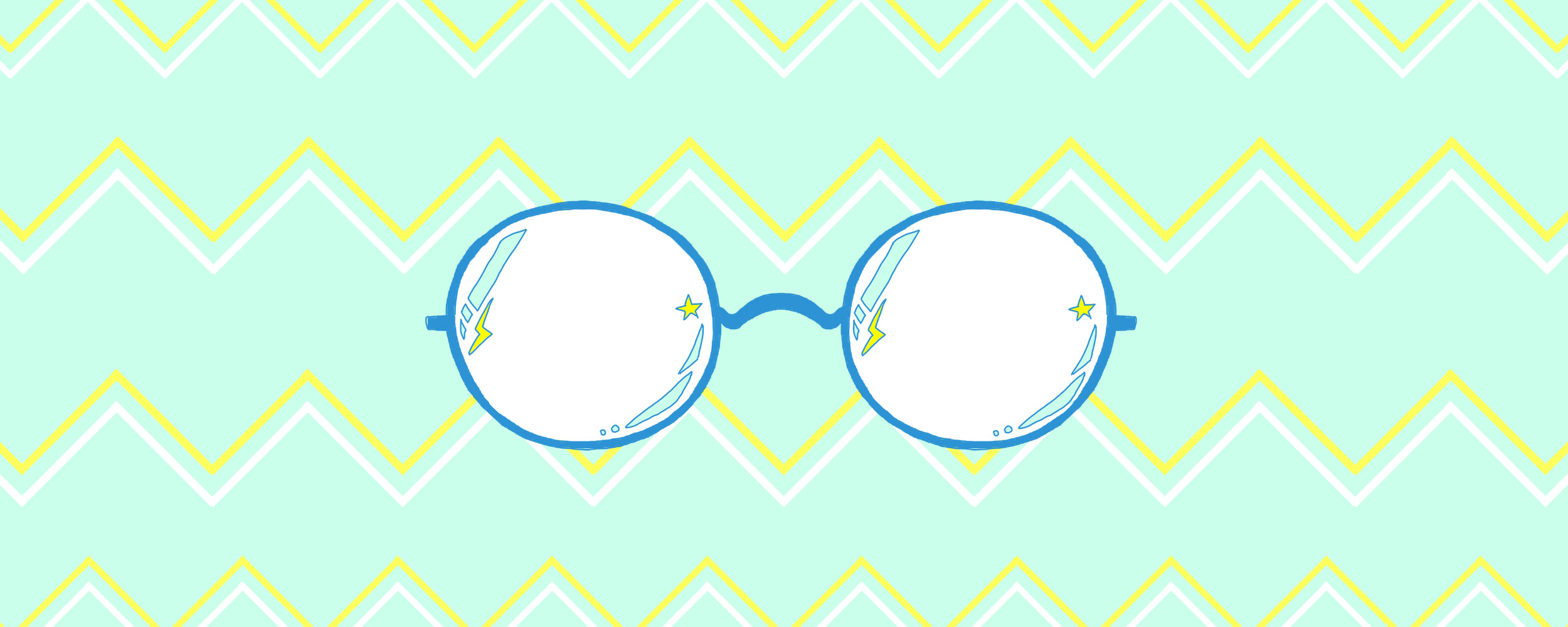青学生活
名前変換
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
『サイクリングロード』
部活も終わり、着替えを済ませた桃城は、越前と二人で駐輪所に向かった。
「腹減ったー!なぁ、なんか食って帰ろうぜ!」
「いいっスね。」
慣れた感じで桃城の肩につかまり、越前は桃城の愛車(モモスペースギア)の荷台に立った。
それを確認してから、桃城はペダルをこぎ始める。遅くもなければ速くもないスピードで。
「今日はマックにしようぜ。」
「そっスね。」
寄り道の場所を決めると、マックを目指して角を曲がる。桃城は口笛を吹きながら、何を食おうかと考えを張り巡らせていた。
「ねぇ桃センパイ。」
「おう、どうした。」
「ストレッチの時、なんで笑ってたんスか?」
桃城は驚いた、といより焦った様子で越前の顔をバッと見上げた。
「桃センパイ!前…!」
「え…」
ドンッ!!
「うっ…」
余所見をしてしまったせいで、民家の石垣に衝突してしまった。しかし自転車は倒れず、衝突の衝撃を受けただけだった。
「大丈夫っスか?」
衝突寸前に自転車から飛び降りた越前が、桃城に駆け寄る。衝突しゆく先輩を見捨て、自分だけ脱出したのだ。
「あぶねーな、あぶねーよ…」
「まったく…気を付けてくださいよ。」
「あ、あぁ、悪いな!」
自転車の方向を変えると、越前はまた桃城の後ろに乗った。
「つーか、何でそんなに驚いたんスか?」
「いや、なんでもねーよ!」
「ふーん…。ま、いいけどね。」
ストレッチが“ひとりえっち”に聞こえたなんて、恥ずかしくて言えない。俺はどうかしている、思春期過ぎる、越前がその手の話をするわけがないじゃないか、と心を落ち着かせてハンドルを握った。
「早く行きましょーよ。腹減って死にそうなんスけど。」
桃城は、俺の方が死にそうだったと思いながらペダルをこぎ始めた。
急な坂道に差し掛かったので、立ちこぎで力いっぱいペダルを踏む。
「ねぇ桃センパイ。」
「…なんだ…。」
息も絶え絶えに聞く。いくら桃城といえど、部活の後の坂道はキツかった。だがこれもマックのためだと思えば乗り越えられる。
「立海戦、楽しみっスね!」
「…あぁ…そ…そうだな!…」
今の桃城は、立海戦よりもマックが楽しみだ。だが先輩としてそれは口に出してはいけない、いや、この坂道の前ではまともに話すことすらままならない。
「皇帝…だっけ?部長と同じくらい強いんでしょ?」
「Σど…?!」
その瞬間、ペダルをこぐ足を踏み外し、思い切り股間を打った。桃城は自転車から降り、その場でうずくまった。
「ちょっ…!大丈夫っスか?!」
越前の問いかけにも答えられず、ただうめき声を上げるばかり。そんな桃城を見るに見かね、越前は桃城の腰を叩いてあげた。いくら“自分さえ良ければそれで良い”をモットーに生きている越前でも、男同士、その痛みは痛いほど分かる。
「桃センパイ、さっきからおかしいっスよ?」
皇帝が“童貞”に聞こえたなんて、ましてやそれが原因で股間を打って瀕死状態になっているなんて絶対に言えない。ホントどうしたんだ俺、過敏すぎるぞ、部長と同じくらい強い者の総称を童貞って言うのはおかしいだろ、しっかりしろ俺、と、激しい痛みの中で自分に言い聞かせた。
そんな痛切な表情の桃城を見て、越前は桃城の様子を気にしていた。
テニスで悩みがあるのでは…と。
しかし、越前は「自力でなんとかしろ」というタイプなので、敢えて何も聞かなかった。
お腹は鳴っているけれど、桃城の股間が落ち着くまで待っててあげよう、それくらいはしてあげようと、越前はしばらく桃城の背中を叩いていた。
それは丁度、夕方5時のチャイムが鳴った時だった。
終わり
1/25ページ