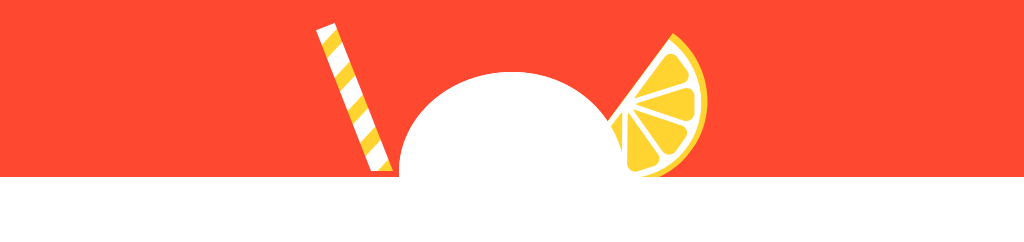コラボ阿弥陀
名前変換
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
下校途中、突然雨が降り出した。
もちろん傘など持っていなかったあたしは、慌てて近くのコンビニへと避難した。
入ってすぐの雑誌コーナーに移動すると、そこには見慣れた後輩がいて、ジャンプか何かを立ち読みしていた。
「リョーマ。」
名前を呼ぶと、ジャンプからあたしへと視線を移し、どうもと軽く挨拶をしてきた。
「リョーマも傘無し?」
「先輩も?」
「うん。だって天気予報見てなかったし。」
「俺は見てたけど、降るなんて言ってなかったっスよ。」
いきなり勢い良く降りだした雨。きっと夕立かなんかだろうから、すぐ止むかもしれない。けど、いつ止むか分からない雨をコンビニでやり過ごすのは気まずいってもんだ。
「ねぇ、隣のファミレス移動しない?」
「別にいいっスよ。」
せーのでコンビニを出て、すぐ隣のファミレスに駆け込んだ。ファミレスなら長居しても気まずくないし、ジュースでも飲みながら話していれば、あっという間に時間が過ぎるだろう。
そんなことを考えながらメニューを開いた。
「そういえば、一人で帰ってるなんて珍しいじゃん。桃は?」
「さぁ。何か急いでたみたいっスよ。」
「ふーん。で、頼むもの決まった?」
「決まったっス。」
桃の急いで帰った理由に特に興味はないので、テーブルにある呼び出しスイッチを押した。するとすぐ、店員がやってきた。
「ドリンクバー二つで。」
「あ、あとチョコレートパフェ。」
さりげにリョーマが魅力満載のオーダーをしたので、
「を二つ。」
と、すかさず頼んでしまった。最初はパフェを頼もうか迷ったけど、一人で食べるのは何かアレなのでやめようと思っていたが、これなら心置きなく食べられる。
メニューを渡し、ドリンクバーでそれぞれ好きな飲み物を持ってきて、ようやく落ち着くことができた。
外はまだ雨が降っており、先ほどよりも強くなった。
「……。」
「……。」
リョーマと二人きりになったことがないことに気付くと同時に、それ故に話題が見つからないことにも気付いた。
共通の話題といったらテニス部のことしかなく、私生活においての共通点など全く無いに等しい。
なら、テニス部の話をしよう。
「ねぇ。」
「はい?」
「関東大会の不二戦覚えてる?あんたがベンチコーチ席に座った時の。」
「覚えてるっスよ。」
「あの消えるサーブ、あれ近くで見るとどんな感じだった?」
乾がカットサーブだからどうたらこうたらと言っていたが、あたしには半分も理解できなかったあの消えるサーブ。かの星飛馬だけに許された球種だと思っていたが、実際にやってのけたのがうちの部員だ。
「どんな感じって聞かれても、消えてたとしか言えないんスけど。」
「やっぱり?」
「不二センパイに直接聞いたら?伝説のハジケリストセンパイになら何度も見せてくれるんじゃない?」
そうかな、と言おうとしたが、丁度パフェが運ばれてきたのでタイミングを逃してしまった。
「不二も神業だけど、英二のアクロバティックも中々できないよね。」
リョーマに同意を求めたが、ムスっとした顔で生クリームをすくっていた。食べるのに集中したいから話し掛けるな、ということなのだろうか。
それでもあたしは続けた。
「手塚のゾーンでしょ?乾のデータでしょ?それから大石のテリトリーにタカさんの波動球、桃の曲者っぷりに海堂のド根性…うちって結構すごいよね。」
リョーマはさくらんぼを避けると、アイスを大きくすくった。パフェしか眼中にないといった感じで、あたしの話など聞いていないようにも思える。
「もちろん、リョーマも相当なもんだけどね。」
そう言うと、一瞬こちらを見てまた目を逸らした。
「でもさー、テニスしてる時はあんなに凄い奴らだけど、普段は全然普通なんだよね。むしろアホと言ってもいいようなこと平気でするし。」
「例えば?」
少し興味を引けたようだ。
「英二の英語の答案。」
さらに興味を引いたらしく、大きい目があたしを捕らえた。
「日本文を英文に直す問題で、“ケイコは夫とメグミが話しているのを見て嫉妬した”っていうのがあったんだけど、英二は何て書いたと思う?」
「何て書いたんスか?」
「“Keiko was ajienss for darlin and megumi.She looking taiking time.”」
「え…」
「ケイコワズアジエンスフォーダーリンアンドメグミ、シールッキングトーキングタイム。」
リョーマは、信じられないといった表情で、スプーンを口に運ぶ手を止めた。いや、止めたというより止まったと言った方が正しい。
「ね?アホでしょ?もう何言ってるのって感じでしょ?アジエンスってお前!って感じでしょ?」
「なんか無茶苦茶っスね…。」
この答案を見て爆笑するあたしの横で、大石が一生懸命英二を慰めていたのを思い出した。
その大石もまた、ちょっと抜けている。
「大石もあぁ見えてマヌケ伝説あるんだよ。」
「大石センパイ?」
「うん。」
あたしもアイスを口に運びながら、思い出し笑いを噛み殺した。
「自然教室の時、宿舎の廊下にパンツ落としたんだよ。そんで、女子に拾われてた。」
「廊下に…?」
「うん、廊下に。」
アイスに刺さってたウエハースを取り、アイスに付けながら食べた。リョーマはそのままウエハースだけを食べてしまったみたいだった。
「パンツのゴムの裏のとこに大石の名前が書いてあったらしくてさー。持ち物の名前書いて来いってしおりには書いてあるけど、普通書いて来ないよね。」
「それもそうだけど、パンツだけは落とさないっスよ。」
「でしょー?結構ぬけてるよね。」
手塚ですらパンツには名前を書いて来なかったというのに。
「あ、手塚で思い出したんだけど、」
「思い出したって、部長の話してないっスけど。」
自分の中では手塚の名前を出したはずだったが、どうやら言葉にしていなかったらしい。
「まぁいいから聞きなよ。」
「はぁ…。」
「こないだ練習終わった後手塚と部室で二人になっちゃってさ。お互い黙ってるのも気まずいから、昨日の夕飯何食べた?って聞いたわけ。」
「どうでもいー質問っスね。」
自分でもそう思ったけど、とっさにそう口から出てしまったのだから仕方ない。手塚も共通の話題が少ないのだから仕方ない。下ネタなどもってのほかだ。
「で、手塚が『カキフライだ』って言ったあと、あたしにも何食べたか聞いてきたの。会話のキャッチボールが奇跡的にできてるでしょ?」
「はぁ…。」
「だから、『あたしんちはドリアだった』って答えたの。そしたら手塚が、えっ?って顔して、もう一度言ってくれって言うわけよ。」
「何で?」
パフェを一口食べようとしたらパフェグラスから溶けたアイスがつたっていたので、紙ナフキンで拭いつつ続けた。
「ドリアが『ゴリラ』って聞こえたんだってさ。夕飯がゴリラとか無くない?あたし一瞬でもゴリラ食ったと思われたんだよ?ゴリラなんて食えないっつーの。」
あの時の手塚の表情は、きっとこの先いくつになっても忘れられないと思う。
「部長って耳悪いんスか?」
「そうじゃないんだけど、ホラ、あの人クソ真面目でしょ?普通に考えたらゴリラなんて食わないけど、もしかしたらそういう人もいるかもしれない、その人の家庭の事情なのかもしれない、って思ったから否定はできなかったんだってさ。手塚なにげにウケるよね。」
「考えらんないっスね。」
「でしょ?以外にあの人おかしいとこあるのよ。あ、そうだ。乾に取れないデータがあるの知ってた?」
眼鏡つながりで乾のことを思い出した。
「乾先輩に?そんなのあるんスか?」
「あるんだなーこれが。」
「不二先輩のデータとか?」
「まぁそれもそうなんだけど、それは不二が見せないからじゃん?見れても取れないデータが乾にもあるんですよ。」
乾といえばデータであり、テニス以外でもかなり役に立つ。
が、普段はぶっちゃけそれしか取り柄がない。多少モテるけど、大半の女子からは根暗だと評判だ。何しろ何でも知っている。
そんな乾でも取れないデータとは。
「スミレちゃんのパンツ。」
「え…?」
スプーンを口に運ぶリョーマの手が、ピタッと止まった。
「だから、スミレちゃんのパンツ。」
「…どーゆーコトっスか?」
「乾に頼めば何でもデータ取ってくれるんだけど、スミレちゃんのパンツの柄だけは取れないらしい。」
「それって…取れないんじゃなくて取りたくないだけなんじゃないっスか?」
「まぁ、そうだよね。」
「つーかそんなこと頼んだんスか?」
「うん。」
リョーマは呆れたと言わんばかりに、大きめのため息をついた。
「タカさんだってあんなに力持ちなのに、膝カックン100%的中だから。お手本のようにカックンってなるから。」
「そういえば昨日もやってたっスね。」
本当に毎日やったって引っ掛かるタカさん。しかもカクンとなる時に「ふほっ」という、吐息にも似た奇声を発する。
続けて「桃と海堂なんて」と始めようとすると、
「伝説のハジケリスト先輩。」
スプーンを手に持ったままのリョーマが言った。
「さっきから先輩のこと暴露しちゃってるけど、いーんスか?」
「あー…」
最初はリョーマとの話題に困り、唯一共通のテニス部の話を始めた。その結果、それがやつらの暴露になってしまった。
でも、一応目的を持った上での暴露だ。あたしも一応青学テニス部のマネージャーだから…
あたしがリョーマに伝えたかったこと。
それは、
「みんなバカみたいにテニスが上手いし強いけど、同じ人間だから。」
「だから?」
「焦る必要はないってことですよ。」
焦ってまわりが見えなくなったら、自分すら見失ってしまう。リョーマなら大丈夫だろうけど、いつか手塚と戦う時が来たら…
そう考えると、少しだけ心配だった。
「別に…焦ってないっスけど。」
リョーマは少しむくれてしまったけど、そんな意味で言ったわけじゃないから
「うん。リョーマは強いから大丈夫だと思ってるよ。」
静かに言うと、照れたように顔を横に向けた。
気付くとあたしもリョーマも、パフェグラスが空だった。
「あいつらに負けないくらい、リョーマもすごい技もってるし。何より、常に向上心があるでしょ?」
空いたパフェグラスをテーブルの端に置きながら続けた。
「手塚もみんなも、リョーマには超期待してるしさ。」
「伝説のハジケリスト先輩は?」
「え?」
「伝説のハジケリスト先輩は、俺に期待してるの?」
リョーマの大きい目に、あたしの顔がはっきり映っている。
「当たり前じゃん!」
そう答えると、リョーマの口角がほんの少し上がった。
「…伝説のハジケリスト先輩には負ける。」
「何が?」
「テニス部で一番、すごい技持ってるから。」
あたしには、リョーマの言葉の意味が分からなかった。
席を立ち、お会計を済ませている間も考えていたけど、全く分からない。
あたしが持ってるすごい技といえば、どこでも寝れる、人の言葉を物凄く聞き間違える、くらいしか思いつかない。
考え込みながら、リョーマの後についてファミレスを出た。
「雨、止んだみたいだけど。」
言われて顔を上げると、さっきまでの雨が嘘みたいに晴れ渡っていた。
「ねぇ、あたしのすごい技って何??」
「…教えない。」
「えー!超気になるし!教えてよー!」
「ヤダ。」
いくら聞いても教えてくれなかったけど、なぜかリョーマが嬉しそうだったから、あたしもちょっと嬉しくなった。
明日乾あたりにでも聞いてみようかな。
そんなことを考えながら、リョーマと並んで、雨上がりの道を歩いた。
終わり
【後書き】
お題『高等技術』。これを上手に書くのが高等技術なんじゃないかと思う。
当初は、手塚と不二にジェンガでもやらせようかと目論んでおりましたが、非常に地味、かつ、今の自分の力ではオチが難しい題材であると踏んだので没にしました。
まぁどっちにしろ残念な感じではありますよね。
リョーマが思う、マネージャーが持つ高等技術とは一体何のことでしょう。(残念ながら今回は下ネタではありません)
ここまでお付き合い頂き、ありがとうございました!