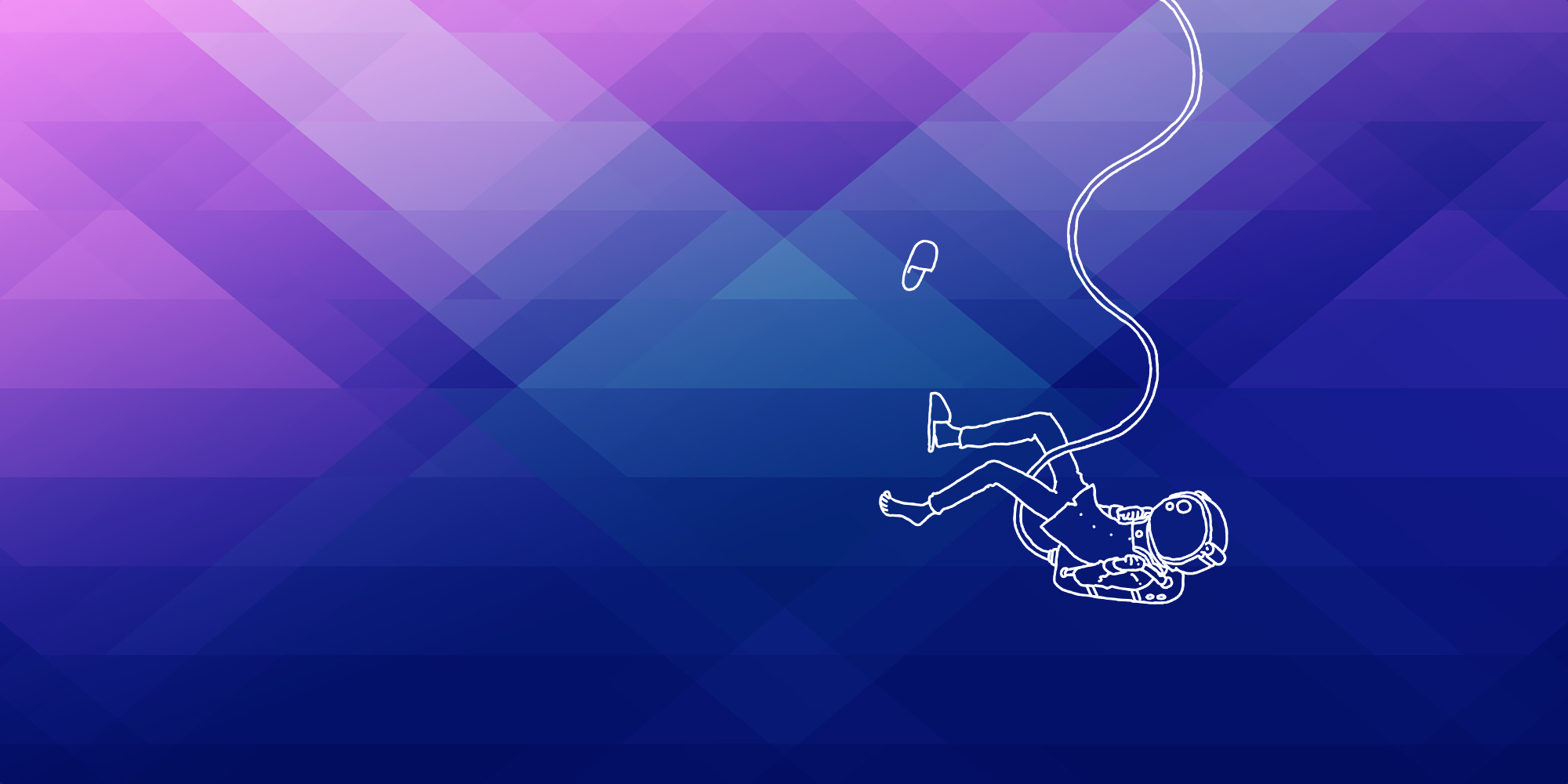お好きなお名前を
はじめましてこんにちは
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
やばい。いや、なにがやばいってあの、色々ありすぎて全部やばい。
まず、目の前の松永さん。これ本物だよね、あの夢小説とかでよくある所詮トリップものってやつだよね。もちろん松永さん推しの私としては、目の前に推しがいるという信じられない事実にいろんな意味で頭がクラクラしている。
それに加え、私がまさかトリップするなんて、という正に『事実は小説よりも奇なり』な出来事に頭がガンガンと警鐘を鳴らしている。さらに、これが一番やばいと思う案件だが、松永さんがとても(それもおそらく尋常ではないほど)怒っている。私は今自分の膝の上へ置いた手を震えながら凝視しているわけだが、目の端に形の崩れた茶器(らしきもの)が見える。そして、下を向いているということは私の胸元も視界に入る。胸元……つまりパジャマ代わりに着ていたスウェットに陶磁器の欠片がいくつもくっついているのが分かる。ズボンに血が滲んでいるのも見えるので、過度の緊張で麻痺しているだけでおそらくは手なども怪我をしているのだろう。
つまり、私のこの惨状、視界の端に映るぐちゃぐちゃの茶器、松永さんから発せられるピリピリ(なんて生易しいものではない)とした雰囲気、これらの方程式から解を導くに、私は確実に死ぬのではなかろうか。
「聞こえなかったのかね?」
聞き覚えのある声が目の前から聞こえて、常とは違う意味で心臓が跳ねる。
「出会い頭に数多の茶器を割り、こちらが名乗ったにも関わらず、謝罪どころか己の名も明かさないとは……とても育ちが良いとみえる」
ゲームで散々と聞いた松永節は、現実においてもやはり健在らしい。諸々の意味で泣いてしまいたい。どうせ殺されるのならば一層の事、一思いに殺してほしい。そうは思ったものの、やはり謝罪を含め、名は名乗らればなるまいと意を決して顔を上げた。それに、なんとかひねり出したひとつの可能性に賭けるために私は行動しなければいけないのだ。
「松永弾正久秀様、お初にお目にかかります。 名無しの 奈子と申します。此度は、松永様の……その……茶器を壊してしまったこと!誠に申し訳ございませんでした!」
これほどまでにかしこまった敬語を使ったことがないために合っているのか分からないが、やはり無礼は避けたい(今更ではあるが)。途中、なにをどう敬語で言おうか迷い、詰まってしまい最終的に勢いで謝罪してしまった。
しかし、もう私には前に進むしか道は残されないのだ。
「姓を名乗るということは、君は武家か公家の生まれなのかね?それにしては礼儀もなっていないし……少々見慣れない衣を纏っているね」
きた。礼儀云々を突っ込まれたのはこの際どうでも良い。生きて帰れたらマナーを一から学べばいいのだ。
ここで私が尽力すべきことは礼儀ではなく、生き残るために松永さんに興味を持ってもらうことだ。この時代、姓を名乗るのは武家や公家の特権だという私の曖昧な歴史の知識と、この世界の時系列に賭けて良かった。
「はい、私は武家でも公家の生まれでもございません。松永様が御覧になっていなければ、説得の余地がございませんが……私はあの姿見を通じて別世界の別の時代からやって参りました」
出し惜しみはしない、一番重要かつ大きな情報を伝える。もしも、松永さんが鏡の不可思議な現象をたまたま見ていなかったならば、頭のおかしい狼藉者としてこの場で切り伏せられてもおかしくはない。これはまさに命を賭けた大博打だ。義輝さんとかなら快活に笑って楽しみそうだけど。
目の前の松永さんは顎に手を当ててなにやら考えている。私は先ほどまでは震えていないが、やはり汗は止まらない。次の松永さんの一言で、私が数十秒後も今と同じように息をしているかが決まると言っても過言ではないだろう。
「ふむ……たしかに、私はこの目で見たよ。君が朧気な足取りで鏡の中からこちら側へ倒れ込んだのをね。その点は信ずるに値するだろう。だが、」
猛禽の瞳がこちらを捕らえる。
「君が別の世界、別の時代から来たという証拠にはなるまい?それに、君がその別世界の別の時代から来たのだからといって、私の茶器を壊してしまったことを不問とする理由にはならないのだよ」
たしかにそうだ。
私のこの服だってただ見慣れない着物だと言われればそれで終いとなる。それに茶器のこと。私が不本意でこちらに来たからといって、はいそうですかと許されるわけではない。今から私が言う言葉がここ一番の大勝負だ。私の出す条件を松永さんが飲んでくれるかどうか。更には、あの姿見を通じて私がこちらとあちらの世界を行き来できるかどうか。この二つが噛み合わなければ、私は地にふすことになるだろう。
しかし、これしか道はない。なにもせず確実に死の道を歩むより、最後まで足掻いて僅かなパーセンテージに賭けたい。
「はい、ですので私にひとつ提案がございます。私が別世界、別時代の人間だと信じてもらえるよう、こちらの世界にはないモノやあちらの情報を松永様へお渡しするのです」
私の表情がニヤリと動いたのがわかった。
まず、目の前の松永さん。これ本物だよね、あの夢小説とかでよくある所詮トリップものってやつだよね。もちろん松永さん推しの私としては、目の前に推しがいるという信じられない事実にいろんな意味で頭がクラクラしている。
それに加え、私がまさかトリップするなんて、という正に『事実は小説よりも奇なり』な出来事に頭がガンガンと警鐘を鳴らしている。さらに、これが一番やばいと思う案件だが、松永さんがとても(それもおそらく尋常ではないほど)怒っている。私は今自分の膝の上へ置いた手を震えながら凝視しているわけだが、目の端に形の崩れた茶器(らしきもの)が見える。そして、下を向いているということは私の胸元も視界に入る。胸元……つまりパジャマ代わりに着ていたスウェットに陶磁器の欠片がいくつもくっついているのが分かる。ズボンに血が滲んでいるのも見えるので、過度の緊張で麻痺しているだけでおそらくは手なども怪我をしているのだろう。
つまり、私のこの惨状、視界の端に映るぐちゃぐちゃの茶器、松永さんから発せられるピリピリ(なんて生易しいものではない)とした雰囲気、これらの方程式から解を導くに、私は確実に死ぬのではなかろうか。
「聞こえなかったのかね?」
聞き覚えのある声が目の前から聞こえて、常とは違う意味で心臓が跳ねる。
「出会い頭に数多の茶器を割り、こちらが名乗ったにも関わらず、謝罪どころか己の名も明かさないとは……とても育ちが良いとみえる」
ゲームで散々と聞いた松永節は、現実においてもやはり健在らしい。諸々の意味で泣いてしまいたい。どうせ殺されるのならば一層の事、一思いに殺してほしい。そうは思ったものの、やはり謝罪を含め、名は名乗らればなるまいと意を決して顔を上げた。それに、なんとかひねり出したひとつの可能性に賭けるために私は行動しなければいけないのだ。
「松永弾正久秀様、お初にお目にかかります。 名無しの 奈子と申します。此度は、松永様の……その……茶器を壊してしまったこと!誠に申し訳ございませんでした!」
これほどまでにかしこまった敬語を使ったことがないために合っているのか分からないが、やはり無礼は避けたい(今更ではあるが)。途中、なにをどう敬語で言おうか迷い、詰まってしまい最終的に勢いで謝罪してしまった。
しかし、もう私には前に進むしか道は残されないのだ。
「姓を名乗るということは、君は武家か公家の生まれなのかね?それにしては礼儀もなっていないし……少々見慣れない衣を纏っているね」
きた。礼儀云々を突っ込まれたのはこの際どうでも良い。生きて帰れたらマナーを一から学べばいいのだ。
ここで私が尽力すべきことは礼儀ではなく、生き残るために松永さんに興味を持ってもらうことだ。この時代、姓を名乗るのは武家や公家の特権だという私の曖昧な歴史の知識と、この世界の時系列に賭けて良かった。
「はい、私は武家でも公家の生まれでもございません。松永様が御覧になっていなければ、説得の余地がございませんが……私はあの姿見を通じて別世界の別の時代からやって参りました」
出し惜しみはしない、一番重要かつ大きな情報を伝える。もしも、松永さんが鏡の不可思議な現象をたまたま見ていなかったならば、頭のおかしい狼藉者としてこの場で切り伏せられてもおかしくはない。これはまさに命を賭けた大博打だ。義輝さんとかなら快活に笑って楽しみそうだけど。
目の前の松永さんは顎に手を当ててなにやら考えている。私は先ほどまでは震えていないが、やはり汗は止まらない。次の松永さんの一言で、私が数十秒後も今と同じように息をしているかが決まると言っても過言ではないだろう。
「ふむ……たしかに、私はこの目で見たよ。君が朧気な足取りで鏡の中からこちら側へ倒れ込んだのをね。その点は信ずるに値するだろう。だが、」
猛禽の瞳がこちらを捕らえる。
「君が別の世界、別の時代から来たという証拠にはなるまい?それに、君がその別世界の別の時代から来たのだからといって、私の茶器を壊してしまったことを不問とする理由にはならないのだよ」
たしかにそうだ。
私のこの服だってただ見慣れない着物だと言われればそれで終いとなる。それに茶器のこと。私が不本意でこちらに来たからといって、はいそうですかと許されるわけではない。今から私が言う言葉がここ一番の大勝負だ。私の出す条件を松永さんが飲んでくれるかどうか。更には、あの姿見を通じて私がこちらとあちらの世界を行き来できるかどうか。この二つが噛み合わなければ、私は地にふすことになるだろう。
しかし、これしか道はない。なにもせず確実に死の道を歩むより、最後まで足掻いて僅かなパーセンテージに賭けたい。
「はい、ですので私にひとつ提案がございます。私が別世界、別時代の人間だと信じてもらえるよう、こちらの世界にはないモノやあちらの情報を松永様へお渡しするのです」
私の表情がニヤリと動いたのがわかった。