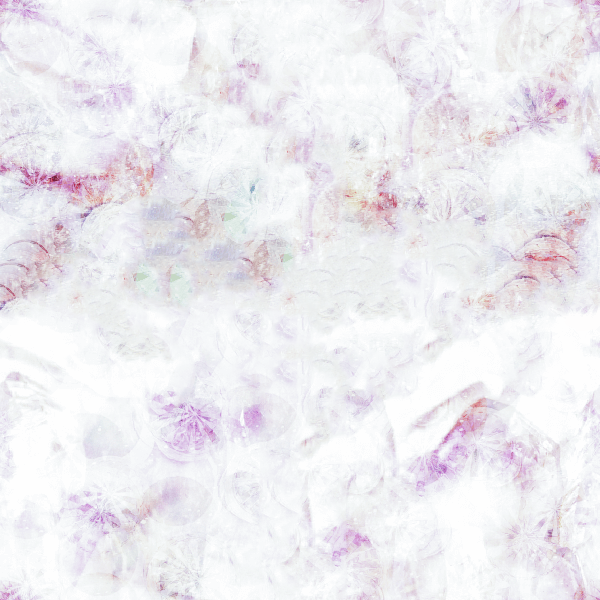恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「親父、あの」
「おう」
「姐さ……いや、ナマエさんの姿をさっき見かけたんスけど」
「あぁ?」
ある夜、事務所に戻ってきた時だった。ひっそりと西田から告げられた言葉にドスの効いた声で反応すれば、西田は「ヒィッ!」と情けない声を出す。
「また性懲りもなくこの町におるんか、アイツは」
そして舌打ちとともに苛立ちを隠さない声を上げては、続けて「で、どこで見た?」と西田に問う。コイツは俺とナマエの関係を知る数少ない組員の一人だ。彼女の存在を知る組員は一握りで、それはなんとなく、あまり極道の世界に近しい存在にしたくなかった心情からなのだが……付き合っている張本人が組織の幹部なのだから無意味なのではと思う時期もありながら、それでも今となってはその判断は功を奏したのではとも思う。
「とは言っても、ギリギリ神室町ではないスけど、向こう側にいる姿が見えたっていうか」
「ええから早よ言えや、どこやねん」
車を置いて事務所へと戻る最中に目撃したらしい西田の話を聞いてみれば、たしかにギリギリ神室町ではないという言い方をするべきか、ほぼ神室町だろと言うべきか。またしてもすぐ近くにいるということは事実である。
別れて以来初めて顔を合わせたあの夜、敢えて傷を抉るようなことを言ったのだ。これできっと、神室町には来ることもなくなるのではないかという期待を込めて。これ以上この町に足を踏み入れてほしくないのは、遭遇する可能性を懸念してなのも一つあるが、なにより俺とは全く関係のない場所や関わりのない人間との居場所を早く見つけてもらいたいとの思いもある。
長い溜息をついては椅子から腰を上げ「ちょいと出てくる」とだけ残せば、西田の「ハイッ!」との返事を背中で受け再び夜の街へと繰り出した。
アイツの話だと、おそらく会社の人間と思われるグループの中にいたらしい。色々飲み屋はあるというのに何故このタイミングでこんなに近い場所なのか、こっちがどんな思いでいると思っているのだろうか。全く、勘弁してほしいものである。
心の中でそうぼやきながらも、どうしてこうやって外を彷徨っているのか。結局のところ、放っておけないのだと痛感する。それはそうだ、好きじゃなくなったどころか大切で大切で仕方なくて、カタギとしての幸せを手にしてほしいから意を決して離れたのだ。
散々酷い振る舞いをしておいてそれでも大切だなんて、身勝手にも程があるのは承知している。それでもどれだけ考えても、こんなやり方しか俺には思いつかなかった。
西田が見かけてから時間も経っていることから、流石にもうこの辺りにはいないだろうか。別れたとはいえ、結局ナマエのことがずっと頭から離れないのだ。せめて俺と別れた今の日々を、楽しそうに過ごしているところが見られたのなら……そうすれば多少は吹っ切れるかもしれないと期待して事務所を出てきたものの、どうやらそれも叶わないらしい。
何やってるんだか。そう自分自身に呆れ、事務所へ戻ろうかと思ったその時だった。
目線の先を、ナマエが横切って行くのがたしかに見えたのだ。思わずその姿を追えば、男に笑顔を向けて会話をしながら並んで歩いている。それが間違いなくナマエであることで、急に自分が冷静ではなくなっていくのがわかる。
彼女を見かけてからすぐに二人は別れた。男は逆方向に歩き出し、ナマエは前方のタクシーへと向かう。二人の関係性は不明だが、付き合っているとすれば簡単に一人で帰さないだろうとも思う。おそらくそういった仲ではないはずだと、頭ではそう理解しようとしているはずなのによくわからない焦燥感に駆られ、そこからは衝動的に身体が動く。
「どうして……!?」
「すまんのぅ、連れが忘れ物しとってな。ちょっと借りてくで」
「え、あのっ……吾朗さんっ!」
混乱しているナマエを無理矢理連れ出し、人通りの無い路地へと、まるで放り投げる様に。今俺は何をやっているのだろうか、それもわからないほどに抑えきれない黒い感情が渦巻いてしまっていた。
「さっきの、泣いて引っかけた男か? 仕事が早いのぅ」
今ではもう、俺の前でああやって笑いかけることはない、もうこんな怯えた目しか向けてはもらえないのだ。それだって自分でそう仕向けたことだが、どうしても考えずにはいられないだなんて。今まで彼女が笑顔を向けていた先は俺だったはずなのに、と。
俺の問いに、違うと言ってほしいだけだった。それなのに目の前の女は何も言わない。今まで見たこともないような悲しげな表情を向けるだけで、否定の言葉も出てこない、首を横に振ることもしない。それが今の俺を支配している感情を逆撫でしていく。
「神室町はお前みたいな奴が来る所やないねん」
そして理性を失い、そこからは思うがままに噛み付くようなキスをしていた。彼女のくぐもった声が聞こえて、それがまた余計に欲を掻き立てられる。
それでも彼女は素直に身を委ねることをせず、その華奢な身体で必死に抵抗を続ける。ナマエの力など、俺にとっては些細なものでしかない。放っておいても良かったが、無駄な抵抗などやめておけと言い聞かせる代わりに、敢えてその両手を拘束する行動をとった。
深く長い口付けは欲を膨らませるだけで、もっと、もっとと彼女を欲してしまう。そこで一度唇を離し、煩わしく感じてしまう自分のグローブを脱ぎ捨て、直接ナマエの肌に触れた。不思議なもので、最後に彼女を抱いてからそこまで日は経っていないはずなのに、とても久しぶりに触れたような感覚になる。
そして触れた彼女の身体に、その熱に、まるで浮かされて眩暈がするようにさえ感じた瞬間。この手で纏めていたはずの彼女の手がするりと抜けたと同時に、頬に痛みと衝撃が走った。
それだって、俺からすれば大して痛くもないものな筈なのに。だがそれをくらってハッと気付いた時には、悲しく怯えた彼女が涙声で口にした。
「もう、構わないで……」
そしてすぐにこの場を立ち去るナマエを、勿論追いかけることなど出来ない。殴られた頬よりも、胸の方が痛むのは何故なのか。その痛みにさえ苛立ちを感じ、また舌打ちをひとつ。そして徐にスマホを手にしては操作する。
「よう。俺、今ヒマしとんのやけど」
そんな痛みを感じておきながら、でも久しぶりに彼女に触れたことで抑えきれない欲が湧き上がってしまったことも苛つく一因でしかない。
「今日は朝まで一緒におれるで」
好意を寄せているのを隠しもしない女を適当に選び、欲の捌け口のためにただ呼び出すのだ。これでもう、二度とナマエに愛されることはないだろう。
俺はもう、正真正銘「最低な男」なのだから。
「おう」
「姐さ……いや、ナマエさんの姿をさっき見かけたんスけど」
「あぁ?」
ある夜、事務所に戻ってきた時だった。ひっそりと西田から告げられた言葉にドスの効いた声で反応すれば、西田は「ヒィッ!」と情けない声を出す。
「また性懲りもなくこの町におるんか、アイツは」
そして舌打ちとともに苛立ちを隠さない声を上げては、続けて「で、どこで見た?」と西田に問う。コイツは俺とナマエの関係を知る数少ない組員の一人だ。彼女の存在を知る組員は一握りで、それはなんとなく、あまり極道の世界に近しい存在にしたくなかった心情からなのだが……付き合っている張本人が組織の幹部なのだから無意味なのではと思う時期もありながら、それでも今となってはその判断は功を奏したのではとも思う。
「とは言っても、ギリギリ神室町ではないスけど、向こう側にいる姿が見えたっていうか」
「ええから早よ言えや、どこやねん」
車を置いて事務所へと戻る最中に目撃したらしい西田の話を聞いてみれば、たしかにギリギリ神室町ではないという言い方をするべきか、ほぼ神室町だろと言うべきか。またしてもすぐ近くにいるということは事実である。
別れて以来初めて顔を合わせたあの夜、敢えて傷を抉るようなことを言ったのだ。これできっと、神室町には来ることもなくなるのではないかという期待を込めて。これ以上この町に足を踏み入れてほしくないのは、遭遇する可能性を懸念してなのも一つあるが、なにより俺とは全く関係のない場所や関わりのない人間との居場所を早く見つけてもらいたいとの思いもある。
長い溜息をついては椅子から腰を上げ「ちょいと出てくる」とだけ残せば、西田の「ハイッ!」との返事を背中で受け再び夜の街へと繰り出した。
アイツの話だと、おそらく会社の人間と思われるグループの中にいたらしい。色々飲み屋はあるというのに何故このタイミングでこんなに近い場所なのか、こっちがどんな思いでいると思っているのだろうか。全く、勘弁してほしいものである。
心の中でそうぼやきながらも、どうしてこうやって外を彷徨っているのか。結局のところ、放っておけないのだと痛感する。それはそうだ、好きじゃなくなったどころか大切で大切で仕方なくて、カタギとしての幸せを手にしてほしいから意を決して離れたのだ。
散々酷い振る舞いをしておいてそれでも大切だなんて、身勝手にも程があるのは承知している。それでもどれだけ考えても、こんなやり方しか俺には思いつかなかった。
西田が見かけてから時間も経っていることから、流石にもうこの辺りにはいないだろうか。別れたとはいえ、結局ナマエのことがずっと頭から離れないのだ。せめて俺と別れた今の日々を、楽しそうに過ごしているところが見られたのなら……そうすれば多少は吹っ切れるかもしれないと期待して事務所を出てきたものの、どうやらそれも叶わないらしい。
何やってるんだか。そう自分自身に呆れ、事務所へ戻ろうかと思ったその時だった。
目線の先を、ナマエが横切って行くのがたしかに見えたのだ。思わずその姿を追えば、男に笑顔を向けて会話をしながら並んで歩いている。それが間違いなくナマエであることで、急に自分が冷静ではなくなっていくのがわかる。
彼女を見かけてからすぐに二人は別れた。男は逆方向に歩き出し、ナマエは前方のタクシーへと向かう。二人の関係性は不明だが、付き合っているとすれば簡単に一人で帰さないだろうとも思う。おそらくそういった仲ではないはずだと、頭ではそう理解しようとしているはずなのによくわからない焦燥感に駆られ、そこからは衝動的に身体が動く。
「どうして……!?」
「すまんのぅ、連れが忘れ物しとってな。ちょっと借りてくで」
「え、あのっ……吾朗さんっ!」
混乱しているナマエを無理矢理連れ出し、人通りの無い路地へと、まるで放り投げる様に。今俺は何をやっているのだろうか、それもわからないほどに抑えきれない黒い感情が渦巻いてしまっていた。
「さっきの、泣いて引っかけた男か? 仕事が早いのぅ」
今ではもう、俺の前でああやって笑いかけることはない、もうこんな怯えた目しか向けてはもらえないのだ。それだって自分でそう仕向けたことだが、どうしても考えずにはいられないだなんて。今まで彼女が笑顔を向けていた先は俺だったはずなのに、と。
俺の問いに、違うと言ってほしいだけだった。それなのに目の前の女は何も言わない。今まで見たこともないような悲しげな表情を向けるだけで、否定の言葉も出てこない、首を横に振ることもしない。それが今の俺を支配している感情を逆撫でしていく。
「神室町はお前みたいな奴が来る所やないねん」
そして理性を失い、そこからは思うがままに噛み付くようなキスをしていた。彼女のくぐもった声が聞こえて、それがまた余計に欲を掻き立てられる。
それでも彼女は素直に身を委ねることをせず、その華奢な身体で必死に抵抗を続ける。ナマエの力など、俺にとっては些細なものでしかない。放っておいても良かったが、無駄な抵抗などやめておけと言い聞かせる代わりに、敢えてその両手を拘束する行動をとった。
深く長い口付けは欲を膨らませるだけで、もっと、もっとと彼女を欲してしまう。そこで一度唇を離し、煩わしく感じてしまう自分のグローブを脱ぎ捨て、直接ナマエの肌に触れた。不思議なもので、最後に彼女を抱いてからそこまで日は経っていないはずなのに、とても久しぶりに触れたような感覚になる。
そして触れた彼女の身体に、その熱に、まるで浮かされて眩暈がするようにさえ感じた瞬間。この手で纏めていたはずの彼女の手がするりと抜けたと同時に、頬に痛みと衝撃が走った。
それだって、俺からすれば大して痛くもないものな筈なのに。だがそれをくらってハッと気付いた時には、悲しく怯えた彼女が涙声で口にした。
「もう、構わないで……」
そしてすぐにこの場を立ち去るナマエを、勿論追いかけることなど出来ない。殴られた頬よりも、胸の方が痛むのは何故なのか。その痛みにさえ苛立ちを感じ、また舌打ちをひとつ。そして徐にスマホを手にしては操作する。
「よう。俺、今ヒマしとんのやけど」
そんな痛みを感じておきながら、でも久しぶりに彼女に触れたことで抑えきれない欲が湧き上がってしまったことも苛つく一因でしかない。
「今日は朝まで一緒におれるで」
好意を寄せているのを隠しもしない女を適当に選び、欲の捌け口のためにただ呼び出すのだ。これでもう、二度とナマエに愛されることはないだろう。
俺はもう、正真正銘「最低な男」なのだから。