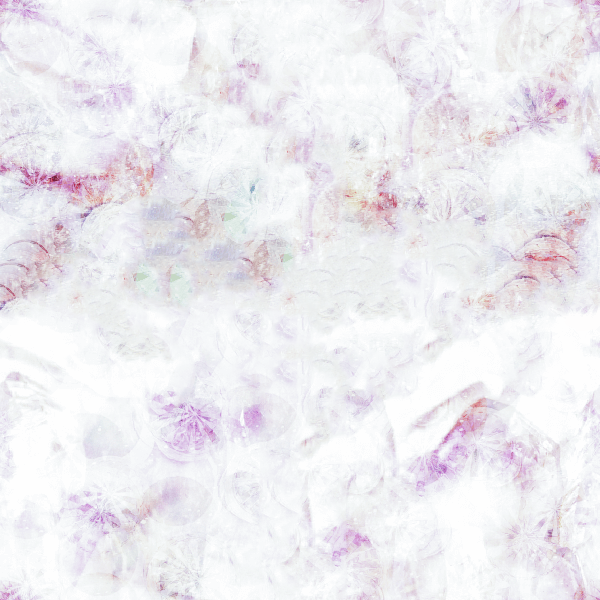恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
この日このタイミングでこの言葉を伝えたことに、特に意味はない。ずっとそうするべきだと考えていた想いがたまたまこのとき口を突いて出た、それだけだった。もちろんナマエはハッとしてこちらを見てくる。
「……え?」
ついに言ってしまったという気持ちが正直なところで、だがいい加減伝えなければとも思っていたのだ。これは良い機会であり、そして口にしたならもう戻ることは出来ないだろう。
腹を括り、ナマエに向き合い、決して嘘などではないと伝えるべくもう一度繰り返す。
「別れてくれや」
丸い瞳が見開かれて、まるで信じられないと言わんばかりの表情を浮かべながら、震える声でどうしてと紡がれて胸が痛んだのも一瞬でしかなかった。
そしてなんらかのスイッチが入ったかのように、ここからは自分でも驚くくらい淡々と酷い言葉を並べていった。変に優しい言葉をかけるよりも、もう二度と関わりたくないほど最低な男だと、未練など残さず綺麗サッパリ関係を断てるならその方がいいのだと言い聞かせて。
「殴って満足するんなら殴ればええ」
彼女の右手の動きを察してそう口にする。目の前にいるのはお前を裏切った「最低な男」なのだから、躊躇いなく殴ればいいと煽るような行動をとってみせた。
すると悲しそうに表情が歪みながらも、何故か止まった彼女の右手はそのまま下へと垂れてしまう。躊躇いなのか優しさなのか、なんにせよこんなときに何を迷うことがあるのだろうとどうしてだか苛立ちを覚えた。
「まぁそんなワケやから、もう連絡してこんといてな。あのコに誤解されたら大変や、あんな極上の女は他におらんしな! ……あぁ、もし納得いってないんやったら金でも積んだるで」
そしてその言葉に、ついにナマエの目から涙が綺麗に溢れ落ちる。それでもやはり何も言わないまま、ただ一人部屋を出て行ってしまった。
深く深く傷付けたのは一目瞭然で。それならば「最低」だの「大嫌い」だの、思い切り引っ叩いてそう吐き捨ててくれたのならどれだけ良かったか。
これで、本当に終わってしまうのか、と。自分で編み出したこの状況に舌打ちを一つして、急に一人静かな空間で煙草に火をつけた。
俺とナマエの関係を知る人間はそう多くない……が、知っている奴に限って厄介な奴ばかりなのが難点である。もし彼女のために身を引いたなんてことが知れたときには、おそらく彼奴等は是が非でも俺とナマエを引き合わせようとすることは目に見えている。「想い合っているのならちゃんと話し合うべきだ」などと、余計な一言を添えてくることも想像は容易い。
「今思えば、別に大した女やなかったわ」
だからナマエの前だけでなく、彼等の前でも最低な男として同じ振る舞いを見せる。彼女が耳にすれば、また深く傷付き涙するであろう言葉を並べて。
これでコイツ等も、ヨリを戻せだなんて間違っても言わないだろう。彼女にも「あんな男はやめておけ」と、きっと遠ざけるに違いない。
なんでどうしてと騒ぐ彼奴等の問いに簡単に言えば、俺は彼女から「奪う」ことしかできない男だと気付いたからだ。
カタギ同士の「普通の恋愛」をよく知りはしないながらも、それでもこれが「普通ではない恋愛」だということはわかっていた。そのうえで「それでもいい」と、ふんわり笑って伝えられたその言葉はとても嬉しいものだったのを今も覚えている。
俺と付き合うことで、我慢させることや悲しませることも多かったろうと思う。それでも理解しようと努力をしてくれていることも伝わっていたし、そんなナマエが心から大切で愛しい存在であるのは間違いない。
でも少しずつ、彼女にとってこれでいいのだろうかと迷いが生じるようになってしまった。
「最近はアレないんか?」
「あれ?」
「ほれ、前によく行ってたやろ、友達と」
「あぁ……」
俺と会えない日に友達と近況報告やらも兼ねた食事会に時々参加していたナマエの口から、そういえば最近めっきりその話題を聞かなくなったなと、なんとなく尋ねてみたそのとき。少し言いにくそうに「最近は、みんな忙しいので……」と、なんだか目を逸らしたような気がした。たまたまそう見えただけのようにも感じられたが、それから日々のなかで少し意識して会話をしていけば、友人や会社関係の付き合いの話がパタリと無くなっていたことに気付く。
会えないと思っていたところで急に時間が出来ることもある。その度に真っ先にナマエに連絡しては、迎えに行くと言っても大丈夫だからと神室町に来ることが多かった。頑なに大丈夫と言い張るのは、もしかすると職場付近で見られると困るのかもしれないと……迎えに行くと口にするのは、彼女にとって迷惑なのかもしれないと控えるようにもなった。
その代わりとでも言うのか、神室町によく来るようになり、そして俺が紹介した神室町のお馴染みの顔ぶれと頻繁に会うようになる。それ自体は別に悪いことではないし、彼等との関係が良好なのは俺にとっても有り難いことである。
そんなある日、神室町でいつものメンバーとの飲み会を終え、いつもより酔いがまわっているナマエに聞いたことがあった。
「珍しく酒が進んでたな」
「そうですね。楽しくて、つい」
「まぁ、楽しかったならええか」
「ふふ、みなさん、わかってくれるので……なんでも話せるから、楽しくなっちゃいました」
ふわふわとしながら紡がれたその言葉の意味を、それから遅れて理解する。
あぁ、そうか。彼女の生活において以前はあったはずの周囲との関係性が、どうして今では聞くことがないのか、無くなってしまったのか。それは他でもない、俺とともにいることで失ってしまったのではないかと。
わかってくれる、なんでも話せる、そんな人間はナマエにとってはもう、神室町の中でも俺を知る一部の人間しかいなくなってしまっているのだ。誰のせいでって、まさに俺のせいで。
それでも会えばその笑顔は変わらないもので、変わらず隣にいてくれることに安堵しながらも、それが彼女にとって幸せなことなのかと考えるようになった。それからもナマエは変わらず神室町に通い続ける。それはつまり新しい居場所でありながら、きっともう此処しかないのだろうとも思った。
複雑な思いを感じながら、それでもだからと言ってこの時点ではすぐに別れなど考えたりはしない。まぁ、言ってしまえば俺自身がまだ彼女を側に置いておきたい気持ちが強かったからで、これでいいのかと自問自答しながらも、でもナマエの笑顔に曇りがないのだからいいだろうと都合良く解釈して関係は続く。
そんな毎日が変わったきっかけは、ナマエが知人の結婚式に出席した日のことだ。その帰りに合流した彼女は煌びやかな装いなのもあり、一段と綺麗だった。そして「幸せそうで、私まで嬉しくなっちゃいました!」と、弾む声で伝えてくる。
「そうか……やっぱり、ナマエも憧れたりするんか?」
「え……それは、そうですね。人並みには、かな」
可愛らしく照れた笑みで、恥ずかしそうにそう口にする彼女はやはりとても綺麗で……それと同時に、彼女が夢見る幸せというものを、極道である俺には叶えてやることは出来ないのだろうという後ろめたさも湧き上がったこの瞬間から、あの都合の良い解釈とやらは消えた。
ナマエの望む幸せも叶えてやれないのをわかっていながら、このまま一緒にいることで彼女からあらゆるものを奪いながら縛り続けることが、はたして本当に正しいのかと。そしてきっといつか気付くだろう。これまで普通に手にしていた様々なものが離れていったのは、俺のせいだと。
そのときにショックを受けるのか、俺を恨むのか……それでもおそらく、ナマエがその事実に気付き前のように戻りたいと願うその頃にはきっと、もう彼女の周りには何も残されていないのでは。
時間が経てば経つほどその想いは募り、わかっていながら騙し騙し付き合うようなかたちになるのは耐えられなくなる。今ならまだ間に合う、彼女も俺と出会う前の生活を取り戻せるだろう。
ナマエに愛おしさが込み上げれば込み上がるほど、大切だと思えば思うほど、比例するように「だから、別れなければ」という思考もついて回り続けた。日に日に別れという言葉を意識するようになっていく。
そして、あの日。
「なぁ、別れてくれんか?」
「……え?」
ついに言ってしまったという気持ちが正直なところで、だがいい加減伝えなければとも思っていたのだ。これは良い機会であり、そして口にしたならもう戻ることは出来ないだろう。
腹を括り、ナマエに向き合い、決して嘘などではないと伝えるべくもう一度繰り返す。
「別れてくれや」
丸い瞳が見開かれて、まるで信じられないと言わんばかりの表情を浮かべながら、震える声でどうしてと紡がれて胸が痛んだのも一瞬でしかなかった。
そしてなんらかのスイッチが入ったかのように、ここからは自分でも驚くくらい淡々と酷い言葉を並べていった。変に優しい言葉をかけるよりも、もう二度と関わりたくないほど最低な男だと、未練など残さず綺麗サッパリ関係を断てるならその方がいいのだと言い聞かせて。
「殴って満足するんなら殴ればええ」
彼女の右手の動きを察してそう口にする。目の前にいるのはお前を裏切った「最低な男」なのだから、躊躇いなく殴ればいいと煽るような行動をとってみせた。
すると悲しそうに表情が歪みながらも、何故か止まった彼女の右手はそのまま下へと垂れてしまう。躊躇いなのか優しさなのか、なんにせよこんなときに何を迷うことがあるのだろうとどうしてだか苛立ちを覚えた。
「まぁそんなワケやから、もう連絡してこんといてな。あのコに誤解されたら大変や、あんな極上の女は他におらんしな! ……あぁ、もし納得いってないんやったら金でも積んだるで」
そしてその言葉に、ついにナマエの目から涙が綺麗に溢れ落ちる。それでもやはり何も言わないまま、ただ一人部屋を出て行ってしまった。
深く深く傷付けたのは一目瞭然で。それならば「最低」だの「大嫌い」だの、思い切り引っ叩いてそう吐き捨ててくれたのならどれだけ良かったか。
これで、本当に終わってしまうのか、と。自分で編み出したこの状況に舌打ちを一つして、急に一人静かな空間で煙草に火をつけた。
俺とナマエの関係を知る人間はそう多くない……が、知っている奴に限って厄介な奴ばかりなのが難点である。もし彼女のために身を引いたなんてことが知れたときには、おそらく彼奴等は是が非でも俺とナマエを引き合わせようとすることは目に見えている。「想い合っているのならちゃんと話し合うべきだ」などと、余計な一言を添えてくることも想像は容易い。
「今思えば、別に大した女やなかったわ」
だからナマエの前だけでなく、彼等の前でも最低な男として同じ振る舞いを見せる。彼女が耳にすれば、また深く傷付き涙するであろう言葉を並べて。
これでコイツ等も、ヨリを戻せだなんて間違っても言わないだろう。彼女にも「あんな男はやめておけ」と、きっと遠ざけるに違いない。
なんでどうしてと騒ぐ彼奴等の問いに簡単に言えば、俺は彼女から「奪う」ことしかできない男だと気付いたからだ。
カタギ同士の「普通の恋愛」をよく知りはしないながらも、それでもこれが「普通ではない恋愛」だということはわかっていた。そのうえで「それでもいい」と、ふんわり笑って伝えられたその言葉はとても嬉しいものだったのを今も覚えている。
俺と付き合うことで、我慢させることや悲しませることも多かったろうと思う。それでも理解しようと努力をしてくれていることも伝わっていたし、そんなナマエが心から大切で愛しい存在であるのは間違いない。
でも少しずつ、彼女にとってこれでいいのだろうかと迷いが生じるようになってしまった。
「最近はアレないんか?」
「あれ?」
「ほれ、前によく行ってたやろ、友達と」
「あぁ……」
俺と会えない日に友達と近況報告やらも兼ねた食事会に時々参加していたナマエの口から、そういえば最近めっきりその話題を聞かなくなったなと、なんとなく尋ねてみたそのとき。少し言いにくそうに「最近は、みんな忙しいので……」と、なんだか目を逸らしたような気がした。たまたまそう見えただけのようにも感じられたが、それから日々のなかで少し意識して会話をしていけば、友人や会社関係の付き合いの話がパタリと無くなっていたことに気付く。
会えないと思っていたところで急に時間が出来ることもある。その度に真っ先にナマエに連絡しては、迎えに行くと言っても大丈夫だからと神室町に来ることが多かった。頑なに大丈夫と言い張るのは、もしかすると職場付近で見られると困るのかもしれないと……迎えに行くと口にするのは、彼女にとって迷惑なのかもしれないと控えるようにもなった。
その代わりとでも言うのか、神室町によく来るようになり、そして俺が紹介した神室町のお馴染みの顔ぶれと頻繁に会うようになる。それ自体は別に悪いことではないし、彼等との関係が良好なのは俺にとっても有り難いことである。
そんなある日、神室町でいつものメンバーとの飲み会を終え、いつもより酔いがまわっているナマエに聞いたことがあった。
「珍しく酒が進んでたな」
「そうですね。楽しくて、つい」
「まぁ、楽しかったならええか」
「ふふ、みなさん、わかってくれるので……なんでも話せるから、楽しくなっちゃいました」
ふわふわとしながら紡がれたその言葉の意味を、それから遅れて理解する。
あぁ、そうか。彼女の生活において以前はあったはずの周囲との関係性が、どうして今では聞くことがないのか、無くなってしまったのか。それは他でもない、俺とともにいることで失ってしまったのではないかと。
わかってくれる、なんでも話せる、そんな人間はナマエにとってはもう、神室町の中でも俺を知る一部の人間しかいなくなってしまっているのだ。誰のせいでって、まさに俺のせいで。
それでも会えばその笑顔は変わらないもので、変わらず隣にいてくれることに安堵しながらも、それが彼女にとって幸せなことなのかと考えるようになった。それからもナマエは変わらず神室町に通い続ける。それはつまり新しい居場所でありながら、きっともう此処しかないのだろうとも思った。
複雑な思いを感じながら、それでもだからと言ってこの時点ではすぐに別れなど考えたりはしない。まぁ、言ってしまえば俺自身がまだ彼女を側に置いておきたい気持ちが強かったからで、これでいいのかと自問自答しながらも、でもナマエの笑顔に曇りがないのだからいいだろうと都合良く解釈して関係は続く。
そんな毎日が変わったきっかけは、ナマエが知人の結婚式に出席した日のことだ。その帰りに合流した彼女は煌びやかな装いなのもあり、一段と綺麗だった。そして「幸せそうで、私まで嬉しくなっちゃいました!」と、弾む声で伝えてくる。
「そうか……やっぱり、ナマエも憧れたりするんか?」
「え……それは、そうですね。人並みには、かな」
可愛らしく照れた笑みで、恥ずかしそうにそう口にする彼女はやはりとても綺麗で……それと同時に、彼女が夢見る幸せというものを、極道である俺には叶えてやることは出来ないのだろうという後ろめたさも湧き上がったこの瞬間から、あの都合の良い解釈とやらは消えた。
ナマエの望む幸せも叶えてやれないのをわかっていながら、このまま一緒にいることで彼女からあらゆるものを奪いながら縛り続けることが、はたして本当に正しいのかと。そしてきっといつか気付くだろう。これまで普通に手にしていた様々なものが離れていったのは、俺のせいだと。
そのときにショックを受けるのか、俺を恨むのか……それでもおそらく、ナマエがその事実に気付き前のように戻りたいと願うその頃にはきっと、もう彼女の周りには何も残されていないのでは。
時間が経てば経つほどその想いは募り、わかっていながら騙し騙し付き合うようなかたちになるのは耐えられなくなる。今ならまだ間に合う、彼女も俺と出会う前の生活を取り戻せるだろう。
ナマエに愛おしさが込み上げれば込み上がるほど、大切だと思えば思うほど、比例するように「だから、別れなければ」という思考もついて回り続けた。日に日に別れという言葉を意識するようになっていく。
そして、あの日。
「なぁ、別れてくれんか?」