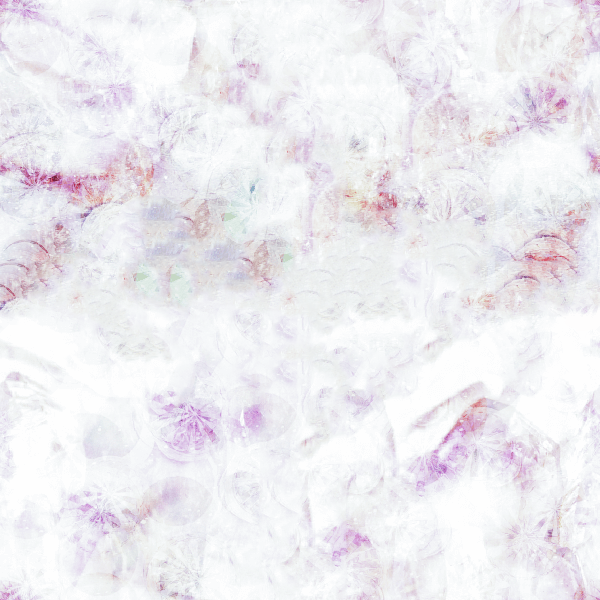恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
ある日の夜、親父のもとに一本の電話がかかってきた。着信に出るなり早々「お前が俺に何の用や」というその一言はやたら不機嫌で、はたして発信元は誰からなのか。一瞬、もしかして先日別れたナマエさんではとの考えを巡らせてみるが、さすがに彼女相手にこんな声で対応しないかとも思いながら様子を窺う。
すると途中から目に見えて親父の苛々が募っていくのがわかり、そしてしまいには怒鳴りだした。
「ド阿呆!! そないなクズとわかっとるなら意地でも止めろや!! あぁ!? 酷い目に遭ってからじゃ遅いやろが!!」
凄まじい声でそんなことを言いながら、血相を変えて事務所を飛び出して行ったのだ。事務所内にいた組員は「一体何事だ!?」と騒然としながらも、何かしらの緊急事態の可能性に備え、連絡があればすぐに動けるようにしつつ親父の連絡を待つ。
しばらくして無事に親父は帰ってくる。しかしここを飛び出して行った時の憤慨や威勢の良さは何処へやら……戻ってきた親父はというと、嘘のように意気消沈した様子だった。その雰囲気は「何かあったんスか!?」と、声をかけていいものかどうかも躊躇うほど。親父がここまで気を落とすような出来事だなんて誰も想像がつかない。組員同士で目を合わせて、互いにクエスチョンマークを浮かべるだけだった。
それからの親父は何処か上の空といった日々。事務所に顔は出すものの、すぐにフラッとどこかへ行っては、戻ってきてもどこか心ここに在らず。
そんなある日、確認したい要件があり何度電話をかけても繋がらない。困ったなぁ、親父のことだから神室町にはいると思うけど……そう思ったタイミングでちょうど事務所の電話が鳴り、もしや親父かと思えば相手は冴島の叔父貴だった。叔父貴も仕事絡みで連絡したらしく、親父が今不在であることに加え、連絡がつかないことを伝えれば「なんやアイツ、まだ腑抜けとんのか」と口にしていた。どうやら叔父貴には心当たりがあるらしい。
「冴島の叔父貴、すんません……」
「気にせんでええ。ひとまず事務所に顔出せとは伝えといた」
そしてその電話からしばらく経った頃、再び冴島の叔父貴から電話が来たと思えば、お馴染みのバッセンの屋上で親父を見つけたと。そして事務所に顔を出すように伝えてくれたらしく、電話越しながら頭を下げ礼を伝える。
礼なんていらんと、そんな叔父貴に「あの……やっぱり、ナマエさんのことっスかね」と溢す。親父があそこまでおセンチになる相手……俺にはやはり、彼女くらいしか心当たりがない。
「まぁ、アイツも迷っとるみたいやったな」
「そうっスか、やっぱり……」
別れたと聞かされたとき、最初は信じられなかったんだ。彼女が仕事でミレニアムタワーに訪れていた頃……まだ二人が互いの名前も知らない頃から、時々二人の様子を目にしてきた。
顔を合わせていくうちに名前を知って、交わす会話も少しずつ増えて。そして徐々に互いに好意があるのだろうとわかる雰囲気が見て取れて、晴れて付き合うことになったときの親父の御機嫌さといったら……親父のなかなか見られない珍しい様子を、今も覚えている。
だが、親父はやはりその立場もあり、どうしても彼女との約束を守ることが出来ない場面もあった。時間が遅れるだとか、そもそもその日の予定そのものが駄目になってしまうことだって。その度に事務所内で、ときには車の中で、すぐさま電話をかけて「すまんな」と、本当に心苦しそうに謝っているのだって何度目撃したことだろう。
ナマエさんは理解がある人だから心配ないと聞いてはいても、やはり仕方のないスケジュール変更とはいえ度重なることで親父が責められたらどうしようと、俺も車の時は出来るだけかっ飛ばして運転したことが無きにしも非ず。
頻度としては高くないものの、彼女を車に乗せて出掛ける機会に運転手として同行していれば、親父の穏やかな表情や良い意味で気を張らずいられる相手だからこその雰囲気を目の当たりにして……実はそんな親父の様子を見ていて、俺はどこか微笑ましい気持ちになったりする。
ずっと親父と共にいればわかる。好き勝手やってる人でありながら、親として組を背負っていくことの大変さも、東城会という大きな組織の幹部として上に立つことの重さも。そしてこれまでも、俺が知る以上に沢山大変な思いをしてきているだろうということも。
そんな親父に、束の間でも心穏やかに過ごせる時間があるのなら、そんな時間があったっていいじゃないかって……俺はそう思っているんだ。
だから別れたと聞いたときは本当に驚いたし、親父から切り出したことも信じられなかった。それにその話をしている親父は別れを告げた側のはずなのに、どこからどう見てもフラれた側のような様子だったし。
「せやけど兄弟のことや、納得しとらんことをそのままにするような奴やないやろ」
「……そうっスよね、俺もそう思います」
「この後なにかあったら、彼奴を頼むな」
「ハイッ!」
そうして冴島の叔父貴との電話を終えた俺は「よし!」と気合いを入れ直し、親父のアレコレを準備することに。そうしていればじきに親父も事務所へと戻って来た。
「お疲れ様です!」
「おい西田、ちょいとええか」
声をかけられ「はい!」と返事をして、親父とともに奥へと進む。そこで向き合う親父の表情はどこか意を決したようなものだ。
「後で出掛ける、車の準備しとけや」
「ハイッ! あぁそれと、一応スーツも出しておきました」
「あ?」
「もしナマエさんの所に行くなら、その格好じゃない方がいいかと思って」
すると親父は一瞬驚きを見せたすぐ後、フッと笑って「なんや、話が早いのぅ」と口にする。
どうやら親父は覚悟を決めたらしい。願わくば、また親父が彼女と一緒にいられますように。
***
お疲れ様ですとひとまず今日も無事に終わり、職場を出てはほっとして気が緩む帰り道。歩いていれば電話が鳴って「あれ、何かやり残したかな?」なんて思いながらディスプレイを確認すると、一瞬息が止まる思いになる。
吾朗さん、そんな表示に一気に鼓動は早くなり、戸惑う気持ちに溢れていく。何かの間違いなのではと思いながらも、なかなか鳴り止まないコールは意図して私を呼んでいるのだろうか。急に緊張感に呑み込まれそうになりながら、震えがちな指でおそるおそるその電話に出る操作をする。
「……もしもし?」
うるさいくらいに鳴りだす心臓の音に邪魔され、そう答えた自分の声が聞こえないんじゃないかという気さえする。
電話の向こうの彼は「あぁ、その……俺やけど」と、相手が私であることも手違いではなさそう。でも今になって電話が来る心当たりなんて何も無くて、何事だろうかと不安ばかりが折り重なるように募るだけ。
「話したいことがある、それで連絡した。これからそっちに行ってもええか?」
しばしの沈黙のあとに聞こえた声は、向こうもどこか言い辛さを感じているのか端的な言葉だけが伝えられる。
車で近くに来ている、と……言われた方向に目を向ければ、確かに見覚えのある車が停まっていて、そこから吾朗さんが降車してきた。
互いに耳に電話をあてたまま、距離はあれど確かに相手を確認して、そして立ち止まっている私の元へと彼が一歩一歩近付いてくる。電話はまだ繋がっているものの、もはやただディスプレイが秒数を刻んでいるだけである。その距離が近くなるにつれ、彼が先に電話を切った。
スーツなのは一応この辺りに来ることを考慮してなのだろうか。それにしてもこうして俯瞰的に見れば、普段の格好とはまた別の威厳がある。あの賑やかで煌びやかな神室町でさえ背景に過ぎなくなるのだから、そこから出ればたちまち「要人」であることが見て取れる隠しきれないその雰囲気が私の緊張感を高める。
わざわざこうしてやって来てまで話したいこととは一体……まさかもう一度フラれるのだろうかなんて、考えたくないことも浮かんでしまう。
「突然すまん。出来れば直接伝えたくてな」
真っ直ぐに向けられる視線に動けないでいれば、ついにもう手を伸ばせば届く距離に。
次に吾朗さんと会ったときには「久しぶり、元気ですか?」って普通に言えていたらと数時間前に話をしたが、それはもう少し傷が癒えてからの話であって。突然のことに何を口にすればいいのかもわからなくて、彼の言葉を待つしか出来ない。
「少しだけ時間くれるか?」と問われ、躊躇いながらも頷いて続きを待つ。何が飛び出すのか、それを待つこの時間がこわくてたまらない。こんなふうに改めて何かを伝えようとするその表情は、先日の花火の時とはまた違う真剣なもので……それが更に緊張感を増していく要因でしかない。
「単刀直入に言う。俺と、もう一度やり直してもらえないか」
そしてはっきりと放たれた一言に、まるで時間も景色も止まったような感覚になる。静かな世界に、私と彼の二人だけのような。
その言葉を脳内で必死に理解しようとして、繰り返して、そして少しずつ思うことは……やり直すって、なに。だって、何言ってるの。
「……今度は、どういうつもりなんですか」
そんな声がやっと出た頃には、思わず彼から目を逸らしてしまう。それに動揺も隠せない。だってそうでしょう、あまりにも身勝手すぎやしないか。あんなふうに、何があっても私とは別れるなんて決意を見せて、俺の気持ちを無駄にするなとか言っておいて、それがここにきてやり直してくれって、どれだけ勝手な男なの。どれだけ私のことを翻弄すれば気が済むの。
「人の気も知らないで、そんなこと……別れることだって、やっと受け入れられるようになってきたのに」
自分でも簡単には説明の出来ない感情がどんどん込み上げてきて、それは次第に抑えられなくなっていく。逸らした目を再び彼へと向け、思うまま感情を彼に投げつける。
「離れろって言ったり戻れって言ったり、本当になんなの!? 別れたくないって話をしてもそれは無理だって言われて、受け入れるしかないんだってやっとの思いで納得した途端に、やっぱりやり直せないかって……本当に身勝手すぎるんですけど」
「せやな、それはその通りや」
「私の、気持ちは……? 吾朗さんが勝手に一人で決めて、勝手に突き放したくせに、勝手にっ……」
言いたいことは沢山あるのに、ここで言葉に詰まってしまって。さらには涙まで込み上げてきそうになるものだから、顔を上げられなくなってしまう。
すると下がった視界には、彼の足元がこちらに一歩踏み出した様子が映った。そのすぐ後に、彼の片腕が私の背へと控えめに回ったのがわかる。それだって腹が立つ。彼の左手はポケットに入ったままだし、なんでそんな弱々しく抱き寄せるの。片手間でとりあえずみたいなそんな温もりなんかじゃなくて、どうせなら離れないようにちゃんと両腕でしっかり抱きしめてよって、そんな不満まで出てくる。
こんなに近くにいられることなどもう二度とないだろうと、そんなことを言われるだなんて有り得ないだろうと。万が一も考えることさえしていなかったこの状況に加えて、やっぱりこの懐かしい香りや感覚は私の感情をおかしくしてしまう。
そんな不満が出てきてしまうって、つまり彼にきちんと抱きしめてもらいたいってことじゃない。
「重症やねん」
「は?」
自身の感情に戸惑っていたところに、上から彼の声がしてそちらに意識を向けた。
「仕事が手につかん、他の女も抱けん、毎日支障出まくりやで」
「そんなの知らない。私だって、別れろって言われたあのときから、ずっと辛くて……」
自分でそういう状況にしたくせに、なにが重症だ。そんな文句だって言ってやりたいのに、彼がこんなにも近くにいるせいでそんな苦言もつい溶かされてしまいそうになる。
「自分勝手なのは百も承知しとる。それでもやっぱり、ナマエじゃないとアカンかった」
あぁもう、本当になんなの。そうだとしても、そんなの気付くのが遅すぎるよ。どうして、私がやっと前を向こうとした今なの。
「……私を幸せには出来ないって言い切ったのに?」
「でもお前は、俺じゃなきゃ幸せになれんとも言っとったやろ」
「次に出逢う人と幸せになれって言ってきたくせに」
「せやから、今こうして出逢ったな」
「誰と」
「俺と」
「これって出逢いなんですか」
「前代未聞の劇的な運命の出逢いやろが」
「適当なこと言ってますけど、待ってただけでしょ!?」
「お前も言うてたやろ、次に出逢う女と幸せになれって」
「こういう意味で言ったんじゃない」
「せやけど、何をどう言われようが自分が一緒におりたいヤツくらい自分で選ぶわ」
「自分がめちゃくちゃなこと言ってるって、わかってますか!?」
思わず顔を上げて抗議の言葉を口にすれば、もう迷いのない吾朗さんの右眼が真っ直ぐこちらを見ている。
「わかっとる。でも俺はお前がええ」
あの夜、私を納得させるために散々言葉を並べて伝えてきたあらゆることを、この人は今このたった一言で全て無かったことにしようとしている。
「もしお前が言ってくれたように、こんな俺でも誰かを幸せに出来るんなら……他の女を幸せにしたいなんて思わんし、お前を他の男にやるのも考えたくない。俺は、ナマエがええ」
あの日やっと言えた私のさよならも、苦しみながら貴方が出した結論なのだからと理解に費やした私の時間も、たったこれだけの言葉で無駄にしようとしてくるのだから。
本当に本当に、自分勝手にもほどがある!
「今日はそれだけ伝えに来た。突然のことで驚かせたのもあるやろし、今すぐに返事をくれとは言わん。ただ、少し考えてもらえんか」
すっと彼が離れれば、ふわりとその懐かしい香りが舞っては消える。そして「また連絡する」と、そう口にして彼は車へと引き返すべく背中を向けた。
歩き出していく後ろ姿が徐々に離れていく様に、背中が遠ざかるほど視界も滲む。
なんで、どうして……こうも勝手な男に振り回されてもうウンザリって、結局そんなふうに突き放せない私は、やっぱり。
だから駆け出して、追いかけて。
その腕を取り「待って!」と呼びかければ、それに彼も足を止めて再びこちらを振り返る。あまりに衝動的に引き留めてしまったから、少し驚いているようにも見える彼を前に何をどう伝えたらいいかわからなくて。
そんな私の言葉を待つように、彼は何も言わないままで私を見る。でも咄嗟のことで、この状況を説明するにも上手い言葉が見つからない。私はどうして急に淋しくなってしまったのだろう。
「また連絡するってことは、これっきりじゃないってわかってるんです。それなのに……行かないでって思っちゃった」
だからもう、思ったそのままのことを。
「そうやって、また勝手に一人でどっかに行かないでって……置いて行かないでって思っちゃって、だから……」
震える声で伝えれば、吾朗さんがフッと笑ったような気がした。
「ナマエが望むなら、お前がもう顔も見たくないって思うまで一緒におるで」
そうかけられた声も、その表情も、もう悲しいものなんかじゃなかった。最後に見た時に纏っていた苦しみも迷いも嘘みたいに晴れた吾朗さんが、堂々とした態度ではっきり言葉にしてくれた。一緒にいる、と……。
あぁ、私はきっと、ずっとこれが欲しかったんだなって……そうわかったときには奥底にしまいこんでいた「好き」が溢れ出して、やっぱり彼が大切で仕方ないと自覚したならもう戻れない。
「……本当に?」
「ナマエに嘘付くのは何よりしんどいって身に沁みたからな、もう二度とお前に嘘はつかん」
「私と一緒にいて、また苦しくなったりしないですか?」
「お前が俺といて幸せだって言ってくれるなら、もうなんも苦しいことなんかないで。あの夜の言葉は信じてええんやろ?」
貴方といて私は幸せだった。それは嘘偽りない私の真実。いまだに引き留めている彼の腕を離さないまましっかり頷いて、そしてもう一つ信じてほしいものを……今の私の気持ちを、やっぱり震えてしまうかもしれないけれど、それでもきちんと言葉に紡ぐ。
「私は、これからも吾朗さんといたい」
「……それがさっきの返事でええな?」
彼のその問いに「はい」と頷けば涙が流れて。そんな私を宥めるように頭を撫でてくれるけれど、生憎今はそれじゃあ足りない。
「あの、吾朗さん」
「なんや」
「……抱きしめてくれませんか」
「あー……なんや、その、場所も場所やから我慢しとるんやで、一応」
せやから少しだけな、なんて言いながらも満更でもない顔をして、今度そこきちんとその両手に包まれる。その瞬間、やっぱりまた涙が流れ出す。
だって今日のこの抱擁は、この前のような勘違いがキッカケのものではない。ちゃんと彼が私とともにいることを選んでくれて、その意思をもってしてくれたこと。やっと本当の彼に抱きしめてもらえたような気がして、それがこの上なく嬉しくて。すぐ解かれたほんの数秒の抱擁が、こんなに充足感に満たされるなんて。
「このままどっか出かけよか」
離れる寸前、耳元で囁かれたその誘いに頷く私にも、もう迷いはない。
「でも、お仕事はいいんですか?」
「仕事なんてしてられんやろ」
だいたい今デートせんでいつするんやと、そう言いながら私の手を取り車へとエスコートされる。そして彼が後部座席のドアに手を掛けたかと思えば、そのまま開けることなく私を振り返りながら言うのだ。
「せやけど、この車に乗ったらもう帰れなくなるかもしれんで。ええか?」
それはどういうことかと、いまいちピンと来ていない様子を見せる私へと彼はさらに続けた。
「うっかりそのまま俺ん家に連れて帰ってまうかもしれん」
うっかり。そう言うけど、普通はうっかりして起こることを予告出来るはずがないのだから、もうそれは意図的に起こると告げられているようなもの。
「……明日は送ってもらえますか? あと、必要なものだけ取りに戻らせてもらえたら」
「ヒヒッ、了解や」
私の言葉に口角を上げて、満足気な顔で肯定の返事をしながら彼がドアを開けた。
車内へと二人で順に乗り込みドアが閉じられたなら、これまでの悲しい日々はもう過去のこととなる。
すると途中から目に見えて親父の苛々が募っていくのがわかり、そしてしまいには怒鳴りだした。
「ド阿呆!! そないなクズとわかっとるなら意地でも止めろや!! あぁ!? 酷い目に遭ってからじゃ遅いやろが!!」
凄まじい声でそんなことを言いながら、血相を変えて事務所を飛び出して行ったのだ。事務所内にいた組員は「一体何事だ!?」と騒然としながらも、何かしらの緊急事態の可能性に備え、連絡があればすぐに動けるようにしつつ親父の連絡を待つ。
しばらくして無事に親父は帰ってくる。しかしここを飛び出して行った時の憤慨や威勢の良さは何処へやら……戻ってきた親父はというと、嘘のように意気消沈した様子だった。その雰囲気は「何かあったんスか!?」と、声をかけていいものかどうかも躊躇うほど。親父がここまで気を落とすような出来事だなんて誰も想像がつかない。組員同士で目を合わせて、互いにクエスチョンマークを浮かべるだけだった。
それからの親父は何処か上の空といった日々。事務所に顔は出すものの、すぐにフラッとどこかへ行っては、戻ってきてもどこか心ここに在らず。
そんなある日、確認したい要件があり何度電話をかけても繋がらない。困ったなぁ、親父のことだから神室町にはいると思うけど……そう思ったタイミングでちょうど事務所の電話が鳴り、もしや親父かと思えば相手は冴島の叔父貴だった。叔父貴も仕事絡みで連絡したらしく、親父が今不在であることに加え、連絡がつかないことを伝えれば「なんやアイツ、まだ腑抜けとんのか」と口にしていた。どうやら叔父貴には心当たりがあるらしい。
「冴島の叔父貴、すんません……」
「気にせんでええ。ひとまず事務所に顔出せとは伝えといた」
そしてその電話からしばらく経った頃、再び冴島の叔父貴から電話が来たと思えば、お馴染みのバッセンの屋上で親父を見つけたと。そして事務所に顔を出すように伝えてくれたらしく、電話越しながら頭を下げ礼を伝える。
礼なんていらんと、そんな叔父貴に「あの……やっぱり、ナマエさんのことっスかね」と溢す。親父があそこまでおセンチになる相手……俺にはやはり、彼女くらいしか心当たりがない。
「まぁ、アイツも迷っとるみたいやったな」
「そうっスか、やっぱり……」
別れたと聞かされたとき、最初は信じられなかったんだ。彼女が仕事でミレニアムタワーに訪れていた頃……まだ二人が互いの名前も知らない頃から、時々二人の様子を目にしてきた。
顔を合わせていくうちに名前を知って、交わす会話も少しずつ増えて。そして徐々に互いに好意があるのだろうとわかる雰囲気が見て取れて、晴れて付き合うことになったときの親父の御機嫌さといったら……親父のなかなか見られない珍しい様子を、今も覚えている。
だが、親父はやはりその立場もあり、どうしても彼女との約束を守ることが出来ない場面もあった。時間が遅れるだとか、そもそもその日の予定そのものが駄目になってしまうことだって。その度に事務所内で、ときには車の中で、すぐさま電話をかけて「すまんな」と、本当に心苦しそうに謝っているのだって何度目撃したことだろう。
ナマエさんは理解がある人だから心配ないと聞いてはいても、やはり仕方のないスケジュール変更とはいえ度重なることで親父が責められたらどうしようと、俺も車の時は出来るだけかっ飛ばして運転したことが無きにしも非ず。
頻度としては高くないものの、彼女を車に乗せて出掛ける機会に運転手として同行していれば、親父の穏やかな表情や良い意味で気を張らずいられる相手だからこその雰囲気を目の当たりにして……実はそんな親父の様子を見ていて、俺はどこか微笑ましい気持ちになったりする。
ずっと親父と共にいればわかる。好き勝手やってる人でありながら、親として組を背負っていくことの大変さも、東城会という大きな組織の幹部として上に立つことの重さも。そしてこれまでも、俺が知る以上に沢山大変な思いをしてきているだろうということも。
そんな親父に、束の間でも心穏やかに過ごせる時間があるのなら、そんな時間があったっていいじゃないかって……俺はそう思っているんだ。
だから別れたと聞いたときは本当に驚いたし、親父から切り出したことも信じられなかった。それにその話をしている親父は別れを告げた側のはずなのに、どこからどう見てもフラれた側のような様子だったし。
「せやけど兄弟のことや、納得しとらんことをそのままにするような奴やないやろ」
「……そうっスよね、俺もそう思います」
「この後なにかあったら、彼奴を頼むな」
「ハイッ!」
そうして冴島の叔父貴との電話を終えた俺は「よし!」と気合いを入れ直し、親父のアレコレを準備することに。そうしていればじきに親父も事務所へと戻って来た。
「お疲れ様です!」
「おい西田、ちょいとええか」
声をかけられ「はい!」と返事をして、親父とともに奥へと進む。そこで向き合う親父の表情はどこか意を決したようなものだ。
「後で出掛ける、車の準備しとけや」
「ハイッ! あぁそれと、一応スーツも出しておきました」
「あ?」
「もしナマエさんの所に行くなら、その格好じゃない方がいいかと思って」
すると親父は一瞬驚きを見せたすぐ後、フッと笑って「なんや、話が早いのぅ」と口にする。
どうやら親父は覚悟を決めたらしい。願わくば、また親父が彼女と一緒にいられますように。
***
お疲れ様ですとひとまず今日も無事に終わり、職場を出てはほっとして気が緩む帰り道。歩いていれば電話が鳴って「あれ、何かやり残したかな?」なんて思いながらディスプレイを確認すると、一瞬息が止まる思いになる。
吾朗さん、そんな表示に一気に鼓動は早くなり、戸惑う気持ちに溢れていく。何かの間違いなのではと思いながらも、なかなか鳴り止まないコールは意図して私を呼んでいるのだろうか。急に緊張感に呑み込まれそうになりながら、震えがちな指でおそるおそるその電話に出る操作をする。
「……もしもし?」
うるさいくらいに鳴りだす心臓の音に邪魔され、そう答えた自分の声が聞こえないんじゃないかという気さえする。
電話の向こうの彼は「あぁ、その……俺やけど」と、相手が私であることも手違いではなさそう。でも今になって電話が来る心当たりなんて何も無くて、何事だろうかと不安ばかりが折り重なるように募るだけ。
「話したいことがある、それで連絡した。これからそっちに行ってもええか?」
しばしの沈黙のあとに聞こえた声は、向こうもどこか言い辛さを感じているのか端的な言葉だけが伝えられる。
車で近くに来ている、と……言われた方向に目を向ければ、確かに見覚えのある車が停まっていて、そこから吾朗さんが降車してきた。
互いに耳に電話をあてたまま、距離はあれど確かに相手を確認して、そして立ち止まっている私の元へと彼が一歩一歩近付いてくる。電話はまだ繋がっているものの、もはやただディスプレイが秒数を刻んでいるだけである。その距離が近くなるにつれ、彼が先に電話を切った。
スーツなのは一応この辺りに来ることを考慮してなのだろうか。それにしてもこうして俯瞰的に見れば、普段の格好とはまた別の威厳がある。あの賑やかで煌びやかな神室町でさえ背景に過ぎなくなるのだから、そこから出ればたちまち「要人」であることが見て取れる隠しきれないその雰囲気が私の緊張感を高める。
わざわざこうしてやって来てまで話したいこととは一体……まさかもう一度フラれるのだろうかなんて、考えたくないことも浮かんでしまう。
「突然すまん。出来れば直接伝えたくてな」
真っ直ぐに向けられる視線に動けないでいれば、ついにもう手を伸ばせば届く距離に。
次に吾朗さんと会ったときには「久しぶり、元気ですか?」って普通に言えていたらと数時間前に話をしたが、それはもう少し傷が癒えてからの話であって。突然のことに何を口にすればいいのかもわからなくて、彼の言葉を待つしか出来ない。
「少しだけ時間くれるか?」と問われ、躊躇いながらも頷いて続きを待つ。何が飛び出すのか、それを待つこの時間がこわくてたまらない。こんなふうに改めて何かを伝えようとするその表情は、先日の花火の時とはまた違う真剣なもので……それが更に緊張感を増していく要因でしかない。
「単刀直入に言う。俺と、もう一度やり直してもらえないか」
そしてはっきりと放たれた一言に、まるで時間も景色も止まったような感覚になる。静かな世界に、私と彼の二人だけのような。
その言葉を脳内で必死に理解しようとして、繰り返して、そして少しずつ思うことは……やり直すって、なに。だって、何言ってるの。
「……今度は、どういうつもりなんですか」
そんな声がやっと出た頃には、思わず彼から目を逸らしてしまう。それに動揺も隠せない。だってそうでしょう、あまりにも身勝手すぎやしないか。あんなふうに、何があっても私とは別れるなんて決意を見せて、俺の気持ちを無駄にするなとか言っておいて、それがここにきてやり直してくれって、どれだけ勝手な男なの。どれだけ私のことを翻弄すれば気が済むの。
「人の気も知らないで、そんなこと……別れることだって、やっと受け入れられるようになってきたのに」
自分でも簡単には説明の出来ない感情がどんどん込み上げてきて、それは次第に抑えられなくなっていく。逸らした目を再び彼へと向け、思うまま感情を彼に投げつける。
「離れろって言ったり戻れって言ったり、本当になんなの!? 別れたくないって話をしてもそれは無理だって言われて、受け入れるしかないんだってやっとの思いで納得した途端に、やっぱりやり直せないかって……本当に身勝手すぎるんですけど」
「せやな、それはその通りや」
「私の、気持ちは……? 吾朗さんが勝手に一人で決めて、勝手に突き放したくせに、勝手にっ……」
言いたいことは沢山あるのに、ここで言葉に詰まってしまって。さらには涙まで込み上げてきそうになるものだから、顔を上げられなくなってしまう。
すると下がった視界には、彼の足元がこちらに一歩踏み出した様子が映った。そのすぐ後に、彼の片腕が私の背へと控えめに回ったのがわかる。それだって腹が立つ。彼の左手はポケットに入ったままだし、なんでそんな弱々しく抱き寄せるの。片手間でとりあえずみたいなそんな温もりなんかじゃなくて、どうせなら離れないようにちゃんと両腕でしっかり抱きしめてよって、そんな不満まで出てくる。
こんなに近くにいられることなどもう二度とないだろうと、そんなことを言われるだなんて有り得ないだろうと。万が一も考えることさえしていなかったこの状況に加えて、やっぱりこの懐かしい香りや感覚は私の感情をおかしくしてしまう。
そんな不満が出てきてしまうって、つまり彼にきちんと抱きしめてもらいたいってことじゃない。
「重症やねん」
「は?」
自身の感情に戸惑っていたところに、上から彼の声がしてそちらに意識を向けた。
「仕事が手につかん、他の女も抱けん、毎日支障出まくりやで」
「そんなの知らない。私だって、別れろって言われたあのときから、ずっと辛くて……」
自分でそういう状況にしたくせに、なにが重症だ。そんな文句だって言ってやりたいのに、彼がこんなにも近くにいるせいでそんな苦言もつい溶かされてしまいそうになる。
「自分勝手なのは百も承知しとる。それでもやっぱり、ナマエじゃないとアカンかった」
あぁもう、本当になんなの。そうだとしても、そんなの気付くのが遅すぎるよ。どうして、私がやっと前を向こうとした今なの。
「……私を幸せには出来ないって言い切ったのに?」
「でもお前は、俺じゃなきゃ幸せになれんとも言っとったやろ」
「次に出逢う人と幸せになれって言ってきたくせに」
「せやから、今こうして出逢ったな」
「誰と」
「俺と」
「これって出逢いなんですか」
「前代未聞の劇的な運命の出逢いやろが」
「適当なこと言ってますけど、待ってただけでしょ!?」
「お前も言うてたやろ、次に出逢う女と幸せになれって」
「こういう意味で言ったんじゃない」
「せやけど、何をどう言われようが自分が一緒におりたいヤツくらい自分で選ぶわ」
「自分がめちゃくちゃなこと言ってるって、わかってますか!?」
思わず顔を上げて抗議の言葉を口にすれば、もう迷いのない吾朗さんの右眼が真っ直ぐこちらを見ている。
「わかっとる。でも俺はお前がええ」
あの夜、私を納得させるために散々言葉を並べて伝えてきたあらゆることを、この人は今このたった一言で全て無かったことにしようとしている。
「もしお前が言ってくれたように、こんな俺でも誰かを幸せに出来るんなら……他の女を幸せにしたいなんて思わんし、お前を他の男にやるのも考えたくない。俺は、ナマエがええ」
あの日やっと言えた私のさよならも、苦しみながら貴方が出した結論なのだからと理解に費やした私の時間も、たったこれだけの言葉で無駄にしようとしてくるのだから。
本当に本当に、自分勝手にもほどがある!
「今日はそれだけ伝えに来た。突然のことで驚かせたのもあるやろし、今すぐに返事をくれとは言わん。ただ、少し考えてもらえんか」
すっと彼が離れれば、ふわりとその懐かしい香りが舞っては消える。そして「また連絡する」と、そう口にして彼は車へと引き返すべく背中を向けた。
歩き出していく後ろ姿が徐々に離れていく様に、背中が遠ざかるほど視界も滲む。
なんで、どうして……こうも勝手な男に振り回されてもうウンザリって、結局そんなふうに突き放せない私は、やっぱり。
だから駆け出して、追いかけて。
その腕を取り「待って!」と呼びかければ、それに彼も足を止めて再びこちらを振り返る。あまりに衝動的に引き留めてしまったから、少し驚いているようにも見える彼を前に何をどう伝えたらいいかわからなくて。
そんな私の言葉を待つように、彼は何も言わないままで私を見る。でも咄嗟のことで、この状況を説明するにも上手い言葉が見つからない。私はどうして急に淋しくなってしまったのだろう。
「また連絡するってことは、これっきりじゃないってわかってるんです。それなのに……行かないでって思っちゃった」
だからもう、思ったそのままのことを。
「そうやって、また勝手に一人でどっかに行かないでって……置いて行かないでって思っちゃって、だから……」
震える声で伝えれば、吾朗さんがフッと笑ったような気がした。
「ナマエが望むなら、お前がもう顔も見たくないって思うまで一緒におるで」
そうかけられた声も、その表情も、もう悲しいものなんかじゃなかった。最後に見た時に纏っていた苦しみも迷いも嘘みたいに晴れた吾朗さんが、堂々とした態度ではっきり言葉にしてくれた。一緒にいる、と……。
あぁ、私はきっと、ずっとこれが欲しかったんだなって……そうわかったときには奥底にしまいこんでいた「好き」が溢れ出して、やっぱり彼が大切で仕方ないと自覚したならもう戻れない。
「……本当に?」
「ナマエに嘘付くのは何よりしんどいって身に沁みたからな、もう二度とお前に嘘はつかん」
「私と一緒にいて、また苦しくなったりしないですか?」
「お前が俺といて幸せだって言ってくれるなら、もうなんも苦しいことなんかないで。あの夜の言葉は信じてええんやろ?」
貴方といて私は幸せだった。それは嘘偽りない私の真実。いまだに引き留めている彼の腕を離さないまましっかり頷いて、そしてもう一つ信じてほしいものを……今の私の気持ちを、やっぱり震えてしまうかもしれないけれど、それでもきちんと言葉に紡ぐ。
「私は、これからも吾朗さんといたい」
「……それがさっきの返事でええな?」
彼のその問いに「はい」と頷けば涙が流れて。そんな私を宥めるように頭を撫でてくれるけれど、生憎今はそれじゃあ足りない。
「あの、吾朗さん」
「なんや」
「……抱きしめてくれませんか」
「あー……なんや、その、場所も場所やから我慢しとるんやで、一応」
せやから少しだけな、なんて言いながらも満更でもない顔をして、今度そこきちんとその両手に包まれる。その瞬間、やっぱりまた涙が流れ出す。
だって今日のこの抱擁は、この前のような勘違いがキッカケのものではない。ちゃんと彼が私とともにいることを選んでくれて、その意思をもってしてくれたこと。やっと本当の彼に抱きしめてもらえたような気がして、それがこの上なく嬉しくて。すぐ解かれたほんの数秒の抱擁が、こんなに充足感に満たされるなんて。
「このままどっか出かけよか」
離れる寸前、耳元で囁かれたその誘いに頷く私にも、もう迷いはない。
「でも、お仕事はいいんですか?」
「仕事なんてしてられんやろ」
だいたい今デートせんでいつするんやと、そう言いながら私の手を取り車へとエスコートされる。そして彼が後部座席のドアに手を掛けたかと思えば、そのまま開けることなく私を振り返りながら言うのだ。
「せやけど、この車に乗ったらもう帰れなくなるかもしれんで。ええか?」
それはどういうことかと、いまいちピンと来ていない様子を見せる私へと彼はさらに続けた。
「うっかりそのまま俺ん家に連れて帰ってまうかもしれん」
うっかり。そう言うけど、普通はうっかりして起こることを予告出来るはずがないのだから、もうそれは意図的に起こると告げられているようなもの。
「……明日は送ってもらえますか? あと、必要なものだけ取りに戻らせてもらえたら」
「ヒヒッ、了解や」
私の言葉に口角を上げて、満足気な顔で肯定の返事をしながら彼がドアを開けた。
車内へと二人で順に乗り込みドアが閉じられたなら、これまでの悲しい日々はもう過去のこととなる。