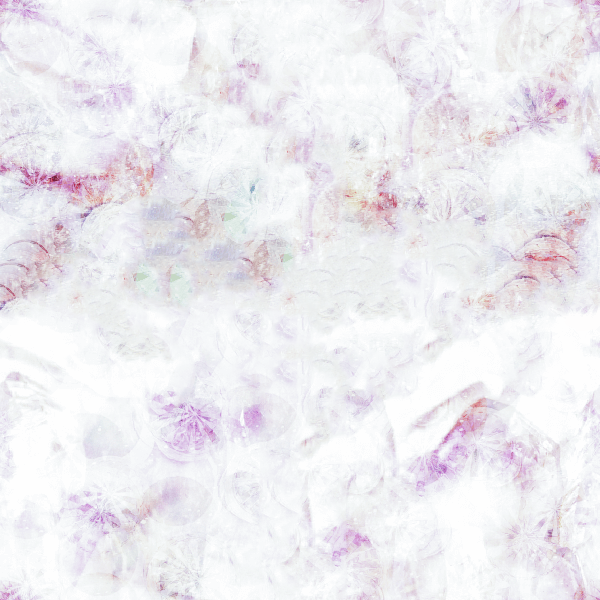恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「先日はどうもありがとうございました。お二人のおかげで、ちゃんと吾朗さんと話すことが出来ました」
あの日はあれからどうなったのかと花ちゃんから連絡が来たのだが、吾朗さんとは結局お別れをしたということ、そして詳しいことは自分の気持ちが落ち着いた後日にきちんとお話させてほしいとだけ伝えて数日……。
もう神室町へは行かないと決めた私のため、今日は二人がわざわざ職場の近くまで来てくれたのだ。仕事の合間に近場のカフェで二人と待ち合わせれば、合流した二人の表情は曇っている。
「あーあ。なんだか俺も残念な気分だなぁ」
「本当ですよ! 二人とも、お互いを想ってとはいえ……」
「でも、一緒にいたいと思ってもらえないなら、無理矢理繋ぎ止めてもきっと幸せにはなれないから」
多少なりとも時間が経ったことで、今では素直にそう思えるようになった。
大人になればなるほど「好き」だけじゃ駄目なんだと再認識させられて、そして私も彼の言ってた意味がほんの少しだけわかってしまったから。相手に幸せになってほしい、でもその相手は自分じゃないって。
吾朗さんのあんな苦しそうで悲しそうな顔を、あの日初めて目にしたとき。そんな顔をさせているのは私のせいなのだとわかった。彼も同じことを言っていたように、私もその事実が耐えられなくて、そしてそんな私が彼を縛り続けるなんて自分を許せなくなってしまうとも思った。
なんだかんだで私のことを考えてくれて、とても優しい人だから。その気持ちを利用するように涙で訴えたなら……もう何も言わずに隣にいてくれるだけでいいからと我儘を言ったなら、もしかしたら彼が折れてまだもう少しくらい一緒にいられたのかもしれない。けれど、そうしてともに過ごす関係に未来はないとも思うから。
ずっと側にいたはずの私が、彼のことをなにもわかっていなかった。だからきっと私は、彼を幸せに出来るようなそんな相手にはなり得なかっただろう。
「でも最後に、吾朗さんの本当の気持ちが聞けたのは良かったです。何も知らないままだったら、変な引きずり方しちゃっていたので。あ、その手段はかなり強引でしたけど」
「あれは、その……嘘ついちゃってごめんね」
「でも、実に神室町っぽい理由だったでしょ?」
「社長はちょっとやり過ぎでしたよ! 真島さんとの電話で、息を吸うように嘘ばっかり並べて!」
「しかも内容が内容だから、見てるこっちはもうヒヤヒヤだったんだからね!」「私も最初、なんのこと言われてるかサッパリで……話は噛み合わないし怒られるしで大変だったんですよ」だなんて、今だからこんなノリで話すことが出来るようになっているけど。
「もう少し経って、私があの人にバッタリ会っても『久しぶりですね、元気ですか?』って普通に挨拶が出来そうになったら、また神室町に遊びに行きますね。そのときは、前に行きそびれちゃったカラオケにみんなで行きたいなぁ」
「そうだね。俺はいつでも暇してるからさ、連絡待ってるよ」
「もう社長! 暇なら仕事してください!」
相変わらずの二人のやり取りが、これまでとなにも変わらないと思わせてくれているみたいで、とても安心出来る空気感を漂わせてくれる。それが今の私にはとても有り難くて、とても嬉しい。
あの夜やっと言えた「さよなら」で、彼もようやく苦しむこともなくなるのだろう。
私ももうこれからは、今日は神室町に行く為にお洒落をしようとか、仕事を早く終わらせようとか……そんなことを考える時間がなくなるのだろう。そして少しずつ、それが当たり前になっていくのかな。
***
「こないな所で何してんねや」
「……見てのとおりや」
「西田が探しとったで」
バッティングセンターの屋上で煙草を吸っていれば、背後から聞こえる聞き慣れた声に顔を向けることなく応答する。
「ええ加減、いっぺん事務所に顔出せや」
どうやら西田に泣きつかれたらしい冴島からそう促されるものの、聞こえないフリをしてその場を動かないでいれば、奴も隣へとやって来た。
「……せっかく来たんや、下で打ってくか?」
「アホか、遊びに来たワケやあらへん」
「なんや、つまらんのぅ」
そう適当なことを口にしてまた黙る俺につられてなのか、隣の男もしばらく黙ったまま、ただ横に居るだけである。遊びに来たわけではないというこの男だが、かといって無理矢理事務所に連れ戻しに来たような素振りも今のところ見せてはいない。
「もうあれから、三日か四日くらいは経つんか?」
煙草を吸い終わっても変わらず動く気のない俺に、ようやくなにか口にしたかと思えばそんなことで。数日前……とはいえ、それが何日前かなどいちいち厳密に数えてなどおらず、そのくらい経つんじゃないか程度の認識でしかない。そして隣の男が指すその日のことは、もう過ぎた日でしかないというのに。
「お前の望んだ通りになったやないか」
「……せやな」
「それやったら、いつまでも腑抜けとったってしゃあないやろ」
「そんなんとちゃう」
「仕事が手についとらんクセによう言うわ」
俺とナマエの関係を知る人間はそう多くないものの、知っている奴に限って厄介な奴ばかり。前にも思ったそれには、勿論この男も含まれている。
「……なぁ兄弟。お前、ホンマに納得いっとるんか」
それでもこれまでは特に口を出してくることも無いままだった冴島が、この件に触れたのはこれがはじめてのことではないだろうか。
「……納得せなアカンやろが」
「別れたんやったらナマエは他人や。あいつがどんな男選ぼうが、もうお前には関係ないやろ。次に出逢う奴がどんなにええ男やろうとどんなに悪い男やろうと、お前が口出し出来る立場やないで。ましてや、二人が一緒におるところに割り込みなんぞ以ての外やろうが」
微かに笑いながら「まぁ、今回は秋山の嘘で済んだけどな。にしても、お前がアッサリ信じるんや。余程上手い作り話やったんやな」なんて続けたこの男は、俺が話すこともなく既に事情を知っているらしい。本当に神室町の奴らは厄介で、そのくせ話が回るのも早くて面倒だ。
「次に同じようなことがホンマにあったときに、お前は黙ってられるんか?」
そう聞く冴島は知らないのだ、これがはじめてではないことを。実際にナマエが他の男と並んでいた場面を目にして、嫉妬に駆られてしまったことを。それで言うなら実は二度目に値するわけであり、その二度とも黙っていられなかったなど口が裂けても言えないわけで。
俺とナマエを無理矢理鉢合わせるように仕向けた秋山も、おそらくだが桐生からなにやら話を聞いてのはずだ。でなければタイミングが良すぎると、今思えばそう頭は回るし特に巧妙な嘘でもなかった。それなのに、いざ突然ナマエの名前を出されて彼女が悲しい思いをするかもしれないと言われたならば、思考回路が欠如したように動いてしまうとは。
「さっき、秋山達がナマエに会ってきたらしい」
それで言葉に詰まっていれば、続いて告げられた内容に微々たる表情の強張りで反応してしまう。
彼女はもう、終わったこととして新たな毎日を過ごしているのだろうか。
「ナマエもずっとお前の話やったと。それにお前の側におったんに、お前がそんなこと考えとるのに気付かなかったって、申し訳なさそうにしとったらしい」
「別れたっちゅうのにアイツは……いつまでそないなこと気にしとんねん」
「お前もやろ」
鼻で笑われながらそう言われてしまえば、返す言葉もなくなってしまう。現に自分もその通りで、言われたことが頭から今日も離れない。
「おかしな話やで」
「何がや?」
「今までも似たようなことがある度に、相手の為や思って離れて……でもその時はいつも納得出来てたんや。仕方ないことだと、割り切ることだってちゃんと出来とったはずなのにな」
もう過ぎた日でしかないはずのあの日が、どうしても過去にならないのだ。過去として終わらせてしまえば、望む通りの結末になるというのにもかかわらず。
こんなにいつまでも尾を引くとは、なにが今回に限ってこんなにくすぶっているのか。きっと情が移り過ぎてしまっているだけだろうと、そんな一言ではどうにも片付かないのはなぜなのか。
「そんなん、簡単なことやろが」
「あぁ?」
「今まではそうでも、今回は納得がいっとらんてことやろ」
いや、まぁそうなのだが。シンプルなことを堂々と自信満々に言われて、だからどうして今回に限ってそうなのかということを問いたいのに、横の男は「納得しとらんからや」なんて当たり前のことを述べてくる。
本当に……だがときに、こういう真っ直ぐ過ぎるところが逆に羨ましくもあるのだが。
「お前もナマエも口を揃えて『好きだから別れる』言うとるが……俺には、互いに相手のこと考え過ぎて駄目になっとるようにしか見えん」
「相手のこと考えとらんよりはええやろ」
「ナマエの周りにあったモンが失くなる言うても、それだってアイツがホンマに嫌やったら、もっと早よアイツが自分から離れることも出来たやろ。それに安心せや、アイツは一人になんてならん。少なくともこの町には、お前等を理解しとる人間がちゃんとおる」
「真島。お前だって、今は一人じゃないんやで」と、そんな妙にくすぐったくなるような一言まで添えながら、冴島は続けるのだ。せやから、やりたいようにやればええやろ、と。
「ええやないか。好きなら側に居て守ってやる、それの何がアカンねや。それでも心配なら、アイツが一人にならんようお前が隣におってやればええ。後になって、もっと一緒に居られたならなんて思っても遅いんやで」
そう言われてふと思い出す。もしかすると、それは自身の妹への想いもどこか含まれているのかもしれない。以前、たまたま話の流れで冴島が口にしていたのだ。自分の生き方に後悔はしていないものの、それでももう少し一緒に居てやれたらと思うことはあった、と。
「どうせきっぱり他人になりきれんのやろ、それならお前がきっちり守ってやれや」
「……今更やろ、きっと」
「それを決めるんは俺でもお前でもなくナマエやろ。まぁ、遅くなればなるほど『今更や』言われるのは確かやけどな」
そして冴島は横を離れて行く……と思えば、最後に背中越しで聞こえてきたもの。
「どうせならナマエに『飽きたからもういらん』て言われるまで側におったれや」
ナマエのいない飲みの席で、どうして別れたんだと騒がれた時に自分で口にしていたことである。それを引用され告げられたその一言は、やはり今耳にしても身勝手さしか感じない。
ホテルで別れを告げた時、飽きただの興味がなくなっただの、更には他の女と比べる言動までとった男に対して……しかも状況としても、直前まですることはしておいて。嘘とは言え今思い返しても、なかなかに酷い状況で酷い言葉を並べたなと思ってしまう。で、その後も顔を合わせる度にそれは続いたというのに。
それにも拘らず、あの女は。今もそんな男のことばかりで、挙句の果てには「気付かなかった」と申し訳なく思うなどと……。
「ったく、ホンマにお前は……」
これじゃあ本当に悪い男に引っかかるのも時間の問題なのではないのか、全く。まぁ、それで言うと俺も悪い男に当て嵌まるのかもしれない。そんなことを考えて思わず自嘲しつつも、どうせ他人になんてなれないだろと見透かされたように指摘されたことは、ごもっともだと言わざるを得ない。
──別れを告げられるその瞬間までずーっと幸せでした。吾朗さんだって、ちゃんと誰かを幸せにしてあげられる人なんですよ。
もしもその言葉が本当なのであれば、こんな俺でも誰かを幸せに出来るというのなら……その「誰か」はナマエであってほしいだなんて、今更そんなことを望んでもいいのだろうか。
結局のところ俺だって今も、そんなアイツのことばかりなのだ。
あの日はあれからどうなったのかと花ちゃんから連絡が来たのだが、吾朗さんとは結局お別れをしたということ、そして詳しいことは自分の気持ちが落ち着いた後日にきちんとお話させてほしいとだけ伝えて数日……。
もう神室町へは行かないと決めた私のため、今日は二人がわざわざ職場の近くまで来てくれたのだ。仕事の合間に近場のカフェで二人と待ち合わせれば、合流した二人の表情は曇っている。
「あーあ。なんだか俺も残念な気分だなぁ」
「本当ですよ! 二人とも、お互いを想ってとはいえ……」
「でも、一緒にいたいと思ってもらえないなら、無理矢理繋ぎ止めてもきっと幸せにはなれないから」
多少なりとも時間が経ったことで、今では素直にそう思えるようになった。
大人になればなるほど「好き」だけじゃ駄目なんだと再認識させられて、そして私も彼の言ってた意味がほんの少しだけわかってしまったから。相手に幸せになってほしい、でもその相手は自分じゃないって。
吾朗さんのあんな苦しそうで悲しそうな顔を、あの日初めて目にしたとき。そんな顔をさせているのは私のせいなのだとわかった。彼も同じことを言っていたように、私もその事実が耐えられなくて、そしてそんな私が彼を縛り続けるなんて自分を許せなくなってしまうとも思った。
なんだかんだで私のことを考えてくれて、とても優しい人だから。その気持ちを利用するように涙で訴えたなら……もう何も言わずに隣にいてくれるだけでいいからと我儘を言ったなら、もしかしたら彼が折れてまだもう少しくらい一緒にいられたのかもしれない。けれど、そうしてともに過ごす関係に未来はないとも思うから。
ずっと側にいたはずの私が、彼のことをなにもわかっていなかった。だからきっと私は、彼を幸せに出来るようなそんな相手にはなり得なかっただろう。
「でも最後に、吾朗さんの本当の気持ちが聞けたのは良かったです。何も知らないままだったら、変な引きずり方しちゃっていたので。あ、その手段はかなり強引でしたけど」
「あれは、その……嘘ついちゃってごめんね」
「でも、実に神室町っぽい理由だったでしょ?」
「社長はちょっとやり過ぎでしたよ! 真島さんとの電話で、息を吸うように嘘ばっかり並べて!」
「しかも内容が内容だから、見てるこっちはもうヒヤヒヤだったんだからね!」「私も最初、なんのこと言われてるかサッパリで……話は噛み合わないし怒られるしで大変だったんですよ」だなんて、今だからこんなノリで話すことが出来るようになっているけど。
「もう少し経って、私があの人にバッタリ会っても『久しぶりですね、元気ですか?』って普通に挨拶が出来そうになったら、また神室町に遊びに行きますね。そのときは、前に行きそびれちゃったカラオケにみんなで行きたいなぁ」
「そうだね。俺はいつでも暇してるからさ、連絡待ってるよ」
「もう社長! 暇なら仕事してください!」
相変わらずの二人のやり取りが、これまでとなにも変わらないと思わせてくれているみたいで、とても安心出来る空気感を漂わせてくれる。それが今の私にはとても有り難くて、とても嬉しい。
あの夜やっと言えた「さよなら」で、彼もようやく苦しむこともなくなるのだろう。
私ももうこれからは、今日は神室町に行く為にお洒落をしようとか、仕事を早く終わらせようとか……そんなことを考える時間がなくなるのだろう。そして少しずつ、それが当たり前になっていくのかな。
***
「こないな所で何してんねや」
「……見てのとおりや」
「西田が探しとったで」
バッティングセンターの屋上で煙草を吸っていれば、背後から聞こえる聞き慣れた声に顔を向けることなく応答する。
「ええ加減、いっぺん事務所に顔出せや」
どうやら西田に泣きつかれたらしい冴島からそう促されるものの、聞こえないフリをしてその場を動かないでいれば、奴も隣へとやって来た。
「……せっかく来たんや、下で打ってくか?」
「アホか、遊びに来たワケやあらへん」
「なんや、つまらんのぅ」
そう適当なことを口にしてまた黙る俺につられてなのか、隣の男もしばらく黙ったまま、ただ横に居るだけである。遊びに来たわけではないというこの男だが、かといって無理矢理事務所に連れ戻しに来たような素振りも今のところ見せてはいない。
「もうあれから、三日か四日くらいは経つんか?」
煙草を吸い終わっても変わらず動く気のない俺に、ようやくなにか口にしたかと思えばそんなことで。数日前……とはいえ、それが何日前かなどいちいち厳密に数えてなどおらず、そのくらい経つんじゃないか程度の認識でしかない。そして隣の男が指すその日のことは、もう過ぎた日でしかないというのに。
「お前の望んだ通りになったやないか」
「……せやな」
「それやったら、いつまでも腑抜けとったってしゃあないやろ」
「そんなんとちゃう」
「仕事が手についとらんクセによう言うわ」
俺とナマエの関係を知る人間はそう多くないものの、知っている奴に限って厄介な奴ばかり。前にも思ったそれには、勿論この男も含まれている。
「……なぁ兄弟。お前、ホンマに納得いっとるんか」
それでもこれまでは特に口を出してくることも無いままだった冴島が、この件に触れたのはこれがはじめてのことではないだろうか。
「……納得せなアカンやろが」
「別れたんやったらナマエは他人や。あいつがどんな男選ぼうが、もうお前には関係ないやろ。次に出逢う奴がどんなにええ男やろうとどんなに悪い男やろうと、お前が口出し出来る立場やないで。ましてや、二人が一緒におるところに割り込みなんぞ以ての外やろうが」
微かに笑いながら「まぁ、今回は秋山の嘘で済んだけどな。にしても、お前がアッサリ信じるんや。余程上手い作り話やったんやな」なんて続けたこの男は、俺が話すこともなく既に事情を知っているらしい。本当に神室町の奴らは厄介で、そのくせ話が回るのも早くて面倒だ。
「次に同じようなことがホンマにあったときに、お前は黙ってられるんか?」
そう聞く冴島は知らないのだ、これがはじめてではないことを。実際にナマエが他の男と並んでいた場面を目にして、嫉妬に駆られてしまったことを。それで言うなら実は二度目に値するわけであり、その二度とも黙っていられなかったなど口が裂けても言えないわけで。
俺とナマエを無理矢理鉢合わせるように仕向けた秋山も、おそらくだが桐生からなにやら話を聞いてのはずだ。でなければタイミングが良すぎると、今思えばそう頭は回るし特に巧妙な嘘でもなかった。それなのに、いざ突然ナマエの名前を出されて彼女が悲しい思いをするかもしれないと言われたならば、思考回路が欠如したように動いてしまうとは。
「さっき、秋山達がナマエに会ってきたらしい」
それで言葉に詰まっていれば、続いて告げられた内容に微々たる表情の強張りで反応してしまう。
彼女はもう、終わったこととして新たな毎日を過ごしているのだろうか。
「ナマエもずっとお前の話やったと。それにお前の側におったんに、お前がそんなこと考えとるのに気付かなかったって、申し訳なさそうにしとったらしい」
「別れたっちゅうのにアイツは……いつまでそないなこと気にしとんねん」
「お前もやろ」
鼻で笑われながらそう言われてしまえば、返す言葉もなくなってしまう。現に自分もその通りで、言われたことが頭から今日も離れない。
「おかしな話やで」
「何がや?」
「今までも似たようなことがある度に、相手の為や思って離れて……でもその時はいつも納得出来てたんや。仕方ないことだと、割り切ることだってちゃんと出来とったはずなのにな」
もう過ぎた日でしかないはずのあの日が、どうしても過去にならないのだ。過去として終わらせてしまえば、望む通りの結末になるというのにもかかわらず。
こんなにいつまでも尾を引くとは、なにが今回に限ってこんなにくすぶっているのか。きっと情が移り過ぎてしまっているだけだろうと、そんな一言ではどうにも片付かないのはなぜなのか。
「そんなん、簡単なことやろが」
「あぁ?」
「今まではそうでも、今回は納得がいっとらんてことやろ」
いや、まぁそうなのだが。シンプルなことを堂々と自信満々に言われて、だからどうして今回に限ってそうなのかということを問いたいのに、横の男は「納得しとらんからや」なんて当たり前のことを述べてくる。
本当に……だがときに、こういう真っ直ぐ過ぎるところが逆に羨ましくもあるのだが。
「お前もナマエも口を揃えて『好きだから別れる』言うとるが……俺には、互いに相手のこと考え過ぎて駄目になっとるようにしか見えん」
「相手のこと考えとらんよりはええやろ」
「ナマエの周りにあったモンが失くなる言うても、それだってアイツがホンマに嫌やったら、もっと早よアイツが自分から離れることも出来たやろ。それに安心せや、アイツは一人になんてならん。少なくともこの町には、お前等を理解しとる人間がちゃんとおる」
「真島。お前だって、今は一人じゃないんやで」と、そんな妙にくすぐったくなるような一言まで添えながら、冴島は続けるのだ。せやから、やりたいようにやればええやろ、と。
「ええやないか。好きなら側に居て守ってやる、それの何がアカンねや。それでも心配なら、アイツが一人にならんようお前が隣におってやればええ。後になって、もっと一緒に居られたならなんて思っても遅いんやで」
そう言われてふと思い出す。もしかすると、それは自身の妹への想いもどこか含まれているのかもしれない。以前、たまたま話の流れで冴島が口にしていたのだ。自分の生き方に後悔はしていないものの、それでももう少し一緒に居てやれたらと思うことはあった、と。
「どうせきっぱり他人になりきれんのやろ、それならお前がきっちり守ってやれや」
「……今更やろ、きっと」
「それを決めるんは俺でもお前でもなくナマエやろ。まぁ、遅くなればなるほど『今更や』言われるのは確かやけどな」
そして冴島は横を離れて行く……と思えば、最後に背中越しで聞こえてきたもの。
「どうせならナマエに『飽きたからもういらん』て言われるまで側におったれや」
ナマエのいない飲みの席で、どうして別れたんだと騒がれた時に自分で口にしていたことである。それを引用され告げられたその一言は、やはり今耳にしても身勝手さしか感じない。
ホテルで別れを告げた時、飽きただの興味がなくなっただの、更には他の女と比べる言動までとった男に対して……しかも状況としても、直前まですることはしておいて。嘘とは言え今思い返しても、なかなかに酷い状況で酷い言葉を並べたなと思ってしまう。で、その後も顔を合わせる度にそれは続いたというのに。
それにも拘らず、あの女は。今もそんな男のことばかりで、挙句の果てには「気付かなかった」と申し訳なく思うなどと……。
「ったく、ホンマにお前は……」
これじゃあ本当に悪い男に引っかかるのも時間の問題なのではないのか、全く。まぁ、それで言うと俺も悪い男に当て嵌まるのかもしれない。そんなことを考えて思わず自嘲しつつも、どうせ他人になんてなれないだろと見透かされたように指摘されたことは、ごもっともだと言わざるを得ない。
──別れを告げられるその瞬間までずーっと幸せでした。吾朗さんだって、ちゃんと誰かを幸せにしてあげられる人なんですよ。
もしもその言葉が本当なのであれば、こんな俺でも誰かを幸せに出来るというのなら……その「誰か」はナマエであってほしいだなんて、今更そんなことを望んでもいいのだろうか。
結局のところ俺だって今も、そんなアイツのことばかりなのだ。