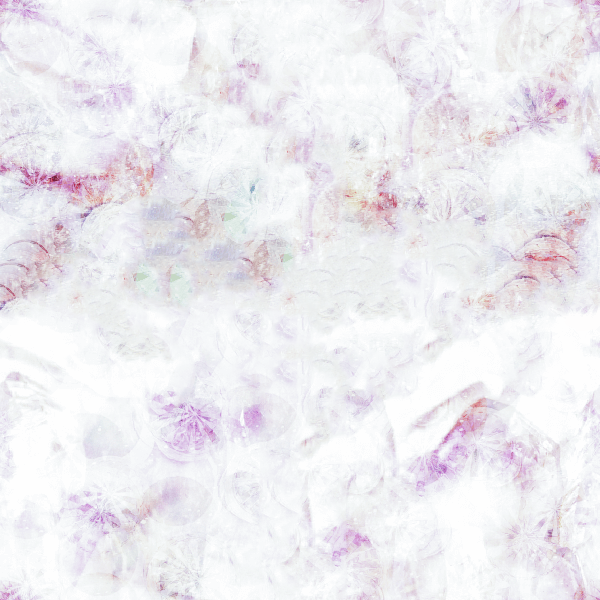恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
とあるビルの屋上にて、暗くなった空の下で数分置きにスマホを確認するのも何度目か。
「まだかなぁ、花ちゃん……」
昼間に連絡が来て、急遽仕事終わりに会うことになったのだ。今ではすっかりお友達なのだからそれは不思議なことではないものの、珍しいのはこの場所を指定してきたこと。
ここは神室町のとある雑居ビルの屋上だ。花ちゃんによれば、今日は都内某所で花火大会があるらしい。一緒に見ようと誘われて、彼女が言うにはここのビルの屋上は穴場でお勧めだと言う。
せっかくの機会だし秋山さんと二人で見ることも提案してみたが、今日は久しぶりに女同士で「たまには私の話も聞いて!」と……たしかにここ最近はいつも私が聞いてもらってばかりだったから、今日は私が聞き役になれればなと思って。
ただ、そうなると神室町内に足を踏み入れなければならず、昨日の今日ともありそこに関しては個人的にとても抵抗があった。とはいえ、昨夜の出来事は誰にも言ってないのだから彼女に悪気はないし、いつものように天下一通り付近で待ち合わせて一緒に行動すれば大丈夫かなという気持ちでいれば、残念ながら「仕事が押してるので先に行ってて」と……。
そのためあの人に出会わないようにと祈りつつドキドキしながら街を歩き、一足先にこの場へとやってきて彼女を待っているというのがここまでのいきさつである。
「あ……」
すると確かに、絶妙な角度で遮るものなく、夜空に綺麗な花が咲き始める。
始まっちゃったな。そう思いながら次々に咲き乱れるそれらをぼーっと眺めていると、なにやらバンと音がした。扉が開かれた音か、閉じられた音か……どちらにせよそんなに大きな音を立てるほどの勢いに驚きながら、まさか花ちゃんかなと音の鳴った方向へ顔が向く。
すると誰かに、物凄い力と勢いで腕を引かれてしまう。そしてこの出来事はどれも一瞬で、誰が、どうして、自分の身に一体何が起こったのか。理解する間もなく上から声がするのだ。「ド阿呆! なにやっとんねん!」と、それはもう物凄い怒りの声というかなんというか……。
気付けば誰かの胸に収まっていて、微かに懐かしい香りがして、でも何故か私は怒られている。「しょうもない奴に引っかかりおって!」と……え、待って、なに。なんのこと? ていうか、どうして……。
苦しいくらいきつく抱きしめられていて、その相手が誰なのかわかったときには、この感覚がなんだか懐かしくてたまらなくなる。少しばかり目の奥がツンとして、でも悲しいとか辛いとか、そんなんじゃないのに。
「で、男はどこや!?」
「あの、吾朗さん?」
「あぁ!?」
「急に、どうしたんですか?」
心なしか息を切らしていて、なにやら必死に言っているけれど……言われてる意味も彼の行動もよくわからないことで、そんな込み上げた気持ちが今度は混乱へとすり替わっていく。
「どうもこうもあるかボケ! 阿呆な女を止めに来たんやろが」
「……それって、私のことですか? 阿呆ってなんで!?」
「そんなことより男が先や! まさか逃げたんとちゃうやろな!?」
「男? あの、誰のことですか!?」
どうしたのかという私の質問から、どういうワケか受け答えの度に段々と苛立っていく吾朗さん。阿呆だのボケだの言われる心当たりもなく、でも彼は苛々を隠すことなくぶつけてくるため私もムキになって返事をしてしまう。そんなやり取りを繰り返せば、ここで一層心当たりのないワードが飛び出した。
「お前のこと誑かしたホストや、隠しとるんならさっさと出せ!」
「……ホスト?」
さっきから何言ってるの? そんな気持ちがたぶん表情に露骨に現れているだろうと思う。そして私の様子に吾朗さんもこれまでの焦りを感じさせる様子から一変、急に大人しくなる。おそらく私の態度から、嘘や隠し事はないと判断したのだろう。
「お前、なんでこんな所に一人でおるんや?」
私を解放しつつ、それでもまだどこか釈然としないような眼差しを向けながらそんなことを聞いてくる。
きっと彼は、何か勘違いか人違いの類をしているのでは。それがすぐにわかって、彼にとってさっきの抱擁はただの勘違い……もしくは抱きしめたかった人は違う人だったんじゃないのかと気付くと、それはそれで悲しくて淋しい気持ちが溢れてしまう。
「私は今日、花ちゃんに誘われたんです。花火大会があって、この場所だと綺麗に見えるから一緒に見ようって。でも彼女、仕事が押しちゃって遅れるってメッセージが来て、だから一人で先に見ながら待ってたんです」
そんな悲しさを誤魔化すように花火に視線を戻しながら、どういう誤解をしているのかわからない彼に事情を説明する。夜空には相変わらず、綺麗な花が色や形を変えながら咲き続けている。
目を丸くしながらも、私の視線につられるように夜空に咲く色とりどりのそれを確認した彼は、やはりまた疑いの目で私を見るなり「ホンマに一人なんやな?」と聞いてきた。どこか会話が噛み合っていない気がするというか、一体何を気にしているのだろうか。
すると何やら吾朗さんが思い立ったようで、どこかに電話をかけ始める。そして繋がったらしいその電話で、開口一番に相手を威圧する低い声を出した。
「お前、俺のことハメたな?」
「ナマエちゃん、無事でした?」
「あぁ!? とぼけやがって、ふざけんなや! 今からぶん殴りに行ったるわ、そこから動くなよ」
「そのくらい言わないと行かないでしょう? それに真島さんがまずやるべきことは、ここへのカチコミじゃないと思いますけど」
彼の電話のやり取りの相手は……私には声は聞こえないけれど、なんとなく秋山さんなんだろうなと思う。ああだこうだと言っているうちに向こうの電話が切れたようで、舌打ちとともに「ホンマに余計なことしよって」という恨み言が聞こえた。
「吾朗さんは、なんて言われてここに来たんですか?」
「お前とそんな話するために来たんとちゃう」
「散々人に阿呆とかボケとか言っておいて」
たぶんこうなってくると、花ちゃんがここに来るように言ったのもそういうことだったのかな、なんて。
二人揃って横並びで花火に視線を移しているのは、気まずい思いからお互いを見ることが出来ないからだ。双方視線を逃す先が、たまたま目の前に広がるそれなだけ……それでもまさか、思わぬ形でこんなふうに彼と並んで花火を眺めるだなんて。
付き合っているときは、そんな日時の決まっているイベントに関しての約束なんてどうなるかわからなかったから。それに神室町ならともかく、この町の外で人が多いところは騒がれないよう配慮しなきゃ、とかも。約束がもし駄目になったことで「すまんな」なんて悲しい声で謝らせるのも嫌だし、私は別に「その日のそのイベント」に拘らなくても、時間が合うときに一緒に楽しく過ごせればなんだって良くて。
だからこうして並んで花火を見るなんて、実ははじめてのこと。残念なのは、楽しく笑い合って眺めることが出来ないことだろう。
「……金貸しから電話が来て、やたら焦った声で言うてきた。ナマエが、よりによって神室町イチ悪評極まりないホストに捕まったって」
そうしていれば彼が重い口を開いた。どこをどうなればそんなことになっているのか、その一言に思わず隣の彼をチラリと見てしまう。
彼が聞いた話だと、そのホストは客の女性を風俗送りにするのが特段上手いとか、また過去に数多の女性が彼のDV被害に遭っているとか、女と金にだらしなくてトラブルが絶えず、良いのは顔だけだとか……あぁ、もちろんコレは全部秋山さん談で。それが本当なら確かに悪評極まりない男ではあるけれど、神室町にそんなホストが実在するのかそれとも架空の話なのか。
どちらかは不明ながらも、とにかくそんな男と私が今日はデートで、手始めに二人でここで花火を見るって聞いた、という連絡が秋山さんから来たらしい。で、秋山さんからそのホストの数々の最低エピソードを色々と聞かされていくうちに頭に血が上り、慌ててここへやって来たと。ちなみに、そんな男にうまいこと言いくるめられた私のことを「阿呆な女」呼ばわりしていたようだ。
「心配してくれたんですか?」
ぼそっと訊ねてみたものの、彼は私を見ることもなければその問いに口を開くこともない。
「仮にその話が本当だったとしても、もう吾朗さんには関係ないことなんじゃないんですか?」
「阿呆か。お前をそないなクズにやるために手放したんとちゃう」
何も言ってくれない彼にやっぱり淋しさを感じて、少し不貞腐れるようにそうぶつけてみる。すると気のせいか思わぬ言葉が返ってきて、今度は驚きながらもしっかりはっきり彼に目を向ける。
「手放した? 捨てたんじゃなくて?」
だって、その二つのワードは似て非なるものではないか。でも相変わらず、彼は視界に私を捉えない。
「私のこと、もう好きじゃないんですよね?」
「おう」
「他に好きな人が出来たって」
「おう」
「身体の相性も抜群なんですもんね」
「おう」
「……目を見て答えてください」
身体ごと向き合って彼に訴えれば、彼も辛うじて顔だけこちらに向ける。少しだけ眉を顰めた、なんだか苦しそうな表情を見せながら。
「その話が本当なら、それはそれでいいんです。吾朗さんが幸せならそれでいいの。別に私のことわざと傷付けなくても、ちゃんと聞き分け良く離れるから。だから……本当のことをちゃんと言ってくれないと、私はいつまでも前を向けないんです」
彼のそんな顔を、私はこれまで見たことがなかったなと……そしてその苦しそうな表情で紡がれた声は、またも懐かしさを感じるような優しいものなのだから。
「本当のことを話したら……俺の為にも、これからは前を向いてくれや」
それでわかった。今ここにいる吾朗さんは、ちゃんと私の知る吾朗さんなんだって。
私が好きになった、私を愛してくれた彼は「前を向け」と言うけれど……それじゃあまるで、これからもやっぱり隣に貴方はいないと言われているようなものじゃないか。
「俺には、お前を幸せにしてやることは出来ん」
その一言は、別れてくれと言われた時よりも鋭いものとして心に突き刺さる。
だって今かけられている言葉は、あの時と違ってどこか信じられないようなものなんかじゃない。目の前にいるのは私を想う吾朗さんであり、そんな彼が真剣な眼差しではっきりと否定の言葉を述べたのだから。
「俺は、ナマエに幸せになってもらいたんや」
そうどこか他人任せな言い方は、その言葉の後ろにあるのが「それは俺じゃない」ということなのだろう。私自身は、吾朗さん以外の男性の横で幸せに思える未来など少しも想像出来ないというのに。
「誰もが思う『普通の恋愛』も『普通の幸せ』も、俺には与えてやることは出来ん。お前の周りのモンをどんどん奪うだけ奪って、我慢させることばっかりで、そのくせ与えられるモンも何も無い。お前がどう思っていようが、それは事実でしかあらへん。それが耐えられんのや」
綺麗事を並べてるけど本当は単に別れたいだけなんでしょうと、普通の人が相手ならそう思っていたかもしれない。
でもそれがいかに彼の本心か、私にはわかってしまうから。周囲と違う恋愛だということは、誰よりも私自身が身にしみて感じていたもの。
「愛した女一人幸せに出来ない男がいつまでもナマエのことを縛り続けるのは、俺自身が許せなくてな。せやからお前は、ちゃんとお前のことを幸せにしてくれるヤツに出逢うべきなんや。別に他に女もおらん、ナマエのことだって今も変わらず愛しとる、でも俺じゃあアカンねや」
「……なにそれ。それは、吾朗さんの自己満足でしょう?」
「あのな、人の気も知らんと勝手なこと言うなや。いくらお前でも許せんことだってあるで」
「だって私は『吾朗さんがいい』のに……奪ってるとか縛ってるとか、そんなこと一切感じてなんてないのに」
頼りないような声で絞り出すように必死にそう訴えてみても、彼の悲しそうな顔は変わらない。それがより彼と私の考え方の違いを浮き彫りにしているようで、離れていきそうな目の前の彼をどうしたら繋ぎ止められるのだろうか。
「私のことを幸せにしてくれる人って言うけど……私の幸せを思うなら、そのまま吾朗さんが隣にいてよ。私は、吾朗さんじゃなきゃ……」
だけど言葉でどんなに伝えても、彼はちっとも笑ってくれないのだ。どうして、いつもみたいに自信満々な笑顔で「それもそうやな」って言ってよ。
でもそんな言葉も貰えない。貴方はこれからもそのままでいてくれていいよって、私はきちんと幸せだよって、まだ足りないならもっと伝えるから、だからお願い。
「ねぇ、吾朗さん!」
「すまんな」
そんな私の願いも虚しく、優しい声でありながらしっかりと拒絶されてしまう。
「別れることを考えてたんも、別にここ最近のことやない。もっと前から、早よ手放してやらんととは思っとった。それがまぁ、俺もお前が好きな気持ちからずるずると先延ばしにしてもうて、あの日になったっちゅうだけや。早ければ早いほどナマエの為にもなるし、悲しませることもなかったのにな。ホンマに俺はどうしようもない男や」
悲しく笑いながら告げられたその言葉に必死に首を横に振る。早いも遅いもない、吾朗さんと別れることが私の為なはずがないでしょう、こんなに悲しい出来事でしかないのに。だからそんなこと言わないでよって、そんな気持ちがどんどん溢れてくる。
でもそれとは別に、もっと前からそんなことを考えていた事実が私に違うショックを与える。だって私は、ずっとずっと、幸せでしかなかったのに。そう思うと、いかに自分のことしか考えてなかったのか痛いほど感じてしまう。
「だからお前は、こんなヤクザのことは早よ忘れなアカン。そして次に出逢ったヤツと、今度はきちんと幸せになってくれや」
私は一緒にいれば嬉しくて幸せで、だから気付かなかった。一緒にいることで吾朗さんを苦しめていただなんて、そんなこと想像もしていなかった。これまで私は彼の隣にいたはずなのに、そんなふうに彼が悩んでいたことも知らずに、ただ自分が幸せでいるだけで……本当に、なんて愚かなのだろう。
もし私が少しでも早く彼の苦しみに気付いていれば、もし何かしら手を伸ばせていれば、何か言葉をかけられていれば、もっと幸せだと伝えられていたら……もしものことばかりを今になって考えても、もう手遅れで。
「それが、本当の……?」
「別れてくれって言ったあの日、こうやって馬鹿正直に本音で話をしとったら、かえって互いに別れられなくなると思った。ナマエの為だなんて優しさを見せて別れてくれと言ったところで、すんなり頷けないやろ? せやからあんな嘘ついて酷い言葉並べて、傷付けるだけ傷付けて……そうでもせんと離れられんと思ったからや、すまんかったな」
そんな謝罪の言葉なんて、私のほしいものじゃない。すまないと思っているなら、私の気持ちを……でも今の今までそんな彼の気持ちに気付きもしなかった私じゃあ、どのみちこの先、彼の隣に居続けることは出来ないだろうとも思った。
「だからナマエに対して絶対に思うはずがないようなことも、心を鬼にして言うてたんやで。俺の気持ちを無駄にせんといてな」
彼がこうして本当のことを口にする気になったのは、今はもう「既に別れている」からこそなのだろう。そうして彼は視線を前方の花火へと戻し、もう私を見ることはしなくなった。
もしかしたら、泣き喚いて駄々をこねてでもみれば……でもそうして無理矢理側にいてもらっても、きっともう見せてくれるのはさっきの悲しげな笑顔でしかないんだ。私の知るあの彼らしい笑顔を、迷いなく私へ向けてくれる日々はもう来ないのだとわかる。
別れを固く決意した彼を前にして、私はもう彼に目をやることも、花火を見ることも出来なくて……どうしたら彼を繋ぎ止められるのかなんて思考が働くこともなくなってしまった。私は一緒にいたくても、彼がそれを望んでいないんだ。
「私は……吾朗さんといて、ちゃんと恋愛してたんですよ。大人になってもこんな気持ちで恋をすることが出来るんだって、吾朗さんのおかげで知ったんです」
例え周りと少し違った恋愛だったとしても、それは比べる必要もないもので。淋しい思いや辛い思いも全部ひっくるめて、私にとって他には代えがたいとてもとても大切な恋であったし、貴方を好きになって得たものはたしかに幸せで溢れていた。もしもこれが最後になってしまうのであれば、それだけは知っていてほしい。
「それに、別れを告げられるその瞬間までずーっと幸せでした。吾朗さんだって、ちゃんと誰かを幸せにしてあげられる人なんですよ。だから、それは絶対に忘れないでくださいね」
やっぱり私は、心の底から吾朗さんが好きなんだ。だから、そんな顔をさせてしまうくらいなら。
「吾朗さんも、次に出逢う人とは今度こそ幸せになってください。約束ですよ」
だから明日からは、またいつもの吾朗さんらしく楽しく生きてくださいね。
「さようなら」
今も次から次へと綺麗に輝き続ける花火だけが、立ち去る私の背中を見送る。
それでも、涙で神室町を去るのはきっと今日が最後だろう。
「まだかなぁ、花ちゃん……」
昼間に連絡が来て、急遽仕事終わりに会うことになったのだ。今ではすっかりお友達なのだからそれは不思議なことではないものの、珍しいのはこの場所を指定してきたこと。
ここは神室町のとある雑居ビルの屋上だ。花ちゃんによれば、今日は都内某所で花火大会があるらしい。一緒に見ようと誘われて、彼女が言うにはここのビルの屋上は穴場でお勧めだと言う。
せっかくの機会だし秋山さんと二人で見ることも提案してみたが、今日は久しぶりに女同士で「たまには私の話も聞いて!」と……たしかにここ最近はいつも私が聞いてもらってばかりだったから、今日は私が聞き役になれればなと思って。
ただ、そうなると神室町内に足を踏み入れなければならず、昨日の今日ともありそこに関しては個人的にとても抵抗があった。とはいえ、昨夜の出来事は誰にも言ってないのだから彼女に悪気はないし、いつものように天下一通り付近で待ち合わせて一緒に行動すれば大丈夫かなという気持ちでいれば、残念ながら「仕事が押してるので先に行ってて」と……。
そのためあの人に出会わないようにと祈りつつドキドキしながら街を歩き、一足先にこの場へとやってきて彼女を待っているというのがここまでのいきさつである。
「あ……」
すると確かに、絶妙な角度で遮るものなく、夜空に綺麗な花が咲き始める。
始まっちゃったな。そう思いながら次々に咲き乱れるそれらをぼーっと眺めていると、なにやらバンと音がした。扉が開かれた音か、閉じられた音か……どちらにせよそんなに大きな音を立てるほどの勢いに驚きながら、まさか花ちゃんかなと音の鳴った方向へ顔が向く。
すると誰かに、物凄い力と勢いで腕を引かれてしまう。そしてこの出来事はどれも一瞬で、誰が、どうして、自分の身に一体何が起こったのか。理解する間もなく上から声がするのだ。「ド阿呆! なにやっとんねん!」と、それはもう物凄い怒りの声というかなんというか……。
気付けば誰かの胸に収まっていて、微かに懐かしい香りがして、でも何故か私は怒られている。「しょうもない奴に引っかかりおって!」と……え、待って、なに。なんのこと? ていうか、どうして……。
苦しいくらいきつく抱きしめられていて、その相手が誰なのかわかったときには、この感覚がなんだか懐かしくてたまらなくなる。少しばかり目の奥がツンとして、でも悲しいとか辛いとか、そんなんじゃないのに。
「で、男はどこや!?」
「あの、吾朗さん?」
「あぁ!?」
「急に、どうしたんですか?」
心なしか息を切らしていて、なにやら必死に言っているけれど……言われてる意味も彼の行動もよくわからないことで、そんな込み上げた気持ちが今度は混乱へとすり替わっていく。
「どうもこうもあるかボケ! 阿呆な女を止めに来たんやろが」
「……それって、私のことですか? 阿呆ってなんで!?」
「そんなことより男が先や! まさか逃げたんとちゃうやろな!?」
「男? あの、誰のことですか!?」
どうしたのかという私の質問から、どういうワケか受け答えの度に段々と苛立っていく吾朗さん。阿呆だのボケだの言われる心当たりもなく、でも彼は苛々を隠すことなくぶつけてくるため私もムキになって返事をしてしまう。そんなやり取りを繰り返せば、ここで一層心当たりのないワードが飛び出した。
「お前のこと誑かしたホストや、隠しとるんならさっさと出せ!」
「……ホスト?」
さっきから何言ってるの? そんな気持ちがたぶん表情に露骨に現れているだろうと思う。そして私の様子に吾朗さんもこれまでの焦りを感じさせる様子から一変、急に大人しくなる。おそらく私の態度から、嘘や隠し事はないと判断したのだろう。
「お前、なんでこんな所に一人でおるんや?」
私を解放しつつ、それでもまだどこか釈然としないような眼差しを向けながらそんなことを聞いてくる。
きっと彼は、何か勘違いか人違いの類をしているのでは。それがすぐにわかって、彼にとってさっきの抱擁はただの勘違い……もしくは抱きしめたかった人は違う人だったんじゃないのかと気付くと、それはそれで悲しくて淋しい気持ちが溢れてしまう。
「私は今日、花ちゃんに誘われたんです。花火大会があって、この場所だと綺麗に見えるから一緒に見ようって。でも彼女、仕事が押しちゃって遅れるってメッセージが来て、だから一人で先に見ながら待ってたんです」
そんな悲しさを誤魔化すように花火に視線を戻しながら、どういう誤解をしているのかわからない彼に事情を説明する。夜空には相変わらず、綺麗な花が色や形を変えながら咲き続けている。
目を丸くしながらも、私の視線につられるように夜空に咲く色とりどりのそれを確認した彼は、やはりまた疑いの目で私を見るなり「ホンマに一人なんやな?」と聞いてきた。どこか会話が噛み合っていない気がするというか、一体何を気にしているのだろうか。
すると何やら吾朗さんが思い立ったようで、どこかに電話をかけ始める。そして繋がったらしいその電話で、開口一番に相手を威圧する低い声を出した。
「お前、俺のことハメたな?」
「ナマエちゃん、無事でした?」
「あぁ!? とぼけやがって、ふざけんなや! 今からぶん殴りに行ったるわ、そこから動くなよ」
「そのくらい言わないと行かないでしょう? それに真島さんがまずやるべきことは、ここへのカチコミじゃないと思いますけど」
彼の電話のやり取りの相手は……私には声は聞こえないけれど、なんとなく秋山さんなんだろうなと思う。ああだこうだと言っているうちに向こうの電話が切れたようで、舌打ちとともに「ホンマに余計なことしよって」という恨み言が聞こえた。
「吾朗さんは、なんて言われてここに来たんですか?」
「お前とそんな話するために来たんとちゃう」
「散々人に阿呆とかボケとか言っておいて」
たぶんこうなってくると、花ちゃんがここに来るように言ったのもそういうことだったのかな、なんて。
二人揃って横並びで花火に視線を移しているのは、気まずい思いからお互いを見ることが出来ないからだ。双方視線を逃す先が、たまたま目の前に広がるそれなだけ……それでもまさか、思わぬ形でこんなふうに彼と並んで花火を眺めるだなんて。
付き合っているときは、そんな日時の決まっているイベントに関しての約束なんてどうなるかわからなかったから。それに神室町ならともかく、この町の外で人が多いところは騒がれないよう配慮しなきゃ、とかも。約束がもし駄目になったことで「すまんな」なんて悲しい声で謝らせるのも嫌だし、私は別に「その日のそのイベント」に拘らなくても、時間が合うときに一緒に楽しく過ごせればなんだって良くて。
だからこうして並んで花火を見るなんて、実ははじめてのこと。残念なのは、楽しく笑い合って眺めることが出来ないことだろう。
「……金貸しから電話が来て、やたら焦った声で言うてきた。ナマエが、よりによって神室町イチ悪評極まりないホストに捕まったって」
そうしていれば彼が重い口を開いた。どこをどうなればそんなことになっているのか、その一言に思わず隣の彼をチラリと見てしまう。
彼が聞いた話だと、そのホストは客の女性を風俗送りにするのが特段上手いとか、また過去に数多の女性が彼のDV被害に遭っているとか、女と金にだらしなくてトラブルが絶えず、良いのは顔だけだとか……あぁ、もちろんコレは全部秋山さん談で。それが本当なら確かに悪評極まりない男ではあるけれど、神室町にそんなホストが実在するのかそれとも架空の話なのか。
どちらかは不明ながらも、とにかくそんな男と私が今日はデートで、手始めに二人でここで花火を見るって聞いた、という連絡が秋山さんから来たらしい。で、秋山さんからそのホストの数々の最低エピソードを色々と聞かされていくうちに頭に血が上り、慌ててここへやって来たと。ちなみに、そんな男にうまいこと言いくるめられた私のことを「阿呆な女」呼ばわりしていたようだ。
「心配してくれたんですか?」
ぼそっと訊ねてみたものの、彼は私を見ることもなければその問いに口を開くこともない。
「仮にその話が本当だったとしても、もう吾朗さんには関係ないことなんじゃないんですか?」
「阿呆か。お前をそないなクズにやるために手放したんとちゃう」
何も言ってくれない彼にやっぱり淋しさを感じて、少し不貞腐れるようにそうぶつけてみる。すると気のせいか思わぬ言葉が返ってきて、今度は驚きながらもしっかりはっきり彼に目を向ける。
「手放した? 捨てたんじゃなくて?」
だって、その二つのワードは似て非なるものではないか。でも相変わらず、彼は視界に私を捉えない。
「私のこと、もう好きじゃないんですよね?」
「おう」
「他に好きな人が出来たって」
「おう」
「身体の相性も抜群なんですもんね」
「おう」
「……目を見て答えてください」
身体ごと向き合って彼に訴えれば、彼も辛うじて顔だけこちらに向ける。少しだけ眉を顰めた、なんだか苦しそうな表情を見せながら。
「その話が本当なら、それはそれでいいんです。吾朗さんが幸せならそれでいいの。別に私のことわざと傷付けなくても、ちゃんと聞き分け良く離れるから。だから……本当のことをちゃんと言ってくれないと、私はいつまでも前を向けないんです」
彼のそんな顔を、私はこれまで見たことがなかったなと……そしてその苦しそうな表情で紡がれた声は、またも懐かしさを感じるような優しいものなのだから。
「本当のことを話したら……俺の為にも、これからは前を向いてくれや」
それでわかった。今ここにいる吾朗さんは、ちゃんと私の知る吾朗さんなんだって。
私が好きになった、私を愛してくれた彼は「前を向け」と言うけれど……それじゃあまるで、これからもやっぱり隣に貴方はいないと言われているようなものじゃないか。
「俺には、お前を幸せにしてやることは出来ん」
その一言は、別れてくれと言われた時よりも鋭いものとして心に突き刺さる。
だって今かけられている言葉は、あの時と違ってどこか信じられないようなものなんかじゃない。目の前にいるのは私を想う吾朗さんであり、そんな彼が真剣な眼差しではっきりと否定の言葉を述べたのだから。
「俺は、ナマエに幸せになってもらいたんや」
そうどこか他人任せな言い方は、その言葉の後ろにあるのが「それは俺じゃない」ということなのだろう。私自身は、吾朗さん以外の男性の横で幸せに思える未来など少しも想像出来ないというのに。
「誰もが思う『普通の恋愛』も『普通の幸せ』も、俺には与えてやることは出来ん。お前の周りのモンをどんどん奪うだけ奪って、我慢させることばっかりで、そのくせ与えられるモンも何も無い。お前がどう思っていようが、それは事実でしかあらへん。それが耐えられんのや」
綺麗事を並べてるけど本当は単に別れたいだけなんでしょうと、普通の人が相手ならそう思っていたかもしれない。
でもそれがいかに彼の本心か、私にはわかってしまうから。周囲と違う恋愛だということは、誰よりも私自身が身にしみて感じていたもの。
「愛した女一人幸せに出来ない男がいつまでもナマエのことを縛り続けるのは、俺自身が許せなくてな。せやからお前は、ちゃんとお前のことを幸せにしてくれるヤツに出逢うべきなんや。別に他に女もおらん、ナマエのことだって今も変わらず愛しとる、でも俺じゃあアカンねや」
「……なにそれ。それは、吾朗さんの自己満足でしょう?」
「あのな、人の気も知らんと勝手なこと言うなや。いくらお前でも許せんことだってあるで」
「だって私は『吾朗さんがいい』のに……奪ってるとか縛ってるとか、そんなこと一切感じてなんてないのに」
頼りないような声で絞り出すように必死にそう訴えてみても、彼の悲しそうな顔は変わらない。それがより彼と私の考え方の違いを浮き彫りにしているようで、離れていきそうな目の前の彼をどうしたら繋ぎ止められるのだろうか。
「私のことを幸せにしてくれる人って言うけど……私の幸せを思うなら、そのまま吾朗さんが隣にいてよ。私は、吾朗さんじゃなきゃ……」
だけど言葉でどんなに伝えても、彼はちっとも笑ってくれないのだ。どうして、いつもみたいに自信満々な笑顔で「それもそうやな」って言ってよ。
でもそんな言葉も貰えない。貴方はこれからもそのままでいてくれていいよって、私はきちんと幸せだよって、まだ足りないならもっと伝えるから、だからお願い。
「ねぇ、吾朗さん!」
「すまんな」
そんな私の願いも虚しく、優しい声でありながらしっかりと拒絶されてしまう。
「別れることを考えてたんも、別にここ最近のことやない。もっと前から、早よ手放してやらんととは思っとった。それがまぁ、俺もお前が好きな気持ちからずるずると先延ばしにしてもうて、あの日になったっちゅうだけや。早ければ早いほどナマエの為にもなるし、悲しませることもなかったのにな。ホンマに俺はどうしようもない男や」
悲しく笑いながら告げられたその言葉に必死に首を横に振る。早いも遅いもない、吾朗さんと別れることが私の為なはずがないでしょう、こんなに悲しい出来事でしかないのに。だからそんなこと言わないでよって、そんな気持ちがどんどん溢れてくる。
でもそれとは別に、もっと前からそんなことを考えていた事実が私に違うショックを与える。だって私は、ずっとずっと、幸せでしかなかったのに。そう思うと、いかに自分のことしか考えてなかったのか痛いほど感じてしまう。
「だからお前は、こんなヤクザのことは早よ忘れなアカン。そして次に出逢ったヤツと、今度はきちんと幸せになってくれや」
私は一緒にいれば嬉しくて幸せで、だから気付かなかった。一緒にいることで吾朗さんを苦しめていただなんて、そんなこと想像もしていなかった。これまで私は彼の隣にいたはずなのに、そんなふうに彼が悩んでいたことも知らずに、ただ自分が幸せでいるだけで……本当に、なんて愚かなのだろう。
もし私が少しでも早く彼の苦しみに気付いていれば、もし何かしら手を伸ばせていれば、何か言葉をかけられていれば、もっと幸せだと伝えられていたら……もしものことばかりを今になって考えても、もう手遅れで。
「それが、本当の……?」
「別れてくれって言ったあの日、こうやって馬鹿正直に本音で話をしとったら、かえって互いに別れられなくなると思った。ナマエの為だなんて優しさを見せて別れてくれと言ったところで、すんなり頷けないやろ? せやからあんな嘘ついて酷い言葉並べて、傷付けるだけ傷付けて……そうでもせんと離れられんと思ったからや、すまんかったな」
そんな謝罪の言葉なんて、私のほしいものじゃない。すまないと思っているなら、私の気持ちを……でも今の今までそんな彼の気持ちに気付きもしなかった私じゃあ、どのみちこの先、彼の隣に居続けることは出来ないだろうとも思った。
「だからナマエに対して絶対に思うはずがないようなことも、心を鬼にして言うてたんやで。俺の気持ちを無駄にせんといてな」
彼がこうして本当のことを口にする気になったのは、今はもう「既に別れている」からこそなのだろう。そうして彼は視線を前方の花火へと戻し、もう私を見ることはしなくなった。
もしかしたら、泣き喚いて駄々をこねてでもみれば……でもそうして無理矢理側にいてもらっても、きっともう見せてくれるのはさっきの悲しげな笑顔でしかないんだ。私の知るあの彼らしい笑顔を、迷いなく私へ向けてくれる日々はもう来ないのだとわかる。
別れを固く決意した彼を前にして、私はもう彼に目をやることも、花火を見ることも出来なくて……どうしたら彼を繋ぎ止められるのかなんて思考が働くこともなくなってしまった。私は一緒にいたくても、彼がそれを望んでいないんだ。
「私は……吾朗さんといて、ちゃんと恋愛してたんですよ。大人になってもこんな気持ちで恋をすることが出来るんだって、吾朗さんのおかげで知ったんです」
例え周りと少し違った恋愛だったとしても、それは比べる必要もないもので。淋しい思いや辛い思いも全部ひっくるめて、私にとって他には代えがたいとてもとても大切な恋であったし、貴方を好きになって得たものはたしかに幸せで溢れていた。もしもこれが最後になってしまうのであれば、それだけは知っていてほしい。
「それに、別れを告げられるその瞬間までずーっと幸せでした。吾朗さんだって、ちゃんと誰かを幸せにしてあげられる人なんですよ。だから、それは絶対に忘れないでくださいね」
やっぱり私は、心の底から吾朗さんが好きなんだ。だから、そんな顔をさせてしまうくらいなら。
「吾朗さんも、次に出逢う人とは今度こそ幸せになってください。約束ですよ」
だから明日からは、またいつもの吾朗さんらしく楽しく生きてくださいね。
「さようなら」
今も次から次へと綺麗に輝き続ける花火だけが、立ち去る私の背中を見送る。
それでも、涙で神室町を去るのはきっと今日が最後だろう。