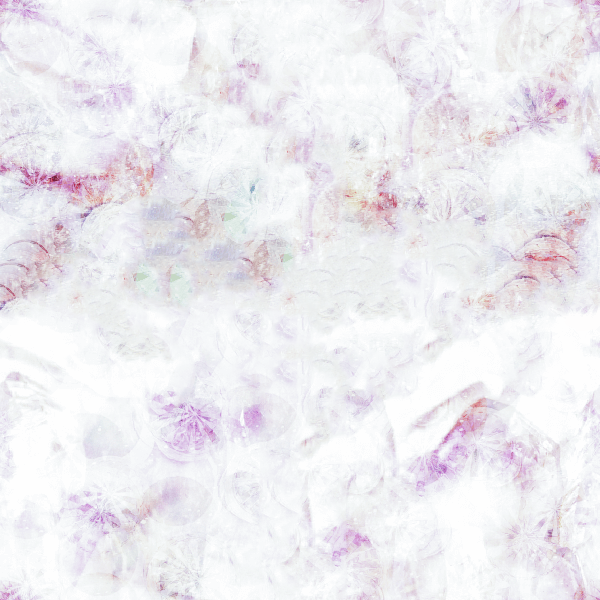恋の犠牲者はどちらか
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「なぁ、別れてくれんか?」
神室町のラブホテル。もうそろそろ時間が迫り退室の支度を進めていれば、つい先ほどまで愛し合った男女が口にするとは思えない言葉が聞こえた。
「……え?」
聞き間違いにしては、随分とタチの悪い間違え方をしたなと思う。そのため一瞬反応が出来ずに、遅れて出てきたのは戸惑いを含む声。
「別れてくれや」
今度は決して聞き間違いなんかじゃなかった。
彼は私の元へと近付いてきて、私の目を見て、とても真剣かつ冷酷な表情で、はっきりした声で、唇の動きもたしかにそれと相違のないものだった。
別れてくれ。そう言われたことはただただ現実の出来事でしかないと、目や耳から伝わる様々な情報により無情にもそう突きつけられたのだ。
嘘でしょう、どうして急に。なんだかまるで蛇がじりじりと巻き付いてきたみたいにゆっくり、でも確実に追い詰められているような……私は首でも絞められているのだろうかと、そう錯覚するほど徐々に息苦しさまで感じてしまう。
「えっ、と……どうして?」
理解するのに時間を要して、やっと出た声は震えていて。だって今の今まで、私達がここでしてた行為はなんだったのか。
「あ? そんなん、もうお前に興味がなくなったからや」
淡々と言ってのけるその様子だけでは、まるで別れ話を口にしているとは思えないほど軽い。多少の申し訳なさとか、なんとも言えない言いずらさとか、そんな素振りが僅かにでも見られるのならともかく。そんなものを全く見せずに、まるで世間話のノリなのは何故なの。
この状況がよくわからずに戸惑う私のことなど他所に、彼はヒヒッと笑い出してそれはそれは楽しそうな顔になる。
「実はな、顔良しスタイル良し身体の相性も抜群なめちゃくちゃええ女に出会ってな! せやから、お前とはもう終いや」
……あれ、おかしいな。私達、付き合ってたよね?
「身体の相性も、抜群って……」
「せやで! いやぁ俺もびっくりしたわ、ナマエも悪くないんやけど、上には上がおるモンやな!」
悪びれることもなく他の女と関係を持ったということを、しかもその女と相性が良かったということを、至極嬉しそうに私に報告してくる目の前の男の精神は如何に。
それでもまだどこか信じられない気持ちで、揺れる瞳で彼を見つめる。笑えない冗談だけど、悪ふざけが過ぎただけだって言ってくれるんじゃないかって、この期に及んでまだどこか縋るような思いを捨てられない。だって今まで私の隣にいてくれた彼はこんな人だったっけ、それとも今の彼が実は本当の彼なのかな。
人がそうやって、ただでさえ混乱しているというのに。
「しかもな、お前がさせてくれんようなプレイも喜んでしてくれるんやで。聞きたいか? あぁ?」
何が悲しくて、好きな男と他の女のプレイを聞かせられなきゃならないというの。もちろん「じゃあ聞かせてよ」だなんて言えるはずもなく、今の私は不快感を露わにした表情をしていることだろう。
でもこの人には容赦とか遠慮とか、そういうものはないらしい。
「それに加えて、ピル飲んどるからゴム無しでも出来るなんて最高やろ! なぁ?」
付け加える、デリカシーもなかった。つまり私は、ただただ彼の欲のためだけに捨てられるのか。ふざけないでよ。
そう思った途端に右手が衝動的に動く。その一瞬の動きを、もちろん彼は見逃すような人じゃない。
「殴って満足するんなら殴ればええ」
と、そう言う彼のその目はとてもとても冷たいもの。視線に捉えられた私は思わず動きが止まってしまう。その見下ろす表情からは、私への愛情なんて一切感じられなかった。
決して短くはないともに過ごした期間は、一体この人にとって何だったのだろう。
「ほれ、どうした? 殴りたいんやなかったんか?」
いつでもええで、ほれ。そうやってわざと顔を近付けて促してまでくる始末で。
まぁお前のビンタなんぞ、桐生ちゃんのデコピンにも満たない微々たるモンやろうけどな! そう言ってまた、どこか楽しそうに悪い笑顔を見せるんだ。
あぁ、そうか。私のビンタなんてそんなもん。この人にとって物理的に痛くないのは勿論のこと、精神的にだって痛くも痒くもないものなのだろう。それがわかってただ単純に悲しくなって、この右手は重力に則りぶらんと垂れた。
せめて最後に、ひと匙の罪悪感くらい感じてくれればいいのに。引っ叩いたところで彼に痛みもなにも残らないとなると、もはや殴っても無意味なんじゃないかとも思えてしまう。
私はやっぱり、彼が好きだから。急にスイッチを切るように「今から嫌い」だなんてなれないから。
少し前まであんなに私のことを優しく抱いてくれていたはずが、それは最後に見せてくれた優しい幻でしかなくなったなんて、そんなの信じたくない。信じたくないけど。
「まぁそんなワケやから、もう連絡してこんといてな。あのコに誤解されたら大変や、あんな極上の女は他におらんしな! ……あぁ、もし納得いってないんやったら金でも積んだるで」
ついには、どのコか知らない「あのコ」のために手切れ金の話まで持ち出してくる。私とのこれまでは、彼にとってお金でなかったことに出来る程度の日々だったらしい。あぁ、もう、これまで私の隣にいたのは別人なんじゃ……そう思ってしまうくらいに、私の知る彼の姿がガラガラと崩れていくのがわかった。
何をしても、何を言っても、もうこの人に私の言動が響くことはないのだろうと思わせられるその雰囲気に、私はなす術もなくなってしまった。
情けなくぐずぐずと鼻を啜りながら自分のバッグを手にして、一人無言でホテルの部屋を出る。こうして泣きながら飛び出したところで、当然彼が追いかけてくることもないということを身をもって味わう。
ホテルに入るときは晴れていたのに、今はザーッと雨が降っている。傘なんてない、でもコンビニで買う気にもならない。泣きながら雨に濡れて、でも今はそれが気にならないほど他のことなんてどうでも良い。
何がいけなかったんだろう。上手くやってたと思ってたのにな。あぁ、でもさっきの話だと身体の相性云々で乗り換えるって話だったか。なにそれ、私が彼という男性に惹かれたのはもっと別のものだったのに、彼はそんな深い理由で私と付き合っていたわけじゃなかったなんて。
もう付き合って三年くらいになるんだっけ。頻繁に会えない人だから私は倦怠期だなんてあまり感じてなかったけど、彼にとってはそうじゃなかったのかも。普通の恋愛じゃなかったから大変なこともあったけど、でもそんなの関係ないと思えるほどにあの人を愛していたのは間違いなくて。
「……私、これでもけっこう頑張ってたんだけどなぁ」
ぼそっと呟いたこの言葉は雨音が誤魔化してくれる。それならこれまでの思い出も彼への気持ちも、どうせなら全部流してくれればいいのに。
神室町のラブホテル。もうそろそろ時間が迫り退室の支度を進めていれば、つい先ほどまで愛し合った男女が口にするとは思えない言葉が聞こえた。
「……え?」
聞き間違いにしては、随分とタチの悪い間違え方をしたなと思う。そのため一瞬反応が出来ずに、遅れて出てきたのは戸惑いを含む声。
「別れてくれや」
今度は決して聞き間違いなんかじゃなかった。
彼は私の元へと近付いてきて、私の目を見て、とても真剣かつ冷酷な表情で、はっきりした声で、唇の動きもたしかにそれと相違のないものだった。
別れてくれ。そう言われたことはただただ現実の出来事でしかないと、目や耳から伝わる様々な情報により無情にもそう突きつけられたのだ。
嘘でしょう、どうして急に。なんだかまるで蛇がじりじりと巻き付いてきたみたいにゆっくり、でも確実に追い詰められているような……私は首でも絞められているのだろうかと、そう錯覚するほど徐々に息苦しさまで感じてしまう。
「えっ、と……どうして?」
理解するのに時間を要して、やっと出た声は震えていて。だって今の今まで、私達がここでしてた行為はなんだったのか。
「あ? そんなん、もうお前に興味がなくなったからや」
淡々と言ってのけるその様子だけでは、まるで別れ話を口にしているとは思えないほど軽い。多少の申し訳なさとか、なんとも言えない言いずらさとか、そんな素振りが僅かにでも見られるのならともかく。そんなものを全く見せずに、まるで世間話のノリなのは何故なの。
この状況がよくわからずに戸惑う私のことなど他所に、彼はヒヒッと笑い出してそれはそれは楽しそうな顔になる。
「実はな、顔良しスタイル良し身体の相性も抜群なめちゃくちゃええ女に出会ってな! せやから、お前とはもう終いや」
……あれ、おかしいな。私達、付き合ってたよね?
「身体の相性も、抜群って……」
「せやで! いやぁ俺もびっくりしたわ、ナマエも悪くないんやけど、上には上がおるモンやな!」
悪びれることもなく他の女と関係を持ったということを、しかもその女と相性が良かったということを、至極嬉しそうに私に報告してくる目の前の男の精神は如何に。
それでもまだどこか信じられない気持ちで、揺れる瞳で彼を見つめる。笑えない冗談だけど、悪ふざけが過ぎただけだって言ってくれるんじゃないかって、この期に及んでまだどこか縋るような思いを捨てられない。だって今まで私の隣にいてくれた彼はこんな人だったっけ、それとも今の彼が実は本当の彼なのかな。
人がそうやって、ただでさえ混乱しているというのに。
「しかもな、お前がさせてくれんようなプレイも喜んでしてくれるんやで。聞きたいか? あぁ?」
何が悲しくて、好きな男と他の女のプレイを聞かせられなきゃならないというの。もちろん「じゃあ聞かせてよ」だなんて言えるはずもなく、今の私は不快感を露わにした表情をしていることだろう。
でもこの人には容赦とか遠慮とか、そういうものはないらしい。
「それに加えて、ピル飲んどるからゴム無しでも出来るなんて最高やろ! なぁ?」
付け加える、デリカシーもなかった。つまり私は、ただただ彼の欲のためだけに捨てられるのか。ふざけないでよ。
そう思った途端に右手が衝動的に動く。その一瞬の動きを、もちろん彼は見逃すような人じゃない。
「殴って満足するんなら殴ればええ」
と、そう言う彼のその目はとてもとても冷たいもの。視線に捉えられた私は思わず動きが止まってしまう。その見下ろす表情からは、私への愛情なんて一切感じられなかった。
決して短くはないともに過ごした期間は、一体この人にとって何だったのだろう。
「ほれ、どうした? 殴りたいんやなかったんか?」
いつでもええで、ほれ。そうやってわざと顔を近付けて促してまでくる始末で。
まぁお前のビンタなんぞ、桐生ちゃんのデコピンにも満たない微々たるモンやろうけどな! そう言ってまた、どこか楽しそうに悪い笑顔を見せるんだ。
あぁ、そうか。私のビンタなんてそんなもん。この人にとって物理的に痛くないのは勿論のこと、精神的にだって痛くも痒くもないものなのだろう。それがわかってただ単純に悲しくなって、この右手は重力に則りぶらんと垂れた。
せめて最後に、ひと匙の罪悪感くらい感じてくれればいいのに。引っ叩いたところで彼に痛みもなにも残らないとなると、もはや殴っても無意味なんじゃないかとも思えてしまう。
私はやっぱり、彼が好きだから。急にスイッチを切るように「今から嫌い」だなんてなれないから。
少し前まであんなに私のことを優しく抱いてくれていたはずが、それは最後に見せてくれた優しい幻でしかなくなったなんて、そんなの信じたくない。信じたくないけど。
「まぁそんなワケやから、もう連絡してこんといてな。あのコに誤解されたら大変や、あんな極上の女は他におらんしな! ……あぁ、もし納得いってないんやったら金でも積んだるで」
ついには、どのコか知らない「あのコ」のために手切れ金の話まで持ち出してくる。私とのこれまでは、彼にとってお金でなかったことに出来る程度の日々だったらしい。あぁ、もう、これまで私の隣にいたのは別人なんじゃ……そう思ってしまうくらいに、私の知る彼の姿がガラガラと崩れていくのがわかった。
何をしても、何を言っても、もうこの人に私の言動が響くことはないのだろうと思わせられるその雰囲気に、私はなす術もなくなってしまった。
情けなくぐずぐずと鼻を啜りながら自分のバッグを手にして、一人無言でホテルの部屋を出る。こうして泣きながら飛び出したところで、当然彼が追いかけてくることもないということを身をもって味わう。
ホテルに入るときは晴れていたのに、今はザーッと雨が降っている。傘なんてない、でもコンビニで買う気にもならない。泣きながら雨に濡れて、でも今はそれが気にならないほど他のことなんてどうでも良い。
何がいけなかったんだろう。上手くやってたと思ってたのにな。あぁ、でもさっきの話だと身体の相性云々で乗り換えるって話だったか。なにそれ、私が彼という男性に惹かれたのはもっと別のものだったのに、彼はそんな深い理由で私と付き合っていたわけじゃなかったなんて。
もう付き合って三年くらいになるんだっけ。頻繁に会えない人だから私は倦怠期だなんてあまり感じてなかったけど、彼にとってはそうじゃなかったのかも。普通の恋愛じゃなかったから大変なこともあったけど、でもそんなの関係ないと思えるほどにあの人を愛していたのは間違いなくて。
「……私、これでもけっこう頑張ってたんだけどなぁ」
ぼそっと呟いたこの言葉は雨音が誤魔化してくれる。それならこれまでの思い出も彼への気持ちも、どうせなら全部流してくれればいいのに。
1/13ページ