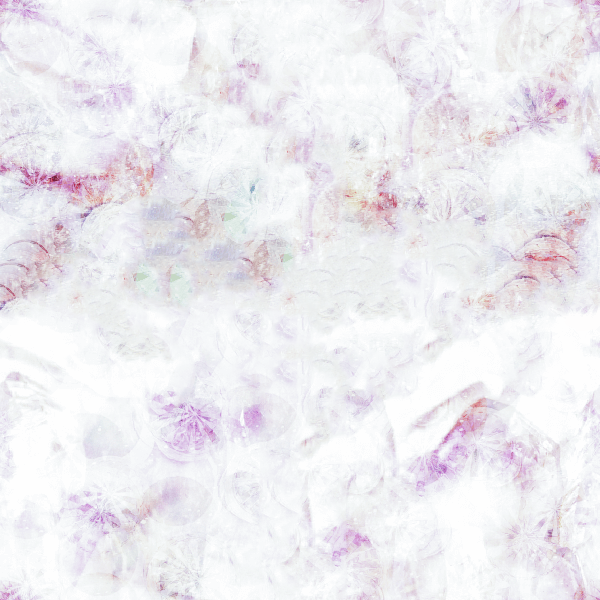Short story
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「俺なぁ、バツイチやねん」
以前、真島さんがお酒の勢いでぽろっとこぼしたその言葉を、ふと思い出した。なにかきっかけがあったとかじゃなく、本当にたまたま思い返されたという。
それを耳にしたのは、まだこうして付き合う前のことだ。まぁ、彼の年齢的に一度くらいそういうことがあっても今どき珍しくもないしと、特に気にならなかった。当時はお友達としての会話だし、「へぇ、そうなんですね! 結婚してたのは意外でした」なんて笑って返して、その話題はそれで終わったのだ。
変えられない事実ではあれど、それはもう通り過ぎた過去のこと。今さらどうこう考えることに意味なんてないはずなのに、なぜか今になって唐突に、そして妙に気になってしまった。なんなのこの感情、ちょっと面倒くさいなぁなんて、そんな自分にも自己嫌悪してしまう。
「……どうかしたか?」
「え!?」
一緒に並んで歩いていたときだ。ふと私の視界に、こちらを覗き込む真島さんが現れて、つい焦りの声が出た。そして「急に大人しくなったな、なにかあったんか?」と聞かれ、返事にも困ってしまう。
なにもない……ただ私が、勝手に以前の話を思い出して、それに対してモヤモヤしてるなんて、彼にとっては迷惑でしかないだろう。せっかくのデートなんだ、だから「大丈夫ですよ」と笑って誤魔化して、また会話を再開させる。
なにがそんなに気になるって、だって「自分のやりたいように生きる」という言葉をそのまま体現しているような真島さんが、その人生を誰かとともにしようとしていたことが、彼を知れば知るほど不思議に感じてしまうんだ。なんと言えばいいのか、彼に選ばれたその方はすごいなぁっていう、小学生の感想文みたいな言葉しか浮かばないのだけど。
そして、選ばれた人が羨ましいと、過去の終わった話にさえも羨望する自分自身がいて、それにも戸惑ってしまう。私は、彼にそんなふうに思ってもらえるのかななんて、急にどこからか面倒くさい感情が一度出てきてしまうと、なかなか引っ込んでくれないのも困ったものだ。
あぁ、もうやめよう。昔の話じゃん。人と比べたって私は私でしかないし、彼が今選んでくれているのは私なんだ。他の人じゃない。それだって紛れもない事実。
それなのに……「この先、もう他の人はいらない。この人だけでいい」って思う存在が、過去とはいえ真島さんにはいたのだと、その事実がどうにもモヤモヤしてしまう。終わった出来事にもかかわらず、こんな気持ちにさせられるなんて……わかるのは、彼の過去さえ欲しくなってしまうほど、私にとって彼が特別なのだろうということ。
「俺とおるのに考え事とはのぅ」
「真島さんのこと考えてたんですよ」
一息つこうと入った喫茶店。目の前に座る彼が、煙草を吸いながら静かにぼやく。飲み物を口にしながら、ぼんやり外を眺めるフリをしてモヤモヤを必死に掻き消そうとしている私の心は、どうやら隠し通せていなかったらしい。
「そのわりには、浮かない顔しとるやろが」
「そうですね、自分でもびっくりするくらい真島さんのことが好きみたいで」
「なんやそれ」
真島さん相手に誤魔化すなんて分が悪い。それがわかってるから、気づかれてしまったのなら素直に白状する。それに、ものは言いようだ。考えているのはあなたのことですって、たぶん、彼にとって悪いことではないはず。
「その……真島さん、昔、結婚してたって。だから、お嫁さんに選ばれた人が羨ましいなぁって、急にふと思っちゃったんです。なんででしょうね、本当に突然なんですけど」
重い雰囲気にもしたくないから、できるだけ笑って言うんだ。
「過去にヤキモチ妬いちゃうなんて、面倒くさいなぁって思いますよね。私も自分でそう思っちゃって、それで、ちょっと……まぁ、羨ましいっていうか、私もいつか、真島さんにそんな存在に選ばれたらいいなっていう、憧れみたいな感じですかね」
言い終わるなり、これ以上の言葉を飲み込むよう、すぐにストローへ口をつけた。ひんやりとしたドリンクが、少しでもこの心を冷静にさせてくれたならいいのに。
軽い感じで伝えたから、険悪なムードにこそなってはいないけれど……それでも、私の突然の言葉にこちらをまじまじと見つめる彼が目の前にいて、気まずさが膨らんでいく。
「……あの、あんまり真面目に受け止めなくていいですよ」
「あぁ? それやったら、今の言葉はふざけ半分だったんか?」
「そうじゃないですけど」
「心配せんでも、この先ずっと一緒におる女はナマエだけやで」
「……じゃあ、そこまで思ってもらえるのは、真島さん史上で二人目の女ですかね、私」
「二人目? なに言っとんのや、『最後の女』やろ」
やはり、ものは言いようだなと思った。でも、それはそれで、やっぱりズルいなぁって思ってしまう。
「それで言えば、どうせなら『最初で最後の女』がよかったなぁって……そう思っただけです」
「最初で最後なぁ……」
そう、最初で最後。私が「もう、この先はこの人しかいらない」って選ぶのは、今までもこれからも真島さんだけなんだろうと思う。
最初で最後、唯一無二、そんな特別感。だから、やっぱり……せっかくなら、私も彼にとっての最初で最後の存在になりたかったなぁなんて、そんな叶わない夢を見るのも、このわずかな時間で終わらせなければ。
少なくとも、目の前にいる彼は、これからを私とともに歩くつもりで隣にいてくれるのだから。私がこの目で見るべき夢は、終わった出来事を羨むことじゃないはずだ。
「ええやん、それ」
「はい?」
「喉から手が出るほど欲しいポジションやな」
すると、なにやら笑みを浮かべご満悦な様子を見せる彼が、疑問の眼差しを浮かべる私に続ける。
「ナマエにとっての『最初で最後』っちゅうヤツや。もちろん、俺やろ?」
「あ、当たり前のように言いますけど、大前提として、私のことが何よりいちばんじゃなきゃダメですよ!」
「おう。そんなん標準装備やで」
「いつも優しくしてくれて、いつも目一杯愛してくれて」
「それだっていつもどおりやないか」
「他の女性に目もくれずに」
「お前がおるんや、他なんていらんやろ」
「あ、それに私を悲しませないとか」
「ヒヒッ、基本中の基本やな」
「私に嘘をつかないとか」
「俺も嘘は嫌いやからな」
「私が悲しいときや淋しいときは飛んできてくれる、なんてのは、さすがに難しいですよね」
「なにが難しいねん。いつも一緒におれば、駆けつける必要もあらへんやろ。安心せぇ」
もはや、言葉を探しては絞り出すようにアレコレ述べる私に対して、彼は言葉を選ぶ時間を設けることなく、答えをすぐに返してくる。
言葉のキャッチボールと例えられるそれは、私が戸惑いながら投げる緩やかなボールを、真島さんは受け止めるなりド直球のストレートで私へと返してくるみたい。彼のボールには迷いがなくて、しかも、その力強さに私は受け止めるのに必死。彼には敵わないなって、そんな気持ちにさせられてしまう。
「……じゃあ、こんな無理なことばっかり言ってる女なのに、それでも笑って『ええで』って言ってくれますか?」
「おう、ええで」
私の最初で最後の特別な男になろうと言葉を尽くしてくれる彼が、ニカッと自信に満ちた笑顔で、そう真っ直ぐに告げてきた。それを目の当たりにしてしまえば、よくわからない嫉妬なんて、もうどうでもよくなっていく。なんで、あんなこと思っちゃったんだっけ。そう思わせるほど、彼の言葉の説得力は強いから本当に不思議だ。
やはり「自分のやりたいように生きる」を体現している真島さんが、こうやって我儘を並べるように何を言っても、そんな私を受け止める気満々で、私の為にそこまで言い切ってくれるのだから。私の気持ちを受け入れること、私のために言葉を尽くしてくれること。それだって、彼の「やりたいこと」だとしたら……。
きっと、私が自分で思ってる以上に、私は彼にとってちゃんと特別なのかもしれない、なんてね。
以前、真島さんがお酒の勢いでぽろっとこぼしたその言葉を、ふと思い出した。なにかきっかけがあったとかじゃなく、本当にたまたま思い返されたという。
それを耳にしたのは、まだこうして付き合う前のことだ。まぁ、彼の年齢的に一度くらいそういうことがあっても今どき珍しくもないしと、特に気にならなかった。当時はお友達としての会話だし、「へぇ、そうなんですね! 結婚してたのは意外でした」なんて笑って返して、その話題はそれで終わったのだ。
変えられない事実ではあれど、それはもう通り過ぎた過去のこと。今さらどうこう考えることに意味なんてないはずなのに、なぜか今になって唐突に、そして妙に気になってしまった。なんなのこの感情、ちょっと面倒くさいなぁなんて、そんな自分にも自己嫌悪してしまう。
「……どうかしたか?」
「え!?」
一緒に並んで歩いていたときだ。ふと私の視界に、こちらを覗き込む真島さんが現れて、つい焦りの声が出た。そして「急に大人しくなったな、なにかあったんか?」と聞かれ、返事にも困ってしまう。
なにもない……ただ私が、勝手に以前の話を思い出して、それに対してモヤモヤしてるなんて、彼にとっては迷惑でしかないだろう。せっかくのデートなんだ、だから「大丈夫ですよ」と笑って誤魔化して、また会話を再開させる。
なにがそんなに気になるって、だって「自分のやりたいように生きる」という言葉をそのまま体現しているような真島さんが、その人生を誰かとともにしようとしていたことが、彼を知れば知るほど不思議に感じてしまうんだ。なんと言えばいいのか、彼に選ばれたその方はすごいなぁっていう、小学生の感想文みたいな言葉しか浮かばないのだけど。
そして、選ばれた人が羨ましいと、過去の終わった話にさえも羨望する自分自身がいて、それにも戸惑ってしまう。私は、彼にそんなふうに思ってもらえるのかななんて、急にどこからか面倒くさい感情が一度出てきてしまうと、なかなか引っ込んでくれないのも困ったものだ。
あぁ、もうやめよう。昔の話じゃん。人と比べたって私は私でしかないし、彼が今選んでくれているのは私なんだ。他の人じゃない。それだって紛れもない事実。
それなのに……「この先、もう他の人はいらない。この人だけでいい」って思う存在が、過去とはいえ真島さんにはいたのだと、その事実がどうにもモヤモヤしてしまう。終わった出来事にもかかわらず、こんな気持ちにさせられるなんて……わかるのは、彼の過去さえ欲しくなってしまうほど、私にとって彼が特別なのだろうということ。
「俺とおるのに考え事とはのぅ」
「真島さんのこと考えてたんですよ」
一息つこうと入った喫茶店。目の前に座る彼が、煙草を吸いながら静かにぼやく。飲み物を口にしながら、ぼんやり外を眺めるフリをしてモヤモヤを必死に掻き消そうとしている私の心は、どうやら隠し通せていなかったらしい。
「そのわりには、浮かない顔しとるやろが」
「そうですね、自分でもびっくりするくらい真島さんのことが好きみたいで」
「なんやそれ」
真島さん相手に誤魔化すなんて分が悪い。それがわかってるから、気づかれてしまったのなら素直に白状する。それに、ものは言いようだ。考えているのはあなたのことですって、たぶん、彼にとって悪いことではないはず。
「その……真島さん、昔、結婚してたって。だから、お嫁さんに選ばれた人が羨ましいなぁって、急にふと思っちゃったんです。なんででしょうね、本当に突然なんですけど」
重い雰囲気にもしたくないから、できるだけ笑って言うんだ。
「過去にヤキモチ妬いちゃうなんて、面倒くさいなぁって思いますよね。私も自分でそう思っちゃって、それで、ちょっと……まぁ、羨ましいっていうか、私もいつか、真島さんにそんな存在に選ばれたらいいなっていう、憧れみたいな感じですかね」
言い終わるなり、これ以上の言葉を飲み込むよう、すぐにストローへ口をつけた。ひんやりとしたドリンクが、少しでもこの心を冷静にさせてくれたならいいのに。
軽い感じで伝えたから、険悪なムードにこそなってはいないけれど……それでも、私の突然の言葉にこちらをまじまじと見つめる彼が目の前にいて、気まずさが膨らんでいく。
「……あの、あんまり真面目に受け止めなくていいですよ」
「あぁ? それやったら、今の言葉はふざけ半分だったんか?」
「そうじゃないですけど」
「心配せんでも、この先ずっと一緒におる女はナマエだけやで」
「……じゃあ、そこまで思ってもらえるのは、真島さん史上で二人目の女ですかね、私」
「二人目? なに言っとんのや、『最後の女』やろ」
やはり、ものは言いようだなと思った。でも、それはそれで、やっぱりズルいなぁって思ってしまう。
「それで言えば、どうせなら『最初で最後の女』がよかったなぁって……そう思っただけです」
「最初で最後なぁ……」
そう、最初で最後。私が「もう、この先はこの人しかいらない」って選ぶのは、今までもこれからも真島さんだけなんだろうと思う。
最初で最後、唯一無二、そんな特別感。だから、やっぱり……せっかくなら、私も彼にとっての最初で最後の存在になりたかったなぁなんて、そんな叶わない夢を見るのも、このわずかな時間で終わらせなければ。
少なくとも、目の前にいる彼は、これからを私とともに歩くつもりで隣にいてくれるのだから。私がこの目で見るべき夢は、終わった出来事を羨むことじゃないはずだ。
「ええやん、それ」
「はい?」
「喉から手が出るほど欲しいポジションやな」
すると、なにやら笑みを浮かべご満悦な様子を見せる彼が、疑問の眼差しを浮かべる私に続ける。
「ナマエにとっての『最初で最後』っちゅうヤツや。もちろん、俺やろ?」
「あ、当たり前のように言いますけど、大前提として、私のことが何よりいちばんじゃなきゃダメですよ!」
「おう。そんなん標準装備やで」
「いつも優しくしてくれて、いつも目一杯愛してくれて」
「それだっていつもどおりやないか」
「他の女性に目もくれずに」
「お前がおるんや、他なんていらんやろ」
「あ、それに私を悲しませないとか」
「ヒヒッ、基本中の基本やな」
「私に嘘をつかないとか」
「俺も嘘は嫌いやからな」
「私が悲しいときや淋しいときは飛んできてくれる、なんてのは、さすがに難しいですよね」
「なにが難しいねん。いつも一緒におれば、駆けつける必要もあらへんやろ。安心せぇ」
もはや、言葉を探しては絞り出すようにアレコレ述べる私に対して、彼は言葉を選ぶ時間を設けることなく、答えをすぐに返してくる。
言葉のキャッチボールと例えられるそれは、私が戸惑いながら投げる緩やかなボールを、真島さんは受け止めるなりド直球のストレートで私へと返してくるみたい。彼のボールには迷いがなくて、しかも、その力強さに私は受け止めるのに必死。彼には敵わないなって、そんな気持ちにさせられてしまう。
「……じゃあ、こんな無理なことばっかり言ってる女なのに、それでも笑って『ええで』って言ってくれますか?」
「おう、ええで」
私の最初で最後の特別な男になろうと言葉を尽くしてくれる彼が、ニカッと自信に満ちた笑顔で、そう真っ直ぐに告げてきた。それを目の当たりにしてしまえば、よくわからない嫉妬なんて、もうどうでもよくなっていく。なんで、あんなこと思っちゃったんだっけ。そう思わせるほど、彼の言葉の説得力は強いから本当に不思議だ。
やはり「自分のやりたいように生きる」を体現している真島さんが、こうやって我儘を並べるように何を言っても、そんな私を受け止める気満々で、私の為にそこまで言い切ってくれるのだから。私の気持ちを受け入れること、私のために言葉を尽くしてくれること。それだって、彼の「やりたいこと」だとしたら……。
きっと、私が自分で思ってる以上に、私は彼にとってちゃんと特別なのかもしれない、なんてね。