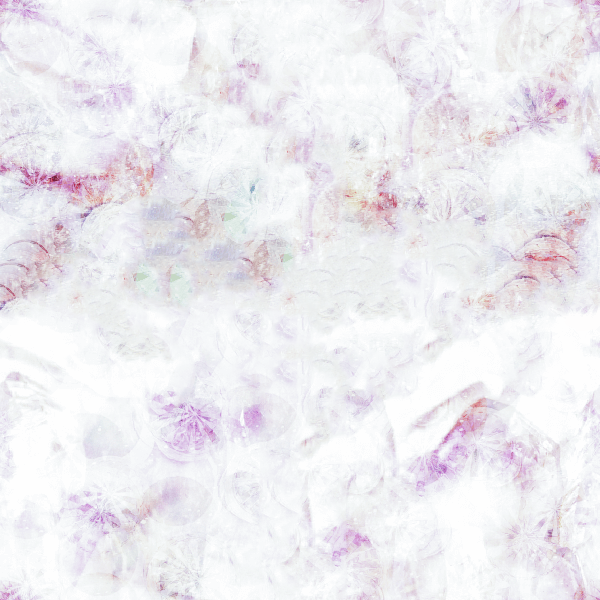Short story
Name Change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
帰宅して靴を脱ぎ部屋に上がる。今日、家を出るときにウキウキしながら履いた新品のそれは、無造作に玄関に散らばってしまった。でも、今は直す気力がない。身に付けたアクセサリーも外していく。そして、今日のためにと新調したワンピース。これもまた、するりと脱ぎ捨てた。
私が、少しでも綺麗に見えますように。一つひとつ、どれもそんな魔法をかけるような気持ちで身に纏ったものだ。それらが、役割を成すことなく私のもとから解かれていくこの瞬間は、本当に虚しくなる。これだって、もう何回目だろう。
大好きな彼と会えるはずだった。忙しい人だから、最近はなかなか会うことができずにいて、今日こそ、やっと。いよいよ待ち合わせの時間が迫り、はやる気持ちを抱えながら神室町方面へ向かっていた。その道中で、彼からの電話が鳴って……当然、タイミングとしても「どこにいる?」みたいな会話が繰り広げられる電話だとしか考えていなかった。だから、弾む声で「もしもし」と電話に出た私を、彼は申し訳なさそうな声で突き落としてくるだなんて、信じたくなかった。
思わず、この手からすり抜けそうになった電話。はっとして慌てて握り直すものの、彼の言葉はもう話半分で、それこそ反対の耳から抜けていく感じだ。
「すまんな」
「ううん、大丈夫」
あぁ、このやり取りも何度目か。もはやテンプレートになってきたような会話に、溜息さえも出なくなってきた。そして、切れた電話に心の中で悪態をつく。せめて、あと一時間早くに連絡してくれれば、だなんて仕方のないことを。わかっている、彼だって仕事なんだ。働いていればどうしようもないことがある。理解しているよ、そんなのお互い様だから。
でも、今日は……言葉は悪いが、ドタキャンされてしまった前のデートの埋め合わせの、さらに埋め合わせなのだ。つまり、これでデートがお流れになって三回連続ではないか。
さらに言えば、今日という日は彼が指定してくれたもので、世間ではクリスマス。クリスマスにはしゃぐような年齢でもなくなったとはいえ、一緒に過ごそうと思ってくれたのかなとか、やっぱりちょっとばかり期待しちゃうじゃん。これがこれからも続く可能性を思うと、さすがになんだかなぁと思えてしまう。
それでも、特殊な彼のお仕事柄、大丈夫と言うしかないし、嫌だと言って困らせることの方がもっと嫌だから。そういうことをひっくるめて、彼のためにと思い「大丈夫」と言ったのは嘘じゃない。彼も頑張っているから、私も次に会えるときまで頑張ろうって、たいして楽しくもない日や辛い日も、理不尽な日だって乗り越えてきたんだ。それが、今日だったのにな。
もともと頻繁に会えるような人じゃないから、余計に……デートが立て続けに何度もだめになっていると、さすがにショックが大きい。
ふと鏡に映る、シャワーを浴びたあとの自分。綺麗に見えたらと試行錯誤したヘアもメイクもリセットされて、「少しでも素敵な女に見えますように」という願いを込めてかけたはずの魔法は、もうすべて解けてしまった。部屋着になり、「ただの私」となった今、あとはこのまま明日を迎えるのみである。
私の携帯はいまだに無音なまま。なんの知らせも告げてくれないことに、また虚しくなる。はじめてこういう事態になったときは、会えないかわりにこまめに連絡してくれたりと手厚いフォローがあった。「仕方ないことですから、そんなに気にしなくても大丈夫ですよ」と、こっちが申し訳なく思ってしまうくらいだった。
さすがに三回目ともなると、彼も慣れたのだろうか。そう思いたくなるくらい、今の今までサッパリ何もない。なんだそれ。楽しみにしてたのは私だけだったのかな。
あーあ、今ごろはきっと、一緒に街を歩いて美味しいご飯を食べて……だなんて、叶わなくなってしまったデートに想いを馳せたところでどうしようもない。あ、そういえばご飯……外で食べる気満々で特に用意もせずいたから、残念ながら家にたいしたものはない。かといって、コンビニ程度だろうと、もう外に出るのも気が乗らない。
吾朗さんには会えないし、気分は沈むしお腹も減るし、もう踏んだり蹴ったりだ。部屋で一人むすっとしていれば、ずっと沈黙だったものから電子音がした。
相手は、まさに考えていた人だ。連絡が来たことの嬉しさと、会うことのできない淋しさが重なり、複雑な思いで電話に出る。
「もしもし?」
「おう。もう家におるか?」
「うん」
「それやったら、悪いんやけど十分後くらいに外に出とってくれんか? 両手が塞がってドア開けられんわ」
「……ん?」
「じゃあ、またあとでな。頼むわ」
交わされた会話は、用件だけの手短な電話。そして、途切れた電話を目にしながら疑問に思う。
どういうこと。十分後に外? え、それって、ここに来るってこと? うそ、会えるの!? いやいや、でも、さっきは「予定が変わってすまんな」って言われたんだけど。
ええと、あの……もしかして、人違いの可能性があるのでは。混乱する頭で、わりと本気でそんな結論が導き出される。だとしたら、彼は、誰に会うつもりで……まさか、他の女の人、とか? というか、両手が塞がってドア開けられないってなに。じゃあ、どうやって電話してたの。
いろいろ考え始めるとキリがなくて、とりあえず言われたとおりに外へ出てはみるものの、本当に来るのかな。少し待って来なければ、いよいよ電話をかける相手を間違えた説が濃厚になる。そうなると今度は、その相手が誰なのかという問題が出てきてしまうではないか。これ以上嫌な思いが重なるくらいなら、よくわからないけど、ひとまずここに来てくれることを願うしかない。
その願いが通じたのか、この辺りに似つかわしくない立派な車が目の前に停車された。そこから降りてきたのは、間違いなく電話をかけてきた吾朗さんだ。また、その両手にはさまざまな袋を手にしていて、たしかに塞がっている。
「おう、すまんな! ほれ、いろいろあるんやけど、まぁとりあえず入ってからやな」
「え、あぁ、うん……あ、どれか持とうか?」
「あぁ、別にええわ。ドアだけ開けてくれや」
吾朗さんの両手の荷物からは、やけに食欲をそそるいい匂いが。そして、心なしか彼が上機嫌であるようにも見える。事態が飲み込めないまま部屋に入れば、「とりあえず、よさそうなモン適当に用意したで!」と、立派で美味しそうな料理の数々が袋から出てくる。
これはどういう状況なのか。脳内処理が追いつかないでいれば、そんな私に、吾朗さんが心配そうな声を上げた。
「……もしかして、どれもイマイチやったか!? コレとか、ナマエが好きそうやなと思うてたんやが」
「あ、ううん! そうじゃなくて……」
どうやら人違いではないらしい、たぶん。
「いや、その、まさか吾朗さんが来てくれると思わなくて。だって、仕事が忙しいって、電話で……」
「あぁ? せやから、その電話で言うたやろ」
あれ、そうだっけ。電話での会話を一生懸命思い出してみるけど、そんなこと言われてたかな。「仕事が押して予定が変わったから、待ち合わせには間に合わん」と。その一言が、浮足立っていた私を地に叩きつけるかのように強烈すぎて、それしか思い出せない。「でも、吾朗さん、待ち合わせは無理だからって」だなんて口にする相変わらずの私に、彼が不思議そうに続けた。
「せやで。だから、そのまま車でナマエの家まで行くって伝えたやろが」
「お前、まさか聞いとらんかったんか!?」と驚愕する彼を前に、あぁ、もしかしてと、ひとつの心当たりが脳裏をかすめた。
「あのね、私。その……待ち合わせに間に合わないって言われたとき、今日は会えなくなったんだとばかり思って、それがすごくショックで……そこで、持ってた電話を落としかけちゃって」
待ち合わせには間に合わない。その言葉のあと、指からふっと力が抜けたあの瞬間。耳からずれてしまったと認識して、慌ててもとに戻したときに、たしかに吾朗さんは何か言っていた気もする。
「それでもかまわんか? ……おい、ナマエ? 聞こえとるか?」
「あぁ、ごめん! うん、私は大丈夫だから」
「なら、またあとで連絡するわ。すまんな」
「ううん、大丈夫」
また耳に当てたときには、そんな流れになっていたっけ。
「だから、会えると思ってなかったから……それに、これ、わざわざ用意してくれたの? あの、ちょっと今、嬉しすぎて頭が追いついてないっていうか……」
高揚する気持ちが混ざりながらそう口にすれば、彼は私の頭を撫でてヒヒッと笑う。
「ほう。そないに感激するほど会いたかったってことでええな?」
「それは、もう……だって、ずっと会えてなかったから」
「せやな。それはホンマにすまんかったわ。今日も、本当なら街を歩いたりしたかったやろ」
「そんなのいい。吾朗さんと過ごせるならどこだっていいもん」
「ヒヒッ、今日はずいぶんと素直やなぁ」
さっきと違って、今じゃあ新しい服や靴もなければ、綺麗なアクセサリーもいつもと違うメイクだってない。そんな「ただの私」だけど、少しだけかかった魔法が残っていたのか、それともクリスマスプレゼントなのか。
どちらにせよ、楽しみにしていたのは私だけじゃなかったみたいだ。そうわかるほどノリノリで料理をセッティングしては、「乾杯するでー!」という彼の笑顔が印象的な、そんなクリスマスの夜のお話。
私が、少しでも綺麗に見えますように。一つひとつ、どれもそんな魔法をかけるような気持ちで身に纏ったものだ。それらが、役割を成すことなく私のもとから解かれていくこの瞬間は、本当に虚しくなる。これだって、もう何回目だろう。
大好きな彼と会えるはずだった。忙しい人だから、最近はなかなか会うことができずにいて、今日こそ、やっと。いよいよ待ち合わせの時間が迫り、はやる気持ちを抱えながら神室町方面へ向かっていた。その道中で、彼からの電話が鳴って……当然、タイミングとしても「どこにいる?」みたいな会話が繰り広げられる電話だとしか考えていなかった。だから、弾む声で「もしもし」と電話に出た私を、彼は申し訳なさそうな声で突き落としてくるだなんて、信じたくなかった。
思わず、この手からすり抜けそうになった電話。はっとして慌てて握り直すものの、彼の言葉はもう話半分で、それこそ反対の耳から抜けていく感じだ。
「すまんな」
「ううん、大丈夫」
あぁ、このやり取りも何度目か。もはやテンプレートになってきたような会話に、溜息さえも出なくなってきた。そして、切れた電話に心の中で悪態をつく。せめて、あと一時間早くに連絡してくれれば、だなんて仕方のないことを。わかっている、彼だって仕事なんだ。働いていればどうしようもないことがある。理解しているよ、そんなのお互い様だから。
でも、今日は……言葉は悪いが、ドタキャンされてしまった前のデートの埋め合わせの、さらに埋め合わせなのだ。つまり、これでデートがお流れになって三回連続ではないか。
さらに言えば、今日という日は彼が指定してくれたもので、世間ではクリスマス。クリスマスにはしゃぐような年齢でもなくなったとはいえ、一緒に過ごそうと思ってくれたのかなとか、やっぱりちょっとばかり期待しちゃうじゃん。これがこれからも続く可能性を思うと、さすがになんだかなぁと思えてしまう。
それでも、特殊な彼のお仕事柄、大丈夫と言うしかないし、嫌だと言って困らせることの方がもっと嫌だから。そういうことをひっくるめて、彼のためにと思い「大丈夫」と言ったのは嘘じゃない。彼も頑張っているから、私も次に会えるときまで頑張ろうって、たいして楽しくもない日や辛い日も、理不尽な日だって乗り越えてきたんだ。それが、今日だったのにな。
もともと頻繁に会えるような人じゃないから、余計に……デートが立て続けに何度もだめになっていると、さすがにショックが大きい。
ふと鏡に映る、シャワーを浴びたあとの自分。綺麗に見えたらと試行錯誤したヘアもメイクもリセットされて、「少しでも素敵な女に見えますように」という願いを込めてかけたはずの魔法は、もうすべて解けてしまった。部屋着になり、「ただの私」となった今、あとはこのまま明日を迎えるのみである。
私の携帯はいまだに無音なまま。なんの知らせも告げてくれないことに、また虚しくなる。はじめてこういう事態になったときは、会えないかわりにこまめに連絡してくれたりと手厚いフォローがあった。「仕方ないことですから、そんなに気にしなくても大丈夫ですよ」と、こっちが申し訳なく思ってしまうくらいだった。
さすがに三回目ともなると、彼も慣れたのだろうか。そう思いたくなるくらい、今の今までサッパリ何もない。なんだそれ。楽しみにしてたのは私だけだったのかな。
あーあ、今ごろはきっと、一緒に街を歩いて美味しいご飯を食べて……だなんて、叶わなくなってしまったデートに想いを馳せたところでどうしようもない。あ、そういえばご飯……外で食べる気満々で特に用意もせずいたから、残念ながら家にたいしたものはない。かといって、コンビニ程度だろうと、もう外に出るのも気が乗らない。
吾朗さんには会えないし、気分は沈むしお腹も減るし、もう踏んだり蹴ったりだ。部屋で一人むすっとしていれば、ずっと沈黙だったものから電子音がした。
相手は、まさに考えていた人だ。連絡が来たことの嬉しさと、会うことのできない淋しさが重なり、複雑な思いで電話に出る。
「もしもし?」
「おう。もう家におるか?」
「うん」
「それやったら、悪いんやけど十分後くらいに外に出とってくれんか? 両手が塞がってドア開けられんわ」
「……ん?」
「じゃあ、またあとでな。頼むわ」
交わされた会話は、用件だけの手短な電話。そして、途切れた電話を目にしながら疑問に思う。
どういうこと。十分後に外? え、それって、ここに来るってこと? うそ、会えるの!? いやいや、でも、さっきは「予定が変わってすまんな」って言われたんだけど。
ええと、あの……もしかして、人違いの可能性があるのでは。混乱する頭で、わりと本気でそんな結論が導き出される。だとしたら、彼は、誰に会うつもりで……まさか、他の女の人、とか? というか、両手が塞がってドア開けられないってなに。じゃあ、どうやって電話してたの。
いろいろ考え始めるとキリがなくて、とりあえず言われたとおりに外へ出てはみるものの、本当に来るのかな。少し待って来なければ、いよいよ電話をかける相手を間違えた説が濃厚になる。そうなると今度は、その相手が誰なのかという問題が出てきてしまうではないか。これ以上嫌な思いが重なるくらいなら、よくわからないけど、ひとまずここに来てくれることを願うしかない。
その願いが通じたのか、この辺りに似つかわしくない立派な車が目の前に停車された。そこから降りてきたのは、間違いなく電話をかけてきた吾朗さんだ。また、その両手にはさまざまな袋を手にしていて、たしかに塞がっている。
「おう、すまんな! ほれ、いろいろあるんやけど、まぁとりあえず入ってからやな」
「え、あぁ、うん……あ、どれか持とうか?」
「あぁ、別にええわ。ドアだけ開けてくれや」
吾朗さんの両手の荷物からは、やけに食欲をそそるいい匂いが。そして、心なしか彼が上機嫌であるようにも見える。事態が飲み込めないまま部屋に入れば、「とりあえず、よさそうなモン適当に用意したで!」と、立派で美味しそうな料理の数々が袋から出てくる。
これはどういう状況なのか。脳内処理が追いつかないでいれば、そんな私に、吾朗さんが心配そうな声を上げた。
「……もしかして、どれもイマイチやったか!? コレとか、ナマエが好きそうやなと思うてたんやが」
「あ、ううん! そうじゃなくて……」
どうやら人違いではないらしい、たぶん。
「いや、その、まさか吾朗さんが来てくれると思わなくて。だって、仕事が忙しいって、電話で……」
「あぁ? せやから、その電話で言うたやろ」
あれ、そうだっけ。電話での会話を一生懸命思い出してみるけど、そんなこと言われてたかな。「仕事が押して予定が変わったから、待ち合わせには間に合わん」と。その一言が、浮足立っていた私を地に叩きつけるかのように強烈すぎて、それしか思い出せない。「でも、吾朗さん、待ち合わせは無理だからって」だなんて口にする相変わらずの私に、彼が不思議そうに続けた。
「せやで。だから、そのまま車でナマエの家まで行くって伝えたやろが」
「お前、まさか聞いとらんかったんか!?」と驚愕する彼を前に、あぁ、もしかしてと、ひとつの心当たりが脳裏をかすめた。
「あのね、私。その……待ち合わせに間に合わないって言われたとき、今日は会えなくなったんだとばかり思って、それがすごくショックで……そこで、持ってた電話を落としかけちゃって」
待ち合わせには間に合わない。その言葉のあと、指からふっと力が抜けたあの瞬間。耳からずれてしまったと認識して、慌ててもとに戻したときに、たしかに吾朗さんは何か言っていた気もする。
「それでもかまわんか? ……おい、ナマエ? 聞こえとるか?」
「あぁ、ごめん! うん、私は大丈夫だから」
「なら、またあとで連絡するわ。すまんな」
「ううん、大丈夫」
また耳に当てたときには、そんな流れになっていたっけ。
「だから、会えると思ってなかったから……それに、これ、わざわざ用意してくれたの? あの、ちょっと今、嬉しすぎて頭が追いついてないっていうか……」
高揚する気持ちが混ざりながらそう口にすれば、彼は私の頭を撫でてヒヒッと笑う。
「ほう。そないに感激するほど会いたかったってことでええな?」
「それは、もう……だって、ずっと会えてなかったから」
「せやな。それはホンマにすまんかったわ。今日も、本当なら街を歩いたりしたかったやろ」
「そんなのいい。吾朗さんと過ごせるならどこだっていいもん」
「ヒヒッ、今日はずいぶんと素直やなぁ」
さっきと違って、今じゃあ新しい服や靴もなければ、綺麗なアクセサリーもいつもと違うメイクだってない。そんな「ただの私」だけど、少しだけかかった魔法が残っていたのか、それともクリスマスプレゼントなのか。
どちらにせよ、楽しみにしていたのは私だけじゃなかったみたいだ。そうわかるほどノリノリで料理をセッティングしては、「乾杯するでー!」という彼の笑顔が印象的な、そんなクリスマスの夜のお話。
1/4ページ