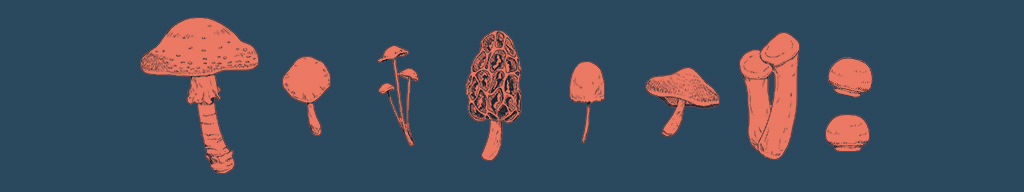Dead by Daylight
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
メアリー。それが彼女の名前。俺のお気に入りのサバイバー。
殺人鬼から逃げるのに、その膝まで伸びた髪の毛は邪魔だろうに、君は一向に切ろうとしない。
まあ、俺も長い方が好みだからぜひともこのままでいてほしいと思う。
直接ちゃんと面と向かって話したことはない。エンティティに儀式内での会話は規制されているから。
いや、そんなものなくても面と向かって話すことはないのかもしれない。
だって俺は殺人鬼で、君は俺から逃げる生存者なんだから。
メアリーが霧の森に来てから、俺は彼女をストーカーするのが趣味になった。
彼女以外の生存者を処したあとに何も気付いていないで無力なトーテムをひたすら壊してまわる君を。
たまたまハッチを見つけて、数センチ先も見えない暗闇を眺めたりする君を。
チェストを漁って偶然見つけたグレードの高い工具箱をまるでバッグのように持ち歩く君を。
仲間と雑談しながら発電機を修理したものだから、何回も爆発させてる君を。
仲間を助けようと一生懸命に走っていく君を。
俺は何枚も撮った。同じ構図だろうと、同じ瞬間だろうと、彼女の全てをカメラに収めた。
写真をプリントアウトして、フォトアルバムに丁寧に差し込んでいく作業がたまらなく幸福だった。
そんなことを続けていたある日だった。彼女がいる儀式だった。
気配を消して発電機のもとへ向かい近くの岩陰から修理を進める生存者を見つめた。
二人で修理しているうちの一人はメアリーで、今日は真剣にその手を進めているようだった。
もう少しで発電機が修理完了するというとき、一緒に修理していたメグに存在を気付かれてしまってマーキングは失敗した。
発電機の火花は派手に散っており、もうそこには誰もいないことを俺に教えた。
それからというもの調子が悪く、フックに吊っても救助されそのまま逃がしていた。
気付けば五台の発電機は全て修理され、最後の最後で吊るしたサバイバーは既に助けられて、そのままゲートから出て行った。
まあ、こんなこともあるか。仕方ない。そう思っていた。
しかしコラプスの禍々しい空気はそのまま世界を侵食していくばかりで終わる気配がない。
またゲート前で誰か待ってるのか、面倒くさいな、なんて小言をこぼしながら振り返った。
彼女が、あのレンガの壁の向こうからこちらを覗いている。儀式中の俺みたいに。陰からじっと見つめてきている。
訳が分からなかったが、俺はゲートの手前まで行って同じようにしゃがんで、覗き込んでやった。
するとどうだろう、今まで見たことがなかった笑顔を俺に向けながら引っ込んだのだ。
俺も彼女を真似して引っ込み、またちらりと覗いて、目が合ったら引っ込むを繰り返した。
傍からしたら何やってんのか意味不明だったが、俺は楽しくて、嬉しくて、しょうがなかった。
あともう少しでコラプスが終わるというとき、彼女から俺のほうにやってきた。
思わず後ずさってしまったが、メアリーは臆さずにじっと俺の顔を見ていた。
『たのしかった、また会えるかな?』
えへへ、と照れ笑いをしてみせる。愛おしくなってふと彼女の頬に手を添えた。
血なまぐさいであろう手袋に触れられても嫌な顔ひとつもせずに、受け入れてくれる彼女に
カメラを取り出してハンドサインを送る。撮ってもいいかと。メアリーは笑顔でいいよと答えてくれた。
カシャッと軽快な音が鳴る。それを合図に彼女は行かなきゃと俺の手からすり抜けていった。
いつものように手を振る、すれば偶然振り返ったメアリーも手を振ってくれる。見えなくなるまで、手を振った。
その次に出会ったときは一緒にしゃがんで呪われたトーテムに灯る炎の揺らめきを眺めたり
俺の使ってるナイフが見たいと言うので、俺は彼女の持ってる救急キットの中身を見せてもらった。
新しい衣装をもらったといって一番に俺に見せたいとわざわざ儀式にそれを持ってきたこともあった。
ロッカーでかくれんぼしたり、彼女が黙々と発電機を修理する様子をじっと見たりなどした。
そのたびに写真を撮った。たまに彼女にカメラを貸して、その仲間たちとの写真を見せてくれたりした。もちろん消した。
そして彼女と別れるときは必ず手を振った。見えなくなるまで、いや、見えなくなっても。
あの霧の奥でまだ振ってくれているのかもしれないという希望をこめて。
ソファに寝転びながら、メアリーの写真だけがはいったアルバムを眺めていた。
ここ一週間か二週間、ずっとこんな風に過ごしているような気がする。
前は気が向けばフォトアルバムを整理したり、新聞記事みたいなものを書いてみたり、
コーヒーを淹れてみたり、部屋を雑に片づけてみたりしていたのに、もうそんなもの手につかなかった。
何をするにもメアリーの顔が浮かんで俺の心を攫って行く。いつも俺が命を奪っていくのと同じように。
今までターゲットにこんな感情を抱いたことはない。お気に入りはお気に入りのままだった。
飽きたら、知り尽くしたら、気が変われば殺して、また別にお気に入りを見つけてきた。ずっとその繰り返しだった。
「…この感情はなんなんだ?
今までこんなことはなかった。他の奴は殺せたのに、彼女のことは殺したくない。」
「なんでそんなことを俺に聞くんだ。」
「カレブって人生経験豊富そうだし、何よりまともそうなのがあんたしかいないから。」
「はっ、四六時中酒を呷ってるようないい年こいたおっさんがか。」
「ここには酒を飲めるような健康な人間はいないから。」
「まあ………それもそうだな。
んで、なんだっけ?お前さんの惚気話の続きだっけか?」
度数の高いアルコールが並んでいるこの部屋はいつ来ても酒臭く、空き瓶が散らかっていた。
奥の棚にもいくつものビンテージもののワインやらがこの男の口の中に入るのを待っているようだった。
ゴーストフェイスは酔っているのをいいことに何度もカレブ・クイン、別名デススリンガーと話をしていた。
元の経歴などからして全く関係はないのだが、酒を飲んだカレブは聞き上手になり案外解決策をいくつか提案してくれる。
まるでカウンセラーだね、なんて冗談を言う頃には大概酔いつぶれて寝ているのがオチなのだが。
「んー。惚気なのかは分からないけど、そう思う?」
「そんな風に写真をずっと眺めてんのは重症だと思うがな」
軽快に笑い飛ばしカレブは言う。まあ確かにいい写真だ、とも。
残り少なくなった酒をらっぱ飲みし、はあと大きく息を吐いたところで真剣な表情に変わる。
「いいと思うがな。一回くらいデートとか誘ったらいいじゃねぇか、
儀式なんかほったらかして二人で話して、気持ちをスッキリさせた方がお前もやりやすいだろ。
処刑しようと思えばできた相手を見逃したんだから今更なんも罪に問われんだろうしな。」
「………。」
「…ま、今のお前にとっちゃ、彼女に会えなくなるのが一番ダメージでかそうだなあ」
「言えてるね。」
そして何度か会話を交わした後いつも通り酔いつぶれたカレブを背に部屋を出た。
次出会ったら、彼女と言葉を交わそうと決心して。
精神病棟が佇むこの場所になんの思い入れもない。
ぼーっとしてたら亡霊でも出てきそうな不気味で陰鬱な空気のこの場所が俺は嫌いだ。
闇というには明るすぎる。どちらかといえば精神的な闇を感じさせる。
ここに来る人間は大概闇を抱えている、だからこそエンティティに選ばれる。
わざわざこんな場所に来なくたって皆分かっている。まるで懺悔をさせるような場所だ。教会なんてものはないのに。
とはいえ今回の儀式には彼女も参加しているからわがままも言っていられない。
カレブの言った通り、二人きりで会話をしたい。そのためにはさっさと他の生存者を殺してしまおう。
そう思い足を一歩踏み出したとき、ひらひらと舞っている布切れに引っ張られそのまま振り返った。
『こんにちは。また会えたね。』
「………。」
『今日はね、あなたと話したかったの。
立ち話も疲れちゃうし病院のベッドに座りながら話さない?』
驚きながらもこくりと頷くと、彼女は何の躊躇いもなく俺の手を掴んだ。
手袋越しでもわかる彼女の手のぬくもりが心地よくて心が躍る。いつまでも握っていたい。
引かれるまま中心にそびえたつ建物に入り、土にまみれて汚れ切った階段をあがっていく。
乱雑に置かれたベッドに二人で腰かけしばらく金属が軋む音を聞いていた。
『…まずね、あなたの名前が知りたいの。
みんなはゴーストフェイスとか、あだ名で呼ぶでしょ?
私はあなたの本名で呼びたい、だめかな。…それと声も。』
「………、ダニー・ジョンソン。」
『…だにー、』
薄い桃色の唇で俺の名を呼ぶ君が愛おしい。ベッドの上に広がる長い髪の毛は芸術のように美しく、
ほんの微かなまつ毛の影が頬に落ちているのが見える、瞳はまっすぐな黒で引き込まれるようだった。
このまま彼女の全て奪い去ってしまえたらどんなにいいかと頭の中で様々な妄想が走り回る。
じっとして黙ってたらいつしか実行してしまう危機感から、俺は彼女の名前を呼んだ。
「メアリー、だっけ。」
『そう 呼んでくれてうれしい』
「…俺も嬉しかったよ。」
空気に流されてメアリーの滑らかな髪の毛を撫でる。
どうしてそんなに嬉しそうに眼を閉じるのか。今君の前にいるのは殺人鬼だっていうのに。
君のことをこっそりと付け回して勝手に写真なんかもたくさん撮って、君の仲間も散々殺して
その死に顔なんかも撮影しては写真に出して眺めるような男で、そんな奴が隣にいて触れてるというのに
恐れのひとつも見せずにまるで恋人に向けるような笑顔を俺になんか見せてしまって。
『ダニーは、好きなひといる?』
「嫌いなのならたくさんいるけどね」
『そうなんだ!私はダニーが好き、はじめて会った時から、好き』
「奇遇だね 俺もメアリーが一番好き。」
『両想い?』
「かな」
『じゃあ、手を繋がなきゃ』
手を繋ぐ理由はよくわからないが彼女の言う通りに手袋を外す。すこし冷えた空気が新鮮だった。
だがすぐに彼女の手に包み込まれてその冷たさは瞬く間に消えていき、気付けばメアリーのぬくもりばかりになった。
好きを伝えるのはもっと難しいことだと思っていた。しかし簡単だからこそ難しいものなのかもしれない。
『今日はずっと繋いでいようね』
「……そうだね」
今日は手は振ることはなさそうだ。
そんなことを思いながら、俺は彼女の手を強く握りしめた。
end.
1/1ページ