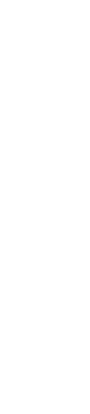[さらにカオス]鬼時間へようこそ[妖ウォ×コナン+まじ快]
その様子を歪に感じていながらも、結局二人は何も口を出せない。しかしそんなことも気にもせず、ケータは現状について考える。どう考えたって異常なのだ。まぁそもそも鬼時間という現象が不可思議なものであるのには違いないが、鬼時間に複数人―しかも普段妖怪と関わっていない人が紛れ込んでいるのは如何にもおかしい。
「さて、そろそろこの空間から脱出しましょうか!赤鬼君を倒したから襲われる心配はほぼ皆無でしょうが、 素人のあなた方が長くいて何か変な事になったら大変ですし。」
「謎だらけ、だけどね。」
イナホの言葉に苦笑いしながらケータは頷き、コナンと快斗に声を掛ける。全く何が何だか分からない二人は、(片方は精神年齢的意味合いで)年下の二人に大人しくついていくことしかできなかった。異常事態である中、ケータは目指すべき出口に向かいながら雑談を振った。イナホは慣れたもので普通に話に乗り時には興奮気味にしゃべるが、あからさまない空間でのほほんとした日常会話が為されていることにコナンと快斗は驚きを隠せない。イナホの一方的な発言をBGMに、コナンがポツリと呟いた。
「イナホが普通じゃないのは今日一日で散々実感したが、あの子だって大概だよな。」
コナンは今までのやり取りで、彼がイナホが昼間言っていた"彼"が目の前のいるケータだと理解していた。というのも、興奮したイナホが漏らした言葉をちゃんと聞きとっていたからだ。何とも歪な雰囲気に顔を顰めていると、突然黄金のふすまが見えた。いつもある、分かりやすいロックチェーンは見えない。しかし、ふすまはピクリとも動かない。
「え?!」
「こりゃあまた謎が増えましたな。」
ふすまが開かないことに驚きの声を上げるケータと、呑気にけど真剣に呟くイナホ。普通なら、素直に返してくれるはず。なのに、まるで反発するようにふすまが開かない。
「な、なにをしているの?」
コナンはつい子供ぶって戸惑っている二人に声を掛けた。そのコナンの顔には、少し汗が見えていた。コナンのその反応に、ケータはイナホと顔を見合わせる。そしてケータはコナンの視線に屈むと、真剣そうな表情そのままに冷静に返した。
「この鬼時間って普通、このふすまから帰ることが出来るんだ。けど、なぜか今日はびくとも動かないんだ。」
「ちなみに物理攻撃は辞めといた方がいいですよ。何せマジモンの異世界なので、びくともしません。一度マジで試してみたんですけど、こっちがダメージ喰らいましたし。」
「何やってんの、イナホさん……。」
開かないなら物理で……と言おうとした瞬間にイナホに言われ、万策尽きたことを実感しコナンは困惑する。こんな異世界に、どれだけ放置されなければならないのか、と。しかし、その不安を払拭するかのような場違いな声がその場に響いた。
「まぁ大丈夫ですよ!なんてったってここには、妖怪マスターがいらっしゃいますから!」
「だから、辞めてって……。」
イナホの根拠のない言葉にケータは辟易しながら返す。ケータにとって、”友達”がいることも”友達”と協力して厄介事を解決することも、”日常の一部”であって特別なものではない。だからイナホの評価を過大評価だと思っているが、事実”天野ケータ”の名前は妖魔界で遍く知られるようになっている。なにせ妖怪ウォッチの制作者の孫という時点で稀有な存在であるのに加え、その持ち前の行動力で人間界と妖魔界の危機を幾度となく救っているのだ。現実をしっかりと把握していないのはケータの方である。
往生際悪く認めようとしないケータに、流石のコナンと快斗も呆れの目を向けることしかできない。いくらケータが否定しようが、現実が証拠である。”普通”なら、こんな魑魅魍魎のことを視えることはないし、視えたとしても関わるのを避けるだろう。だが、ケータにとって今の光景が”普通”であるのだから、他人―妖怪とかかわりのない人間からして普通でないのは当たり前。しかし、その溝にケータ自身が気づいていないのだからどうしようもない。閑話休題。
「むむっ!ここから妖気の気配が!」
ずっと黙り込んでいたウィスパーが、突然声を上げた。急に存在感を出したウィスパーにコナンも快斗も驚きを隠せなかったが、イナホとケータにとっては慣れたもの。しかもウィスパーの適当ぶりを身をもって知っているケータは呆れ目を向けて軽く流そうとした。が、今回はウィスパーの他にも普段は”ウィスパーの気のせい”と取り合わないジバニャンとUSAピョンもウィスパーの意見に賛同する。これは何かある。そう直感で感じたウォッチャー二人はお互いの顔を見合わせるなり頷いて、ボタンを押して時計から光を発した。その光はコナンとキッドが見慣れた腕時計型ライトの白いものとは異なり、どこか青白く不思議な雰囲気を漂わせていた。コナンと快斗は二人の行動に突っ込みを入れようとするも、真剣な表情を浮かべているものだから突っ込むに突っ込めなかった。青白い光を時計から出し、あちこち照らす小学校高学年二人の奇行を眺めること数秒。青白い光に当てられた場所に靄が現れた。当てられる前は何にもなかったのに。そしてそのまま光が当てられ続けると靄が晴れた。晴れたところに立っていたのは……。
「た、立て札?」
この時代ではめったに見られなくなった立て札―しかも木製のもの―が鎮座していた。
「さて、そろそろこの空間から脱出しましょうか!赤鬼君を倒したから襲われる心配はほぼ皆無でしょうが、 素人のあなた方が長くいて何か変な事になったら大変ですし。」
「謎だらけ、だけどね。」
イナホの言葉に苦笑いしながらケータは頷き、コナンと快斗に声を掛ける。全く何が何だか分からない二人は、(片方は精神年齢的意味合いで)年下の二人に大人しくついていくことしかできなかった。異常事態である中、ケータは目指すべき出口に向かいながら雑談を振った。イナホは慣れたもので普通に話に乗り時には興奮気味にしゃべるが、あからさまない空間でのほほんとした日常会話が為されていることにコナンと快斗は驚きを隠せない。イナホの一方的な発言をBGMに、コナンがポツリと呟いた。
「イナホが普通じゃないのは今日一日で散々実感したが、あの子だって大概だよな。」
コナンは今までのやり取りで、彼がイナホが昼間言っていた"彼"が目の前のいるケータだと理解していた。というのも、興奮したイナホが漏らした言葉をちゃんと聞きとっていたからだ。何とも歪な雰囲気に顔を顰めていると、突然黄金のふすまが見えた。いつもある、分かりやすいロックチェーンは見えない。しかし、ふすまはピクリとも動かない。
「え?!」
「こりゃあまた謎が増えましたな。」
ふすまが開かないことに驚きの声を上げるケータと、呑気にけど真剣に呟くイナホ。普通なら、素直に返してくれるはず。なのに、まるで反発するようにふすまが開かない。
「な、なにをしているの?」
コナンはつい子供ぶって戸惑っている二人に声を掛けた。そのコナンの顔には、少し汗が見えていた。コナンのその反応に、ケータはイナホと顔を見合わせる。そしてケータはコナンの視線に屈むと、真剣そうな表情そのままに冷静に返した。
「この鬼時間って普通、このふすまから帰ることが出来るんだ。けど、なぜか今日はびくとも動かないんだ。」
「ちなみに物理攻撃は辞めといた方がいいですよ。何せマジモンの異世界なので、びくともしません。一度マジで試してみたんですけど、こっちがダメージ喰らいましたし。」
「何やってんの、イナホさん……。」
開かないなら物理で……と言おうとした瞬間にイナホに言われ、万策尽きたことを実感しコナンは困惑する。こんな異世界に、どれだけ放置されなければならないのか、と。しかし、その不安を払拭するかのような場違いな声がその場に響いた。
「まぁ大丈夫ですよ!なんてったってここには、妖怪マスターがいらっしゃいますから!」
「だから、辞めてって……。」
イナホの根拠のない言葉にケータは辟易しながら返す。ケータにとって、”友達”がいることも”友達”と協力して厄介事を解決することも、”日常の一部”であって特別なものではない。だからイナホの評価を過大評価だと思っているが、事実”天野ケータ”の名前は妖魔界で遍く知られるようになっている。なにせ妖怪ウォッチの制作者の孫という時点で稀有な存在であるのに加え、その持ち前の行動力で人間界と妖魔界の危機を幾度となく救っているのだ。現実をしっかりと把握していないのはケータの方である。
往生際悪く認めようとしないケータに、流石のコナンと快斗も呆れの目を向けることしかできない。いくらケータが否定しようが、現実が証拠である。”普通”なら、こんな魑魅魍魎のことを視えることはないし、視えたとしても関わるのを避けるだろう。だが、ケータにとって今の光景が”普通”であるのだから、他人―妖怪とかかわりのない人間からして普通でないのは当たり前。しかし、その溝にケータ自身が気づいていないのだからどうしようもない。閑話休題。
「むむっ!ここから妖気の気配が!」
ずっと黙り込んでいたウィスパーが、突然声を上げた。急に存在感を出したウィスパーにコナンも快斗も驚きを隠せなかったが、イナホとケータにとっては慣れたもの。しかもウィスパーの適当ぶりを身をもって知っているケータは呆れ目を向けて軽く流そうとした。が、今回はウィスパーの他にも普段は”ウィスパーの気のせい”と取り合わないジバニャンとUSAピョンもウィスパーの意見に賛同する。これは何かある。そう直感で感じたウォッチャー二人はお互いの顔を見合わせるなり頷いて、ボタンを押して時計から光を発した。その光はコナンとキッドが見慣れた腕時計型ライトの白いものとは異なり、どこか青白く不思議な雰囲気を漂わせていた。コナンと快斗は二人の行動に突っ込みを入れようとするも、真剣な表情を浮かべているものだから突っ込むに突っ込めなかった。青白い光を時計から出し、あちこち照らす小学校高学年二人の奇行を眺めること数秒。青白い光に当てられた場所に靄が現れた。当てられる前は何にもなかったのに。そしてそのまま光が当てられ続けると靄が晴れた。晴れたところに立っていたのは……。
「た、立て札?」
この時代ではめったに見られなくなった立て札―しかも木製のもの―が鎮座していた。
3/3ページ