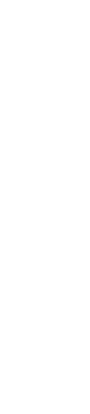[さらにカオス]鬼時間へようこそ[妖ウォ×コナン+まじ快]
体は大きいのに思ったよりも機動性のある赤鬼に、コナンも快斗も演技を忘れて必死に逃げる。しかし、必死に逃げるが余り行き止まりに入ってしまったことに気付かなかった。流石のイナホもこの絶体絶命の状況でいつものようなテンションは保っていられず、ポケットにしまった妖怪メダルを取り出そうと焦っていた。
「マジでここどこだ?!」
「俺も知らねぇ!!オメーこそ知らねぇのかよ!!」
「今回はいつものようにいかなくてだな!!裏路地まで調べてる余裕がなかったんだよ!!マジでピンチじゃねぇか!!」
お互い演技を忘れ罵りあうが、イナホもUSAピョンもそれを仲裁している余裕はなかった。イナホはUSAピョンに無茶ぶりを―この場をなんとかできる妖怪のメダルを渡すように迫り、USAピョンはどれがいいのか悩んで選べずにいた。そんな仲間割れに近い状況であっても、鬼の追撃は終わらない。じりじりと四人に近づいてくる赤鬼に、全員そろって冷や汗をかきまくっていた。イナホは慌てて、一枚のメダルを妖怪ウォッチに挿入した。緊迫した雰囲気の中、陽気なそして間抜けた音楽が妖怪ウォッチから流れ、光の帯でできた逆円錐形のエリアに妖怪が召喚される。呼ばれたのは、"うんがい鏡"。ワープを可能にする妖怪だが、この鬼時間には同じうんがい鏡がいないため無効である。マジでピンチに陥り、鬼に倒されてENDか……。そう思った瞬間、うんがい鏡の鏡から眩しい光が放たれた。光が消えると、異形の存在が赤鬼向かって攻撃している。”攻撃しても無駄"と聞いていたコナンと快斗は安堵と同時に驚愕で言葉が出なかった。が、コナンと快斗はすぐに気づいた。異形の存在―USAピョンと同じ妖怪たちは、まるで統率のとれた行動をしていることに。だれが支持を飛ばしているのかと辺りを見渡すと、木の上に立ち妖怪たちに指示を飛ばす赤い服の子供がいた。
「イナホさん!大丈夫?ハクがメッチャ心配してたよ?」
「アハハハ……。お手数おかけしてすみません、ケータさん。私は大丈夫です。私が好奇心で色々首突っ込んだら素人二人も巻き込む事態となってしまって、しかも結構なピンチだったので助かりました。」
木から声を掛ける存在に、イナホは声だけで誰か判断し返事を返す。イナホのその声を聴いて、ゆっくり木から降りてくる少年。彼の髪型は、天に向かってはねる3つの癖以外は本当に普通のもの。そしてその左腕には、イナホと同じく妖怪との絆を繋ぐ腕時計―妖怪ウォッチがあった。イナホの謎を解こうとしていたところに鬼時間という謎が加わり、さらに"鏡から出てきた少年"という謎が出てくるという、謎が謎を呼ぶ連鎖に、天才的なIQを持ち合わせているコナンと快斗でさえ、考えるのを放棄せざるを得なかった。コナンがどうにか声を絞り出し、イナホが話しかけている少年に声を掛けた。それはもう、"かわい子ぶった江戸川コナン"のものではなかったが、そこまで意識する余裕は、今のコナンになかった。
「お、オメーは一体誰だ?」
「俺?俺は天野ケータ。……普通の小学生だよ。」
「こんなに魑魅魍魎 連れておいて、よく言うぜ……。」
鬼を相手に大立回りをしている"友達"達に一瞥をくれながら、コナンの問いに答える。ケータは普通と言っているがそれが大きな嘘であることはこの光景を見れば一目瞭然である。"普通の小学生"が異空間に入っても驚かず鬼を見ても怯えず、妖怪を引き連れ指示を飛ばし、加えて現状が良くなるように考えることなどありえないのだから。
「わざわざ濁す必要ありませんって、ケータさん。コナン君とKIDさんの記憶、後で消させてもらいますし。覚えていられると少々面倒なので。」
イナホは苦し紛れにごまかそうとするケータとそれを追求しよとするコナンのやり取りを苦笑いをしながら見つめ、状況転換のためケータへ話しかける。ケータは"記憶を消す"という言葉に何の違和感もなく聞いていたが、コナンと快斗は顔を引きつらせる。記憶を消すなどと言ったら、態と事故を起こして脳にダメージでも与えるのかなどと考えてしまう二人だからだ。その実、何の痛みも憶えない物忘れレベルだということを知らずに。
ケータの友達達は強い。ケータとイナホが戦っている友達妖怪を横目に雑談をしている数分のうちに地響きがして、赤鬼が地面に倒れ込んだ。ケータの友達妖怪の勝ちである。赤鬼は紫の煙を出し、その姿を消した。
「勝ちましたね!流石妖怪マスター!!」
「だから、それはあんまり言わないでって!!」
ケータの友達妖怪の強さに「いやぁ、凄いですね~。」とどこか乾いたような笑いをこぼすイナホ。流石のイナホも、リアル鬼ごっこを楽しんでいても鬼に立ち向かう勇気はない。そもそも、イナホは余り友達を喚ばない。本人の気質・クラスの特性・親友の対妖怪特殊体質etc.あるのだが、それ故友達妖怪の能力を把握しきれていない部分がある。性格は熟知しているのだが……。というわけで、このようなピンチに陥った際、適切な妖怪を喚べるかは少々どころかかなりの不安が残る。だからこそ数少ない召喚の場面でも、状況に見合わなすぎる強い妖怪を喚んで大騒ぎになったり、弱い妖怪ばかり喚んでコテンパンにされたりなど、中々友達妖怪の力加減ができていないのだ。
その点、ケータはその性格のこともあるだろうが、数百を超える友達妖怪の力を全て正確的確に理解し、性格も熟知している。そして、妖怪による怪現象にイナホ以上に巻き込まれているからこそ、このようなピンチに陥っても誰を喚ぶべきかすぐに判断することが出来る。だから、鬼時間で悉く鬼を倒していくケータのことを妖怪たちの間では"桃太郎”と呼んでいるのだが、それもまた彼は知らないのだ。彼は、自分の成し遂げたことの凄さを自覚していない。妖怪と関わっていながらも、それに驕り高ぶらない"普通の少年"なのである。
「マジでここどこだ?!」
「俺も知らねぇ!!オメーこそ知らねぇのかよ!!」
「今回はいつものようにいかなくてだな!!裏路地まで調べてる余裕がなかったんだよ!!マジでピンチじゃねぇか!!」
お互い演技を忘れ罵りあうが、イナホもUSAピョンもそれを仲裁している余裕はなかった。イナホはUSAピョンに無茶ぶりを―この場をなんとかできる妖怪のメダルを渡すように迫り、USAピョンはどれがいいのか悩んで選べずにいた。そんな仲間割れに近い状況であっても、鬼の追撃は終わらない。じりじりと四人に近づいてくる赤鬼に、全員そろって冷や汗をかきまくっていた。イナホは慌てて、一枚のメダルを妖怪ウォッチに挿入した。緊迫した雰囲気の中、陽気なそして間抜けた音楽が妖怪ウォッチから流れ、光の帯でできた逆円錐形のエリアに妖怪が召喚される。呼ばれたのは、"うんがい鏡"。ワープを可能にする妖怪だが、この鬼時間には同じうんがい鏡がいないため無効である。マジでピンチに陥り、鬼に倒されてENDか……。そう思った瞬間、うんがい鏡の鏡から眩しい光が放たれた。光が消えると、異形の存在が赤鬼向かって攻撃している。”攻撃しても無駄"と聞いていたコナンと快斗は安堵と同時に驚愕で言葉が出なかった。が、コナンと快斗はすぐに気づいた。異形の存在―USAピョンと同じ妖怪たちは、まるで統率のとれた行動をしていることに。だれが支持を飛ばしているのかと辺りを見渡すと、木の上に立ち妖怪たちに指示を飛ばす赤い服の子供がいた。
「イナホさん!大丈夫?ハクがメッチャ心配してたよ?」
「アハハハ……。お手数おかけしてすみません、ケータさん。私は大丈夫です。私が好奇心で色々首突っ込んだら素人二人も巻き込む事態となってしまって、しかも結構なピンチだったので助かりました。」
木から声を掛ける存在に、イナホは声だけで誰か判断し返事を返す。イナホのその声を聴いて、ゆっくり木から降りてくる少年。彼の髪型は、天に向かってはねる3つの癖以外は本当に普通のもの。そしてその左腕には、イナホと同じく妖怪との絆を繋ぐ腕時計―妖怪ウォッチがあった。イナホの謎を解こうとしていたところに鬼時間という謎が加わり、さらに"鏡から出てきた少年"という謎が出てくるという、謎が謎を呼ぶ連鎖に、天才的なIQを持ち合わせているコナンと快斗でさえ、考えるのを放棄せざるを得なかった。コナンがどうにか声を絞り出し、イナホが話しかけている少年に声を掛けた。それはもう、"かわい子ぶった江戸川コナン"のものではなかったが、そこまで意識する余裕は、今のコナンになかった。
「お、オメーは一体誰だ?」
「俺?俺は天野ケータ。……普通の小学生だよ。」
「こんなに
鬼を相手に大立回りをしている"友達"達に一瞥をくれながら、コナンの問いに答える。ケータは普通と言っているがそれが大きな嘘であることはこの光景を見れば一目瞭然である。"普通の小学生"が異空間に入っても驚かず鬼を見ても怯えず、妖怪を引き連れ指示を飛ばし、加えて現状が良くなるように考えることなどありえないのだから。
「わざわざ濁す必要ありませんって、ケータさん。コナン君とKIDさんの記憶、後で消させてもらいますし。覚えていられると少々面倒なので。」
イナホは苦し紛れにごまかそうとするケータとそれを追求しよとするコナンのやり取りを苦笑いをしながら見つめ、状況転換のためケータへ話しかける。ケータは"記憶を消す"という言葉に何の違和感もなく聞いていたが、コナンと快斗は顔を引きつらせる。記憶を消すなどと言ったら、態と事故を起こして脳にダメージでも与えるのかなどと考えてしまう二人だからだ。その実、何の痛みも憶えない物忘れレベルだということを知らずに。
ケータの友達達は強い。ケータとイナホが戦っている友達妖怪を横目に雑談をしている数分のうちに地響きがして、赤鬼が地面に倒れ込んだ。ケータの友達妖怪の勝ちである。赤鬼は紫の煙を出し、その姿を消した。
「勝ちましたね!流石妖怪マスター!!」
「だから、それはあんまり言わないでって!!」
ケータの友達妖怪の強さに「いやぁ、凄いですね~。」とどこか乾いたような笑いをこぼすイナホ。流石のイナホも、リアル鬼ごっこを楽しんでいても鬼に立ち向かう勇気はない。そもそも、イナホは余り友達を喚ばない。本人の気質・クラスの特性・親友の対妖怪特殊体質etc.あるのだが、それ故友達妖怪の能力を把握しきれていない部分がある。性格は熟知しているのだが……。というわけで、このようなピンチに陥った際、適切な妖怪を喚べるかは少々どころかかなりの不安が残る。だからこそ数少ない召喚の場面でも、状況に見合わなすぎる強い妖怪を喚んで大騒ぎになったり、弱い妖怪ばかり喚んでコテンパンにされたりなど、中々友達妖怪の力加減ができていないのだ。
その点、ケータはその性格のこともあるだろうが、数百を超える友達妖怪の力を全て正確的確に理解し、性格も熟知している。そして、妖怪による怪現象にイナホ以上に巻き込まれているからこそ、このようなピンチに陥っても誰を喚ぶべきかすぐに判断することが出来る。だから、鬼時間で悉く鬼を倒していくケータのことを妖怪たちの間では"桃太郎”と呼んでいるのだが、それもまた彼は知らないのだ。彼は、自分の成し遂げたことの凄さを自覚していない。妖怪と関わっていながらも、それに驕り高ぶらない"普通の少年"なのである。