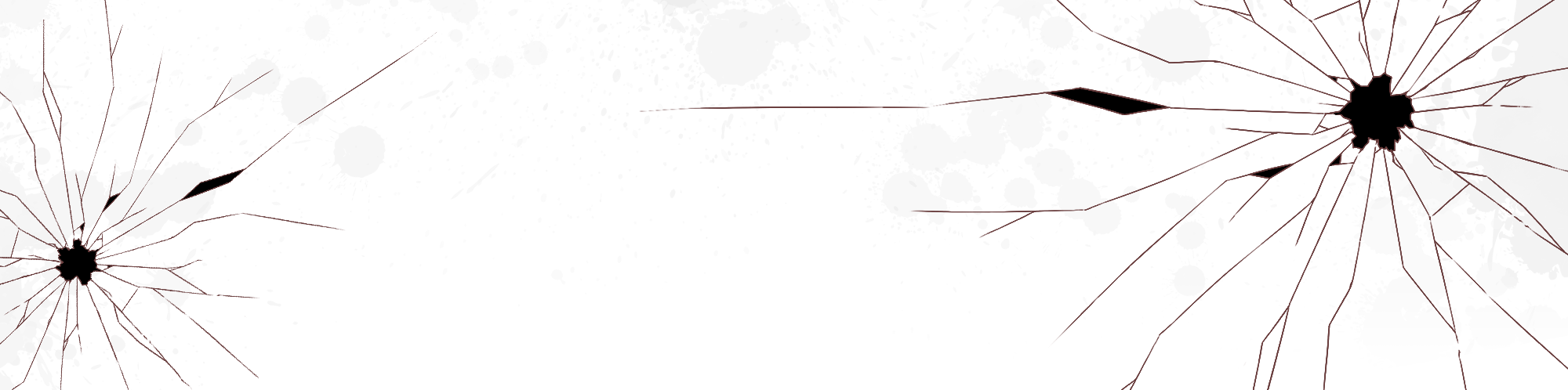第二十一話 己が正義を貫いて
セレンティア総合病院の外科で内視鏡手術を立て続けに3件こなしていたカスパールは、すべての手術が終わってからふうと一つ大きなため息をついた。
変わらない日常。ただ一つ、愛しの婚約者がいないのを除いては。
ほんの気まぐれで院内を散歩していたカスパールは、受付時間が過ぎても大混雑する外来を見て、おや?と疑問に思った。
外科は普通の混み具合で、いつもと変わらない。だが、外来の待合室がずいぶん混んでいるように思う。事務作業を終えたら帰ろうかと考えていたカスパールは、未だ外来診察から解放されない仲間が気がかりになり、仲間の仕事が終わるまで病棟を見て回って時間を潰そうと考えた。
カスパールは内科医のエドワードが更衣室にいるのを捕まえ、飲みに行こうと声を掛けた。エドワードは「嬉しいよ、もうくたくたなんだ」と力なく微笑んだ。
「最近外来がやけに混んでいないか?外科はいつもと変わらないが、他の診療科はずいぶん混んでいるようだ。整形には怪我もしていないのにシップや痛み止めを欲しがる変な患者が来ると聞いたし。何かおかしな気がしないか?」
カスパールはエドワードに最近の異変を聞いてみた。行きつけのワインバルで水のようにワインをがぶ飲みしたエドワードは、「俺も同じだ」とワイングラスをテーブルにたたきつけた。
「変な患者が紹介状で沢山流入してきたんだ。紹介状には奇妙な処方が書いてあってな。診察した限りではその薬は全く必要ないんだ。至って健康なんだよ。だが、その薬がないと辛いと言って、どうしても紹介状通りの薬を欲しがる。そんな患者が急に増えた。肝臓の薬が欲しいから呉れというので検査したら、どこも数値の異常がない。だが、セレスティンを処方してくれという。セレスティンなんか、入院患者にごく稀に出すような薬だぞ?」
「健康なのにセレスティンを欲しがるのか?副作用でほかの臓器がやられてしまうぞ。追加にハクタスを出したりするのか?」
「ああ、ハクタスがないと副作用が辛いだろうからな。追加で出してる。紹介状には書いてなかったが……あの紹介状を書いた医者に会ってみたいもんだ」
「ほかの科も同じなのか?やけに外来が混んでいるが……」
「みんな同じだよ。薬くれ、薬くれ……。やたらマイナーな薬に詳しいのもどこも同じだ」
カスパールは言いようのない胸騒ぎを感じていた。
そんなある日、モナウン調剤薬局のソフィアが声を掛けてきた。確かファティマの友人だった女だ。
「カスパール、話があるの」
喫茶店に入って彼女が話すところによると、モナウン調剤薬局に来る患者が急に増えたという話だった。
「あなたのところはどう?患者増えた気がしない?」
「僕は外科だからな……混み具合は不思議と変わらないんだ。だけど、他の科は急に患者が増えて、みんな疲れているようだ」
「カスパールは怪しいと思わないの?」
「ん?んー、ちょっと様子がおかしいなとは思ってる」
ソフィアはカスパールの顔を覗き込み、語気を強めた。
「カスパールはそれでいいの?セレンティア総合病院の院長になりたいんでしょう?不正や詐欺が裏に絡んでいるかもしれないのよ?」
「何だって?」
変わらない日常。ただ一つ、愛しの婚約者がいないのを除いては。
ほんの気まぐれで院内を散歩していたカスパールは、受付時間が過ぎても大混雑する外来を見て、おや?と疑問に思った。
外科は普通の混み具合で、いつもと変わらない。だが、外来の待合室がずいぶん混んでいるように思う。事務作業を終えたら帰ろうかと考えていたカスパールは、未だ外来診察から解放されない仲間が気がかりになり、仲間の仕事が終わるまで病棟を見て回って時間を潰そうと考えた。
カスパールは内科医のエドワードが更衣室にいるのを捕まえ、飲みに行こうと声を掛けた。エドワードは「嬉しいよ、もうくたくたなんだ」と力なく微笑んだ。
「最近外来がやけに混んでいないか?外科はいつもと変わらないが、他の診療科はずいぶん混んでいるようだ。整形には怪我もしていないのにシップや痛み止めを欲しがる変な患者が来ると聞いたし。何かおかしな気がしないか?」
カスパールはエドワードに最近の異変を聞いてみた。行きつけのワインバルで水のようにワインをがぶ飲みしたエドワードは、「俺も同じだ」とワイングラスをテーブルにたたきつけた。
「変な患者が紹介状で沢山流入してきたんだ。紹介状には奇妙な処方が書いてあってな。診察した限りではその薬は全く必要ないんだ。至って健康なんだよ。だが、その薬がないと辛いと言って、どうしても紹介状通りの薬を欲しがる。そんな患者が急に増えた。肝臓の薬が欲しいから呉れというので検査したら、どこも数値の異常がない。だが、セレスティンを処方してくれという。セレスティンなんか、入院患者にごく稀に出すような薬だぞ?」
「健康なのにセレスティンを欲しがるのか?副作用でほかの臓器がやられてしまうぞ。追加にハクタスを出したりするのか?」
「ああ、ハクタスがないと副作用が辛いだろうからな。追加で出してる。紹介状には書いてなかったが……あの紹介状を書いた医者に会ってみたいもんだ」
「ほかの科も同じなのか?やけに外来が混んでいるが……」
「みんな同じだよ。薬くれ、薬くれ……。やたらマイナーな薬に詳しいのもどこも同じだ」
カスパールは言いようのない胸騒ぎを感じていた。
そんなある日、モナウン調剤薬局のソフィアが声を掛けてきた。確かファティマの友人だった女だ。
「カスパール、話があるの」
喫茶店に入って彼女が話すところによると、モナウン調剤薬局に来る患者が急に増えたという話だった。
「あなたのところはどう?患者増えた気がしない?」
「僕は外科だからな……混み具合は不思議と変わらないんだ。だけど、他の科は急に患者が増えて、みんな疲れているようだ」
「カスパールは怪しいと思わないの?」
「ん?んー、ちょっと様子がおかしいなとは思ってる」
ソフィアはカスパールの顔を覗き込み、語気を強めた。
「カスパールはそれでいいの?セレンティア総合病院の院長になりたいんでしょう?不正や詐欺が裏に絡んでいるかもしれないのよ?」
「何だって?」