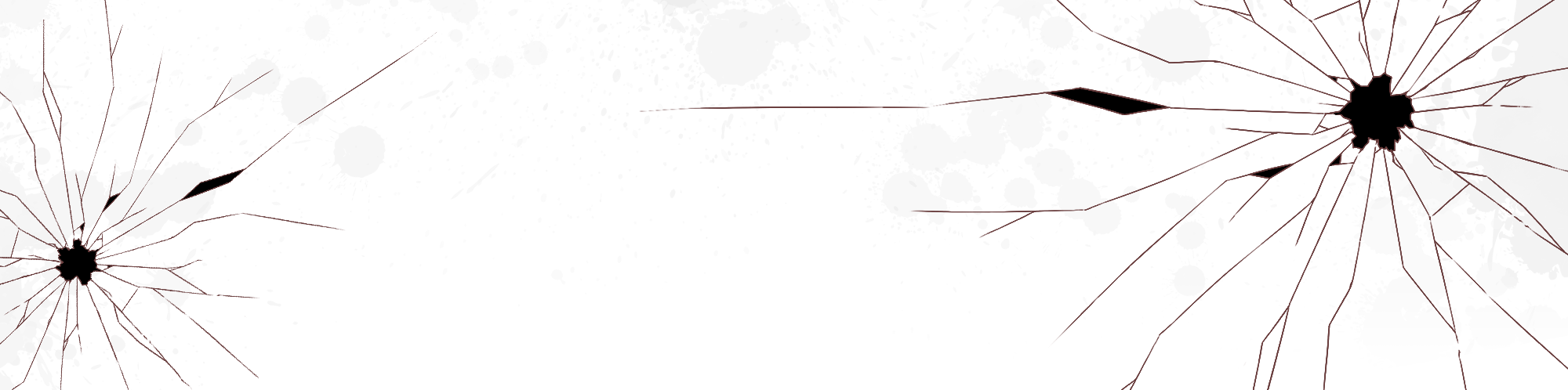第十四話 終わりにしよう
「こんな部屋どこにも隠れようがねえじゃねえか。なるべく部屋の電気付けないで過ごそうぜ。居場所がバレる」
「解ったわ。まあ、今夜は月も出るし、不便はしないでしょう」
こんなボロホテルでは食事も出てこないだろうということで、二人はコンビニエンスストアでハンバーガーやサンドイッチなどを購入し、部屋で手軽に食事を済ませた。もし食事が出てきたとしても、こんな不衛生なホテルの料理は御免被る。
「さ、食事も終わったし……。いつものアレ、よろしくね」
月明りしか照らさない真っ暗闇の部屋で、月光に輪郭だけを縁取られたファティマはニコリと微笑んだ。
「いつもの?ああ、あれか。今日は何したい?」
「ずっと考えてたんだ。何の練習しようかなって。でね、今日は……キスの練習したい」
上目遣いで小悪魔的な笑みを浮かべる、モノトーンのファティマ。ヴィクトールにとってその微笑みは心臓を貫かれるほど残酷な笑みだった。
(……ついに、その練習台にされるのか。……まあ、そうだよな。そのための練習だもんな)
「ああ、良いぜ。ほら、座ったままじゃ遠いよ。立って、こっちに来い」
ファティマはニコニコと機嫌がよさそうだ。多分そんなに拒否反応は起こさないだろう。これができたら、このプログラムは合格証書をあげてもいい。ファティマは両手を後ろ手に回し、目を伏せる。
(これはあくまで、練習。ファティマも特に意識はしていないはずだ。俺のことが好きでこんなことを要求してるわけじゃない。だって、俺はあくまで練習台なんだ。俺がその気になってみろ、ファティマは俺を軽蔑するぞ。俺に怯えて、俺の元から逃げ出す。だから、心を殺せ、ヴィクトール。これは、決して、そういうものじゃないんだ)
ヴィクトールはファティマの小さな身長に合わせ、体を屈め、その唇に唇を重ねようとした。重ねようとして――耐えきれずその場に膝をついた。
「……?あれ?ヴィクター?」
「……ごめん……無理、だ」
「……無理……?あたしとキスするの、嫌?」
(無理だ、耐えられない。そんなの辛すぎる。一度でも口づけを交わしてみろ、俺は我慢できるか?無理だろ。無理だ。だってほら、俺、こんなにもこいつのことを独り占めしたくてたまらない。もう終わりなのか。ここまでなのか。そうか。なら、嫌われるぐらいなら、軽蔑されるぐらいなら、見捨てられるぐらいなら、いっそ、最後に、軽蔑されて、嫌われて、後腐れなく、何もかも御終いに……)
「ヴィク、ター?」
膝をついて俯くヴィクトールに、腰を屈めて様子を窺うファティマ。ヴィクトールは、俯いたまま、決心した。
「ファティマ、もう、終わりにしよう」
「え?」
「解ったわ。まあ、今夜は月も出るし、不便はしないでしょう」
こんなボロホテルでは食事も出てこないだろうということで、二人はコンビニエンスストアでハンバーガーやサンドイッチなどを購入し、部屋で手軽に食事を済ませた。もし食事が出てきたとしても、こんな不衛生なホテルの料理は御免被る。
「さ、食事も終わったし……。いつものアレ、よろしくね」
月明りしか照らさない真っ暗闇の部屋で、月光に輪郭だけを縁取られたファティマはニコリと微笑んだ。
「いつもの?ああ、あれか。今日は何したい?」
「ずっと考えてたんだ。何の練習しようかなって。でね、今日は……キスの練習したい」
上目遣いで小悪魔的な笑みを浮かべる、モノトーンのファティマ。ヴィクトールにとってその微笑みは心臓を貫かれるほど残酷な笑みだった。
(……ついに、その練習台にされるのか。……まあ、そうだよな。そのための練習だもんな)
「ああ、良いぜ。ほら、座ったままじゃ遠いよ。立って、こっちに来い」
ファティマはニコニコと機嫌がよさそうだ。多分そんなに拒否反応は起こさないだろう。これができたら、このプログラムは合格証書をあげてもいい。ファティマは両手を後ろ手に回し、目を伏せる。
(これはあくまで、練習。ファティマも特に意識はしていないはずだ。俺のことが好きでこんなことを要求してるわけじゃない。だって、俺はあくまで練習台なんだ。俺がその気になってみろ、ファティマは俺を軽蔑するぞ。俺に怯えて、俺の元から逃げ出す。だから、心を殺せ、ヴィクトール。これは、決して、そういうものじゃないんだ)
ヴィクトールはファティマの小さな身長に合わせ、体を屈め、その唇に唇を重ねようとした。重ねようとして――耐えきれずその場に膝をついた。
「……?あれ?ヴィクター?」
「……ごめん……無理、だ」
「……無理……?あたしとキスするの、嫌?」
(無理だ、耐えられない。そんなの辛すぎる。一度でも口づけを交わしてみろ、俺は我慢できるか?無理だろ。無理だ。だってほら、俺、こんなにもこいつのことを独り占めしたくてたまらない。もう終わりなのか。ここまでなのか。そうか。なら、嫌われるぐらいなら、軽蔑されるぐらいなら、見捨てられるぐらいなら、いっそ、最後に、軽蔑されて、嫌われて、後腐れなく、何もかも御終いに……)
「ヴィク、ター?」
膝をついて俯くヴィクトールに、腰を屈めて様子を窺うファティマ。ヴィクトールは、俯いたまま、決心した。
「ファティマ、もう、終わりにしよう」
「え?」