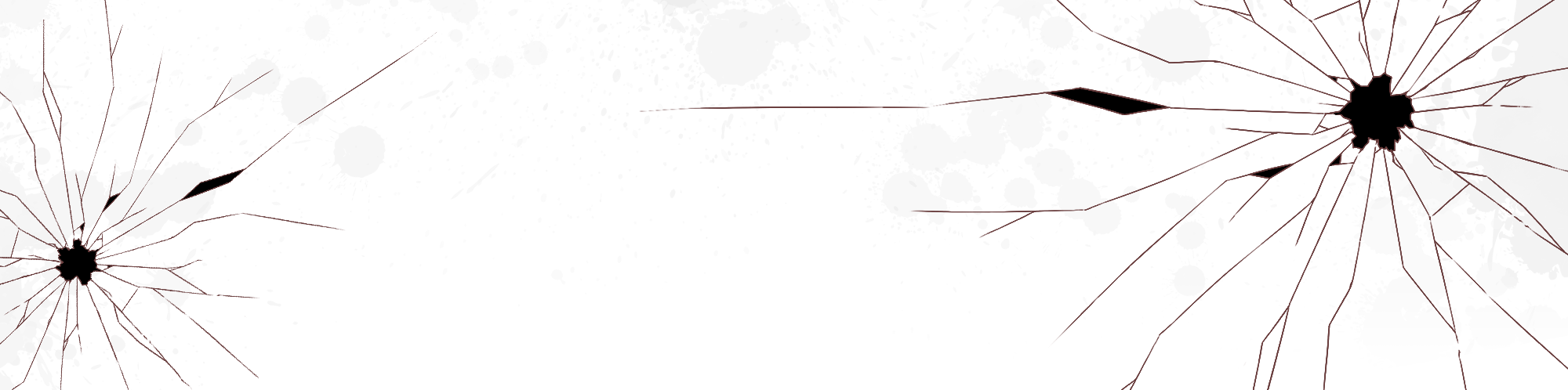第十二話 見捨てられ恐怖症
キープしていたホテルを引き払い、再び方角を変えて逃亡するヴィクトールとファティマ。ヴィクトールは運転しながら静かに涙を流していた。助手席に座り、ヴィクトールの震える手と、無表情に涙を流し続ける横顔を交互に見て、ファティマも沈黙する。
(辛いわよね……。相棒が裏切ったんだもん。今はそうっとしておこう……)
すると、ヴィクトールは鼻をすすりながら静かに語り出した。
「エンリーケと出会って、8年になる」
ファティマは静かに傾聴する。
「組織に入って、最初の3年寮に入れられたんだ。そん時のルームメイトがエンリーケだった。喧嘩もしたが、俺たちはすごく気が合った。退寮させられて、自分たちでアパート契約して、独立して仕事するときに、あいつから言われたんだ。『ルームシェアして、これからも一緒に暮らそうぜ』ってな。俺は最初、その言葉に不安を覚えた。いつか喧嘩して、裏切られたりするんじゃねえかなって。だから言ったんだ。『俺は裏切られるのがこの世でいっちばん嫌いだ。お前、俺を裏切って俺を一人にしたりしないだろうな?』って。あいつは、『安心しろ。俺は絶対裏切らない。ずっと一緒だ』って言ってくれたんだ。それから5年、俺は、ずっとそれを信じていた。今までうまくやってきていたんだ、俺達」
「……」
「見捨てられ恐怖症なんだ、俺。見捨てられたり裏切られたりすると、辛くて怖くて、……ブチ殺したくなる」
「……ヴィクター……」
「……あいつだけは失いたくなかった。ずっと一緒にいられると思っていた」
そこまで話すと、ヴィクトールは路肩に車を停め、声を上げて泣き出した。車のサイドブレーキの上に置いていたティッシュペーパーを数枚引き出して鷲掴みし、顔に押し当てて慟哭するヴィクトール。ファティマはどう声を掛けていいか言葉に詰まり、彼が落ち着くまで背中をさすっていた。
(見捨てられ恐怖症か……。だから今朝、見捨てられる夢を見て、あんなにうなされていたのね。あたし……あたしも、ヴィクターの元から去ったら、この人に殺されるのかしら?……見捨てられる?今まであんなに優しくしてくれたこの人を、いまさら見捨てられる?きっと、すごく寂しいんだわ、この人。もしかして、あたしに優しくしてくれる理由って、見捨てられたくないから……?)
ファティマはどうしてもその疑問を解決してみたいと思ってしまった。訊かないほうがいいだろうかと躊躇したが、思い切って訊いてみる。
「ヴィクターって、どうしてそんなに優しいのかなって、ずっと疑問に思っていたの。ほら、あたしの男性恐怖症を治そうとしてくれたりとか、あたしに乱暴しようとしなかったりとか、殺そうとしなかったりとか……。それってひょっとして」
「あ゙あ゙?!」
突然ヴィクトールが怒気を孕んだ声を上げて睨んできたので、ファティマは怯えて口を噤んだ。
「ごめん」
ファティマの怯えたような顔を見て、ヴィクトールは反射的に威嚇してしまったことを自覚した。怖がらせてはいけない。
「殺せって言われたからってそんな簡単に殺せるかよ?!そんな簡単に殺意なんて起きねーよ。でもお前逃がしたら別の奴にお前殺されるだろ。そしたら逃げるしかねーだろ。生かしてもらってんだからそれでいいだろが。死にたがったら許さねー。何のために男性恐怖症治そうとしたかって?一緒にいるのに不便だからだろうが。それ以上も以下もねえ!」
「わ、解った」
ファティマは一気にまくしたてるヴィクトールの様子に圧倒された。「もしかしたら、私に執着があるのかしら?」という疑問を、論理的に潰されると黙るしかない。
(あたしは別に……でもいいんだけどな……)
(辛いわよね……。相棒が裏切ったんだもん。今はそうっとしておこう……)
すると、ヴィクトールは鼻をすすりながら静かに語り出した。
「エンリーケと出会って、8年になる」
ファティマは静かに傾聴する。
「組織に入って、最初の3年寮に入れられたんだ。そん時のルームメイトがエンリーケだった。喧嘩もしたが、俺たちはすごく気が合った。退寮させられて、自分たちでアパート契約して、独立して仕事するときに、あいつから言われたんだ。『ルームシェアして、これからも一緒に暮らそうぜ』ってな。俺は最初、その言葉に不安を覚えた。いつか喧嘩して、裏切られたりするんじゃねえかなって。だから言ったんだ。『俺は裏切られるのがこの世でいっちばん嫌いだ。お前、俺を裏切って俺を一人にしたりしないだろうな?』って。あいつは、『安心しろ。俺は絶対裏切らない。ずっと一緒だ』って言ってくれたんだ。それから5年、俺は、ずっとそれを信じていた。今までうまくやってきていたんだ、俺達」
「……」
「見捨てられ恐怖症なんだ、俺。見捨てられたり裏切られたりすると、辛くて怖くて、……ブチ殺したくなる」
「……ヴィクター……」
「……あいつだけは失いたくなかった。ずっと一緒にいられると思っていた」
そこまで話すと、ヴィクトールは路肩に車を停め、声を上げて泣き出した。車のサイドブレーキの上に置いていたティッシュペーパーを数枚引き出して鷲掴みし、顔に押し当てて慟哭するヴィクトール。ファティマはどう声を掛けていいか言葉に詰まり、彼が落ち着くまで背中をさすっていた。
(見捨てられ恐怖症か……。だから今朝、見捨てられる夢を見て、あんなにうなされていたのね。あたし……あたしも、ヴィクターの元から去ったら、この人に殺されるのかしら?……見捨てられる?今まであんなに優しくしてくれたこの人を、いまさら見捨てられる?きっと、すごく寂しいんだわ、この人。もしかして、あたしに優しくしてくれる理由って、見捨てられたくないから……?)
ファティマはどうしてもその疑問を解決してみたいと思ってしまった。訊かないほうがいいだろうかと躊躇したが、思い切って訊いてみる。
「ヴィクターって、どうしてそんなに優しいのかなって、ずっと疑問に思っていたの。ほら、あたしの男性恐怖症を治そうとしてくれたりとか、あたしに乱暴しようとしなかったりとか、殺そうとしなかったりとか……。それってひょっとして」
「あ゙あ゙?!」
突然ヴィクトールが怒気を孕んだ声を上げて睨んできたので、ファティマは怯えて口を噤んだ。
「ごめん」
ファティマの怯えたような顔を見て、ヴィクトールは反射的に威嚇してしまったことを自覚した。怖がらせてはいけない。
「殺せって言われたからってそんな簡単に殺せるかよ?!そんな簡単に殺意なんて起きねーよ。でもお前逃がしたら別の奴にお前殺されるだろ。そしたら逃げるしかねーだろ。生かしてもらってんだからそれでいいだろが。死にたがったら許さねー。何のために男性恐怖症治そうとしたかって?一緒にいるのに不便だからだろうが。それ以上も以下もねえ!」
「わ、解った」
ファティマは一気にまくしたてるヴィクトールの様子に圧倒された。「もしかしたら、私に執着があるのかしら?」という疑問を、論理的に潰されると黙るしかない。
(あたしは別に……でもいいんだけどな……)